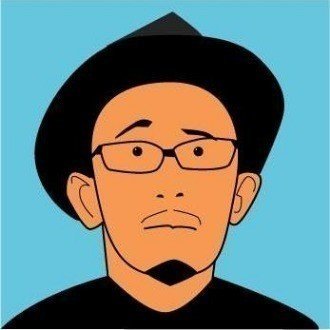デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか
おはようございます 渡邊です。昨日は、一日中天気が悪くて寒かったですね。こういう日がたまにあると、改めて太陽のありがたさが身に沁みます。
さて、今週は「デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか」 – 針貝 有佳 を紹介します。
著者の針貝さんは、デンマーク文化研究家として、ご自身もデンマーク人の夫とデンマークに住みながら、色々な方へのインタビューなどを交えつつまとめた本となります。
北欧の方のライフスタイルといえば、僕の人生において多大な影響を与えて、数年置きに読み返している本 「LESS IS MORE」- 本田 直之 があります。
会社を選ぶ基準は、ポジションやお金といった条件でした。(中略)働き方のオプションを取れるかどうかが重要になってくるし、そうしたライフスタイルをサポートできるような会社が人気を集めるでしょう。
僕自身も、働き方のオプションを取る為に、昨年の10月に実際に転職をしたというのもあり、このタイミングで読むデンマーク人の働き方は、ある種の自分の方向性の再確認という形でもありました。
午後4時までに仕事を片付けられるのか?
多分、多くの日本人にとって一番最初に気になるところは、こんなところなのではないでしょうか?「本当に出来るの?」「どれだけ生産性高いの?」
結論から言うと、実際には4時に帰宅したとして、子供が就寝した後の9時頃や早朝に1~2時間仕事をする人もいるということです。実際に夜9時頃から深夜にかけてメールが活発に飛び交うとのことなので、「する人もいる」というよりは、そういうスタイルが国全体として定着しているのかもしれません。
例えば、国内においても始業が9:00の会社と10:00の会社では、メールやメッセージが活発に飛び交う時間帯が異なるかと思いますが、デンマークの場合、4時以降に長い休憩を1度挟みつつ、夜の9時以降に再開するようなイメージかと思いました。
だが、彼らの言葉には「追われている感」がそれほど感じられない。「追われている感」がまったくないとは言わないが、同時に「追っている感」がある。自分が納得できるように仕事をしたいから、あるいは、翌日の仕事をスムーズにしたいから、フリータイムに仕事をして調整している。
この感覚は、僕自身も非常に近い感じがする。日本では?残業は基本的には、上司の命令の下でするものであって、勝手にしてはいけないとなっているような気がするけど、本当はこっちの方が気楽だし、プロ意識があっていい気がする。
もう一つのポイントは、ランチはサクッと30分とのことです。日本だと、しっかり1時間休憩をとるというスタイルが一般的な気もしますが、来るべき午後の長い仕事時間(9時始業18時終業だとすると、AM3時間、PM5時間)に向けて充電するイメージですが、4時で終了を前提としたデンマークスタイルは昼休憩は少なめで、一気に走りきるという感じなのでしょうか?
僕も、ここ5,6年は基本定時で上がることにしていたのですが、そのためにはと、昼休憩は大抵30分に切り詰めて、午前の仕事の残りと午後への準備に充てるということをしていました。
若い頃のように、1日の終わりが見えないエンドレスだと、ダラーっと行ってしまうのですが、1日の仕事の終わりが見えているが故に、昼は短くするという考えです。また少しピークタイムをズラすことで、飲食店の混雑も回避出来ていて効率が良い気がします。
友達に会ったりする時間はない
第一優先は家族。第二優先は仕事。三番目が娯楽や自分がしたいこと。この優先順位はいつも変わらない。(中略)
だから、友達に会ったりする時間はほとんどない。SNSも一切使わない。SNSを見ると、ものすごくエネルギーを消耗するから。ときどきそんな自分に罪悪感を抱くこともあるけど、でも、やっぱりそこに使う時間はないわ
ポイントとして、78個が挙げられているのですが、その中の1つ目はこれになります。
ポイント1 優先順位が低いものはバッサリ切る
折角、午後4時に帰ったとしても慌ただしい生活を送っていたとしたら、あまり幸せそうには思えないかもしれません。日常生活にゆとりをもち、幸せな日々を送る為には、バッサリと切る勇気が必要です。これは、ドラッカーも言っている劣後順位の決定が非常に関連が深いことになります。
集中できる者があまりに少ないのは、劣後順位の決定、すなわち取り組むべきでない仕事の決定と、その決定の遵守が至難だからである。
優先順位の分析については多くのことがいえる。しかし優先順位と劣後順位に関して順位の決定については、いくつかの重要な原則がある。しかしそれらの原則はすべて分析ではなく、勇気に関わるものである。
「友達に会ったりする時間はない」というと、少し刺激的な発言に聞こえてしまうかもしれませんが、やる余裕が無いというのが現実なのだと思います。勇気を持って、それを守り続けることが、自分の人生を豊かにするポイントとも言えます。
今の会社に転職しようと決めた、要素の一つに、判断基準(Judgement policy)があります。
健康 > 家庭円満 > 法令遵守 > 製造責任 > 顧客満足 > 業績向上
判断に迷った時の羅針盤として、これが設定されているだけで、共通見解としての守るべきものが明確になるのが良いなと思っています。
夫婦間の仕事のバランス
僕は、妻にも自分がしたいことをしてほしいと思っている。僕は仕事をすることで、自分が好きになれる。妻にも仕事をして、ありたい自分でいてほしい
「夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである」というという、いわば昭和的な考え方ですが、実際に内閣府の調査でも、昭和54年に75%を超えていた賛成派も平成28年には、46.7%と過半数を切っている(それでも多い!)ことをみる限り少しづつ変化してきている感はあります。
これは、働き方がどうとか、労働力がどうとかいう話もありつつ、冒頭で引用した、働くことによる自己実現という面でも非常に意味がある話だと考えています。
僕の妻は、長年保育士をしていたのですが、体調を崩したことをきっかけに、転職し元々好きだったアジア雑貨と衣料品を扱うショップのスタッフになりました。40代、未経験からのスタートで、収入も大幅減ではありましたが、なによりも毎日好きな服を着て出かけて、好きなものに囲まれて仕事をするという生活にとても充実しているようです。
また、僕自身が転職をし、リモートワーク中心の生活になったのもあり、ここ数カ月は、
「今日、残業してくから、夕飯遅くなる」
「今日、急遽先輩たちと呑みに行くことになったから夕飯いらない」
といった、僕が結婚生活の十何年の中で何の気なしに何度となく行ってきたことをやってるのを見ると、「折角ご飯の準備始めたのに・・」と寂しくなる一方で、妻が働く楽しさを享受できていることに嬉しさを覚えたりもします。
「休む」から情熱をキープできる
3週間の連休、ましてや1カ月の連休というのは、日本ではまだまだ現実てきではないものの、しっかりと休息を挟むからこそ、エネルギーを注ぎこめるというものがあります。
社員が健康で元気に、ベストコンディションで仕事に取り組むことが生産性アップにつながる。逆に、社員が疲れていたり、モチベーションが上がらない状態では、生産性なんて上がるわけがない
どんなに情熱をもっているプロジェクトでも、何週間にもわたって夜も週末も取り組んでいたら、ずっと同じレベルの情熱をキープできない。僕の場合は、ときどき休憩をいれることで、最後まで高いモチベーションをキープできる
以前働いていた会社で、すごく優秀だし、すごいハードワーカーの人がいたのですが、仕事に情熱を持っているようには余り感じられませんでした。言い方は悪いかもしれませんが、仕事中毒な感じで仕事に飢えてはいるかんじですが、こうしたい!みたいな覇気はあまりなかったです。
僕自身も、ハードワークしていた時は、それなりに仕事を楽しんでいた感もありましたが、決してモチベーションが高い状態ではなかった気もします。
常に仕事に追われ、休む暇も無く働いているとタスクをこなすだけになってしまいがちですが、終業時間後や週末にしっかりと休む時間があるからこそ、その時間の中で、いいアイデアが思いついたり、こんなことをしてみようと思ったりすることが自然発生してくるようになりました。
これは、脳科学的にもDMNの働きにも関係してきますね。
「適材適所」×「社会性(オイル)」
僕は、日本の企業でしか働いたことが無いので、昨今のジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いが正直あまりピンときてはいないです。7年位前に上司の指示の下、職務内容をジョブディスクリプションという形で記載してみたのですが、色々書きすぎてなんかよくわからなくなって、挫折した経験もあります。現時点でも、友人からワタナベ君は今なにしてるの?と聞かれることもよくあるのですが、とにかく色々やっているというのが正しくて、「〇〇です」と一言でいうのは難しい感じだし、自分自身もそういう動きが心地よいというのもありますね。比較的に色々なことに関心があるので、ある意味「適材適所」ということでもあります。
デンマークの組織の強みとして、「適材適所」×「社会性(オイル)」と書かれています。
先ず、ジョブ型雇用の為、採用時点で「適材適所」となっている可能性が高いとのことです。所謂「配属ガチャ」みたいなものが無いということでしょうか?一方で、僕自身のキャリアを振り返ると、大企業におけるある日突然やってくる、「異動」というものを通じて、色々なスキルを身に着けてこれたという点では、この恩恵に預かった訳ですが、実際には突然の異動により腐ってしまっている人や、入社以来ずーっと同じ部署で大した変化もなく不満を持ちながら働き続けている人というのも一定数いるというののが事実です。
もう一つが、「社会性」というオイル、いわば潤滑油みたいなものですね。
デンマーク人が小さい頃からの教育で身に着けてきた「社会性」は、機械を動かすオイルのようなもの
多様性という形がバラバラな個性的な部品がしっかりと噛み合って、組織としての成果を出すために必要なものが、このオイルということです。これには、4つのポイントがあります。
1.解決志向
デンマーク人は、何でもストレートに話をする。我慢を美徳とはせず、何か気になることがあれば、課題として取り上げ、解決策を提示する。
見て見ぬふりもしないし、評論家みたいなコメントや不平不満だけを述べるようなことをせず、問題を感じたら、しっかりと解決にもっていくという、解決志向の率直なコミュニケーションということです。
2.個人的に受け止めないチカラ
2つ目として、個人的に受け止めないというのが挙げられています。ストレートに意見を言い合う環境が故に、批判を個人的に受け止めていたら身が持たない。
批判しているのは、仕事の仕方であって、その人の存在ではない。相手が否定しているのは、自分の意見であって、自分の存在ではない。
自分の意見を伝えるときも、他人の意見を聞くときも「それはそれ、これはこれ」。じぶんという存在と切り離して捉える必要がある。
3.「戦場」を選ぶ意思
自分にとってそれほど重要でないことについては「戦いから降りる」のだ
譲らない、譲れない、引けないところというのは、しっかり大切にしつつも、自分の中でそんなにこだわりが無い部分、意志がないところに関しては、あっさりひいて妥協する。このメリハリがスムーズに物事を進めるコツとして非常に重要であるということです。
4.デモクラシーのマナー
たまたま昨日聞いた講演のなかで、モチベーションが上がる文化の一つとして、「Equal Oppotunity」誰もが平等にチャンスが与えられるというのがありました。同様にデンマークの職場はヒエラルキーがなく、みんなが平等に自分の意見を述べられるような「民主的なルール」があるとのことです。
自分の意見を伝える。他人の意見も聞く。自分を犠牲にして他人に同調するわけでもなく、他人を差し置いて自分が前にでるわけでもない。競い合うのではなく、お互いを尊重して耳を傾ける。
というわけで、今週はデンマーク人の働き方について考えてきました。ほんの一部しか紹介できていませんが、この本では、全部で78のポイントが述べられているのと、巻末には「デンマーク人から学ぶ『働き方のコツ』」のチェックリストも付録についていますので、興味を持った方はぜひ、読んでみてください。
(2025.02.03-02.07)
いいなと思ったら応援しよう!