
正しい読点の位置をマスターして、読みやすい文章を書こう!
今回は「読点(、)」の使い方についてです。読点をうまく使うことで、文章の読みやすさがぐっとアップします!
逆に、間違った場所に入れてしまうと、誤解を招いたり読みにくくなったりすることも…。そんな読点の正しい使い方を6つのポイントに分けて解説していきますね!
接続詞の後ろには読点を忘れずに

例文)
「私は猫が好きです。しかし、犬を飼っています。」
「しかし」「そして」「それでは」など、接続詞を使ったあとには読点を入れましょう。接続詞は文章をつなぐ役割があるので、読点を使って文章にリズムをつけてあげると、スムーズに読み進められるようになります。
接続詞の後ろに読点を入れると、次の内容が自然と頭に入ってくるようになりますよ。
長い主語は読点で区切ろう

例文)
「茶色い帽子を被ってサングラスをかけている若そうな男性が、山を登っている」
主語が長くなると、どこまでが主語でどこからが述語なのかわかりにくくなります。そんなときは、主語の後ろに読点を入れて区切ると、文章がずっと読みやすくなります。
誤解を防ぐための読点の使い方

例文)
「彼女は、口笛を吹きながら洗濯物を片付ける彼を見ていた」(口笛を吹いているのは彼)
「彼女は口笛を吹きながら、洗濯物を片付ける彼を見ていた」(口笛を吹いているのは彼女)
ちょっとした読点の位置で、意味が全く違ってしまいますよね?
読点がないと、意味が誤解されてしまうことがあるんです。そんな場面では、読点をうまく使うことで、読み手に正しい意味を伝えられます。
逆説のあとに読点を入れて対比を強調

例文)
「彼は急いで学校に向かったが、間に合わなかった。」
「〜だが」「〜ですが」などの逆説的な表現を使ったときは、必ずそのあとに読点を入れて区切りをつけましょう。これにより、反対の意味が強調されて読みやすくなります。
名詞が連続しているときは読点で整理
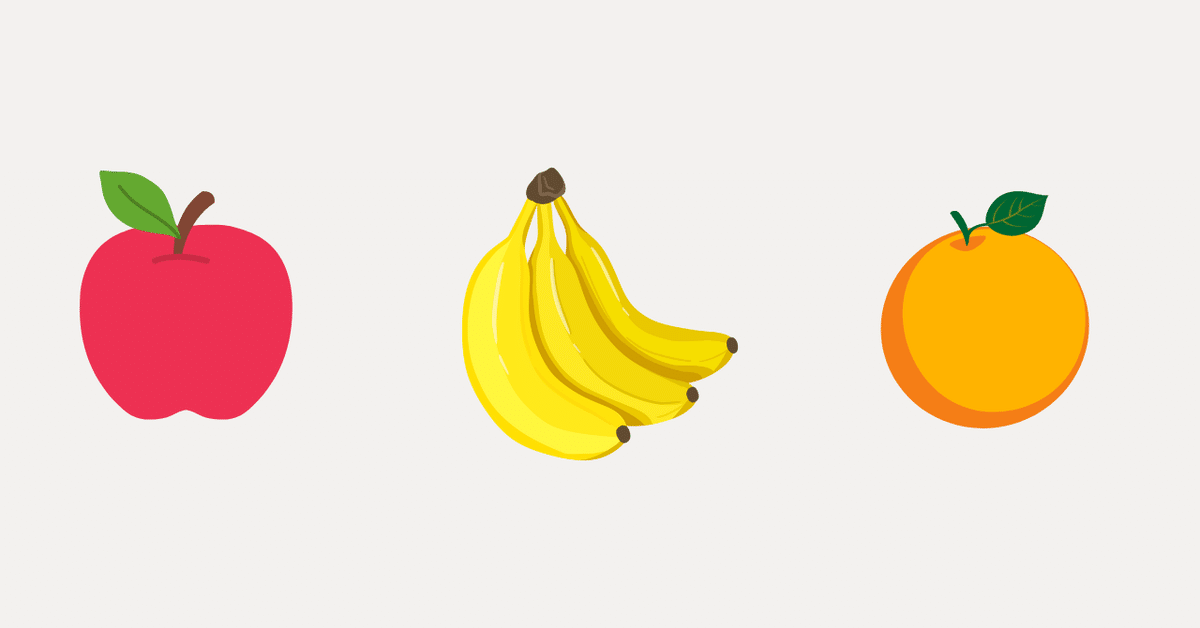
例文)
「リンゴ、バナナ、オレンジが好きです。」
「パソコン、スマホ、タブレットを使っています。」
名詞が連続する場合、それぞれの名詞を読点で区切ってあげましょう。これにより内容が整理され、読みやすくなります。
原因と結果を明確に

例文)
「たくさん食べたので、お腹が痛い」
「彼の説明がわかりやすかったから、すぐに理解できた。」
「なぜこの結果になったのか?」という原因と結果を示す文章では、読点をうまく使ってそれを明確にしましょう。どこまでが原因に関する文章で、どこからが結果に関する文章なのかはっきりさせます。
原因と結果がはっきり区別されていると、読者に伝わる内容もクリアになります。
まとめ
読点の位置を正しく使うことで、文章がクリアになり読みやすくなるのです。接続詞や逆説表現、名詞の連続や原因と結果の文章では、とくに読点を意識してみましょう。
また、注意したいのが読点の打ちすぎです。
一文に何個も打たれていると、読みにくい文章になってしまいます。目安は1文に1〜2個あればいいでしょう。
少なすぎても多すぎても、読みにくくなってしまう読点。正しく使うことを意識しましょう。
読点1つで文章の読みやすさが格段に上がるので、この記事を参考に実践してみてくださいね😉
