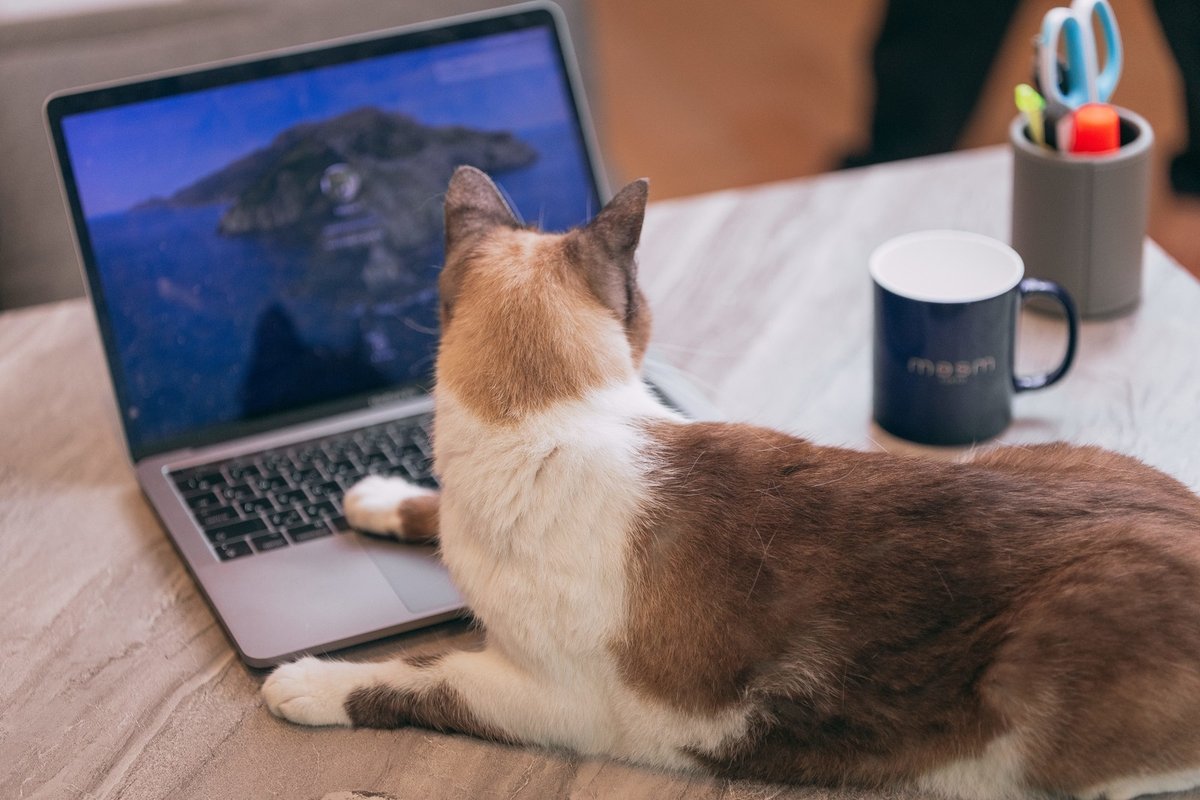【あめの物語 二人の秘密編 1】
「これでも飲みながら帰れ」
「ありがとう、義兄さん」
佐井の異変に気づいたのだろう。駅まで送ってくれた義兄の然りげ無い気遣いが、佐井は嬉しかった。
そんな義兄からもらったハイボールの缶は既に軽くなり、窓枠でコトコト揺れ動いている。その残り少ないハイボールを一口飲んで、佐井はスマホを見た。
画面にはある人たちの氏名が羅列されている。そのリストの中に「工藤陽太」という名前が無いことを願いながら、ゆっくりスクロールしていく。
まだ動力にディーゼルエンジンを使う釜石線は、岩手県の沿岸「釜石市」と内陸部の「花巻市」を結び「新花巻駅」から東北新幹線に接続する。SLマニアに人気の「銀河ドリームライン」が走っているのがこの路線である。
佐井の実家はこの釜石線の終点「釜石」の二つ手前「松倉」から車で五分程度の山間にある。自分の車をもっていない佐井は、実家に帰る時はいつもこの路線を使っていた。
父親の十三回忌の法要で帰省していた佐井は、一泊の予定を一日延ばした。どうしても確かめたいことができてしまい、無理を言って会社を休んだのだった。
今はその帰りで、いつものように釜石線に乗っていた。列車は民話の故郷「遠野駅」を出たばかりで、ゴトゴトとのんびり田園地帯を走っている。
「やはり落ちてるな…… オレは……」列車の震動で倒れそうになる缶を見つめながら、佐井はそんなことを考えていた。
遠野駅から乗ってきた若い女性の三人組が、佐井の後ろのボックスを陣取った。旅行に来たのだろう屈託のない笑い声が耳障りに聞こえ、「チ!」と舌打ちして外の風景に目を移した。
平行して走る釜石自動車道が見え、手前を国道二八三号線が走る。ここは「SL銀河」の撮影スポットにもなっているらしく、車で並走し助手席から撮影タイミングを狙うカメラマンも多いようだ。
「ここの田んぼに、直美が車を落としたんだったな…… あれから何十年が過ぎたんだろう……」思い出が蘇る。
免許を取ったばかりの直美は、中古のカローラを買った。少し運転に慣れはじめた頃、そのカローラに佐井と工藤を乗せ、直美は深夜のドライブにでた。
寒い冬の夜だった。緩い右コーナーに入った直美のカローラは、急に現れたアイスバーンにあっさりと足をとられ、 一メートルほどの崖から滑り落ち、田んぼにひっくり返ったのだった。
後部座席で居眠りをしていた佐井は「ドン」という衝撃で目を覚ました。だが暗闇の中では状況がまったくわからない。わかったのは「自分の頭が身体の下にある」ということだけだった。
「あの時はひどかったが、ま、大概の失敗は時が経てば笑い話か」
工藤陽太は佐井の友人で気仙沼の出身だったが、仕事の関係で釜石にアパートを借りて住んでいた。佐藤直美と工藤陽太には共通の友人がいて、二人はそのつながりだった。だが、佐井が工藤とつるむようになると、なぜか直美はいつも二人のそばにいた。
今思い出すと不思議な関係だった。工藤は直美が好きで、直美は佐井を想っていた。微妙な三角関係は、三人が一緒にいることで絶妙なバランスを保っていた。
そんな工藤がある日を境にまったく連絡が取れなくなったのは、佐井とつるみ出して二年も経たない頃だった。今のように携帯電話など無かった時代だ。アパートにも実家にも電話がつながらない状態ではお手上げだった。
「あの工藤が、当時はそんなことになっていたなんて……」
その後音信不通になっている工藤のことが、なぜか佐井は数年前から気になってしかたがなかった。
その工藤の消息は依然として不明だったが、当時の状況が今回の帰省で少しだけ掴めた。だがやっとわかった工藤の過去が今、佐井の心を落ち込ませていた。
「笑えない過去も存在するか……」
そんなことを考えながらまたスマホに目を移し、氏名と年齢が羅列されているそのリストをゆっくりとスクロールしていく。最後の氏名を確認して「なかった、よかった……」と佐井は胸を撫で下ろした。
『東日本大震災>身元が判明した死亡者>気仙沼市の方の一覧』これが佐井が見ていたページだ。最終更新日付は二〇一二年三月三日、震災からほぼ一年後のリストだった。
気仙沼市では死者数が一二一四人。これだけの人々が犠牲になり、未だに行方不明となっている人が二二〇人もいる。
このことに、佐井は今更ながら驚いていた。
スマホの LEDライトが光ったのは、そんな時だった。佐井は煩わしいのでLINEの「プッシュ通知」は OFFにし、LEDライトが点灯するだけの設定にしていた。
「誰からだろう」ふと気になってLINEを開くと、慈雨からだった。
慈雨は迷いに迷っていた。「今日は水曜日だから、きっと早く仕事終わるはずだわ」とか「でも、本社に出張だったら……」「会議中とか打ち合わせ中だったら、迷惑かけるわ……」などと考えれば考えるほどLINEを送れないでいたのだ。
「もうだめ、だって逢いたいんだから送っちゃえ!」と、勢いで佐井に送信したものの、自分の都合で二か月間も連絡をしていなかった負い目のようなものがあり、文面は遠慮がちになってしまった。
「今日はお仕事何時頃に終るのですか? あなたに逢いたい」
そんな慈雨からのLINEに、佐井は飛び上がりたいほど嬉しかった。
「今実家からの帰りで列車の中だ。オレも逢いたい、新幹線の到着時刻を調べてもう一度連絡する。仙台駅で逢おう」
「はい、駅で待ってます」
スマホで時刻表を確認すると、乗り継ぎに少し待ち時間があった。
「仙台に十五時十二分着の新幹線に乗る、来れるか?」
「わかりました、大丈夫です。中央口で待ってます」
返信は五分くらいしてからきた。
「高校生のガキと一緒だなぁ」と、佐井は心が浮きだっている自分に苦笑した。
「もう二か月が過ぎたのか……」佐井は二か月前の慈雨を思い出していた。
ホテルからの帰り道、人通りの少ない青葉通りを歩きながら慈雨が言った。
「母の体調がとても悪いの。それでつきっきりの看病になるから、しばらく逢えなくなりそうなの……」
「そんなに悪いのか?」
「うん、たぶん長くないと思うわ。だから今はできるだけ一緒にいたいの」
「そうか……」
「ごめんなさい……」
「なにを謝っている、子が親の面倒を見るのは当たり前だ。なにか大変なことになったら連絡するんだ、一人で抱えてはダメだよ」
「ありがとう、そうなった時は連絡します」
そんな会話で別れたきり、慈雨からは今日まで音沙汰なしだった。
…続く…
Facebook公開日 1/12 2019