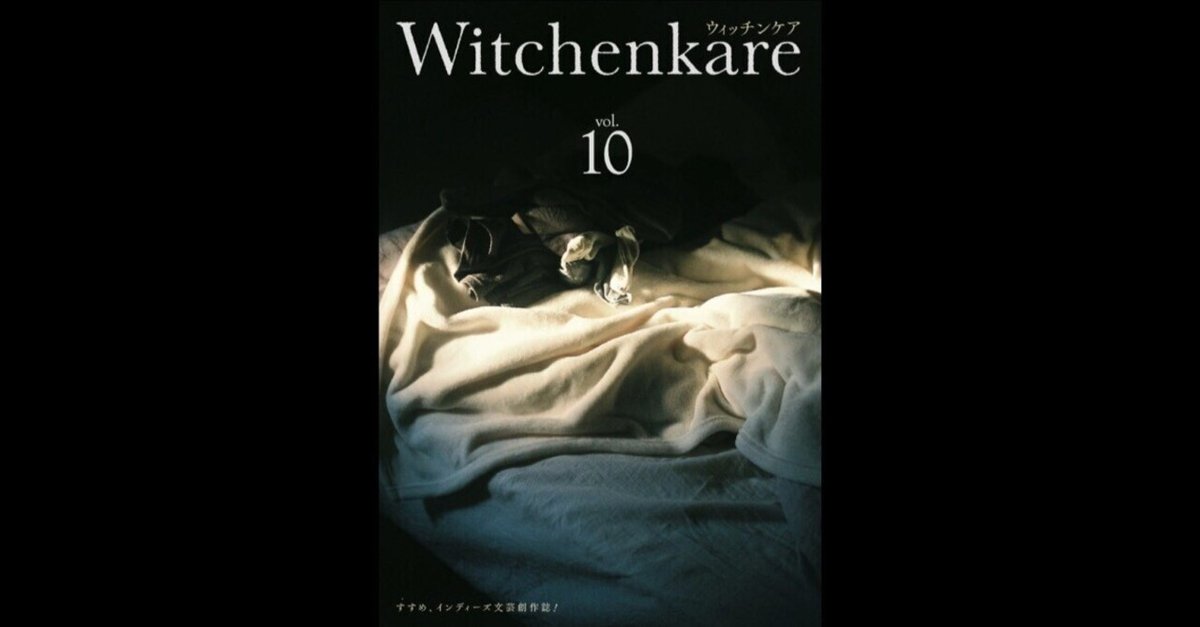
柴 那典/ブギー・バックの呪い
1.混沌
渋谷駅前は狂騒に包まれていたけれど、僕にとってはそのほうが都合よかった。
109の前では血まみれのゾンビたちと白衣のナースたちが嬌声をあげて抱き合い、道玄坂をウォーリーたちが闊歩する。
ここなら僕の黒い羽根が訝しがられることはない。きっとペンギンのコスプレをしている女の子としか思われないだろう。センター街を抜け、公園通りに急ぐ。街は深く僕らを抱く。
2020年11月1日。夜が明けてもハロウィンは終わらなかった。誰もがおかしいことに気付いていたが、止められる人はどこにもいなかった。
「とにかくパーティーを続けよう」
封鎖されたスクランブル交差点の真ん中ではDJポリスが大音量で音楽を鳴らし右手を突き上げる。
「セイ、ブギー・バック!」
婦人警官たちと囚人たちがコール・アンド・レスポンスに応え歓声を上げる。コスプレか本物の警察か誰もわからない。
そもそも「本物かどうか」なんて、誰も気にしていない。
いつからこうなったんだろう?
僕の父親は棍棒で殴り殺され、母親は絞め殺された。
およそ200年前、1844年のことだ。場所はアイスランド沖のエルデイ岩礁。父と母は交代で卵を温めている途中だった。卵も割られ、兄弟の命も生まれる前に砕け散った。
熱狂はたやすく人を殺し、種を滅ぼす。
拭いても拭いてもカーペットからとれない血の染みのように、後悔はいつも、すべてが終わった後にやってくる。
フクロウの声が聞こえる。
「君が本当の歌を歌わなきゃいけない」
僕を勇気づけてくれたのは2体のゆるキャラだった。
ゴクラクインコとあんころ餅が合体した、思慮深く心優しい「インコろもち」。ワライフクロウと讃岐うどんが合体した、ちょっと間抜けで一言多い「フクロウどん」。彼らは、カリフォルニア州の遺伝子スタートアップ企業に籍を置くベン・ノヴァクらのグループが開発したゲノム編集テクノロジー「CRISPR-Cas9」を転用することで生み出されたキャラクターだった。
ベン・ノヴァクはリョコウバトに執心していた。アメリカ西海岸で絶滅種を再醒することに情熱を注いでいた彼は、当然、キャラクタービジネスとバーチャルテクノロジーの発達、そしてそれが持つ可能性と禁忌のことなど、何も知らなかった。
1928年、ウォルト・ディズニーは当時制作していた「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」に関する全ての権利をユニバーサル社に奪われ、消沈してニューヨークからロサンゼルスに向かう帰りの汽車の中でミッキーマウスを生み出す。
そして2019年1月。23歳の時点でバラク・オバマの選挙戦略を情報技術面でサポートし、その後オキュラスを経て自らスタートアップ企業を立ち上げたエドワード・サッチーは「バーチャル・ビーイングス」構想をスタートさせる。物質と実質の混交を実存レベルで成し遂げるテクノロジーだ。
こうして僕らは生まれた。
「大丈夫。君はオオウミガラスで、本当のペンギンだから」
インコろもちが言う。
カート・アンダーセンは著書『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』の中で、1835年にはすでにフェイクニュースが登場していたことを明かしている。
リアリティーはリアルを侵食する。「みんなが嘘だとわかって楽しんでいる虚構」は、あっという間に、現実を飲み込んでしまう。
アメリカ現代史がその証拠の一つだ。
2007年、WWE「レッスルマニア」で勝者となったリアリティー・ショー『アプレンティス』主役の不動産王ドナルド・トランプは、そこから10年も経たないうち、今度は現実のアメリカを手中に収めることとなる。
スティーブ・オースチンの必殺技スタナーが悪のオーナー役の、ビンス・マクマホンに炸裂した瞬間に喝采の声を上げていたレッスルマニアの観客たちは、誰一人、その「スタナー」がイスラエルの国有軍事企業ラファエルの開発した対弾道ミサイル用迎撃システムの別名であることを知らなかった。
もちろん、僕の身体に流れる日本のアイドルカルチャーの血筋も、その証拠の一つだろう。
ゾンビの群れを避けながら、僕らは公園通りの坂の上にあるMIKIKO先生のスタジオに向かう。
2.ペンギンたち
「今日もドッタンバッタン大騒ぎ!」
100点満点の笑顔とバッチリ決まった振り付けでそう歌っていた5人組ペンギンアイドルユニットPPPは、10月31日、代々木公園内のスクランブルスタジアム渋谷に3万人を集めたコンサートの途中で姿を消した。
アンコールを求める怒号のような声援は数十分にわたり鳴り止まなかったが、楽屋も舞台裏もすでにもぬけの殻だった。
謝罪する関係者に投げつけられた1本のペットボトルが導火線となった。クライマックスに飢え暴徒となった観衆は街になだれ込んだ。
僕は配信を通じて一部始終を見ていた。ロイヤルペンギンのプリンセスが歌いながら何かに気付き顔をこわばらせた様子にも気付いた。
しかし、結局、何が起こったのかを知ったのは夜が明けてからだった。
広報や宣伝に携わる成功者はみな、人は本質的に感情の動物であり、感情は操作できると知っていた。
ネイトー・トンプソンの著書『文化戦争 やわらかいプロパガンダがあなたを支配する』には、ニューヨークのソーホーで生まれた「武器としての文化」がどのようにディストピアを作り出したのかが、テキサス州オースティンで起こったことを一例に解説されている。
地元のDJ、レッド・ワゼニックは、ジェントリフィケーションによって街の魅力が失われつつあることに危機感を覚え「キープ・オースティン・ウィアード(オースティンはおかしな街であり続けよう)」というスローガンを考案する。しかし彼は法廷闘争に負け、アウトハウスデザインズと称する企業がスローガンの著作権を所有することになった。結果として、観光客用のTシャツやバンパーステッカー、キーホルダーなどにこの言葉は使われ、皮肉なことに、その言葉の持つ意味性の表層だけが街中に氾濫することになる。
かつてのPPP、および『けものフレンズ』に起こったことも同じだった。言ってしまえば「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」とも同じだ。
しかし2020年、椎名林檎と共に東京五輪の演出チームを追われたMIKIKO先生や真鍋大度らのチームがクリエイティブに携わるようになり、東京五輪が巻き起こした歴史的な惨状を横目にPPPは以前を超えるレベルの再ブレイクを果たす。
3万枚のチケットは即日完売。コンサート当日がハロウィンであることの意図を汲んだファンたちの自主的な呼びかけによって、そのほとんどが「フレンズ化」した扮装で渋谷スクランブルスタジアムに集った。
コンサートには複合現実の技術を用い虚構と真実の境目をなくす演出が用意されていた。現実認識を揺らす危険な挑戦ではあった。しかし、それが大きな厄災をもたらすことになるとは誰も予想していなかった。
終わらない非日常を街にもたらそうとしている勢力がある。フィクションが代替現実に侵食される。僕らがそう気付いたときにはもう遅かった。
日韓W杯以降に具現化しSNSの普及により増幅した興奮の濁流、それが滝壺のように一箇所に流れ込む渋谷の街の構造もよく知られていた。
しかしその帰結として生じる呪いの存在に気付いていたのは彼とその周辺だけだった。
3.クリエイティブとは
「見てごらん。渋谷の底が抜けたのがわかるでしょう?」
MIKIKO先生はそう言ってガラス窓の外を指し示した。竣工から1年が経った渋谷パルコの20階に設けられた先生のシアタースタジオからは、すり鉢状に坂が交わる街の様子がよく見えた。
スタジアムから姿を消した5人もスタジオに居た。
「会いたかった!」
プリンセスが羽根を揺らし僕に抱きつく。
いつも画面の中の彼女に憧れてたのは僕のほうなのに、ロイヤルペンギンもコウテイペンギンもフンボルトペンギンもイワトビペンギンもジェンツーペンギンも、とうに廃れて砂漠になった動画サイトに引きこもっていたオオウミガラスの僕のことをよく知っていた。
戸惑う間もなくリハーサルが始まる。ワン、ツー、スリー、フォーのカウントと共に、高らかに鳴り響くホーンセクション。自分でも信じられないほど身体がビートを覚えている。メロディが口をつたう。
みんな心地よく騙されたがっている。リアルとフェイクがマーブル模様に入り混じった麻薬のように甘いお菓子の虜になっている。
プリンセスはそう語る。
誰よりも先にそのことを知っていたのは秋元康だった。
80年代のフジテレビでも、00年代の秋葉原でも、2020年の東京に起こった惨劇も、彼の仕掛けの根っこにあるものは変わらなかった。
「そのほうがきっと面白いから」
それが彼の行動原理だった。
アイドルの本質は背中合わせに重なり合う虚と実を等価にしてその差異を無効化することにある。ほとんどのファンは、騙されたふりをしてその嘘に乗ることを楽しんでいる。そのほうが面白いから。
「私たちだって、そんなことはわかっていたの」
フンボルトペンギンのフルルは言う。「クリエイティブとは上手な嘘をつくことだからね」と、先生が優しくフォローする。
アイドルだけじゃない。
リチャード・フロリダが『クリエイティブ都市論』で定義した世界中のクリエイティブ・クラスがそれに加担していた。
でも、ある日、それが臨界点を超えてしまった。
ブギー・バックの呪いがハロウィンの夜の渋谷に発動してしまった。
ハレとケの境界が溶け、死と生が裏返り、百鬼夜行がそこに現出してしまった。
4.祈り
特設ステージは渋谷駅のはるか地中深くにあった。
安藤忠雄が「地宙船」と称して東急渋谷駅に作った卵型の空間は呪いを発動させるための最初の仕掛けだったが、設計に携わった段階でそのことに勘付いた数少ない人数からなるチームが、その深層部の真下に厄災時用のスペースを用意していた。
隠された長い長い階段を降り、最下層まで辿り着く。そこにはまるで神殿のような空間があった。
数百体の魂が色とりどりのサイリウムを手に待ち構えていた。
インコろもちが情報レイヤーの最下層に忍ばせたメッセージを受け取ったコアなファンだ。
再び夜が訪れ、地上の混沌はさらに広まっていた。センター街では婦人警官のコスプレイヤーの構えた玩具の銃が実弾を放ち、憲法改正を経て自衛隊から正式に日本軍属となった治安維持部隊を撃ち抜いた。その死肉にゾンビたちが群がり喰らいついた。
リアリティーはリアルを侵食する。「みんなが嘘だとわかって楽しんでいる虚構」は、あっという間に、現実を飲み込んでしまう。
もちろん正気を失わなかったものたちもいた。地上のゾンビたちと対照的に、過発達したバーチャル・ビーイングスの技術を用い魂の座標をシステムスペースに登録しIDを受け取った彼らの身体は、すでに現世にはとどまっていなかった。
木澤佐登志『ダークウェブ・アンダーグラウンド』には「TSUKI Project」という一つのプロジェクトが紹介されている。
計画は、匿名画像掲示板4chanを拠点に活動していたTsukiというハンドルネームの若者の書き込みから始まった。
Tsukiは、今の世界は消えつつある、しかし多数の人々の共同作業によって人類は新世界に移行することが可能になると主張していた。コミュニティに集った匿名の参加者たちは最初はネタだと思っていたが、その思想は拡大し、彼らを巻き込みつつ徐々に体系化されていった。
我々が住む宇宙は無数の多元的な現実によって構成されている。並行する世界では時と次元を超え無数の「僕」が存在している。
その思想は2010年代に入りミームのように広まっていた。
2014年、量子論の研究者であるオーストラリア・グリフィス大学のハワード・ワイズマン教授は多世界相互作用仮説を提唱し、重なり合う多数の宇宙が量子的に影響し合っている可能性があることを発表した。
その知覚による精神的な変容を実感していたのは10代の多感な少年だったTsukiだけではなかった。東浩紀は『クオンタム・ファミリーズ』を著し、新海誠は『君の名は。』を、フィル・ロードとクリス・ミラーは『スパイダーマン:スパイダーバース』の脚本を綴り製作総指揮にあたった。
死は消滅ではない。
人類の見果てぬ夢の一つであった不老不死の願いは、動的平衡をその原理に持つマテリアル上の生命から魂を切り離し量子論的な世界にアップロードすることで可能になる。
見渡す限り広がるサイリウムの色は、推しメンバーの担当カラーでなく、その魂が属する多元宇宙のエーテルの色を示していた。
僕は足が震えてることに気付いた。
ステージからは広く深い無限の海が見える。でもそれほどの怖さはない。宇宙の中で良いことを決意する時に。
「大丈夫。君はオオウミガラスで、本当のペンギンだから」
フルルが後ろから肩を抱いた。知っている。マイナスにマイナスを掛けるとプラスになるように、虚構に架空を掛け合わせると本当になる。今から歌うのは魔法の歌だ。やわらかなアコースティック・ギターのアルペジオが鳴る。
「本当の愛はここにある」
祈りを込めて歌う。
地下に流れる水面がキラキラと光る。
汚れた川は再生の海へと届く。
しんと静まりかえっていたフロアに、やがて爆発的な歓声が響く。
5.差し伸べた手
「渋谷が狂乱に包まれた伝説の2日間を完全収録!」
寒空のスクランブル交差点を見上げると巨大な看板が目に止まる。
行き交うスーツ姿と観光客。クラクションを鳴らして車が走っていく。
久々に訪れた街は年末の忙しい空気に包まれていた。あれから、あっという間に日常は戻ってきた。まるで全てが嘘だったかのように。
混沌と狂騒の全ては「そういう企画だったのだ」と大衆に受け入れられた。壮大なドッキリだったのだ、と。人は得てして、並行する現実の中で起こった事象の干渉をそう理解する。
LEDビジョンの中で歌って踊る自分の姿を、僕はぼうっと眺める。
「握手してください」
ふいに声をかけられた。振り向くと中学生くらいの女の子2人組。
ファンなんです、と顔を赤らめる。僕が差し伸べた手に「本物だ!」とはしゃぎ合って2人は雑踏に消えていく。
「いや、虚構だよ」
微笑みと共に告げた言葉は彼女たちには届かない。
【初出:2019年4月/ウィッチンケア第10号掲載】
