
私がやっている講義の工夫
この記事のまとめ
講義は、出欠もなく、45分で一旦休憩あり。しかも、全部録画でいつでも閲覧OK。宿題もレポートもなく、テストは選択・穴埋めのみ
光栄なことに、勤務先から、工学講義賞、というたいそうな賞をいただいたので、こんなスタイルで講義してますという情報を共有したいと思います。大学で講義をされている同業者への参考になれば幸いです。
対象講義
講義のスタイルは、講義の内容や対象となる学年、人数、教室の形などによって変化します。今回の話は、私が工学部の2年生、3年生向けに実施している2つの科目に関する話です。私も他の講義では他のスタイルで実施しています。
講義概要
講義は、2年生向けのオペレーティングシステムと、3年生向けの分散システム、という科目です。特徴としては、非常に古典的な基礎科目、ということです。どちらも毎年、80名前後が履修しています。
どのくらい古典的かというと、どちらも私が学生時代からある講義です。原点となるバイブルは、タネンバウム本と呼ばれる2000年代の教科書ですが、いくつかの教科書をミックスして、オリジナルの講義資料を作ってます。
コンピュータも分散システムもすでに我々の世界で常時使われており、ある意味成熟した分野ともいえ、その土台となる基礎知識を身につけて欲しいのですが、残念ながら、ワクワクする感じではありません。そんな講義を楽しく、寝かせず、やるには?みたいなのがミッションです。
講義上の工夫点
では、さっそく、工夫しているところを書いていきます。
全録画
コロナ禍にオンライン講義やオンデマンド講義(事前ビデオ収録)を経験したことで、講義を録画したり、録画を公開することに慣れたため、現在、教室で行っている講義もすべて録画して、講義終了後に公開してます。録画は、Zoomを用意して、1人で入って録画をONにしておくだけです。現場での手間としては、講義前にスピーカーマイク持って行くくらいなので、極めてお手軽。公開は、YouTubeを使い、毎年、講義ごとに再生リストが出来上がっていく感じです。たまに講義室のWiFiが不調で録画できなかったり、音声が途絶える(Zoom再接続が起きてマイクがミュートに戻っていた)といった失敗や、音声がハウリング(iPadは音量を0にできないので不可避)して非常に聞きづらい音声で録画されていたりもあるのですが、そこは仕方ないと目をつぶってます。

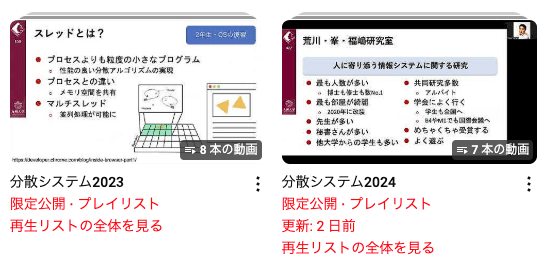
録画しておくことは、学生にとっても、教員にとっても利点があります。
【利点1】コロナやインフルの連絡が来た学生には、ささっとURLを送り、元気があればライブで見れば良いし、ダメなら録画を見てね、と案内するだけです。もともとZoomで録画しているからこそ簡単に対応できます。部活や学会での欠席もどうぞどうぞって感じで、イレギュラー対応が不要になります。
【利点2】加えて、学生たちはいつでも受講、復習ができます。倍速で見ればタイパ良いはずです。理解を深めるためにはどうしても冗長に説明する部分も増えるので、学生自身で速度を調整してもらえたらと思ってます。あと、ビデオを見ながら、横でネットで調べたり、ChatGPTに聞きながら学習するというのも良いでしょう。
【利点3】さらに、教員自身がどうしても急用で講義ができないとき、過去の動画が助けてくれることがあります。実際、今年も1度、昨年の動画を使ってオンデマンドとした回がありました。自宅から配信していた頃は、iPadを使い、文字や絵を書き込みながら講義していたので、そちらの動画の方がわかりやすかったという声もありました。
出欠なし・出席義務なし
講義に出てくるように出欠を取っている講義も多いと思います。私もかつてはそうしていましたが、講義開始時のMoodleのアクセス集中もあるし、上述した全録画を始めたら、まぁ好きなように受講してもらえたら良いんじゃないかと思うようになりました。現状、2年生は8割くらいは講義に来てます。3年生はだんだん減ってきて、今は5割くらいかなという感じ。結局は、最後のテストでドライに点数をつけるので、講義に来てなくても知識が身についていればOkというスタンスです。
講義に休憩
これもコロナ禍で学んだことなのですが、集中力が続くのは15分程度なので、動画も90分1本撮りではなく、30分3本とかに分けましょうという話がありました。そこで、90分の講義の半ばで休憩を入れています。ただ、休憩していいよと言っても学生も何をしたらよいかわからない感じだったので、ここにクイズを挟むことにしました。
前回の講義の内容をいくつか選択・穴埋め問題として用意しておき、復習の時間としています。Moodleの仕様上、小テスト、と表示されてしまいますが、正誤を成績に反映する訳では無いので、過去の資料を見ることはもちろん、隣の人と話しながらやってください、と毎度アナウンスしてます。話すことで、眠気も覚め、早く終わった人はトイレに行ったりして、なんとなくリセットされている手応えを感じたら、再開します。出入りがあると、換気にもなって、眠気を誘発するCO2を減らす意味でも良い効果があります。それでも寝ている学生もいますけど(笑)
特別講師による講義
各講義で、1回ずつ企業の方を呼んで特別講義を行っています。古典的な内容の講義なので面白くないかもしれないけど、世の中にこんなに使われていると知って欲しいと思って、その分野に関係している人を呼んでいます。
今年の特別講師は、
オペレーティングシステム:Google JapanでChromeのカスタマーエンジニアをしている山本氏
分散システム:PFNでネットワークエンジニアをしている清水氏
にお願いしました。二人共、私の研究室の後輩で、私も年に1度会うのを楽しみにしています。技術的な話だけではなく、キャリアの話、研究室の話なども含めてもらうようにお願いしていて、講義を通じた出会いが受講生のキャリア形成にもつながればなと思っています。
他の工夫点
講義中の工夫以外でやっていること
講義構成の見直し
2年前にChatGPTが登場して、さっそく、講義構成に関することを色々と壁打ちして、講義の説明順序を変更したり、抜けている部分を補完したりしました。GPTは膨大な情報を学習済みです。特に、オペレーティングシステムと分散システムは、1990年代から30年以上、全世界の大学で講義されている古典科目といえ、GPTに聴くにはもってこいのお題だなと思いました。結果を鵜呑みにするわけではないのですが、出力は結構参考になりました。


講義資料のアップデート
毎年、講義資料のアップデートをしていってます。オペレーティングシステムについては、すでに6年目ということで、ほとんど変更なしなのですが、分散システムはまだ3年目ということで毎年アップデート中です。2年目は、ブロックチェーン、Web3.0、DAOなどを大幅に追加しましたが、今年は時間の都合で、一貫性について図を増やしたりと軽微なアップデートしかできませんでした。
ただ、内容確認中に気づいた中で大きかったのは、「うるう秒」の廃止です。クロックの回で、2023年11月に「うるう秒」の説明をしていたのですが、その後に廃止のニュースが出ていて、2024年の講義では、慌てて廃止の話を追加した次第です。
問題回収(過去問なし)
オペレーティングシステムも分散システムも、すでに広く使われている基盤技術の基礎知識を獲得する意味合いが強い科目です。そのため、IPAの基本情報技術者試験や応用情報技術者試験くらいのレベルを目指した講義にしています(逆に言うとあまり高度なことはやっていません)。そのため、問題は選択問題と穴埋め問題のみにしています。簡単な代わりに、問題要用紙に直接記入して提出する形にして、問題を回収し、過去問が流出しないようにしています。過去問があると、学生たちはそれしか勉強しないため、幅広い知識を身につけて欲しい講義にはそぐわないと考えてのことです。
試験は30分経ったら提出して退出OKという形にしていますが、半数くらいが30分で終わり、大半の学生60分以内に終わって出ていきます。それでいて、満点近い学生もちらほらいて、オペレーティングシステムでは40%の学生がS、30%の学生Aとなり、過去問がなくても勉強をしている学生はしっかり点数を取ってきます。一方で、10数点〜50点程度の学生も数名出ています。
逆にあまりできてないこと
インタラクティブな講義
やってみたいなと思いつつも、講義内容や受講生の数、講義室の形状、等、様々な理由で、この2つの講義においては実施できていません。
反転学習
これも良いと聞きつつも実現できてません。講義の進め方を大幅に変え、事前に資料を配ったり、ビデオを見せたうえで、講義室ではディスカッションに充てるような形は面白そうではあるのですが。
終わりに
コロナ禍という大きな転機があり、大学における講義の形も大きく変化したと言えます。対面でしかできないこと(実験など)や、対面のほうがより良いこと(グループワークなど創造的作業)などもたくさんありますが、座学による知識獲得系の講義は、教室への物理的参加を強制せず、いつでもどこでも自主的に学ぶ形にしてもいいのではないかと思います。世界では、CourseraやUmedyなどオンライン学習サービスが広がっていますし、程よいコンテンツがあれば、講義はそれを見てもらって単位互換するのも良いのではないでしょうか。
