
【レポート】統括部長になりきってみよう!研修
研修概要・目的
2025年1月7日(火)、NEC事業開発統括部主催の研修にて、戸田が講師を務めました。今回の研修は、2024年6月18日(火)に実施したマネージャー研修の第2回目です。
前回の参加者の中から有志が集まり、次の研修も希望してくださるところから始まりました。その後、この事務局の方々との打ち合わせや、統括部長のヒアリングを経て、完全オリジナルで制作したプログラムです。
今回は、組織の継続的な成長には「人」が重要であり、そのためには管理職の成長が不可欠という考えに基づき、管理職の育成を目的とした研修を実施しました。
研修内容
1) 冒頭挨拶
はじめに、統括部長松田氏より冒頭挨拶をいただきました。研修の目的や期待することとして、事業開発統括部のチームは良い形で進んでいることを前提に、さらに組織が継続的に成長していくためには「人」が重要であり、「誰もが統括部長の視点で考えてみることが大事」というメッセージが伝えられました。
2) 戸田の経験共有
研修は、前半と後半に分かれます。前半は、事務局メンバーからも要望が多かった戸田自身の事業の成功と失敗、特に「人」に関する経験を共有しました。
事業よりも「人」で悩む
戸田は、「人間関係」に関する成功と失敗の経験が多く、別れや出会いを繰り返しながら得た気づきを共有しました。
イトーキ社での経験からは、ほぼ一人で事業を回していた状況で、社内での人間関係や調整に困難だったことや、「3年」という期間を設定されながらも急かされていることなど、現状と自身の動きにジレンマが生まれたこと、また、そこで学んだ上司から言われた「おかげさまの精神」を身に着けたことなどをお話ししました。
デロイトトーマツ DTVSでの経験からは、期待されて入社したため、期待してくれた人に対して応えたいと考えたものの、その人自身が異動してしまったり、大企業としてのルールや制約に苦しんだりしたことによる気づきがありました。
自ら起業したWEでは、一緒にやりたい、と言って入ってくれた仲間がいたものの、「この金額では動けない」「本業がある」などといった理由で離れてしまいました。自分は、一緒にやりたいという気持ちがあったら、「無償でも全力でやりたい」という思いになるが、それを聞いた顧問弁護士から「戸田さんはレアです。みんな自分と同じだと思わないほうがいい」と言われてしまいました。
しかし、「人は変わらない」という結論を出してしまうと、「人に気づきを与える」という事業を行っている自分自身がその事業とは真逆のことを行うことになってしまう、という葛藤を感じました。そこから人との向き合いの重要性について特によく考えるようになったとお話ししました。
思いがけない成功
一方で、思いがけない成功体験へと変化したものがあります。それは以前に立ち上げた事業の経験です。教現役教員のためのプラットフォーム事業「Teacher’s House」をつくり、教育事業として期待して、2022年に立ち上げたものの、その後ずっと0人だったのですが、2025年1月1日、ついに初めてのメンバー登録がうまれました。成功していないけど、「やり続けていたら負けではない。やめなければ成果が出る」と思えたという経験です。
<参加者の感想>
戸田からの共有に対しては、次のようなコメントが寄せられました。
「若く優秀な方には処遇が伴わない」というジレンマを感じました。また事業を作るうえではやはり人間関係が最も重要だな、と感じました。
仕事をする上で「人」、誰と仕事をしていくかで成果が大きく変わっていくのだなと深い気づきを得られた。
一緒に動いてくれる人への感謝は大事。
自分と他人は違う。
発言と行動は必ずしもリンクしない。でも発言することで行動が変わることは多々あるし自分の経験としてもあるので、発言したんだから行動してくれると期待しちゃうよなぁとも思う。難しい。
成し遂げたいという思いが強すぎることが困難や壁を作ってしまう原因になる場合もあるが、最終的には成功につながっているのだろうなと感じた。

3) ワーク:松田さんになりきってみよう
さて、いよいよ本番のワークショップ!このワークショップは、ロールプレイを取り入れたディスカッションワークです。まず、事前に統括部長にヒアリングした内容から、問いを3つ提示します。そして参加者にそれぞれ異なる役割を与え、ある程度議論の方向を見出してから、各役割が混ざったチームに分かれて問いについてディスカッションする、という手順です。
役割A:リーダー
役割B:やる気のある部下
役割C:やる気がない部下
役割D:批判的な部下
➡この役割を持つメンバー3人ないし4人(※)で1チームとして、Aチーム・Bチーム・Cチームの3つのチームに分かれて活動しました。
※全10名だったため、「やる気のある部下」がいるチームは1つのみ
各チームは、与えられた役割を演じながら、リーダー役と議論を行いました。ワーク中は、メンバーが自分の役割をまっとうしながらディスカッションする姿からは、試行錯誤しているようだったり、難しそうだったり、様々な表情が見られました。

4) 発表・リーダー振り返り
約90分のディスカッションの後、各チームのリーダーから、「問い」に対するチームの回答と、ワーク中の気づきを発表しました。
Aチームリーダー: やる気がない部下をいかに動機付けるかに苦労した。
Bチームリーダー: 批判的な意見も議論の材料として捉え、前向きに進めることができた。
Cチームリーダー: 部下それぞれの個性に合わせた対応の難しさを実感した。
また、後日このようなコメントをもらっています。
(意識したこと)誰かを置き去りにしてでも良いアウトプットを得るというよりは、アウトプットの質が下がったとしても全員が参画して検討をすすめることに意識して取り組んだ。
相手の行動や反応に変化が見られないとメンタル的に厳しい。もっと長期間の仕事であれば、単純に一緒に取り組んでいくことで仲良くなっていくとか、相手のモチベーションをあげるポイントとかがわかってくると思うが、今回の限られた時間の中では、相手の行動変容を促がすことが難しかったのと、もしうまく相手のモチベーションコントロールができていたとしても(設定上)変化しないという前提であったこともあり、かなり厳しい状況に追い込まれるという体験ができた
5) 全体振り返り
また、参加者それぞれが、研修を通して得られた気づきや感想を共有し、以下のようなコメントがありました。
やる気がある部下役
気持ち的にはどうしてもネガティブ側に引っ張られがちになるが、話している内容については非常に重要な意見が含まれていると感じ、感情に引っ張られずに事実を理解する大切さに気付いた
やる気がない部下役
やる気がない状態を演じることで、その心理や行動を理解することができた。リーダーの言葉や態度によって、やる気が増減することを実感した。
やる気がないでい続けることの難しさを感じた。会社の中でそのような状況の方は余程のことがあってそうなっているのだと思う。しかしながら、自身の仕事を振り返ると基本的にはやる気があるが、何時でもどのような仕事でも常にやる気を持った態度かと言われるとそうとも言い切れない場面もある。そのようなことは改める必要があると感じた。
6) ワーク:これから、マネージャーとして部下とどのように接していきたいか
研修で得た学びを踏まえ、今後のマネジメントについて、チームで議論しました。各チームからは次のような意見が出ました。
Aチーム: 部下のやる気スイッチを探ること、そして経営陣への働きかけの必要性を認識した。
Bチーム: 部下のやる気を引き出せないのはリーダーの責任であり、その原因を探ることの重要性を再認識した。
Cチーム: やる気のない部下とも真摯に向き合い、長期的な視点でサポートすること、そして短期的な対策として業務の具体化や丁寧なフォローが必要であることを確認した。
また、自分の心に響いた言葉・響かなかった言葉については、より具体的な意見がありました。
例えば、やる気のない部下役を担ったメンバーからは、「自分個人の意見を、正解を求めずに聞いてくれた」(「あなたの視点からみてどうなのかを考えて」「間違ってもいいから」)ことや、「本音が出た部分は心が動いた」(「疲れちゃった」)といったことです。
響かない言葉は、「部門からのトップダウンだから」と言われるとやる気をなくす、という例がありましたが、一方で「そうでもしないと逆に動かない」というリーダー役のジレンマもありました。
いずれにしても、「個人に寄り添った発言をすることが大事なのではないか」と戸田からコメントしました。

まとめ
最後に、改めて統括部長松田氏より、経験の重要性、そして今回の研修を通して得られた気づきを活かして、今後のマネジメントに生かしていくことの重要性が強調されました。
今回の研修の特徴は、ロールプレイを取り入れたワークショップを、事務局メンバーの意見を取り入れながら実施したことです。普段とは異なる立場を演じることで、新たな視点や気づきを得られるように工夫しました。
また、統括部長のヒアリングを基に、実際の業務で起こりうる場面を想定したワークを通して、実践的なスキルを学ぶことも意図しました。マネージャーでいらっしゃるメンバーが、さらに、統括部長としての立ち位置を想定しながら議論や振り返りを重視することで、参加者一人ひとりが主体的に学ぶことができるように設計しました。
<参加者の声>
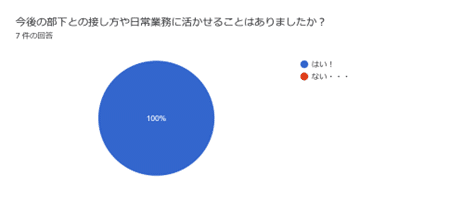
相手へのの寄り添いかたについて学ぶところが多かった。不安の払しょくというのはキーワードだなと思った。ワークではリーダーが具体タスクに落としつつ、タスクの目的を提示する形で部下に寄り添っており、不安の払しょくにつながるところだと感じた
やる気がないときは、相手を否定するのではなく、相手の気持ちを汲み取ることも大事なのだと思った。やる気のない人に正論をぶつけても何も進歩はしないのだろうなと実感した。

期待していた研修を、短期間で設計と実施いただきありがとうございました!
新年早々、いままで受けたなかで5本の指に入るつらい研修でした…
これまで体験したことのない研修だった。やる気のない人との付き合い方についてはモヤモヤが残っているが、そのモヤモヤした気持ちを課題意識として自身で考え続けたい。
チームメンバーが最大効率を出せるようにするため、個々人のやる気の出るポイントの理解をリーダーとして察知できる能力を高めていきたい。
今回の研修で得られた学びを、今後のマネジメントに活かしていくことが期待されます。WEでは、このように各企業(部署)の皆様との密な打ち合わせを基に、オリジナルの研修プログラムを制作いたします。興味を持ってくださった企業の皆様、ぜひお気軽にお問合せください。
お問合せ先:info@we-inc.net
