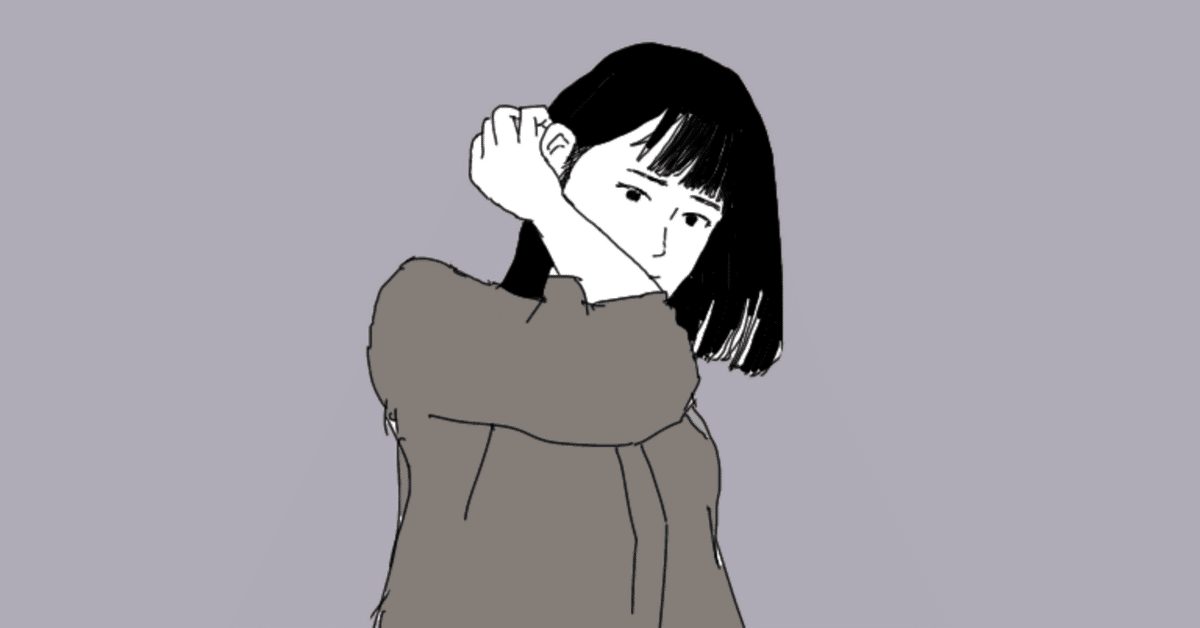
男なんて大嫌い
低い男の声が、斜め後ろから飛び込んで来る。
「あんた、いい加減にしなよ」
そう言われたのは、三次会での出来事だった。流れで付き合う事になったカラオケ。歌いたくもなければ、楽しくも何ともない。隙を見ては席を外し、なるべくカラオケルームの中にいないようにしていたのだが、喫煙室で一人になっていたところ、誰かが入って来た。
「何がよ」
不意なタメ口に、倉本照子が素で答える。振り向かずとも、声の主はわかっている。
「その態度だよ」
前川比呂人。年齢こそ照子より上だが、照子にとっては一応は部下である。直属ではないものの、この度チーフになった照子に対し、比呂人はヒラである。
「はぁ?」
照子は不愉快を隠さずに言う。そもそも、照子はこの男が嫌いだった。同期で、初めて会った時から嫌悪感がある。ガサツで無神経。身体ばかり大きくて脳味噌が小さい。大して仕事が出来る訳でもないが、客先のウケが妙に良かったりする。典型的な「ザ・男」「ザ・体育会系」で、ともすれば少女漫画に出てくる第二の王子様だ。最終的に王子を押しのけてヒロインとくっつくか、サブヒロインの純情可憐な少女と結ばれるパターン。
付き合っている彼女はいないと言うウワサで、騒いでいる女子もいるが、照子からすれば生理的に無理な対象である。
「仕事に私情持ち込むなって言ってんの」
背後で比呂人が煙草に火を着けながら言う。喫煙室に来ておいて何だが、照子は煙草も嫌いだった。自身は煙草を吸うが、電子タバコである。それも好きで吸っている訳ではない。半分はポーズだ。
「私情を挟んだ覚えはないのだけど」
ようやく、照子が振り向く。比呂人が歯を見せて笑っていた。世が言うには、がっちりとした肉体に、スポーツマン系の爽やかな笑顔だろう。照子の苦手なタイプだ。
「バレてないとでも思ってんの?」
露骨に煙草の煙を吐き出して、比呂人が問う。
「何の話?」
実際に何の話かわかりかねる。いや、正確に言うなら、思い当たる節が多過ぎて、どの話をされているのかわからない。
自分の態度が会社の一部で嫌われている事は自覚している。だから、別に何を言われようとも今更になって気にするつもりはなかった。しかし、
「あんた、男キライだろ」
という思わぬ方向からの指摘に、照子は言葉を失った。
何を言われようと適当に流してこの場を去るつもりでいた。しかし、考えてもいなかった不意打ちに揺さぶられた。動揺を隠すのが精一杯で、何も返せなかった。
「図星だ」
比呂人が楽しそうに笑う。普段なら爽やかな笑顔と呼ばれるだろう口許が、途端に厭らしく見える。
「何を根拠に」
返した言葉に後悔する。「バカじゃない?」とでも返せば良かったのだ。「何を根拠に?」 それじゃまるで、サスペンスドラマの追い詰められた犯人だ。「証拠はあるのか?」それは事実を認めている事に他ならない。
「バレバレなんだよ。男嫌いのねんねちゃん」
瞬間的に、顔が赤くなるのを感じる。吹きかけられた煙を掻き消すようにして顔を隠すが、それも隠蔽だと気付かれている気がした。
「失礼にも程がありますよ」
そう答える照子だったが、内心は気が気ではなかった。何を知られている? 単に気取られただけか。それとも、本当に知られているのか。何かを見られたのか。他には誰が知っているのか。
照子は比呂人の指摘通りに、男が嫌いだった。いわゆる男性嫌悪症と言っても差し支えはない。その過去にも色々と原因はあるが、根本的に男性が苦手なのである。
嫌いだし、気持ち悪いし、近寄りたくない。それが本音だ。
しかし、ミサンドリストを自認するほどかと言うと、そうでもない。例えるなら「虫」だ。
簡単な話、不快害虫の代表である「ゴキブリ」が部屋に侵入して来たら、殺虫剤を持って、何としてでも殺しにかかるし、その死骸には触りたくもない。
しかし、街中にハチやトンボがいたとて、「近寄るな」とは思うし、避けはするけれども、自らわざわざ駆除したいとも思わないだろう。
ミサンドリストは自分から害虫を探してまで絶滅させたいような人間が多い。照子にはそこまでの攻撃性がない。自らの「男性嫌悪症」をどうにかしたいと思い、そう言ったコミュニティと接触した事もあったが、そこは狂信者の集いであり、照子の望むものはなかった。
だから、単にクールな人間を装う事にしたのだ。
仕事さえしっかりこなしていれば、仕事第一で生きているから、冷たくてつっけんどんな女なのだ、と思われるように振る舞った。
そして、それは上手く行っているのだと思っていたのだ。
それを「バレている」どころか「バレバレ」だと評されたのは、照子にとっては屈辱でしかない。
「普段からその失礼をブチかましてんは、あんたの方だっての」
比呂人が鼻で笑うように言う。嫌いなタイプの人間だったが、まっすぐで裏表のない性格だと思っていた自分を恥じる。こう言う陰湿で粘性の高い人物だったとは。
「いい加減にして」
先程の失態を取り戻すべく、比呂人に訳のわからない絡まれ方をした、という体で喫煙室を出ようとするが、比呂人の言葉が照子を足止めする。
「あんたにどんな事情があるのかまでは知らないけどね。職場の空気サイアク。とっとと消えるか辞めるか転職して欲しいぐらい」
「ぜんぶ同じじゃないの」
確かに照子は比呂人を嫌っていた。しかし、いつでも笑顔で爽やかな比呂人は、誰とでも仲良くする、空気の読めない「陽キャ」だと思い込んでいたのである。こっちが嫌っているのに仔犬みたいに纏わり付いているものだと思っていたが、よもやこれ程までに嫌悪されていたのは、嫌っている側としても衝撃だった。
「見たトコ、単に男がキライなだけで、レズごっこは出来ても、ガチレズって訳でもないだろ。女子校のノリが抜けねえの?」
比呂人の言葉に、脳味噌が泡立つのを感じる。録音していればセクシャルハラスメントで突き出せる内容だが、照子にとって、もはやそんな事はどうでも良かった。
見透かされていた事が、この上ない屈辱だったのである。
照子の恋愛対象は「男」ではない。当然だ。虫のように嫌悪している存在と恋に落ちるはずはない。かと言って、恋愛対象が女なのかと言うと、そうでもないのだ。
近年はLGBTだとか言って、セクシャル・マイノリティの存在や権利が声高に叫ばれている。しかし、照子にとってはどうでも良かった。
照子自身には、自分の性自認がはっきりとしないのである。
明確なのは大半の男が嫌いだと言うこと。不快な「虫」でも、蝶のように見る分には綺麗な虫もいる。蝶を綺麗だと思う感性は照子にもあるのだ。しかし、それも遠目に見る分に限る。
女子高生がキャーキャー騒ぐような、中性的で見た目の美しい男性アイドルなら、照子にとっても嫌悪感はない。あっても少ない。
しかしそれは、画面の向こうの存在としての話である。傍にいるとなると話が違う。美しい蝶ですら、間近で見ればグロテスクであるように、中性的な美男子でも、近寄ればただの男なのだ。
漫画や小説に出てくる理想的な「男性」ならば嫌悪感はない。けれどそれは人間ではなく、ただの登場人物だ。そこに入れ上げるほど夢想家でもなかった。
確かに、現実世界の照子には「彼女」がいる。
当たり前のように肌を重ねもしたが、照子の性自認が「男」と言う訳でもないのだ。
男が嫌いなだけで、自分が男だとも思わない。別に女に性欲を抱く訳でもない。何となく寂しさを紛らわせて、何となく慕われて、何となく性欲が発散できて、何とはなしに自分の存在が確立できているような気がしていただけである。
すべて、短く罵倒した比呂人の言う通りなのだ。
中学と高校は女子校だった。子供の頃から男性が苦手だったから、自分がレスビアンなのだと思い込んでいた頃がある。中学生の頃だ。
女子校だったから、周囲にも似たような娘は沢山いた。だから、女同士で付き合う事に抵抗はない。
しかし、高校生になった頃、周囲が皆、「レズごっこ」から卒業してしまったのである。
照子の周りには2人だけしか残らなかった。
おそらく環境的にレスビアンになってしまった同級生と、おそらく性同一性障害と思われる先輩だけだ。
同級生から真剣に愛を告白された時に、自分がレスビアンでも性同一性障害でもない事を思い知らされた。だが「ごっこ遊び」を卒業してしまった連中の輪にも入りたくはなかったから、卒業するまでレスビアンを演じた。
先輩の方は、おそらく性自認が男なのだろう。それなりに悩みはあったようだが、容姿や性格など環境的には恵まれていたと言える。幾人もの初心な中等部の女子を食い散らかしていた。
照子もその1人ではあったが。
だが、その先輩の性自認が「男」である事が、照子には耐え難かったのである。だから、途中から距離を取るようになったし、卒業を機に接触は途絶えた。
同級生とも、卒業で違う大学に進学して、そのまま音信不通になる。
大学に通い、そこで思い知らされた。照子は、何者でなかったのである。
自分は「男」でもなければ、レスビアンでもない。
それを生き甲斐に、憎んでしまえるほど男が嫌いな訳でもない。
性的な事に対して潔癖症な訳でもない。二次元のキャラクタに没頭できるほどオタクな訳でもない。
ただ、男が嫌いな、何者でもない女だと思い知らされたのである。
ハッキリしているのは、男が嫌いだということ。その感情を表に出していたつもりはない。仕事では全体的につっけんどんにしていただけだ。
見透かされていた事で、これまでの振る舞いがすべて幼稚な振る舞いだと思えてしまった。比呂人の他に誰が気付いているのかはわからない。だが、全員が気付いているかも知れないと思うだけで、それは恥辱に値した。
例えば、トイレの後、パンツがスカートを巻き込んで、尻を晒している事に自分だけ気付かないまま帰宅し、その事を知らされたような気分である。
誰のせいでない。強いて言うなら自分が悪いのだろう。だが、処理できない感情は他人にぶつけてしまうのが、一番手っ取り早い解決方法である。
「前川さんみたいな無礼な人は嫌いですけども」
だが、そう聞かされた比呂人は平然としている。まるで感情が処理できない。
「はいはい。あんたに嫌われても、あんたが男嫌いでも、女が好きでもどうでもいい。そーゆー感情を仕事に持ち込むなっての」
反省しようにも、当の照子にそんなつもりがなかったのだからどうしようもない。自分はただ、クールにしていただけなのだ。
「何も知らないくせに」
ヒロトを睨みつける。それがクールではない事はわかっている。そして、心の中で、悲惨な事件の被害者である自分の過去をでっち上げ、「だから男嫌いなのは仕方ない」と言う自分を作り上げる。だが、それは嘘だ。
照子自身、何処かで気付いているのだ。自分の男嫌いは、ただの我が儘なのかも知れない、と。
「わかっちゃうけどね。大した事がないことは」
パン!
比呂人の言葉が乾いた音に遮られた。照子の平手が頬に命中していた。だが、比呂人の口許からうっすらとした笑みは消えていない。
照子は何も言わずに、喫煙室を、そしてそのままカラオケ店を後にした。
・
飲み会は、金曜の夜だった。悶々とした気持ちで週末を過ごし、内心で怯えながら出勤した月曜。社内はいつもと変わらなかった。
どう考えても演技ができそうにない部下と接してみたが、自分の男嫌いが露見しているようには思えない。普段通りだ。
昼休みになってようやく、三次会の顛末を知らされたが、どうやら急に気分が悪くなって先に帰った事になっていたらしい。
しかも、会計は照子がかなり大目に支払って帰った事になっている。おそらくは全て比呂人が手配したのだろう。どうやら、引っ叩いた事はなかった事にされているようだし、照子の男嫌いを言いふらされてもいないようだ。
この日は何度か、比呂人とすれ違う事もあったが文字通りすれ違うだけで、特に言葉を交わしたりはしていない。特に接してはいないが、会社では従来通りの比呂人であり、照子を嫌っている様子も見受けられなかった。
どうにか接触を図って真意を問いただしてみたかったが、火曜から木曜までの3日間、比呂人は出張で不在。
金曜は自分が仕事に追われて、その機会を逸してしまった。
・
そして、夜。
あれから1週間だ。先週は楽しくもないカラオケ。今週は、楽しかったはずのパブである。そう、楽しかったはずの。
「どうしたの?」
騒がしい音楽の中、それでも鈴の音のような女の声が届く。隣にいる美也が、露骨に顔を覗き込んでくる。田村美也。照子の恋人である。強いて言うと「彼女」だ。
田村美也という名前も、本名かどうかはわからない。照子自身も、ここではショーコとなっている。
社内とはまるで違う服装で身を固めていた。正直に言えば、会社での服装も、今の服装も自分の好みではない。ここでも、そうあるべき姿を演じているに過ぎないのだ。
自分の、テルコという名前も嫌いだった。照らすと言う感じも嫌いだったし、テルコと言う響きも嫌いだ。
女子校時代、性同一性障害の先輩と何度か身体を重ねたが、彼女は自分が「男」だったので、必然的に自分が「女」の役割となっていた。照子はそこに違和感を感じていたが、だからと言って自分が「男」だと思った事はない。
しかし、性格も容姿も好みも、役割的には「男」が向いていると感じている。
美也とは、別のゲイ・パブで知り合い、その夜のうちに何となく性行為に至り、何となく付き合い始めたのだ。
この店も、美也に教えてもらった。
美也、という猫のような名前とは裏腹に、仔犬のように何処までもついて回る女だ。
猫のような、と言うよりは立場的には完全にネコで、明確に同性愛者だった。本物の彼女からすれば、照子、いや、ショーコの本質は見抜かれているのだろうか。
「別に」
気の無い返事をするショーコ。美也の事は好きだが、愛があるかと聞かれると返答に困る。単に、自分を好きてくれて、面倒も見てくれて、ついでに性欲まで満たせる都合のいい女でしかない。
見目も可愛らしく、甲斐甲斐しく世話を焼きたがる。レズでさえなければ引く手は数多だっただろう。いや、引く手が多かろうと、人を見る目はないのかも知れない。自分みたいな相手が恋人なのだから、と自嘲する。
「機嫌悪いの?」
「別に」
やはり、つれなく答えるショーコの唇を、美也の舌が舐め上げた。
そのまま舌を侵入させ、ショーコの舌と絡める。
ここはそんな相手同士が集うゲイ・パブ。キスしたぐらいでは誰も何も咎めない。
この店には、LGBTと呼ばれる性的少数者が集まる。
ゲイだけの店があるように、レズだけが集まる店もあるが、生粋のレスビアンではないショーコには居心地が悪い。
その点、この店は楽だ。ゲイもレズもバイもいる。そして、ショーコのような何者にもなれない存在も。
正直に言えば、この空間でさえ違和感を感じない訳ではない。だが、こう言っては悪いけれど、普通の社会に馴染めない連中が、ここで自分を曝け出しているのを見ると安心できるのだ。純然たるレスビアンでさえないショーコを慕ってくる女の子もいる。それは心地の良い事なのだ。
周囲を見れば、醜悪な中年体型をボンデージファッションで包んだ中年男性もいる。それは見るに耐えない姿だと思うが、その中身は犯されたくて仕方のないゲイの男性なのだ。そう思うと許せる気がしてくる。
自分が今、レスビアンが好みそうな服装に身を包んでいるのは、一種のコスチューム・プレイだと思っている。
この店ではおそらく大半の人間が本性を曝け出している事だろう。ショーコの場合は違う。レスビアンのショーコを演じる事で、本性を打ち明けられないストレスを発散しているのだ。
いや、ここにいる人間の何割かは、同じような事を考えているのかも知れない。
本当の意味では、ゲイのファションも、レズのファッションも理解は出来ないでいる。だって、好みじゃないんだもの。
でも、多くの人間はそうなのかも知れない。ゲイだから、このゲイ・ファッションにしなければいけない。レズだからピアスをしなきゃいけない。タトゥーをすれば仲間だと思ってくれる。
案外、ゲイやレズを名乗る連中だって、ただ寂しいから、この社会に溶け込もうとしてるだけなのかも知れない。
表の社会が生きづらいからって、こっちの世界なら生きやすいとは限らないのだ。
ただそれでも、表の社会で1人で生きていくのは寂しいから、裏の社会に溶け込もうとしているのかも知れない。
そこに、ピンク色の髪をした、全身タトゥーとピアスの女がいる。心底、アナーキーなファッションが好きなのかも知れないし、表の社会との決別という覚悟を、その身で表しているのかも知れない。ひょっとすると、リストカットと同じような自傷なのかも知れないし、ただ、注目を浴びたいだけなのかも知れない。
そこにいる、馬鹿でかいバニー・ガールの衣装を着た男が2人、いや、この場合はバニー・ボーイか。
1人は細長い色白な体型で、もう1人はボディビル・ジムに通っていそうなぐらい逆三角のアスリート体型をしている。2人ともドぎつい化粧で、漫画に出てくるオカマキャラクタそのものだ。この2人はカップルだろうか。いや、それさえもどうでもいい。
ここは不思議の国のアリスの世界だ。だから、どうでもいい。ここはそんな世界なのだ。
美也と舌を絡めながら、ぼんやり、そんな事を考える。
ここが自分のいるべき世界なのかどうかはわからない。自分がおそらくノンケである事は自覚している。だが、自分の性自認や性的嗜好に、何の不安も心配もない人間などいないのではないか。
美也が甘い酒を飲んでいたのだろう。文字通り甘い舌から、その甘みが消えてしばらく、
「ねえねえ、お姉さんたち、一緒に飲まない?」
最悪な現実が夢を覚ました。
ごく稀に、この店に紛れ込んでくるノーマルな連中だ。
実際、物珍しさや怖いもの見たさで、ゲイ・パブに足を運ぶノンケは確実にいる。
しかし、その大半は借りてきた猫のように大人しく見学して帰るものだ。残った半分も、楽しくは飲んで帰るが、まあ、二度と足を運ぶ事はない。
そして、ごく稀に、こういう勘違いした男が紛れ込んでくるのだ。
確かに、LGBTには性に奔放な人間が多い。特定のパートナーを持たない女もいる。集団でのセックスを好む男もいる。男でも女でも構わない連中だっている。それが一部でも、否定できない部分はあるだろう。
だが時折、この「性に奔放」の部分だけを拡大解釈し、いや、曲解と言った方がいいだろう、女をナンパできるんじゃないかと勘違いした男が現れたりもする。
その典型例がこれだ。今回は3人で、しかも見るからに酔客である。
「ねえ、聞こえたー?」
「間に合ってるわ」
ショーコは美也を隠すようにして、きっぱりと断る。
「そんなツレないコト言わないでさー」
「しつこい」
ショーコの判断は冷静だった。即座に店員を呼んで助けを求めるつもりでいた。しかし、生憎と週末の夜で賑わい、店員の姿が客に紛れて見えない。音楽も相当なボリュームで、ショーコの怒声ぐらいでは誰も気付いていないようだった。
「せっかく飲みに来てるんだしさ」
「そのせっかくを邪魔しないで」
3人がへらへらと笑いながら絡んで来る。ただでさえ男嫌いのショーコにとって、この3人は嫌悪の権化でしかなかったが、今はとりあえず、美也を守る事が最優先だ。
「一緒に楽しく飲もうよぉ」
「美也、行こう」
美也の手を引いて、席を立とうとするが、3人が壁のように行く手を阻む。
「お姉さんたち、ひょっとしてレズ?」
「馬鹿か、お前。こんな店にいるんだから、レズに決まってんだろ」
「俺らが男の良さを教えてあげるよぉ?」
「女同士なんて勿体ないじゃん」
男たちが口々に言う。囃し立てるように酒臭い顔を近付ける。
「くどい! 近寄るな」
ショーコが怒りを露わに怒鳴りつけるが、酔った3人相手では、事態を悪化させるだけだった。
男の1人の手が、ショーコの肩を掴もうとした時、
「ねえねえ、お兄さんたち、一緒に飲まない?」
それを阻んだのは、屈強な肉体の、2人のバニー・ボーイだった。
「げっ」
腕を掴まれた男が、漫画みたいな声で反応する。
「お兄さんたち、ひょっとしてノンケ?」
逆三角の方が満面の笑顔で問う。
「馬鹿ね、あんた。女の子を口説こうとしてるんだから、ノンケに決まってんでしょ?」
細長い色白が、オネエ言葉で答える。
「女相手なんて勿体ない」
「アタシたちが、オトコの良さを教えてあげるわよぉ?」
予め用意されていたコントのような遣り取りに、3人の男は毒気を抜かれて退散した。見たところ、1人は酔った勢いで喧嘩でも始めそうだったが、バニー・ボーイ2人の体格を見て判断したのだろう。
「あの、ありがとうございます」
一息ついたところで、ショーコが我に返り、慌ててバニー・ボーイに礼を言う。
逆三角の方が、ショーコに向けて歯を見せて笑う。
「いーのいーの。ま、あんなのにブチ当たったら、男キライになるのもわかるけどね」
そう言って筋肉質な背中を向けて去って行く。
数秒後、ショーコがバニー・ボーイの言葉に耳を疑う。
バニー・ボーイは異様な高身長だったが、ハイヒールを履いている。
去り行く逆三角の背中。そして、聞き覚えのある声。
「えっ」
思わず、素っ頓狂な声を上げるショーコ。
「どうしたの?」
美也が問う。
「別に」
そう答えるショーコの口許は、笑みの形に歪んでいた。
※ この短編小説はすべて無料で読めますが、お気に召した方は投げ銭(¥100)をお願いします。
なお、この先にはあとがきのようなものしか書かれてません。
ここから先は
¥ 100
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
(´・Д・)」 文字を書いて生きていく事が、子供の頃からの夢でした。 コロナの影響で自分の店を失う事になり、妙な形で、今更になって文字を飯の種の足しにするとは思いませんでしたが、応援よろしくお願いします。
