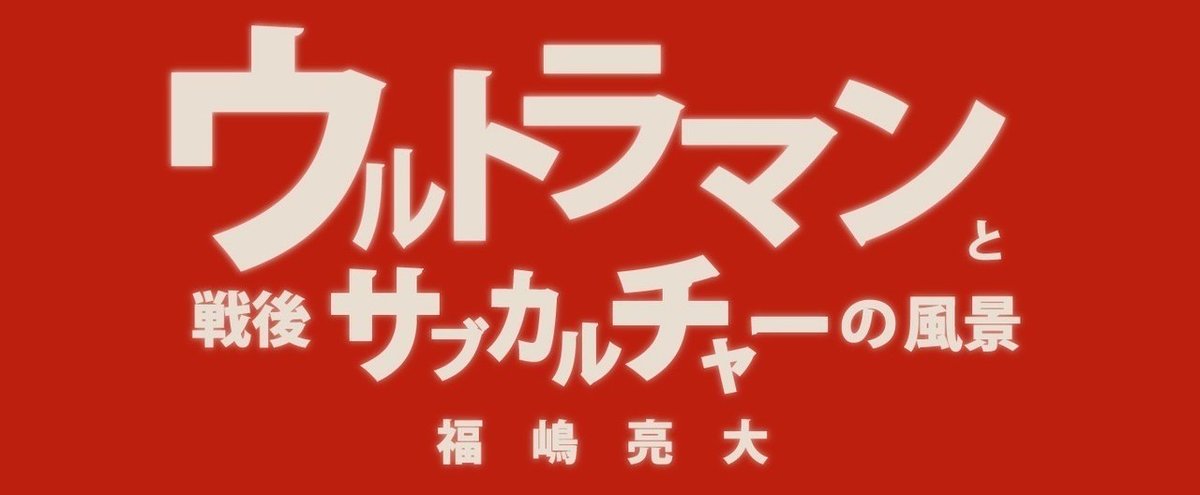
福嶋亮大『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』第六章 オタク・メディア・家族 1 大伴昌司のテクノロジー(2)【毎月配信】
文芸批評家・福嶋亮大さんが、様々なジャンルを横断しながら日本特有の映像文化〈特撮〉を捉え直す『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』。60年代末に大伴昌司が試みた、対象をヴィジュアル化・カタログ化する手法から、〈情報〉による世界把握の欲望の発生、そして後に全面化するオタク的想像力の萌芽について論じます。
情報論的世界把握の原型
このように、内田と大伴は「テレビの擬態」によって、六〇年代後半の『少年マガジン』を領域横断的な「総合雑誌」に変えた。後述するように、七〇年代以降の日本のヴィジュアル化した雑誌はファッション、音楽、アイドル、ポルノグラフィ等に機能分化していくが、『少年マガジン』はその分化の起こる一歩手前で、社会の「全体性」をカタログ化し、若い読者たちを教育しようとした。子供という宛先が強い文化的統合力を獲得したこと――、そこにこそ特撮も含めた戦後サブカルチャーの最大の特性があると言っても過言ではない。
ところで、大伴の強調した「情報」という概念は、世界把握の仕方そのものを変容させるものでもある。すなわち、情報論的な観点から言えば、世界はデータとして細かく分割できるし、また一度データ化してしまえば、そこに相互の関係性(メタデータ)を発見することもできる。有機的なまとまりを分解して断片(データ)の集積に変えた後、その断片どうしの関係から新たな意味を生じさせる――、情報社会ではこのような了解のステップが一般化するだろう(なおエドワード・スノーデンが告発したように、この了解の形式はそのまま大規模な「監視」の技術として展開されている)。
あらゆる対象を詳しくデータ化(解剖!)し、それらを大胆に統合する大伴の手法は、まさに情報論的世界把握の原型を示している。大伴が「オタク」の源流と言われる原因も、この情報の断片へのフェティシズムにある。なぜなら、後のオタクたちも作品の物語やメッセージ以上に、キャラクターの設定やデザインに強いこだわりがあったからだ。
例えば、東浩紀は一九六〇年前後生まれのオタク第一世代に見られる心理として、社会的には無意味なものにあえて耽溺するという「スノビズム」を挙げる一方、オタク系文化の主流が一九九五年頃を境にして、従来のスノビズムから、キャラクターの設定やデザインを集めた「データベース」の消費へと移行したと論じている。東の考えでは、九〇年代のアニメを代表する『エヴァンゲリオン』は「視聴者のだれもが勝手に感情移入し、それぞれ都合のよい物語を読み込むことのできる、物語なしの情報の集合体」として受容されていた[15]。
もっとも、このような現象は九〇年代に突然始まったわけではない。大伴の仕事はすでに六〇年代後半の時点で、スノビズムとデータベース消費の両方にまたがっていた。架空の怪獣の解剖図を真剣にでっちあげた大伴は、無意味なものに価値を与える「オタク的スノッブ」の典型だが、その「設定」へのフェティシズムにおいては、世界のデータベース的(情報論的)な把握を示す。現に、彼の『怪獣図鑑』はウルトラシリーズを「情報の集合体」に読み替えてしまった。現実も虚構も関係なく、あらゆる対象をひとしなみにヴィジュアルな情報として配列した『少年マガジン』の誌面もまた、情報データベースの原型だと言えるだろう。
「記録の時代」の編集者
ここから先は
¥ 540
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
