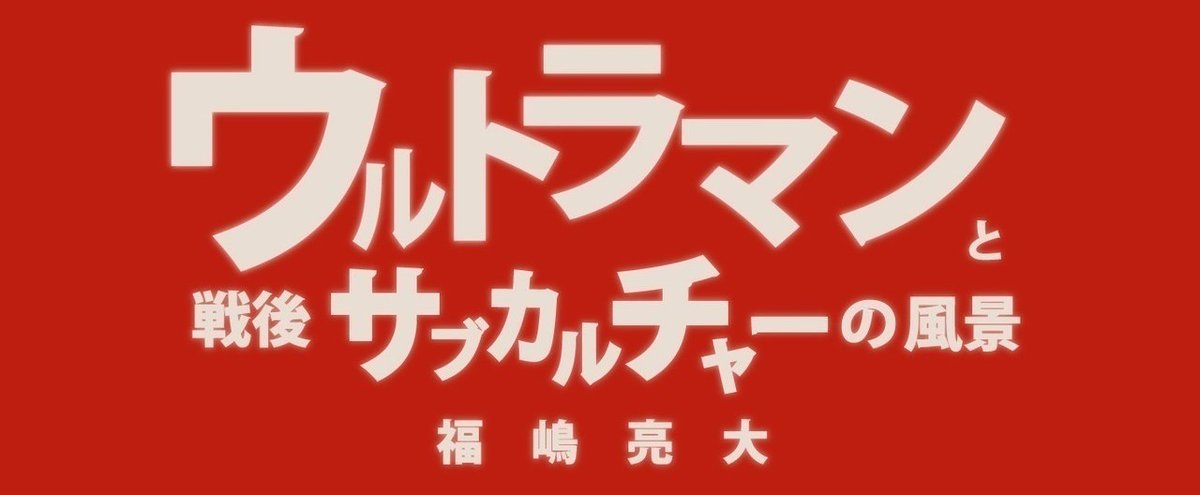
福嶋亮大『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』第四章 風景と怪獣 1 虚構的ドキュメンタリーの系譜(1)
文芸批評家・福嶋亮大さんが、様々なジャンルを横断しながら日本特有の映像文化〈特撮〉を捉え直す『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』。今回は、特撮において現実の風景と虚構の怪獣がどのように結びついてきたのかを、ドキュメンタリー映画として『ゴジラ』と『シン・ゴジラ』を分析することで明らかにしていきます。
第四章 風景と怪獣
特撮を中心にするとき、日本のサブカルチャー史は三世代の「共作」のように見えてくる。すなわち、一九〇〇年代生まれの円谷英二世代、一九三〇年代生まれの金城哲夫世代、一九六〇年代生まれの庵野秀明世代(オタク第一世代)。この三世代が一九〇一年生まれの昭和天皇、一九三三年生まれの今上天皇、一九六〇年生まれの現皇太子にそれぞれ対応することも興味深い。「雑草という草はない」という名言で知られる昭和天皇が生物学的な「メカニズム」の研究者であったこと、そして今上天皇が戦後民主主義の事実上の守護者として振る舞っていることは、ここまで論じてきた内容とも綺麗に符合する。
むろん、世代論は大まかな指標にすぎないので、それを盲信するのは愚かである。しかし、新しいテクノロジーや世界戦争とどの年齢で出会ったかが、作り手の立場をある程度方向づけてしまうことも否定できない。人間は自分で生まれる時代を決められない以上、世代には一種の強制性があり、その負荷は文化や技術との関わり方を規定する。実際、円谷の世代にとって戦争が総じて映画とともに「機械の眼」を進化させる場であったとすれば、金城の世代にとって戦争は総じて「子供の眼」から見られるものであった。
この世代体験はときにイデオロギーやジャンルの違いという敷居も超える。例えば、一九三二年生まれの石原慎太郎は、自伝的な短篇集『わが人生の時の時』(一九九〇年)のなかで、「戦争にいきそこなった子供たち」としての少年時代の自分が、米軍に空襲された際に「敵機の胴体に描かれたどぎつい極彩色のなにやらの漫画を見とどけた」思い出を語るとともに、長じてから鯨や熊のような「人間にはあり得ぬ巨きな存在」と出会ったときの感動を書き綴っている。石原の想像力は、海という広大な無機物に帰ろうとするタナトス(死の本能)とそれを反転させた「蘇生」の欲望だけではなく、人間を圧倒する怪獣的存在に対する恐怖と憧憬を含んでいた。その限りで、石原は政治的立場の異なる大江健三郎やジャンルの異なる金城とも決して遠くない。
改めてまとめれば、一九三〇年代生まれの若者が主導したウルトラシリーズは、映画とテレビ、大人と子供、モダンとポストモダン、戦争と戦後、飛行機と怪獣、前衛と娯楽といった文化的な接合面において成立したテレビ番組である。そこでは若い作り手と若いメディア(テレビ)の力に加えて、先行する世代と先行するメディア(映画)の遺産が大きな作用を及ぼしていた。加えて、ここで再確認するべきは、このシリーズが文字通り現実と虚構にまたがっていたことだ。そこでは怪獣もヒーローも飛行機も基地もすべて虚構のミニチュアであり、大人の社会性も希薄であったが、その背後には常に実在の風景が控えていた。それを踏まえて、私はアニメの人工的なセカイ系との対比で、ウルトラシリーズを「不純なセカイ系」と形容しておいた(第二章参照)。
現実と虚構をじかに重ね合わせることによって、ウルトラシリーズはアニメとは異なる独特の肌合いを獲得した。例えば、一九三七年生まれの実相寺昭雄はいくぶん叙情的な筆致によって、虚構の怪獣を現実の風景と同一視している。
わたしは“消えた”風景の空気感が『ウルトラマン』であり、怪獣たちだったと思う。とりわけ、怪獣たちは消えた風景そのものだった、と思わずにはいられない。わたしたちは、怪獣に、ある時代風景を投影してきたのである。[1]
私も実相寺に倣ってウルトラシリーズにおける「風景」と「怪獣」を等価なものとして考えたい。だが、その前に、そもそも日本の特撮文化がいかに現実の風景(自然物)と虚構の怪獣(人工物)を結びつけたのかを、言い換えればいかに「不純さ」を獲得してきたのかを、大まかに輪郭づけておくのがよいだろう。以下では、まず映画史における「虚構的ドキュメンタリー」という切り口を設定して『ゴジラ』のような戦後の怪獣映画、およびそれに先立つ戦時下の東宝のプロパガンダ映画を瞥見した後、それらのテレビ版の後継者としての昭和のウルトラシリーズの「風景」と「怪獣」について論じていく。そのなかで、私は「映画的怪獣」から「テレビ的怪獣」への推移を読み解くことになるだろう。
1 虚構的ドキュメンタリーの系譜
記録とモンタージュ
映画史の原点におけるリュミエール兄弟とジョルジュ・メリエスという対は、依然として重要な問題を私たちに投げかけている。奇術師にして興行師のメリエスの映画が「特撮」の起源だとしたら、シネマトグラフの発明者であるリュミエールの映画は「ドキュメンタリー」の起源だと言えるだろう。実際、当時の観客は、リュミエールの映画の主題以上に、カメラが偶然に記録した付属的な風景(木の葉の揺らめき、鉄工場の煙、汽車の蒸気……)に魅了されたと伝えられている。撮影者の意図を超えて、生命をもたない自然物までもが映像表現に参加してくること――、そこに草創期の映画のもたらした新鮮な驚きがあった。リュミエールを論じた映画編集者のダイ・ヴォーンは、この作り手のコントロールを超えた映像の生成力を「自生性」と言い表している[2]。
リュミエールの自生的な「現実」を評価する立場からすれば、映像の手品としてのトリック撮影を大々的に導入し、映画の産業化の道筋をつけたメリエスの「虚構」は、堕落した表現にすぎなかった。現に、リュミエール映画のカメラマンの一人は「現場で撮られた自然」を尊重する立場から、メリエスの特撮を「幼稚な幻想」と切り捨てている[3]。だが、その後の映画は、自然科学的な「記録」の媒体であり続ける一方で、モンタージュ(構成)やスクリーン・プロセス(合成)の生み出す「幻想」も手放すことはできなかった。私たちはここで、リュミエール以来の記録主義的映画観とメリエス以来の構成主義的映画観という二つの大きなプログラムを想定できるだろう。
この両者をどう折り合わせるかは、映画の理論においても大きな課題となった。例えば、今村太平は一九四〇年の『記録映画論』で、記録(写すこと)とモンタージュ(構成すること)は「あたかも分析することと綜合することとが思惟の二つの契機である如く、映画における思惟の二つの契機である」というユニークな見方を示した[4]。その一方、フランスの映画批評家アンドレ・バザンは一九五〇年代の論考で、「モンタージュの安易な用法を超え、世界を細分化することなくすべてを表現できるような」表現技法を追求したジャン・ルノワールやロバート・フラハティ、あるいはイタリアのロッセリーニやデ・シーカといった監督たちを高く評価した[5]。マンネリ化したモンタージュに対する批判として、ワンシーン・ワンカットの表現技法やイタリアのネオリアリスモに注目したバザンの理論は、五〇年代末以降、記録主義を復権させたフランスのヌーヴェルヴァーグの映画監督たちにも重要な指針を与えることになる。
ここから先は
¥ 540
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
