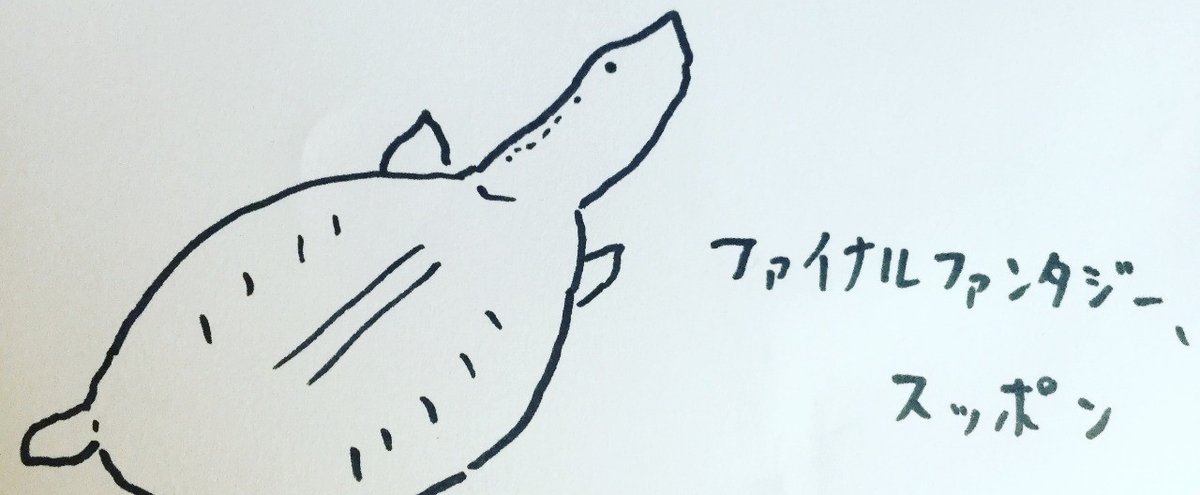
ファイナルファンタジー、スッポン
いまからおよそ四年前、私はスッポンのことばかり考えていました。スッポンによって、自分の人生を救おうとしていました。
その頃の顛末を、二年前、『カルチャーブロス』という雑誌に中篇ルポコラムとして掲載しました。夏の気配が近づく気候の中でまた読んでいただければと思い、ほぼ修正なしでここに再録公開いたします。
※スッポン獲りを楽しむ際は、無用なトラブルを避けるためにも、地域性などを十分考慮して、レジャーの範囲内で行うことをオススメします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ファイナルファンタジー、スッポン」
そうだ、スッポンだ。スッポンだけが、この苦しみから解放してくれるのだ。
それは稲妻に似た確信だった。まるで天啓だった。
窮し、閉塞し、追い詰められたこの状態。そこから私を、いや、すべての人間を救ってくれるのは、スッポンしかいない。私はごくりとツバを飲み、天を仰ぎ、感謝した。「神よ、この世にスッポンを与えてくれて、どうもありがとう」、と。
●
私は、「物書き」という仕事をしている。ルポやコラム、脚本などの執筆に従事することを自らの至上命題と定め、十年ほど前にこの文筆業の道を選んだ。まだ二十歳そこそこの若者であった自分は、未来に幸せな図を託していた。きっと将来、私は豊かな印税生活に身を浸していることだろう。ガウンを羽織り、暖炉の前でロッキングチェアに揺られながらウィスキーロックを呑み、次回作である大河小説の構想を練ったりしているのだろう。そして八歳になる息子に「そろそろお前にもグリズリーの狩りを教えてやらんとな」とか言っているのだろう。そんな、ソース不明の夢を、私は描いていた。印税によって多幸な生活を手に入れるのだと、鼻息を荒くしていた。
なんて愚かな青写真だったのだろう、と忸怩たる思いに駆られる。今現在、私は暖炉の前でウィスキーロックをあおりながら大河小説の構想を練ることなど、もちろんしていない。サイゼリアでミラノ風ドリアを食べながら八百文字程度のコラム原稿のアイディアをうんうんと唸り考える、それくらいが関の山である。
「本を出せば、印税生活が送れるんでしょ?いいなあ」。処女作であるルポの単行本を世間に発表する時、周りの知人友人たちからそんなことを口々に言われた。「いやあ、そんなに簡単な話じゃないと思うよ」などと謙遜はしてみせたが、実際には簡単な話だと思っている自分がいた。一冊出せば、三年は食べていけるくらいの印税を手に入れることができるだろう。勘だけで、そんな皮算用をしていた。たっぷりと時間をかけて物を創作し、それを世に送り出す。そして得た印税を元手にして、また時間をかけて執筆作業をする。なんと豊かで理想的な生活サイクルなのだろう。私は甘美な想像を巡らせ、うっとりとしていた。ところが銀行で記帳した「初めての印税」を見て、私は愕然とした。サラリーマンのボーナスにも満たない些細な額が、そこには刻まれていたのである。その時、私はやっと、現実の厳しさというものを知った。この世には、楽に食べていける生き方など、存在しない。ひとつの仕事にゆっくりと時間を割く生き方など、存在しない。印税生活など、夢のまた夢であったのだ。こうして私は、全てを諦めた。日銭を稼ぐために、どんな仕事でも受けるようになった。自転車操業的な暮らしの中で、お金のことばかりに囚われ、悩むようになった。そして周りを見渡し、改めて理解した。自由業であろうと、サラリーマンであろうと、この社会に住むほぼ全ての大人たちは、日銭の奴隷になっているということを。
月々十八万円が自動的に天から降ってくるシステムはないものか。そんなことを夢想するようになった。月に十八万円があれば、それだけで私は安定的な生活を持続させることができる。月に十八万円が自然と口座に振り込まれる、そんな素敵なシステムがあれば、私は日銭を稼ぐこの苦しみから解放される。もっとやりたいこと、書きたいことに時間を割くことができる。いや、私だけではない。空から月に一回、すべての人々の頭の上に十八万円が降り注ぐというルールさえこの世にあれば、誰もが幸せに生きることができる。サラリーマンが満員電車で地獄の苦しみを味わっているのも、私が目先の仕事ばかりに気を取られ余裕なく生きているのも、天から月に十八万円が降ってこないからだ。神よ、なぜ雨や雪ばかりが降るようにこの世をお造りになったのか。今からでも遅くないから、十八万円も降るようにこの世をバージョンアップしてみないか。
いや、こんな愚にもつかない願いを神に託したところで、どうにもならない。自分で具体的になんとかしなければ、いつまで経っても夢想は夢想のままである。こうして私はいつしか真剣に、「月に十八万円を簡単に手に入れるメソッド」はどこかにないものか、思案するようになった。
まず、現実的に考えてみた。天から十八万円を降らせる方法は、さすがにないだろう。それから、こんな仮説を立ててみた。「でも、月に五日間ほどの労働で、しかも肉体的にも精神的にも極力負担のない労働で、十八万円を稼げる方法だったら、もしかしたらあるのではないか」。根拠などまったくない仮説である。しかし、冒険はいつだって「そこに財宝がある」と信じることから始まる。信じなければ、桃源郷には辿り着かない。「たった五日間の楽な労働で、十八万円を手に入れる」。その方法さえ見つかれば、月の残りの二十五日間は自分の好きなことに使うことができる。旅や読書などのインプットに充ててもいいし、趣味の時間として活用したっていい、夢の二十五日間。もちろん、新作を執筆する時間としても充分なものであろう。
そうだ、「五日間のプチ労働で十八万円を得る」というメソッドを発見しよう。それさえ発見できれば、私は幸せに生きることができる。こうして私の、「生きるための冒険」が始まった。
まずは躍起になって、闇雲に情報収集を行った。ありとあらゆる職業の人を捕まえては「ねえ、たったの数日間だけで十八万円を稼げる仕事って、知らない?」「知ってるんでしょ?教えてよ」「教えてくれないと、大きな声を出すよ」などとデリカシーゼロな感じで、尋ねまわった。誰もが「そんな仕事があるんだったら、こっちが知りたいくらいだ」と答えた。それでも私はめげなかった。毎日毎日、求人誌をしらみ潰しに調べ、ライフハックに関するネットの記事を読み漁り、人生の抜け道はどこかに落ちてはいないかと血眼になって探した。本気だった。楽をして生きるためなら、いくらだって本気になれた。
私は子どもの頃から「蛇口からジュースが出てくればいいのに」とか「土が食べられたらいいのに」などといったことを、真剣に考えていた。そして、あげくの果てには「五日間の労働で十八万円を得る方法が世界のどこかにきっとあるはずだ」と本気で盲信する、十円のような大人になってしまった。そう、私は、切実に、真摯に、そして根源的に「楽をして生きたい」人間なのである。
その日も私は、友人たちが集う飲み会の席で、空気を読まずに「五日間で十八万円を稼ぐ方法について誰か知っている者はいないか」などと聞きまわっていた。友人たちは口を揃えて「そんなことを考えている暇があったら、仕事をしろ」という、至極まっとうなアドバイスを私に送ってきた。やはり今日も収穫はなしか……。私は本日のヒアリングを諦め、テーブルの隅でひとり打ちひしがれた。友人たちはそんな私を放って、それぞれの仕事の愚痴などで盛り上がりだした。するとその中のひとり、Tという男が突然「実はオレ、脱サラすることに決めた」と言い出した。私もその他の友人たちも、驚いた。なんとTは、長年勤めた会社を辞めて、この春から地方で農業をやることにしたと言うのだ。「それって食っていけるの?」という皆のシンプルな問いに対してTは、「まあ、野菜を作るだけだったら生活は厳しいかもしれないけど、他にも色々やろうと思って。猟師とかさ」。
猟師!
聞けばTは去年、狩猟免許を取得したのだという。というのも近年、地方は野生の鹿が増え、畑の作物を荒らすなどといった被害を農家にもたらしている。で、それに比例して、鹿を一頭駆逐すれば数万円を支払う自治体も増えてきている。そこに目をつけたTは農業の傍ら、鹿を狩ることを副業にするという生き方を試してみることにしたのだという。「お金にもなるし、自分の畑を荒らす害獣は具体的に減るし、一石二鳥かな、と思って」とTは笑った。この間まで口内炎がすぐできることくらいしか特徴のなかったTが、まさかそんなワイルドな人生設計を企てていたなんて。みんな、「お前、すごいなあ…」と感心の言葉をTに漏らしていた。しかし、私だけがひとり、違うことに気を取られていた。
(鹿を一頭狩れば、数万円になる……?)
その飲み会のあと、私は急いで家に帰り、ネットで害獣駆除について調べた。なるほど、鹿などの害獣を駆除することでお金をくれる自治体は、確かにたくさん存在する。アベレージは、大体一頭で二万円。私は頭の中のそろばんを一気に弾いた。鹿一頭が二万円になるとすれば、九頭で十八万円。つまり一日に二頭も狩れば、「五日間で十八万円を稼ぐ」というラインは達成できる…。希望の光が射しこんだ瞬間であった。私は興奮した。そうだ、鹿だ。鹿を狩ろう。月に五日間だけ鹿を狩り、生きていくのに必要な十八万円を手にして、残りの二十五日間を好きなことに費やそう。半芸半猟だ。それこそが、私の求めていた人生の抜け道なのだ。
しかし、一旦冷静になり、もう少し深く調べてみると、鹿の狩猟は思っているような楽な副業ではないことに気がついた。まず、罠猟にしても銃猟にしても、狩猟会に入るなどしてきちんとしたテクニックを身に付けなくてはならない。一朝一夕でどうにかなるものではないのだ。それに、鹿が現在日本中の山に増えているといっても、一日に二頭も獲れるようなことはまずないという。相当のプロでないかぎり、五日間で九頭もの鹿を狩ることは、不可能だろう。それに、そもそもが慣れない山での業である。肉体的にも精神的もきついのは明白だ。家の中に「血は吸わないけど、極端に蚊を大きくしたやつ」が入ってきただけで大騒ぎしているような都会育ち丸出しの私が、耐えられるような世界ではない。鹿は、私には、荷が重い。
あっという間に消えた希望を前に、私は落胆した。しかし、まだ完全には諦めがつかなかった。「狩猟」というキーワードには、まだなにかしらの金脈が潜んでいる気がしてならなかったのだ。鹿がダメなら、他の生き物はどうだろうか?たとえば、猪とか。いや、それも現実的ではない。猪は獰猛だと聞いている。アマチュアがおいそれと手を出していい獣ではないだろう。うーん、あと日本には、どんな野生の生き物がいただろうか…。タヌキ?イタチ?ウサギ?いや、ダメだ。小型の動物は高値で売れる気がしないし、動きが素早くて獲るのが大変そうだ。あと、どれも可愛くて、ちょっと気が引けてしまう…。
日本に生息していて、価値が高くて、誰にでも簡単に獲れて、あんまり可愛くない生き物…。
その時、頭に閃光が走った。
スッポンだ。
そうだ、スッポンがいたではないか。コラーゲンたっぷりでおなじみの、カメの仲間である、あのスッポンだ。スッポン鍋などは、高級料理として有名。天然物のスッポンであれば、高値で取引されているのではないだろうか。それに、他の生き物と比べても、簡単に獲れそうである。そしてスッポンは、ちょうどいい感じで、可愛くない。ウサギが「初孫」だとすれば、スッポンは「親戚のよっちゃんのところの次男」、みたいな感じ。YES、そこそこに情が湧かない。良い。その距離感が、獲る者と獲られる者の間には、必要である。
さっそく、図書館に行ってスッポンについて調べてみた。スッポンは日本中の沼や川などに広く生息しており、魚肉ソーセージやミミズなどを餌にして誰でも簡単に釣ることが可能であるという。イケる。すごく、イケる。私は胸の鼓動が高鳴るのを感じた。問題は、釣り上げたスッポンを買い取ってくれるところがあるのだろうか、そして買い取ってくれるとして一体いくらになるのであろうか、という点である。さすがに図書館には「スッポンの上手な売り方」みたいな本は置いてなかったので、続きはネットで調べることにした。「スッポン 売買」で検索する。すると、そこに驚くべきページが現れた。
「ニートだけどスッポン釣りだけで生計を立てて早半年が過ぎた」
そんなタイトルを掲げたスレッドが、2ちゃんねるに存在していたのである。もうすでに、スッポンに目を付け、夢を叶えている者が、この世にいたのだ。私は震える指で、そのスレッドを上からスクロールしていった。
そのスレッド主は、どうやら関西方面に在住している男性のようだった。タイトルにある通り、定職には付いていないが、スッポン釣りだけで月の生活費を稼いでいるという。その生活は、実にシンプル。一日に三~四匹のスッポンを釣り(そのくらいの数は容易に釣れるとのこと)、そして泥抜きなどをしたのち、料亭へと売りに行く。取引額は、小さいもので五千円。大きいものだと一万円。つまり、五日間も釣り糸を垂らしていれば、それだけで二十万円近くの稼ぎになる計算だ。
こんなに上手い話が、あっていいのか。
もちろん、2ちゃんねるは匿名性の世界。私は最初、このスレッドに書きこまれたことを、疑いながら読んだ。しかし、泥抜きとか料亭などといったワードから香る、真に迫ったディティール。それらに触れながら読み進めていくうちに、私は疑いを捨てた。そして確信した。このスレッド主は確実な裏付けを持ってして、これを書き込んでいる。つまり、スッポン釣りだけで生きている人間が、本当に実在する。
歓喜の念が、溢れた。そのスレッドが、眩く輝きだした。
私は、すごい発見をしてしまったのではないか。神は、天から十八万円を降らせる代わりに、この世界にスッポンを遣わせたのではないか。一日に四匹。そして一匹が、一万円である。「五日間で十八万円」は、もはや夢では、ない。
「キング・オブ・副業=スッポン釣り」という新たな仮説が、私の頭上に燦然と輝いた。
あとはもう、確証を得るだけである。はやる気持ちを押さえながら、私はその後もスッポンに関する入念なリサーチを進め、釣り具を買い揃えるなどし、川釣りのハイシーズンである夏を待った。そして蝉が鳴き始めたと同時に、魚肉ソーセージを握りしめて、西へと向かった。
●
四国の、とある川のほとりに、私はいた。地元の釣り具屋に遊漁料は支払い済み、スッポンがよく釣れるというポイントも聞き出し、準備は万端である。あとはスッポンを釣り、それを第三者に高値で売りさえすれば、私の説は立証される。夢は、果たされる。
釣り糸を垂らす。心臓が、高鳴る。さあ、スッポンよ。釣れてくれ。そして、豊かな未来の先へと、私を導いてくれ……。
川面に沈んだ釣り糸を眺めながら、私は高揚感に満たされていた。いま、歴史が変わろうとしているのだ。「真面目に働かなくては、生きてはいけない」。それが、この社会に生きる上で、我々に課せられた宿命である。その呪縛から解放されるための唯一の手段、それがスッポン釣りなのだと私はすっかり確信していた。月の内、たった五日間だけ、釣り糸を垂らし、スッポンを釣る。そして手に入れたお金で、残りの日々を悠々自適に暮らす。夢のような話が、いま、目の前に横たわっているのだ。自分の描いたファンタジーが、あと少しで現実のものになろうとしているのだ。高揚を感じないわけが、ない。
この抜け道メソッドに気づいた人間が、果たして世界に何人いるのだろうか。私は社会の盲点を突いたのである。これは、静かな革命だ。民衆よ、しばし待て!私がいま、スッポンを釣り上げ、それを金に換える。この革命が成し遂げられた暁には、皆もスーツを脱ぎ捨て、川へと走れ。そして、スッポンを釣るのだ。就職など、もうしなくていい。バイトなんかも、辞めてしまえ。スッポンがいる。この国には、スッポンがいるのだ!
私はすっかりナポレオンみたいな気分で、釣り餌にスッポンが食いつく瞬間を待った。
●
釣りを始めて、一時間が経過した頃だったろうか。突然、竿に強い引きがあった。「あれ?マジで?」。私は動揺した。いや、釣りに来ているのだから、当たりがあったのならもっと喜ぶべきなのだろうけど、なぜだか私は、ただただ動揺してしまった。うそ、え、釣れちゃうの?いや、いやいや。そう簡単には釣れないでしょう。これはきっと、ナマズとかザリガニとかでしょう。そんなことを思いながら糸を上げると、それは果たして、スッポンであった。
あれ?釣れてしまった。
指を噛まれないようにして糸を切り、釣り上げたそのスッポンをクーラーボックスへと放り込む。こんなにも呆気なく釣れてしまうものなのか。私は、自分で釣っておいて、なぜか引いていた。クーラーボックス内ではスッポンが、ぬめぬめと動きながら、冷めた目をしてこちらを見つめていた。「もっとリアクションしろよ、待望のスッポン様なんだぞ」とでも言いたげだった。私はどうしていいか分からなくなり、ただただそこに佇んでいた。
なぜ私は、本当にスッポンが釣れてしまった段になって、急にフリーズしてしまったのだろう。なぜ私は、あんなに渇望していたスッポンを前にして、突然に白い気分になってしまったのだろう。不思議なことに、さっきまでのナポレオン気分はもう私の中から消えていた。偽りなく告白すれば「やっべえ、マジで釣れちゃったよ……」というのが、この時のリアルな感想であった。
変な話だが、夢にまで見たスッポンを釣り上げたことで、なぜだかすごく「だるい気分」になってしまったのだ。あれだけスッポンに対して息を巻いていたのに、この急激なトーンダウン。なんだ、一体、なんなのだ、これは。
しかし、自分の気持ちの変化に説明を付けている暇などない。「このスッポンを売る」という次なるミッションを、実行しなければならない。私は遊漁料を払った釣り具屋へと向かった。「スッポンを釣ったんですけど、買い取ってくれるところとかって知りませんかね…?」。店員さんに、尋ねてみた。もちろん、そう簡単には販売ルートに辿りつけるわけがない。ここから、この冒険は最大の難所を迎えるのだと覚悟していた。ところが。
「ああ、それなら僕の知り合いがやってる旅館に聞いてみましょうか」。え?「そこだったら買い取ってくれると思いますよ。このサイズだったら九千円くらいになるんじゃないかな」。とんとん拍子すぎないか。九千円って。S席か。
「いや、やっぱりいいです、ごめんなさい」
気がつくと、私は店員さんにそう告げて、店を飛び出していた。
怖くなっていた。私はこの冒険にまつわるロマンや夢が醒めかけていることに、怖くなっていた。そしてこの時、私はようやく自分の不可思議な気分の変化の正体に気がついた。
私にとってスッポンとは、幻獣だったのだ。私にとってスッポンとは、ファンタジーだったのだ。
私はスッポンに、夢とか野望とかロマンとか、そういったものの一切合切を、託していた。「ニートだけどスッポン釣りだけで生計を立てて早半年が過ぎた」というスレッドは、私にとって幻の黄金郷を指し示す、冒険地図だった。その地図を頼りに、私は想像を膨らませた。この国のどこかにスッポンという生き物がいて、それが私の行き詰った生活に救いを与えてくれる…。そう、私の中のスッポンは、いつの間にか神格化されていたのだ。自分で作った仮説を、いつの間にか伝説の域までチューンアップしていたのである。
夏を待っている間、つまりスッポン釣りのことを想像している間、私はずっと、ワクワクしていた。どんなに鬱屈した日々を送ろうとも、どんなにルーティーンワークに溺れようとも、「いつかスッポン釣りがこの倦怠感を救ってくれるのだ」という信念さえあれば、生きていけた。それは塔に閉じ込められた姫が、「いつか王子様が迎えに来てくれる」という夢想だけを支えに生きる様に似ていた。私にとってスッポンとは、生きるために必要なイマジネーションの産物だった。
しかし、本当にスッポンを釣り、それを売ろうとしたその瞬間、想像が、現実へ変わろうとした。現実の谷底に落ちるその寸前で、「やっぱりいいです」と引き返したわけだが、危ないところだった。
やっと気がついた。私は、スッポン釣りで副収入を得ている自分を想像するだけで、もうすでに、救われていたのだ。
釣ったスッポンは、三日ほど泥抜きをしたあと、鍋にして食べた。とても美味しかった。鍋を空にすると、その先にはまたいつもと変わらぬ日常が待ち受けていた。明日からまた、日銭に縛り付けられる日々が始まる。
しかし、もう大丈夫だ。
また次の夏にスッポン釣りをしている自分の姿を、想像しよう。そして、スッポンをお金に変えている自分を、想像しよう。
来年こそ、私は「楽して生きる」抜け道を手に入れているのだ。そんな空想を広げるだけで、胸は躍り、次の夏が待ち遠しく思える。
私たちは、「ダメな日々」に囚われた姫である。歯医者の予約を当日キャンセルしたり、ちょっとの昼寝のつもりが長時間寝てしまって窓の外の暗さにプチパニックを起こしたり、金曜ロードショーのジブリアニメを結局は惰性だけで最後まで観てしまったり、通帳残高に一喜一憂したり。そんな「ダメな日々」に幽閉された、姫なのだ。そんな私たちに残された、唯一の救い。それは、夢想だ。私たちは夢想することができる。「いつかきっと楽になれる」と、夢想することができる。逃避行の旅へと連れ出してくれる王子様を、想像することができる。私の場合、スッポンこそが、その王子様であったのだ。
大丈夫、生きていける。私たちには、想像力がある。どんなに現実に虐げられようとも、想像力さえあれば、私たちは生きていける。
(了)
