
空間が人に与える影響
今日は、インテリアの家具配置や空間の作り方・人との距離によって、人が受ける影響についてです。
参考文献に挙げた本を読んで以降、改めて自分が設計する際にも意識するようになりました。
空間が人に与える影響
まずは基本的な概念から。
建築計画の分野でも距離によって、人との関係が規定される、という考えがあります。
距離の効果
・パーソナルスペース
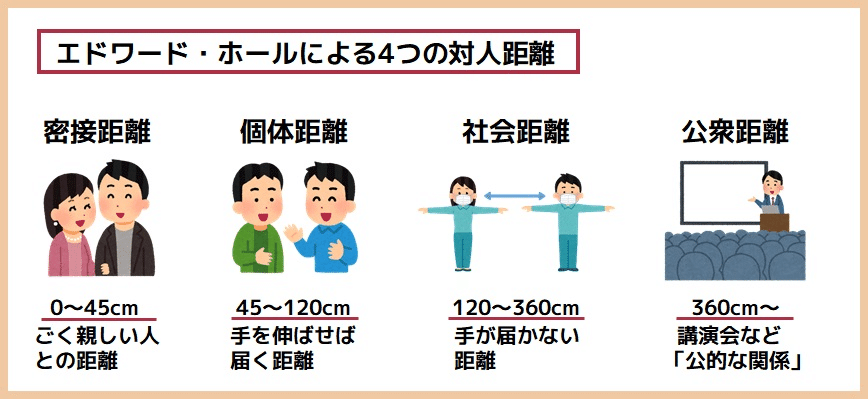
人は、他人が一定の距離よりも近づくと離れたいと感じるようになり、このような心理的領域をパーソナルスペースと言います。そして、アメリカの文化人類学者エドワード・ホールが「距離はコミュニケーションである」と言ったように、関係性によって距離は使い分けられます。
ホールは以下の4つの距離帯を提案しました。
・劇場

また、もっと遠い距離の場合にも、こういった距離の目安は図式のように提示されています。劇場利用の際等に、参考にしてみてください!
向きの効果
・ソシオフーガル・ソシオペタル

また、関係性によってここちよい人との向きも変わってきます。
カナダの精神科医ハンフリー・オズモンドは、親しいものが向き合うように座る状態をソシオペタル、他人が向き合わないように座る状態をソシオフーガルという言葉を提唱しました。
こうして、人の関係によって心地のよい距離・向きは変わります。逆に言えば、家具の距離や向きによっても人との関係が変わるのです。
ここからは、住空間のデザインについてです。
住空間のデザイン
ここからは実際に住宅の計画ではどういった考えに適応できるか、といった内容をまとめていきます。
参考文献に記載した『ちょっと変えれば人生が変わる!部屋づくりの法則』を参照しているので、良かったら見てみてください!
①家族との関係をコントロールする
家族関係を良くするためには、一緒に過ごせる場所 / 一人でいれる場所の2通りの過ごし方に対応できる場所を作ることが効果的です。
1) 家族で過ごしているときに安心して過ごせる場所
・会話は3.6m以内で(遠いと言葉尻がきつくなる)
・3~3.5mの円周上にいると一緒に過ごしている共有感が生まれる
・子供部屋を、子供が家族に会わずに自室に行ける1階や離れに置かない
・家族が集まる習慣を持ち、皆で楽しく憩える場所を作る(集まる場所の共通認識をもつ)
2) 一人になりたいときに自由に過ごせる場所
・誰でも「一人の時間」をもつ居場所が必要
→部屋でなく家具でもよいので各自のコーナーをもつ
・引き戸など、子供が親との距離感を調整しやすい仕掛けを持つ
②環境を整える
家族との関係だけでなく、自分の家を自分のための空間として整えることも大切です。前向きになりたいときや、気分を変えたいときに部屋から変えるのもおすすめです。引っ越しもその一つかと思いますが、まずはインテリアからでも。
これから前向きになりたいとき
・脳のエネルギーを効率的に使うため、部屋の情報を減らす(=片付ける)
・気分が上がるもの、自分が向かっていきたい理想のイメージ等を置く
集中したいとき
1) 集中できる仕掛けを環境を作る
・人に見られない作業場所を作る
・デスクは入り口から遠い位置に、入り口に向かって座る
・人に見られないよう、衝立・植物を置く
・情報を減らす
・動くものを視界に入れない
・部屋の中の色味を揃える
・デスクの前に衝立を置く
2) 適度にリフレッシュできる環境を作る
・緑・景色
・緑視率が10~15%になるように緑を取り入れる
・景色のよい窓前に机を置く
・光環境
・勉強・仕事は日中の明るい時間か青白い光の下で行う
・場所を変える
・勉強・仕事に集中する特定の場所を決める
・気分転換ば場所を変えて、集中する場所ではダラダラしない
・クリエイティブな作業は解放感のある空間、タスク作業は天井が低く小さな空間で
片付け
上記に部屋の情報量を減らす(片付け)を書いていたので、そのコツについて。忙しくなったりすると部屋が散らかったりしますよね。
そういったときは心が満たされていないサインなので、まず欲求を満たすことが大切です。
また、片付けるため(収納にものをしまうとか収納の位置とか)のアクションを減らして、片付けるためのアクション数を減らすのも重要です。
参考文献
・『ちょっと変えれば人生が変わる!部屋づくりの法則』高原 美由紀
