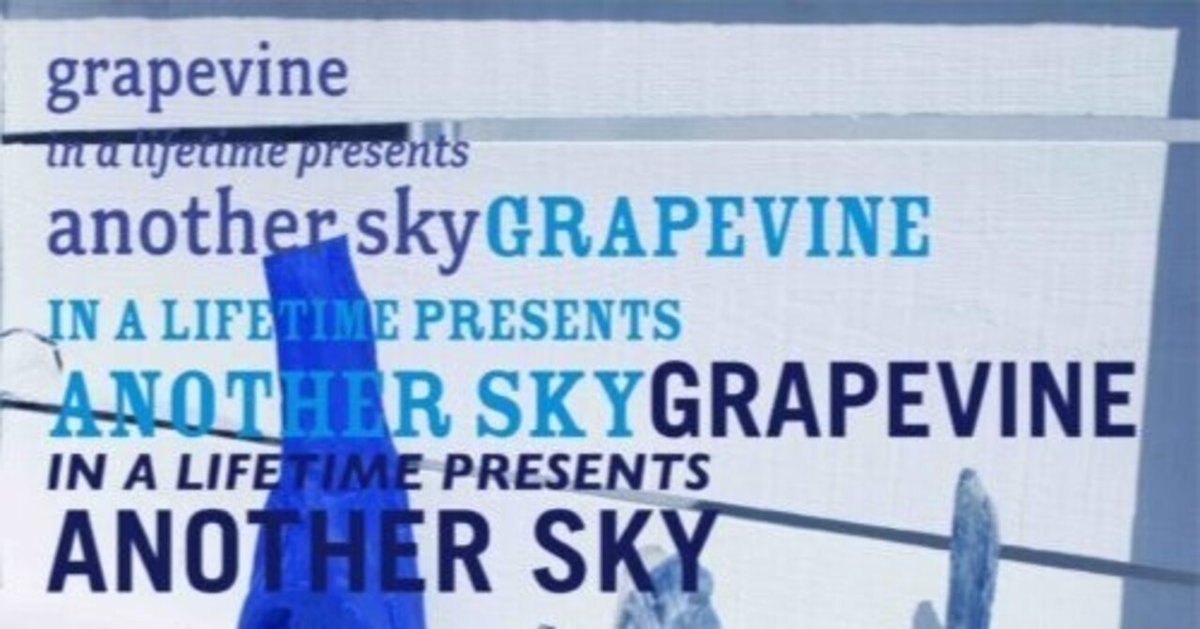
“いつかはきっと あの向こうへと 精一杯息をして” -2022.7.23. GRAPEVINE at 福岡DRUM LOGOS-
GRAPEVINEが今年7月より行っているツアー“IN A LIFETIME presents another sky”。メジャーデビュー25周年、そしてアルバムリリースから20周年を踏まえて5枚目のアルバム“another sky”をフィーチャーし、アルバム全体を再現するライブを展開している。
自分は7月23日の福岡DRUM LOGOS公演に参加したが、その内容の素晴らしさに交えて当日の自分の気持ちを記し残しておきたい。GRAPEVINEの音楽は、いつだって諦めが前提で聴き手に対してそっけないほど現実を突きつけるが、その現実と戦っている弱き者の傍にいてくれる。その得難さがまた一際感じられた一夜。

そうした感触はコロナ禍以降の彼らのライブにおいて、よりわかりやすくより強くなっているような気がする。それを慈しみと表したら「わかってねぇなぁ」と田中和将に鼻で笑われそうな気がするが、この日感じたのはそうした温かさと音楽の醍醐味である。その辺りを中心に今のバインの在り方の強さを語りたい。
※自分の気持ちを綴るのがメインであり、ライブレポートとしてマトモな内容ではないので、それを考慮いただいた上物好きな方は約10000万字お付き合いください
・コロナ禍以降のGRAPEVINE
GRAPEVINEの活動スタンスは極めてアナログなモノで、25年も活動するベテランながら未だに2年に一枚はアルバムをコンスタントにリリースし、その度ツアーをしっかり回る、ロックバンド然としたもの。
パンデミック以降ライブ活動の自粛を余儀なくされ、新たな活動方法を模索するバンドも多い中、(リモートなど試すことを考えたが)どれもはっきりといいイメージを自分たちのなかで描けない以上は動かないことを選択したのも彼ららしい。
その読書量の蓄積から生まれる文学性の高さから、日本語の歌詞を書くことにおいて高い評価を得ている田中が、かの文學界に寄せたエッセイでこの期間に対する見解をその類稀なる文字運びで綴った。それがついに高校の教科書に採用されるというまでの流れは、長年のバインファンなら嬉しさこそあれ驚きはしなかったと思う(やっとこの人の言葉を操る力に世の評価が追いついたかという笑)。
元来から弱者の目線で世界を歌ってきたGRAPEVINEの曲は、本人たちは至って描くことを変えてないにも関わらず、閉鎖的空気が一気に露わになったこの社会ではあらゆる人にとってリアリティを伴い始めたのか、21年リリースの最新作“新しい果実”はいつも以上にファン以外にその魅力が届いている印象がある。
音楽の内容としても、ここ数作はファン以外には一枚目として進めにくい間口の狭さがあったが、久方に「GRAPEVINE入門」としても進めやすい受け皿の広さがあって、新しい魅力と同時に決定版的な充実作となった。
ライブにおいても、このアルバムのリリースより前に20年の秋にパンデミック後初のホールツアーを行い、元来から「ファンとの一体感を求めたコール&レスポンスなど行わない」「オーディエンスがモッシュやシンガロングを起こすような曲などない」「MCもほぼなく、ひたすら演奏を見せつけられるだけで満足させられてしまう」燻銀のライブスタイルは、コロナ禍におけるライブ鑑賞と完全なシンクロを果たしていた。
そうした物理的条件も含め、コロナ以降のGRAPEVINEのライブは「頼もしさ」そして「温かさ」を以前よりも感じるようになった。彼ら自身、人前で演奏することが当たり前の人生を送ってきた中で初めて、それを封じられてしまった期間を過ごして、ライブをすることの重みや尊さを感じているのだろう。
その演奏は以前にも増して真摯で強い響きを携えていたし、田中のドライなジョークに今まで以上に愛を感じてしまうものだ。それこそ“超える”で「今限界を越える そのくらい言っていいか」→「そのくらい言ってゆけ」と背中を押してみたり、“すべてのありふれた光”で「君の味方なら此処で待ってるよ」と手を広げながら歌う姿は以前から変わらないことだが、同じその光景が何倍も温かく感じるのだ。
・過去作の再現性の是非
自分がGRAPEVINEに出会ったのが、今から15年前(中学生卒業)のタイミングでリリースされた“From a smalltown”で、現在30歳に至るまで人生の半分を共に過ごしてきたことになる。通っているライブの本数はDIR EN GREYの方が多いが、そこに並んでGRAPEVINEもほぼ欠かさずバンドヒストリーの過程を目撃してきた。
ただ、もちろん“From a smalltown”以前のアルバムは当然ながら後追いであり大きな思い入れはない。リアルタイムで経験できなかったモノを経験できる機会はとてもありがたいが、あらゆるベテランバンドが過去作をフィーチャーする企画の多くは、サービス的なモノであり「見る側の思い出補正」による満足感が大きく、演者側も乗り気でないゆえに正直物足りないことも多い。
そして、そもそも「最新型が一番かっこいいバンドしか好きでいられない」自分にとっては、過去作の再現なんてしないでくれていい、とすら思ったりする。しかしそこは我らがGRAPEVINE、過去作再現において彼らをその他大勢と同じ物差しで測るのは愚かだと示してくれる出来事があった。
彼らは既に一度過去作再現ライブを行っている。出世作であり世間的に一番認知度の高いセカンドアルバム“Lifetime”の再現ライブだ。自分はこの時先述の理由からライブ参加をスルーした。過去作再現・それも一番ヒットしたアルバムとなれば「ファンサービス」的な意図を感じたし、自分としてはLifetimeに対して後年のアルバムほど魅力も感じていなかったからである。
だが後にライブ映像を見て度肝を抜かれた。そこで演奏されていた“Lifetime”の曲たちは、まるで原曲とはかけ離れた圧巻のクオリティで魅力的なモノへ化けていたのだ。最早新曲として聴けるほど新鮮ですらあり、遠く時代の離れた近年の曲たちに混じって演奏されても違和感がないような、GRAPEVINEの新たな側面にすら思えた。
それだけ彼らが長年積み重ねてきた演奏力や音楽観をもって“Lifetime”を再解釈したことが大きいのは間違いない。特に田中和将のボーカルは、かろうじて原型の匂いを残しつつも最早「女が男に変わったのか」というぐらいの振れ幅で別人に聴こえるから、その進化の凄まじさや長い歩みの歴史の重みに感動を覚えるのだろう。
しかしそれ以上に大きな発見だったのは、彼らがメジャー2枚目(年齢は30歳手前頃か)の時点にして、こうやって約20年後にアップデートされた感覚で演奏されて、それに応えうる進化の余地を持ち合わせた曲たちを作っていたという事実である。
メロディやコード進行も若干懐かしい感覚もありながらも古臭くはなく、田中が書いた歌詞に至っては40歳を超えたこの時点の彼が歌ってしっくりくるものすらある。ベテランに至った彼らが演奏して然り、ぐらいのポテンシャルを持ったアルバムだったのだ。
・another skyというアルバムへの見解
自分が然程期待してなかった“Lifetime”ですら、再現の面白さを見せつけてくれたGRAPEVINE。ともすれば他の過去作再現も見てみたくなるところ、私的に初期作で一番気になっていたのが今回企画の“another sky”だった。
GRAPEVINEは、過去の自分が読んできたインタビューの範囲でも「昔は音を埋めがちだった、長田さん(アルバム“deracine”から“真昼のストレンジランド”までの中期をプロデュース、かなりGRAPEVINEの変化に大きく影響を与えたギタリスト)に“もっと隙間を活かせ”とアドバイスされた」といった発言をしている。
それだけ濃い演奏をしてきたバンドだし、田中自身「歌も楽器の一つとして機能させる方を重視していたから、歌詞も音に自然に混ざる響きを重視して日本語だけど英語的に聴こえるようにしていた」と語っている。ファーストアルバム“退屈の花”の時点で、若手バンドらしい粗っぽい簡素なアレンジは一切なく、既にベテランかのような渋く緻密なアレンジを組んでいる時点であからさまである。
そんな中で“another sky”は初期の中で唯一、演奏に隙間が多く、風通しが良い歌モノが多いアルバムである。中期で田中のボーカルアプローチを中心に大きな変化が見られ、転換期となったと思われる長田進プロデュース作“Sing”に通づる、間を活かした表現に取り組んでいる印象がある(アートワークが寒色中心なのも共通している)。
当時のバインはこのアルバムに対して満足したのか、それともこの路線の取り組み方に力不足を感じたのかはわからないが、次作“イデアの水槽”は、それまで大きな支えとなっていたであろう根岸孝旨氏のプロデュースを離れ、セルフで取り組んだ結果、その時点で一番音数の多い濃いアルバムとなっている(今聴いてもanother skyの次がイデアの水槽なのはどう聴いても信じられないぐらいの振れ幅である)。
この時期、結成メンバーであるベーシスト西原誠氏の(病気でのやむを得ない)脱退も影響し大きなターニングポイントとなっていた(現在の5人編成のメンバーである金戸覚・高野勲の両人の参加が本格化してきていた)時期でもある。その境遇が密度の濃い音楽の方向へGRAPEVINEを駆り立てたのかはわからないが、少なくともanother skyのような方向性の取り組みは当時この一枚きりだった印象である。
つまりは、another skyは彼らの中でも稀有な立ち位置のアルバムであると思うし、彼ら自身がその内容に肯定的であろうと否定的であろうと、“Lifetime”再現で見せたような面白味で今回の再現もまた価値の高い内容になるであろうことは確信していた。特にSing以降“引き算の美学”を国内屈指レベルで極めていったバインが、今一度このアルバムに取り組む面白さ。
核となる大曲“アナザーワールド”は、大切なライブでは都度披露され続けているが個人的に聴けたことがなかったし、シンプルな歌モノロックのなかで“マダカレークッテナイデショー”というゴリッゴリなファンクナンバーが混ざっている良い違和感。
“それでも”や“Colors”といったこのアルバムのカラーを印象付けているスローナンバーは田中&高野によるアコースティック編成“Permanents”名義のバージョンしか聴いたことがなく、本家バージョンを初めて見ることができる。少し挙げてみただけでも見どころの多いライブになることは間違いなかった。
・2022.7.23. 福岡DRUM LOGOS①メロウなスロー曲に酩酊する中盤
不手際で到着が遅れてしまい、着いた頃には“マダカレークッテナイデショー”でソウルフルにシャウトしている田中がいた。本当、コロナ以降でライブ見る際の彼らは気持ちいいぐらいに「ライブをしている楽しさ」が伝わってくる。その混じり気のない純なエネルギーは見ている側を笑顔にする。
去年の“新しい果実”リリースツアー初日で自身初めて訪れたのと同じ会場のDRUM LOGOS。昨年は椅子が用意されてソーシャルディスタンスが設けられていたが、この日はスタンディング。皆が思い思いに体を揺らしているし、歓声も時々上がる。ライブ会場ならではのこのヴァイヴは、見る側の自分にとっても近頃は得られる機会が貴重でホッとする。
この日大きな目的のひとつだったバンド本家アレンジによる“それでも”と“Colors”のスロー曲ゾーンが始まる。西川アニキのテレキャスターの音の良さが際立つ。新しい果実曲でも頻繁に披露しているが、彼は本当に少ない音数のアルペジオの説得力が凄まじい。多少ギターを弾けるようになったから痛感するが、こういうプレイが結局一番難しい。
“それでも”の、日常を柔らかく切り取ったような目線に年齢的にも成熟した田中が歌う良さが、同時にどこか遠い世界に意識を奪われて揺蕩うような“Colors”との対比となり酩酊感をより強めた。この曲の主人公の立場は普通に考えたら悲しいのだが、この美しさに浸れるならこの痛みと共に在ることを受け入れてしまうほどの。丁度自分の子供みたいな我儘な望みに苦しんでた時期だからあまりにも刺さった。
“マドモアゼルの背中を見送る彼はただの未成年
曖昧にして稚拙な祈りでした”
バンドアレンジのColorsは、リズム隊によって意外なほどタイトな響きがある。コロナ以降、ライブを見るということの非日常感の理由を再確認することが多いが、それは音を耳ではなく体全体で浴びる感覚に尽きる。特にベースはそこに音源との圧倒的な差があって、この曲での白玉一発のベースはそれはそれは心地よいものであった。
そこにKing Crimsonのロバートフリップばりのロングトーンによる音響プレイを聴かせる西川アニキがこの時間帯の夕景にシンクロするようにノスタルジックな景色へ誘う。エンディングではそのままアドリブのギターソロの嵐が、Permanentsアレンジでは味わえないほどの感情の昂りを描いてくれた。やはり、この再現ライブはただの再現ライブではない。
・2022.7.23. 福岡DRUM LOGOS②王道ロックソングが続く後半戦へ
“Tinydogs”から“Sundown and hightide”まで続く比較的ストレートなロックソングのゾーンは、歌詞の言葉選びが当時ならではの若気の至り的な響きがあり、そのヒリヒリとした質感に対して、今のスキルによる磐石のグルーヴでタイトな魅力が増した演奏と田中のボーカルとのズレが良い意味での違和感を生み出していた。
バインの近年の曲にはこうしたノリの良さはなかなかないし、同じ盛り上がりでも最近の曲、例えば“リヴァイアサン”は歌詞の目線がどう見ても親父世代からのモノだし明らかに聞こえ方に違いがある。しかし音数の少ないアレンジというのは共通していて、それゆえの良さを現在のGRAPEVINEは的確に引き出していて素晴らしい。
ただ正直言って“ナツノヒカリ”は流石にちょっとニヤリとしてしまった(これが良いか悪いかは人それぞれだが、自分にとっては面白さが勝ってしまう感じでした、申し訳ない)。こういう胸キュン的な内容の曲を、1周どころか3周ぐらいした親父が歌うとそれはそれで別のキュンが生まれてくるというか笑。
・2022.7.23. 福岡DRUM LOGOS③ついに響いたアナザーワールド〜アルバム再現の終幕
そして、待ちかねた“アナザーワールド”である。タイトルからしてこのアルバムの核であるし、今も重要なライブで最終盤に引っ張り出されることがある辺り、彼ら自身にとっても大きな意味を持つ曲なのだろう。
自分もこの曲に関しては思い入れがとても強い。思春期の多感な時期にGRAPEVINEを好きになって、その時点までの全アルバムを辿って。膨大な数の曲の中で特に強い印象を残した曲のひとつだった。秋の夕暮れの肌寒さのような、隠せないような寂寥感のモノが充満している。うつで高校を中退したあの秋、この曲を聴きながら沈む夕日を何度眺めたかわからない。

GRAPEVINEの曲に安直な解釈は野暮であるが、自分はこの曲にやはり“死と明日”というモノを重ねて聴いてしまう。向こう側の世界とは安らぎなのか、そしてそれは危うい思想なのか、それとも明日への希望なのか。
前向きにも後ろ向きにも取れる絶妙な塩梅のコード感と言葉選び、そして切実な田中の声。原曲録音時の中性的な声質は脆弱にも聴こえるがその分高まる焦燥感が胸を打つし、近年のライブ音源で聴ける大人になったその声で聴くと「痛みを知る者の目線から見守る歌」で優しくもある。
正直に言って、この日はこのタイミングでこの曲を聴くために急遽参加を決意した(元々は今回のツアーは9月25日の大阪城野音のみの参加を考えていたのだが)。というのも、6月に自分が長年目標としてきたことを終えてから燃え尽き症候群となり、久しぶりに酷い鬱症状に悩んでいた。結局のところ自分は普通の人では居られないという事実を突きつけられた。
そしてこの状況を変えるために、自分がずっと望んできた「普通の人なら手に入るはずのありふれた幸せ」をついに諦めることになった。そんな自分を受け入れることでしか前に進めなかった。でもそうやって前に進もうとする今の自分にはライブの“アナザーワールド”が間違いなく必要だと思った。
そんな自分の胸中など知るよしもなくサラリと演奏が始まったが、こちらはもう歌い出しから込み上げてくるものを抑えるので必死だった。イントロの寂れた音で、あの夕景が、肌寒さが一気にあの時の自分を連れ戻す。
“だけど空に届きそうで また手を伸ばして 止めて
明日もう一度 いつかはきっと あの向こうへと
精一杯息をして もう いつの間にか僕らには見えやしない”
1サビが終わった時点でマスクの中が人生で一番洪水状態になっていた。確実にあの頃の自分、そしてそれ以降折に触れてこの曲を聴きながら夕日を眺めた瞬間が脳内を駆け巡る。でも田中の声が当時の何倍も強く優しいように、自分もそんな過去の自分と再会する側に成長していたことを実感する。
そして、大きな挫折とありふれた夢を諦めてでも前を行くことを決断した自分を讃えてくれるかのように、この日の“アナザーワールド”は確かに背中を押してくれる歌だった。この音楽が鳴っている間は自分がそのまま存在していいと思わせてくれたし、長い間消えていた生きる衝動や叶えたい夢が蘇っていった。
“甘えちゃいけないとは言い切れない
君は意外と何も言わずとも しっかり前を見てる
君がいないと なんにもできないと はっきり言えないで”
その後にアルバムを締める“ふたり”は、“それでも”と並んで、田中が描く生活感、そこに潜む非日常や感情の移ろいを絶妙に切り取る。“ふたり”というタイトルで“ひとり”の苦い胸中を描いてみせる。
別れの刻が訪れる前から、男とはこうした未来の予感を抱いていて、それでも何となくそうした最悪の結末は起きないのではないかと楽観的でいたい生き物。それが相手の優しさに甘えてるという重さを、実のところわかっていない。というより、わかることから逃げてしまう。それ故に迎えるほろ苦い未来を何度経験しても。
“マリーのサウンドトラック”を最後に持ってきて、エンディングから始まる映画だったかのような構成で本編が終わる。原曲を聴いていた時には抱いてなかった、ノイズロック的なバンドとしての大きなスケールで、ダウナーな終盤の2曲を拭い去るように終わっていく。今のGRAPEVINEの表現スキルで描かれる“another sky”は、少し苦くて甘いロマンス映画のようだった。
・2022.7.23. 福岡DRUM LOGOS④ 磐石のグルーヴを見せる2部
原盤の“another sky”だけでも50分以上の収録時間があり、それを再現した第一部を終えた上で、ここから全時代から満遍ない(かつ、彼らのワンマンライブらしいマニアックな)選曲による2部がスタート。アラフィフにもなって2時間を超え、25曲近く演奏してくれるGRAPEVINE、ファンとしては嬉しいものである。
しかもその仕切り直し1曲目がHereから“想うということ”である。これまた人の波の中で自分を見失っていた自分には刺さる選曲である。以降、歌をじっくり聴かせる曲より横ノリのグルーヴでオーディエンスを揺らすライブ然とした演奏の曲を多めに展開していく。another sky本編との対比も意識されているとおもう。
しかしLifetimeの次にanother skyを再現したということは、おそらく“Here”と“Circulator”の再現ライブが行われる予定はないのだろうが、その辺りの配慮があるのか2部で はHereの曲(コーヒー付きとScare)が演奏されたり、another skyシングル曲のカップリング曲(R&RニアラズやSTUDY)が演奏されていたりもした。
そこに最新作から“さみだれ”の円熟した歌モノの聴かせ方、すっかり新しいライブの主戦力となった“ねずみ浄土”の間を活かしたグルーヴ、久方にシリアスサイドオブGRAPEVINEを具現化した“Gifted”が加わり、キラーチューンである“CORE”も重なって(こういう曲がライブ代表曲になるのもGRAPEVINEらしい魅力)磐石のライブを展開する。
・2022.7.23. 福岡DRUM LOGOS⑤未来を感じさせた最後の2曲
そして2部の締め、アンコールの流れがまた個人的心情にシンクロした美しい瞬間だった。近年は20周年時に発表したシングル曲“Arma”をライブの締めに演奏することが多かった。バンドのこれまでの歩みと、これからの姿勢を示した、彼らには珍しいストレートなサウンドと祝祭的なムードを持つ曲だ。
斜に構えがちな自分はこの曲の魅力があまり理解できないでいたが、聴き飽きたとか失礼な感情でいたはずの自分が、この日はなぜかとても“Arma”を聴きたいという気持ちになっていた。こうやって新しく進もうという今の自分ならArmaの魅力を十二分に感じられる気がしたからだ。
2部のラストでやってくれるもの、そしてこれだけの時間演奏してくれているからアンコールはないものとばかり踏んでいたので、“風の歌”が来たときは少し惜しい気持ちになったが、風の歌も近年は早々演奏されない名曲である。そしてこれまた、偶然とは思えないほど今の自分に必要な言葉が並んでいる曲である。
“散らばっていく それぞれに理屈を抱えて
ただ元の場所にさよならを言うんだ”
“かなしみを明日に変えていく
いつだってそばに君を見て時を刻むんだ
とんだ幻想だと どこの誰が言った?”
予想外だったけど風の歌が聴けたのも良かったし、そもそも既に素晴らしいライブをしてくれてるからArmaはお預けで良いかなと思ったら、一曲だけアンコールと現れた彼らが鳴らし始めたのは待ち望んだその曲だった。
“無限にあるはずの未来が掴みかけてはまた遠ざかる
手を伸ばせもっと 届かないのもそれがご愛嬌”
“例えばほら きみを夏に喩えた
武器は要らない 次の夏が来ればいい”
何とも頼もしかった。コロナ以降のGRAPEVINEは、以前よりずっと「頼もしい」という感覚が強まっていると最初の方に書いたが、その象徴がやはりこの曲に思える。あらゆる痛みを引き受けてきた、現実の重さを歌ってきた男が、その上で未来を歌うのだ。これほど眩しいことはないだろう。
“物語は終わりじゃないさ 全てを抱えていく
愛しみがまだわからない とは言わせない
とそう思うのさ そう歌おう”
物語は終わりじゃない。痛みを背負ったままでも歩いていける。前に進める。やはり音楽が鳴る場所は、GRAPEVINEが紡ぐ歌は、その間だけは、自分がありのまま存在していられるということをあらためて実感した。
自分はどうしたって普通の人間でいられないとわかったし、それが悲しいことに変わりはないが、それでも未来へ向かおうと思える。とりあえず9月25日、自分自身田中和将と同じ目線で歌った経験を経た上で、その場所である大阪城野音で、夕暮れと共に聴ける“another sky”の世界を当面の楽しみに待ちたい。
