
社長が語る、塩野義製薬とのマイルストーン達成の裏側
今回は、先日(9月24日)発表した塩野義製薬との共同創薬研究におけるマイルストーン達成に関する適時開示について、中村からその裏側をお話したいと思います。
塩野義製薬との3年越しの関係が共同創薬研究として実を結ぶまで
塩野義製薬とは、中村が個人的に面識のあった方と息の長い(3年以上)お付き合いをさせいただく中で、当社のmRNA標的低分子創薬を紹介してきました。先方でmRNA標的低分子創薬に注目するエース級の研究者が登場したことをきっかけに、秘密保持契約のもとで共同創薬研究契約の締結に向けた議論が動き出し、2021年11月に契約締結に至りました。
当時、塩野義製薬が当社と契約締結した理由については、新しい技術で社内の創薬ポテンシャルを高めたいという意図よりも、むしろ、塩野義製薬が定める重点疾患領域に対して何としても医薬品開発を実現したい、それには当社の技術が有用だという明確な意図と強い意気込みがあったと中村は認識しています。
2021年の契約締結からこれまでの約3年間、塩野義製薬のご担当者とは新たな医薬品の実現に向け共に励む同志のような関係を築き、着実に共同創薬プロジェクトを推進してきました。そのような経緯から、「今回のマイルストーン達成」は、中村にとっても当社の研究員たちにとっても非常に感慨深いものがあります。
塩野義製薬から学ぶ挑戦の姿勢と当社への高い評価
当社はこれまでに、製薬会社10社との共同研究・共同創薬研究を通じて、各製薬会社の創薬のやり方を見せていただきました。塩野義製薬の創薬のやり方は、他社とはずいぶん異なるところがあり、いくつも新薬を生み出してきた企業として、非常に学ぶところが多いと感じています。
塩野義製薬は、当社との共同創薬プロジェクトに対する真剣度も非常に高く、目的とする効果の有無を検証する既存の評価系がない場合には自ら専用の評価系を新たに構築されるなど、困難な課題に果敢に取り組む勇ましい姿勢は、まさに業界をリードする製薬会社に相応しいとの印象を受けました。
その様な塩野義製薬から、これまでの共同創薬プロジェクトの成果を通じて、技術面や人材面で高い評価と信頼を寄せていただいていることは、当社の研究員たちにとっても大きな自信となっています。

塩野義製薬とのマイルストーン達成が示す、mRNA標的低分子創薬の可能性
製薬会社にとって、早期の創薬研究の進捗は非常にセンシティブな情報であるため、当社が未上場の頃は、各社との進捗についてなかなか思うように情報公開に踏み切れない、という事情がありました。
当社は上場後、東京証券取引所の指針に沿って適切かつ積極的な適時開示に取り組んでおり、2022年12月に契約したラクオリア創薬とは2023年12月に、2023年6月に契約した武田薬品については2024年6月に、それぞれ創薬研究段階の「最初のマイルストーン達成」についての情報公開を行うに至っています。
塩野義製薬との共同創薬研究についても、「今回のマイルストーン達成」を報告できたことは、株主や投資家の皆さまへの透明性と適時適切な情報提供を実践するという観点から、非常に意義のあることだと考えています。
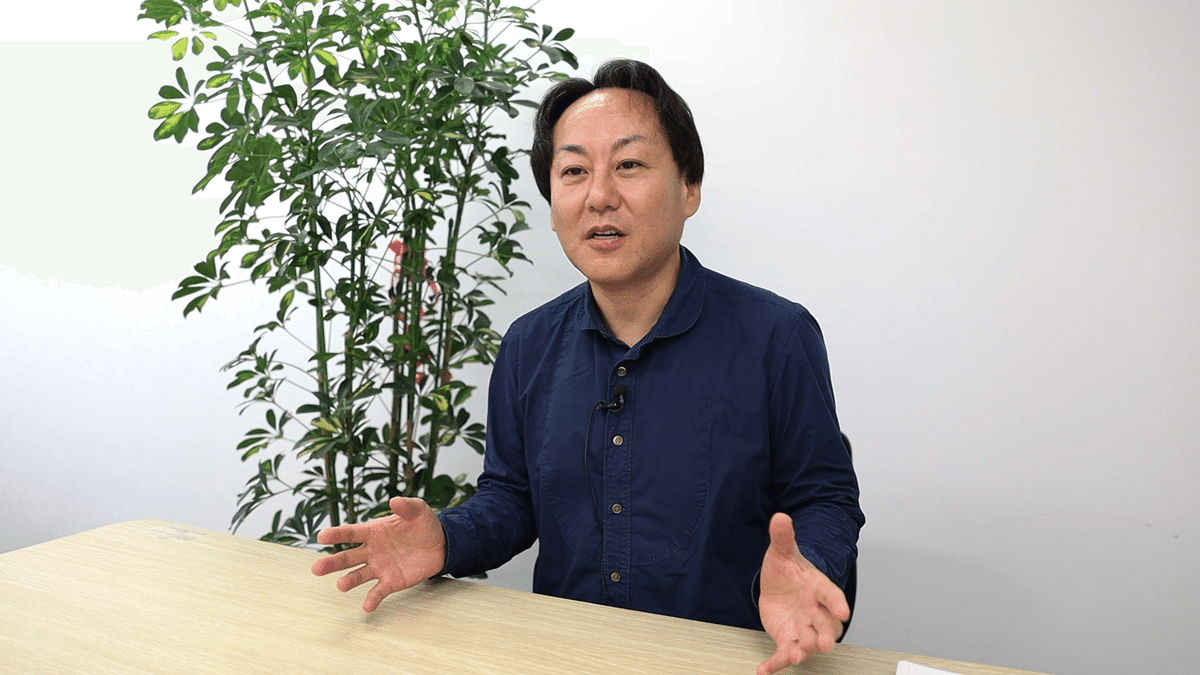
また、今回の塩野義製薬のマイルストーン達成は、すでにご報告しているラクオリア創薬や武田薬品のマイルストーン達成とは意味合いが異なります。
当社と製薬会社とのmRNA標的低分子創薬の共同研究には、大きく分けて「ターゲット探索」、「スクリーニング」、「ヒット化合物検証」、「リード化合物最適化」の4つのプロセスがあります。その中でも、mRNA標的低分子創薬を実施するうえで一番クリティカルかつ当社の寄与割合が大きいプロセスは、mRNA上にターゲット構造を見出す「ターゲット探索」およびターゲット構造に結合する低分子化合物を実験的に発見する「スクリーニング」です。ここでは当社独自のmRNA構造解析技術やスクリーニング技術が必須となります。一方、「ヒット化合物検証」と「リード化合物最適化」のプロセスでは、当社から提供するmRNA標的特有の技術を必要としつつも、タンパク質を標的とした通常の低分子創薬の技術と共通している部分が多くなるため、製薬会社の担当割合がより大きくなります。
ラクオリア創薬や武田薬品との共同創薬研究において「最初のマイルストーン達成」を契約締結後約1年でご報告できたことは、共同研究の前半プロセスにおける当社の技術力の確かさと迅速性を証明するものであると考えています。一方、塩野義製薬との「今回のマイルストーン達成」は、タンパク質を標的とした通常の低分子創薬と共通する部分の成果を含むものであり、当社のmRNA関連の技術的支援があれば、通常の低分子創薬同様にmRNA標的という全く新しい低分子創薬に取り組めることを示唆するものになったのではないかと考えています。
技術革新で挑む、ハイブリッド型ビジネスモデルへの転換
当社がプラットフォーム事業として取り組むmRNA標的低分子創薬には、mRNAを低分子医薬品で標的とするために必要となるmRNA関連技術の開発と、通常の低分子創薬で直面するリスクの両方に影響を受ける難しさがあります。mRNA関連特有の技術については、当社は常に技術革新に努めています。その一例として、大阪大学と当社の研究チームが世界に先駆けて実施した「リード化合物最適化」に関する研究について、その研究成果の一部を2023年11月に学術論文として発表しました。(論文はこちら)
今後も、こうしたmRNA関連の最新技術を製薬会社に提供することを通じて、プラットフォーム事業のさらなる拡大を目指していきます。また、プラットフォーム事業で培った技術力と経験を活かして、今後は自社パイプラインの創出も進めていきます。
このように当社は現在、プラットフォーム型ビジネスからハイブリッド型ビジネスモデルへの転換を果敢に進めているところです。引き続き、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。
