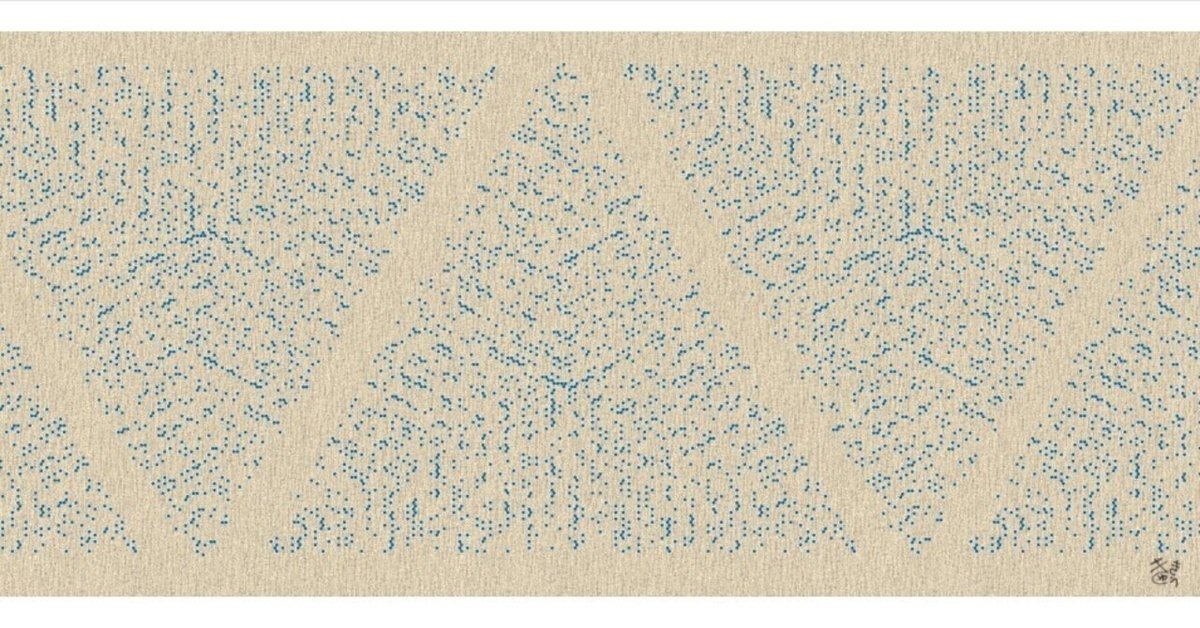
第13話 見果てぬ夢
視界のすぐ下を、地面が目にも止まらない速さで後ろへ流れる。四つん這いのまま全力疾走でもしているかのようだ。それとも、地面スレスレを滑空でもしているのだろうか。
・・・いや、これはやはり地面を走っている。なぜなら、周りの風景が小刻みにゆれているから。
小刻みにゆれながらも、視界の主は走っているその先にあるものを見すえて離さない。
視界の真ん中には、一頭の牡鹿。足元にある何かを夢中で食べていて、こちらに気付く様子はない。しめた、絶好の好機だ。ほんのあと少し、あと数歩。一気に距離を詰めて、仕留めれば・・・。
だが間近まで迫ると、牡鹿は思っていたよりもはるかに大きかった。見上げても背中の輪郭すら視界に収まらない。
その瞬間、顔がくだけんばかりの強烈な衝撃が顎に走った。
とたん、世界が舞う。
まったく出鱈目に視界に入ってくる、遠くの森や闇夜の月。上も下もわからなくなり、目が回る。
状況が呑み込めないまま、今度は全身に強い衝撃をうけた。その衝撃で呼吸が乱れ、激しく咳き込む。気がつくと、周りの風景は舞うのを止め、横倒しのままじっとしている。それを見てようやく、今自分が地面に横たわっていることに気が付いた。続いて、自分の身に何が起きたのかも少しずつ理解し始める。おそらく、牡鹿に後ろ足で顎を蹴り上げられて宙を舞ったのだ。実際、さっき間近にまで迫ったはずの牡鹿は、また離れた所でこちらを睨み付けている。
牡鹿が、ゆっくりとこちらに向かって歩き始める。どうやら、追撃を加えるつもりのようだ。早く起き上がらないと。だが、さっきの一撃で脳が揺れているのか、地に足をつけているのに、未だに上下の感覚が定まらない。脚がうまく動かない。何度も転びそうになる。
牡鹿が駆け出した。まずい。この状態では迎撃できない。
必死に脚を動かし、身体を横へ無理矢理押し出した。たった今、自分が立っていた地面を、牡鹿の大きな角が抉る。間一髪かわせたようだが、平衡感覚はまだ戻っておらず、着地に失敗してまた転ぶ。
狙いを外した牡鹿が、ゆっくりとこちらを振り返る。まだ諦めていないのか。
動け、動け、動け、動け、動け、動け、動け、動け。
すでにほとんど使い物にならなくなった身体を、必死で鼓舞する。気が付くと、口元から温かくてヌルッとしたものが滴り落ちている。たぶん、さっきの攻撃で口のどこかを切ったのだろうが、今はそんなことを気にしている場合ではない。
また牡鹿が近付いてくる。とにかく、今は避けることに専念だ。迎え打つなど、以ての外。
次も横か? いや、二度も同じ手は通用しないかもしれない。次は後ろに下がろう・・・。
だが、ふらついた脚で後ろへ飛ぶのは無茶だった。大した距離は稼げず、突き上げてくる角に追いつかれた。とっさに顔を逸らせたおかげで直撃は避けられたが、左耳に熱いものが走った。
自分でも聞いたことのないような金切り声を上げ、這々の体で逃げ出した。
微睡んだかのように視界が滲むと、次は叩きつけるような大雨の中にいた。
辺りを覆い尽くす、脚の付け根に届くほどの鬱陶しい草と、それを囲う木々。
そして視界の中央には、筋骨隆々とした猪が一頭。こちらを真っ直ぐ睨んでいる。
厄介な相手だ。さっきの牡鹿よりも小柄ではあるが、目方は同じかそれ以上ありそうだ。
後ろを振り返れば、離れた所に農村が見える。あそこにだけは行かせるわけにはいかない。自分だけでは勝ち目がないのは明らかだが、それでも、どうしても、自分だけでやらねばならない。
意を決し、相手との距離を詰める。相手も身構える。
一気に駆け寄り、威嚇する。攻撃はしない。あの引き締まった身体だ、ちょっとやそっと攻撃しても、ほとんど意味はないだろう。威嚇を繰り返し、隙をつくしかない。
だが敵もさる者、何度威嚇しても、動じる様子はまったくない。常に目線を外さず、むしろこちらの隙を窺っているようだ。相手が自分から動く気配もない。このままでは埒が明かない。
いや、待てよ・・・?
全く動く様子がないという事は、もしやそこまでの戦意はないということか。だとすれば、一気に畳み掛ければ勝機が見えるかもしれない。
身体を低くし、相手にゆっくりと近付く。
今だっ。
全力で相手に踊りかかった、その時だった。
突如、猪の姿が叢に隠れたかと思うと、そこから大量の土塊が飛んできた。驚いて、反射的に身を逸らせる。着地して相手に向き直ると、相手は鼻先に迫って来ていた。
鋭い突き上げが腹に炸裂する。全身が砕けるかのような衝撃と共に、
視界が真っ暗になった・・・。
「じゃから、貴様は『甘ったれじゃ』と言うておるのじゃ。」
「一族を裏切る気か?!」
「吠え面をかくなよ・・・。」
雨はまだ降り続いている。
帰らねばとは思うものの、全身の痛みがひどく、微動だにすることができない。誰か、助けてくれ・・・。
すると、どこからともなくヒトの声が聞こえて来た。
「糞っ、逃がしてしもうたかっ・・・。」
「このところ、獣の類が多いのう。」
「これまではここまでひどくなかったんじゃが・・・。」
二人の男はすぐ近くまで来たが、愚痴だけ言い終えると、そのまま立ち去ってしまった。
「・・・・・・。」
雨は今も、傷んだ身体を叩き続ける。
助けを求めたところで、誰も手を差し伸べてくれることはない。そんな事は最初から解っていた。
解っていて、それでもそういう道を選んだ。
手に入れるために、全てを投げ打った。
軋む身体を奮い立たせ、足を引き摺るように歩き出す。
この程度の失敗で立ち止まっているわけにはいかない・・・。
でないと、あの方に笑われる・・・。
「!! ・・・・・・。」
視界に飛び込んできたのは、見慣れた天井だった。
大翔は必死で視線を巡らせたが、目に入るのは日焼けしたカーテンにカレンダー、オンラインゲームの推しキャラのポスターに、制服をかけるハンガーだ。ハンガーのクリップには、ズボンの代わりにケサランパサランが1匹、宙づりにされている。
彼はあわててパジャマの内側を右手でまさぐった。同時に、左手で口元をぬぐってみる。当然のことながら、骨は1本も折れていないし、左手に血が付着することもなかった。
それでも、まるでマラソンを終えた後のように呼吸が乱れている。心臓は激しく脈打ち、耳の奥で潮騒のような音がひっきりなしにくり返す。
“生々しい”などというレベルのものではなかった。イノシシの突進を受けたときなど、本気で「死んだ」と思ったほどだ。むしろ、夢(?)だとわかった今この瞬間でもなお、自分が生きているのが不思議に思える。
だが、この感覚には覚えがあった。
数日前、絵馬の問題に解答した後に見た幻覚。おそらくは、誰かの記憶。
ベッドの上にあぐらをかいたまま、頭をひっかく。おもむろに枕元のスマホを確認すると、午前5時13分だった。
スマホを元に戻すと、今度はその横に置いていたペットボトルの水をぐいっと飲む。ウソのように痛みが引いた後の体の中を、ひんやりとした水が下っていく。
わからない事だらけの夢だった。
たしか前回見た幻覚では、その記憶の主はなにかの謎かけを解こうとしていた。参考にしていたのはいずれも数学の本だったので、おそらくは数学の問題に取り組んでいたものと思われる。だが、今回の夢ではそれらしきものはまったく出てこなかった。もちろん日がな一日、数学の問題だけやっているなどということは普通ないと思うが、それで出て来た日常シーンが野生動物との闘い? いったい、どういう職業の人なのか?
また、その闘いのシーンにも違和感があった。終始、目線が低い。
夢を見ている最中はやけにシカやイノシシが大きいなと思っていたが、今にして思えばむしろこちら側、記憶の主が非常に小柄だったと考えたほうが自然である。おそらく、子供かそれ以下。
しかし数日前、最初に見た幻覚では、目線はそれほど低くなかったような気がする。小雨が降る切り通しをトボトボと歩いていたときは、人並みの目線の高さだったはずだ。
だがそれでも、大翔にはそれらの記憶の主は、すべて同一人物なように思えた。目線の高さの違いはとても大きな違いだが、彼にはそれすら些細な違いに感じられた。例えて言うなら、中学に入ってしばらくした頃、ヒゲが生え始めたり、高い声がストンと出なくなったときに感じた程度の違和感。あのときも多少戸惑いはしたが、自分が別の人間になったとまでは感じなかった。
そしてなにより、記憶を共有しているからこそわかる、彼(?)を駆り立ててやまない強烈な感情。それだけは、これまでに見たすべての幻覚に共通していた。相変わらずそれを言い表す言葉を大翔は思いつかなかったが、どうやら“あの方”に認められたいという欲求は強くあるようだった。
「なんや・・・。謎が深まったなぁ・・・。」
他人の記憶をのぞき見ているという罪悪感と、だからこその高揚感と。それだけのものを感じているのに、情報自体はいっこうに収束する気配がない。こんなことが、後何回続くのだろうか。
ペットボトルのフタを閉めて元に戻すと、スマホで時間を確認した。午前5時15分。
「そういや、さっき見たんやった・・・。」
もう2日連続で深夜に目が覚めている。さっさと寝てしまったほうが身のためだ。
彼はもう一度、布団の中にもぐり込んだ。
彼の机の上には、彼が解答と署名をした絵馬が置かれている。その横で、彼が答えた問題の算額の文字が橙色に光っていた。
To Be Continued…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
