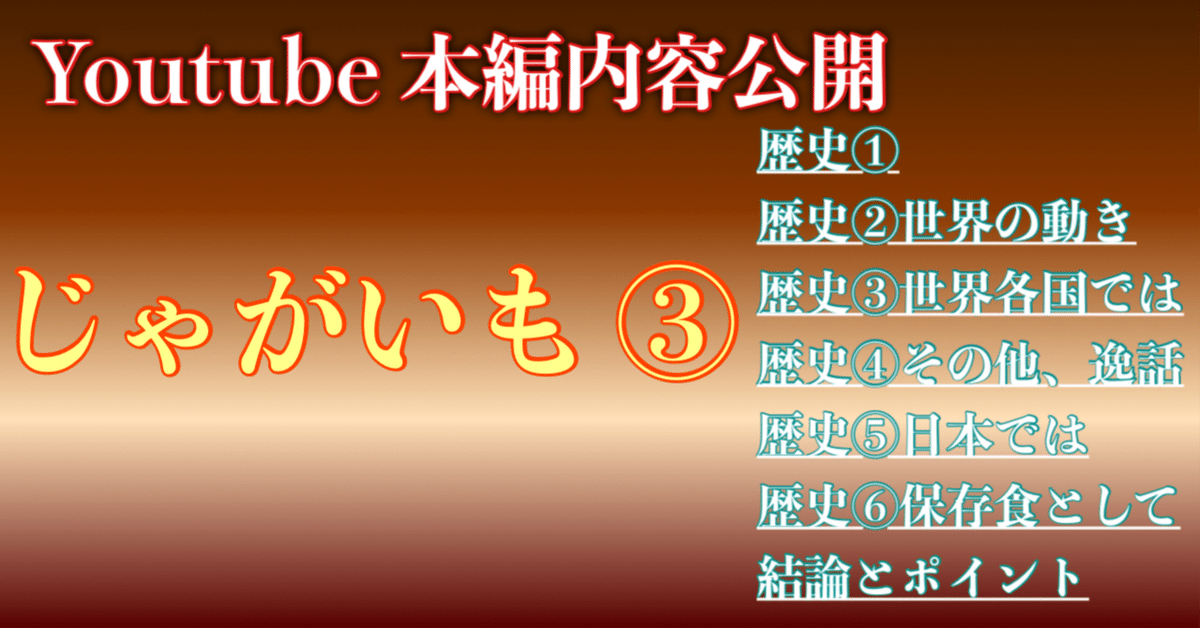
N° 25 じゃがいも③[YouTube本編内容]
じゃがいも ④-③
理論的知識
理論的知識 歴史
・歴史①
・歴史② 世界の動き
・歴史③ 世界各国では
・歴史④ その他の情報と逸話
・歴史⑤ 日本では…
・歴史⑥ 保存食として。
・結論とポイント
------------------
知識→ 歴史
------------------
☆歴史 ①
:南アメリカ、アンデス山脈が原産とされる
小さな芋の原種が中南米に野生している。
:15世紀、大航海時代に
「コロンブス交換」を始めとして
ヨーロッパ各地へ広がり、
日本へは、東南アジアを経て16世紀に渡った。
:品種改良が繰り返され、現在の様な
大型の芋をつける様な品種が開発され
世界中の温帯地域で栽培される。
:南米アンデス中南部のペルー南部に位置する
"チチカカ湖畔" が発祥ともされる。
標高3000〜4000メートルの高地で
紀元500年頃に栽培されたと考えられる。
:ヨーロッパ大陸へ伝えられたのは
インカ帝国の時代で15〜16世紀とされている。
当初、インカ帝国の食の基盤はトウモロコシと
されていたが、ワマン・ポマが1615年に残した
記録やマチュピチュの段々畑の史跡研修、
気象地理条件、食生活の解析など、
多方面からの解析で
食基盤がじゃがいもであった事が示されており
近年、見直されている。
具体的に、誰が・いつ、
伝えたかはハッキリしていない。
スペイン人が本国に持ち帰ったのは、1570年頃
新大陸の「お土産」として
船乗りや兵士たちによってもたらされたと
推測づけられている。
------------------
☆歴史② 世界の動き
:16世紀に南米からヨーロッパにもたらされたが
当初は今より小さく黒色で
見た目も悪かったからか
なかなか受け入れられなかった。
:しかし、それ以前に流通していた、
主要作物よりも寒冷な気候に耐え
痩せている土地でも育つこと、
収量も大きいことから
17世紀にヨーロッパ各国で飢餓がおこると
各国の王は、じゃがいもを広めようとした。
:特に冷涼で農業に不適とされた
アイルランド、北ドイツ〜北欧、
東欧では、食文化を変えるほど普及した。
:麦などと違い、戦争等で、踏み荒らされても
収穫できること、
農民がジャガイモを食べる事で
領主たちが、麦の取り分を増やそうとした狙いもある。
:西洋の飢餓のみならず、
アメリカ、北米、日本、アジア地域にも
普及し、ジャガイモで世界の飢餓から救った
人口は計り知れない。
:ペルーが、国連食糧農業機関(FAO)に提案した
「国際イモ年(IYP:international year of poteto)」が
認められ、2008年を"ジャガイモ栽培8000年"を
記念する「国際イモ年」として
FAOなどが、ジャガイモの一層の普及と啓発を
各国に働きかけることになった。
------------------
☆歴史③ 世界各国では
・イングランド
:ヨーロッパに流入した時に
ヨーロッパには「イモ」という概念がなかった。
そのため、食べれるかどうか?分かるまで
時間がかかったし、
本来有毒である葉や茎も食す様な
料理本がイングランドで出版されてしまい
それをまにうけたイングランド人が
ソラニン中毒を起こした例も。
・アイルランド
:貴族が自分達の麦の配分が増える様に
画策し熱心に農民に勧めたのがキッカケの一つ。
:結果、アイルランドではイモが主食に。
1840年代にじゃがいもの疫病が蔓延した。
その際に、ジャガイモに依存していた
アイルランドでは、ジャガイモ飢餓がおこり
大勢のアイルランド人が
北アメリカに移住した。その移民の中に
後の"第35代アメリカ合衆国大統領"になる
"ジョン・F・ケネディ"さんの曽祖父の
パトリックさんが居たのは、良く知られている。
・北朝鮮
:1990年代後半から、食糧危機が発生したが
この時、政府朝鮮労働党は
「ジャガイモ農業革命」を提唱して
ジャガイモ生産拡大を同時に種子改良
二毛作方針を徹底した。
・ドイツ
:最初に普及したのは、プロイセン。
プロイセンの支配地であった
ブランデンブルク地方は南ドイツとは違い
寒冷で痩せた土地が多く、三十年戦争もあり
しばしば食糧難に悩まされた。
その為、ジャガイモは切り札になり
フリードリヒ2世が栽培を奨励した。
:しかし、他国と同様に不恰好な外見から
嫌われていた為、フリードリヒ2世は
自ら領地に巡回して普及を、訴えたり
毎日ジャガイモを食べたりしていた。
・フランス
:プロイセンの捕虜時代に
プロイセン王国が国力をましたとして、
ジャガイモを知る。
農科学者アントワーヌ=オーギュスタン・パルマンティエの
提言により、ルイ16世が
フランス王国ブルボン朝でも広めようと
マリーアントワネットにジャガイモの花を飾って
夜会に出席されると貴族は関心を持った。
ただ、他の諸国と一緒で庶民の中でも
あまり好まれていなかった。
------------------
☆歴史④ その他の情報と逸話
:1600年頃にスペインからヨーロッパ諸国に
伝播するが、この伝播方法にも諸説あり
ハッキリとしない。
:16〜17世紀には、植物学者による
菜園栽培が主な目的であった。
:ドイツの食習慣にはジャガイモを
フォークで潰して食べる場合があり
第二次世界大戦中にフランスに潜伏した
ドイツのスパイがレストランでジャガイモを
潰していた為、スパイとバレた。
という、ジョークもある。
:第一次世界大戦以降に使用した
"柄付きの手榴弾"が「ポテトマッシャー」に
似ていることから、その手榴弾よ
「ポテトマッシャー」と呼ばれた。
:1612年のアイルランド移民にと共に
北アメリカへ渡り、その後
アメリカ独立戦争における兵士たちの
貴重な食糧源となった。
:アダムスミス(イギリスの哲学者、倫理学者、経済学者)は、
「国富論」において、
「小麦の三倍の生産量がある」と評価しており
瞬く間に麦、水、とうもろこしに並ぶ
「世界4大作物」として地位を確立した。
:フランスに広めたいパルマンティの一計。
王が作らせたジャガイモ畑に
昼間だけ衛兵をつけて、厳重に警備した後、
夜はわざと見張りを付けなかった。
王がそこまで、厳重に守らせるからには、
さぞ美味なのだろうと考えた市民の中から
夜中に畑に盗みに入るものが現れた。
結果的に、パルマンティエの目論見通り
ジャガイモは広まった。
:フランスのジャガイモ料理には
「パルマンティエ」と名のつく様になった。
------------------
☆歴史⑤日本では
:諸説あるが、1598年にオランダ人によって
持ち込まれたとされる。
ジャワ島のジャガタラを経由して長崎へ
伝来した為、"ジャガタライモ"と呼ばれたが
それを略してジャガイモになったという説も。
:江戸時代後期の18世紀末には、
ロシア人の影響で、
北海道、東北地方に移入され、
飢餓対策として栽培された。
:蘭学者の高野長英が、ジャガイモ栽培を奨励した。
:江戸時代後期には、甲斐国の代官であった
中井清太夫も奨励したとされ
1801年(享和元年)には、小野蘭山が
甲斐国の村でジャガイモ栽培を記録していて
アイヌも江戸時代後期に栽培していた。
:本格的に導入されたのは、
明治維新の後で、北海道に開拓された。
:アメリカで、
ウィリアム・スミス・クラークに学び
後に、「イモ代官」と呼ばれた
初代根室兼令湯地定基により
普及し、川田龍吉男爵により、
いわゆる「男爵芋」が定着した。
:当初は、西洋料理の素材として重要であったが
洋食の普及と共に徐々に"肉じゃが"など
日本の家庭料理にも取り入れらる様になった。
:北海道では、
低温で1年半、保管・熟成をさせ
デンプンを糖化させて甘くした
ジャガイモがある。
----------------
☆歴史⑥保存食として
:チューニョ
現在でもボリビアや
ペルー高地(アルティプラーノ)では
利用されている。
見た目は、小石のよう。
塩味のスープに入れて長時間煮込んで食べるが
質の悪いチーニョはアンモニア臭がする。
古くから冷凍乾燥させるという方法で
保存性を高め保存食として利用されてきた。
先のコロンブス時、中央アンデス地域において
冷凍したジャガイモを踏みつけることを繰り返し
水分と毒を抜く方法が発明され長期にわたる
保存と備蓄が可能になった。
:トゥンタ
ペルー南部やボリビアで
少し作り方の違うチーニョ。
:しみいも(ちぢみいも)
山梨県や長野県の一部地域では
ジャガイモを寒冷期の外気温で冷凍させ
踏みつけることを繰り返して
重量と体積を減らし、保存性を高めた方法。
:ポッチェイモ(ペネコショイモ)
北海道のアイヌ民族
秋に収穫しきれなかったものや
傷のあるものを雪の中に放置し
冷凍と解凍を繰り返し
干からびて体積が減る。
食べる際は、水に戻して丸め
団子にして油を引いた平鍋で焼く。
----------------
☆結論とポイント
・それは受けて次第ですが
歴史から読み取れるものは大きい!
・色んな逸話と由来が!
・何かの危機の時に知っておきたい
ジャガイモ保存食の知識。
-----------------------
↑さらに詳しく映像で
気になる方は、YouTubeにて!
[再生リスト]
:本編 Long Ver. 「じゃがいも④-③」
:セルフ切り抜き short ver.
理論的知識 セルフ切り抜き より。
