
肩の痛みで信じちゃいけないアドバイスTOP10【五十肩・腱板断裂】
「気分を害された整形外科医の先生や治療家さんがおられたら、本当にごめんなさい」
今回は「肩の痛みと危険なアドバイス!」がテーマです。
肩の痛みで信じちゃいけないアドバイスTOP 10をお届けします。
※このnoteでは、整形外科医:歌島大輔が医学的根拠をもとに、わかりやく、かつ実践的な医療健康情報をお届けします。
ときどき出てくる「ふんぞり男」とは、その名の通り、ふんぞり返って態度がデカい患者さんです。
肩の痛みで信じちゃいけないアドバイスTOP10
あなたは肩の痛みについて医師や治療家さんに相談した時に、こんなアドバイスをもらったことはないでしょうか?
身体のゆがみが原因だよ
肩を動かさないとカタくなるよ
痛みがおさまるまで動かしちゃダメだよ
腕が上がるんだから腱板断裂はないよ
もう年だから手術しても意味ないよ
とりあえずリハビリやりましょうか・・・
この中に1つでも「ああ、状況によっては適切なアドバイスだよなぁ」って思ったものがあれば、ぜひこの動画は最後までご覧いただきたいです。
特にここでご紹介していない第1位はかなり知っておいていただきたいことだったりしますので、お付き合いください。

ふんぞり男 「なに、そのアドバイス、普通だろうが、俺も言われたことあるぞ」
ふんぞり男さんは肩痛いですもんね。
僕のそばにいていつまでも「痛い痛い」って、
僕の実力が疑われるのでやめてもらえませんか?
ふんぞり男「うるせぇ、なら、さっさと治せ!」
いや、いっぱいアドバイスしてるのに全然実践しないからじゃないですか。
というか、動画の途中で寝ていたり、途中でスキップしたりするじゃないですか。
そういうところですよ・・
と、説教させていただいたところで、
肩の痛みで信じちゃいけないアドバイスTOP 10に移りたいんですが、
これを言った医師や専門家が、イコール信じられない「ヤブ医者」とか「エセ専門家」とは限りません。
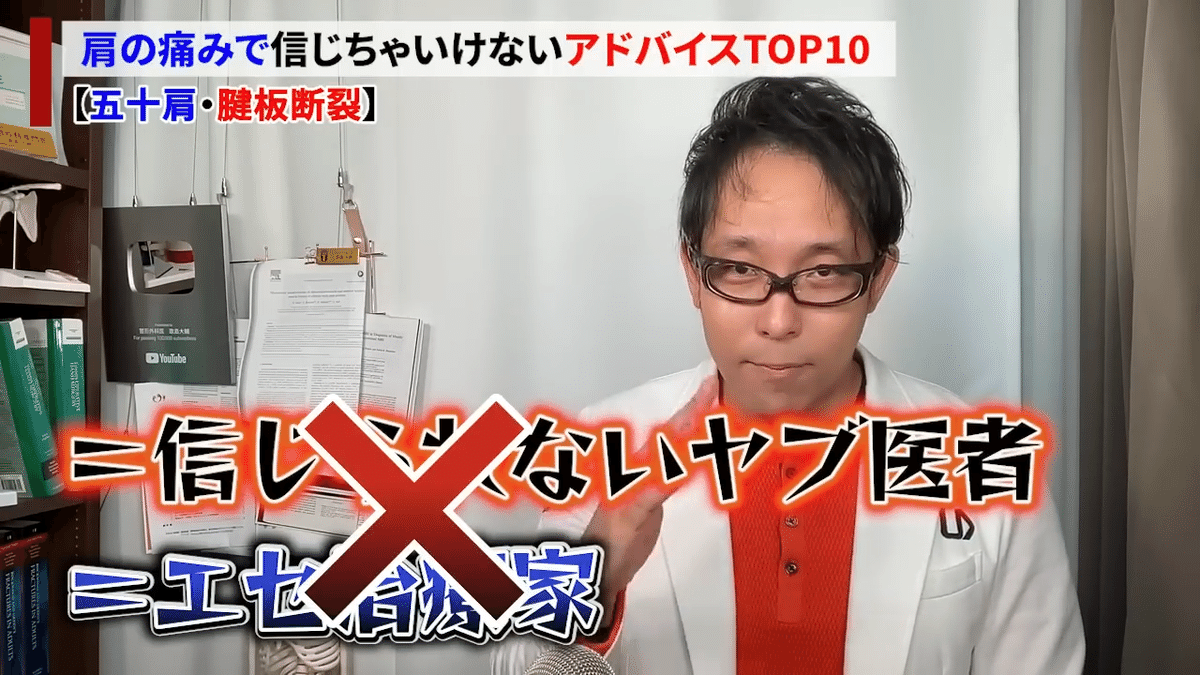
ケースバイケースで、アドバイスは正しくもなれば間違いにもなります。
それは僕も一緒です。
僕が言ったこと全てが正しいなんて、あり得ません。
ですから、なんで信じちゃいけないのかっていう解説をお聞きいただいて、
ご理解いただいた上で、「信じる・信じない」を判断できるようになってください。
というか「信じる」っていう考え方から脱却したいですね。
医療は宗教じゃなくて、医学という科学で成り立っています。
根拠を理解した上で、自分で「判断する・採用する・アドバイスを選ぶ」という考え方がオススメです。
ということで「肩の痛みで信じちゃいけないアドバイスTOP 10」
早速いきましょう。
第10位 ほら石灰があるから石灰沈着性腱板炎だね

まずは、整形外科医がやりがちなアドバイスです。
ふんぞり男「は?レントゲンで石灰が写ってるんだから事実だろうが」
いや、レントゲンで写っているっていうのは、
「所見」であって「診断」ではないんですね。
これめっちゃ大事な視点です。
石灰が写っているけど、その肩の痛みの原因は石灰じゃなくて五十肩みたいなケースは全然少なくないんですよね。
それを石灰沈着性腱板炎と決めつけて、石灰を必死に溶かそうと太い針で注射したり、体外衝撃波治療などを何回もやるようなことをやっても、
全然痛みが良くならないって感じでいらっしゃることがあるんですね。

それはそうです。
痛みや症状の原因に対して治療をするから効果がでるわけであって、
その原因がなんなのかを判断するのが診断です。
その診断がずれていれば、治療も効果が出ないのは当然ですね。
もちろんレントゲンで石灰が写っていて、その石灰があるがゆえ、
もしくはその周囲の強い炎症が痛みの原因であることは多々あるんですよ。
ですから「石灰が写っているから石灰沈着性腱板炎」では怪しいアドバイスなんですが
「石灰が写っていて、痛みの性質として、こうすると痛くてここが痛いとなると、この石灰のせいで痛みが出ている、つまり石灰沈着性腱板炎と考えます」
という説明なら、納得感が強いわけですね。
第9位 五十肩なんて半年もすれば治るから

これも腹立たしいアドバイスですね。
患者さんが甘く見ちゃうのは仕方ないと思うんですよ。
五十肩の一般的なイメージもそうですし、周りの五十肩経験者が軽症だった場合は、そういう考え方になりますよね。
一方で、多くの患者さんを診察していて、重症の五十肩だって診察しているはずの整形外科医や治療家さんがそれを言うのは、
熱意を持って五十肩を治療していないのかな・・って思っちゃいます。
第8位 五十肩の原因はね・・・手首なんだよ

このアドバイスを言うことが多いのは、医師よりも治療家さんですね。
YouTubeを見ていると、このアドバイスをしている治療家さんはかなり多いです。
しかし、まず言えるのは、それは医学的に科学的に検証された説ではなく、まったくの仮説です。
そして、僕の個人的な意見としては、その仮説が正しいかもしれないと考える根拠が異常に薄いというか、
僕の経験からしても、あんまり手首は関係ないだろうなって感じです。
一応、その説を説明されている人の理屈をお伝えしておきます。
デスクワークなどで手のひらが下を向くような姿勢がありますよね。
その姿勢を「回内」っていうんですが、そういう姿勢で作業を続けていくと肩甲骨も含めて体が内向きになっていきます。

いわゆる「巻き肩」のような状態になりがちで、「肩甲骨の動きが悪くなって、肩に負担がかかって五十肩になる」という仮説ですね。

ふんぞり男「あれ、納得したぞ?」
いや、わかります・・納得感ありますよね。
いっぱい反論できるんですが、1つ経験的な反論をすると、
この理屈であれば五十肩の大半はデスクワーカーになりますよね。
このように回内での作業が原因ですって言うなら。
でも、僕は必ず仕事を患者さんには聞くのですが、
デスクワーカーも力仕事もそれ以外の仕事も、まんべんなく特別な偏りはありません。

あとは巻き肩と五十肩の関係として、強い相関関係があるなら、それは研究でも示せますが、そういうエビデンスはありません。
つまり「仮説のメカニズムもまた仮説」
仮説をもとに組み立てられた仮説は、もうグラグラです。
第7位 とりあえずリハビリをやりましょうか

ふんぞり男「は?リハビリやるのは良いことじゃないのか?」
そうですね。
もちろん、多くのケースで良いことだと思います。
でも、このアドバイスに不信感を抱かれる患者さんは少なくないんですよね。
「なんでリハビリをするのか」「リハビリをするとどうなるのか」そういう説明がないからなんです。

ふんぞり男「そんな医者、本当にいるのか?」
って思いますよね。
でも、これって人間のコミュニケーションですから、伝えたつもりでも伝わってないこともありますし、患者さんが持っている前提知識も結構ばらつきがあるので、
どこからどのくらい説明するのがベストなのかって一人一人違うんですね。
ですから、僕も説明したあとに患者さんの表情やリアクションから、
「あれ?伝わってないかも」って思うことはあって、そこで修正することもあるんですね。

ということは、僕も不信感をもたせてしまっている可能性があるんですね。
一方で患者さんも、もうちょっと説明してほしいっていうときに、
それを求めることができればいいですよね。
そこで「なんでそんなこと聞くんだ!」って怒ったり、
怒鳴ったりする医師がいるらしいんですが、
その時点で医師を変えたほうがいいかもしれません。
第6位 肩は内視鏡よりも直視下で開いた方がよく見えていい手術ができるよ

いきなり手術の話になってすみません。
でも、このアドバイスも時々聞くので、ちょっと取り上げたいなと。
肩の手術って内視鏡である関節鏡を使った手術と、通常の比較的大きめの傷を開いて直視下で行う手術があるんですね。
昔は関節鏡の手術は手術器具も未発達だったので、関節鏡手術自体が少なかったんですが、どんどん進化して関節鏡でできる手術は拡大してきています。
僕はもうほぼほぼ関節鏡手術しかしないくらいになっているので、余計にそう思うんですが
「大きな傷から直接見たほうがよく見える」っていう意見は、残念ながら関節鏡にあんまり慣れてない先生の意見じゃないかなって思います。

ふんぞり男 「は?小さな傷より大きな傷で直接見たほうがよく見えるに決まってるじゃないか? 」
いやいや、関節鏡って見ている部分が拡大されて画面に表示されるんですね。
さらに小さな傷を複数開けますので、前から見たり、後ろから見たり、横から見たりと、まさにくまなく関節を観察できるんですね。
これはいくら大きな傷をあけても前の傷を開けたら前だけ、後ろに傷を開けたら後だけしか見えない直視下手術とは大きく違うんです。
関節鏡で見えるくらいに直視下手術で見ようとしたら、傷もどでかくなりますし、大事な筋肉も切らないといけないし、もう見るためだけに大ダメージなので、それはできないんです。
つまり、よく見れるのはどう考えても関節鏡です。
ただ、一方で人工関節とか骨折をインプラントで固定するとか、そういうものはそもそも傷が小さいとインプラントが入らないですから、直視下手術になるわけですね。
第5位 身体のゆがみが原因だよ

これは主に治療家さんがよくされるアドバイスですよね。
本当にたくさんの論文を読みまくっている私ですが・・
この身体のゆがみが肩の原因になるっていうアドバイスの根拠になる研究や論文は見つけられていません。
もしご存知なら教えてほしいです。
直接的な因果関係はなくても、遠い因果関係ならありえそうじゃないですか。
ただ、現時点でこの表現でアドバイスされる治療家さんはご注意いただきたいです。
まず身体のゆがみが何を表しているかが「ふわふわ」しすぎている。
姿勢の左右差なのか
肩甲骨の位置異常なのか
脊椎の側弯なのか
後弯なのか。
ふんぞり男「うわ、小難しい言葉使うな!いいじゃねぇか、なんか歪んでるんだろうからよぉ」
いや、ダメなんです。
人様の大切な身体を治療するのに「なんか歪んでる」でいいわけないじゃないですか。
あまりに無責任です。

そして、その「なんか歪んでる」をもうちょっと定義してみていただくと、治療家さんごとに言うことが違います。
ですから、僕が個人的にオススメするのは「姿勢」という言葉を使ってアドバイスされる治療家さんです。
「姿勢」なら確かに左右の差があったり、良い悪いが定義しやすいので、その「姿勢」を改善するためのアプローチはプラスに働くかもしれません。
ただ、それでも
「姿勢を良くすればその肩の痛みは良くなる・・」っていうのも、言い過ぎです。
「姿勢」はたくさんある、遠く関係がありそうなものの1つでしかありません。
それがすべてとか、それが大きな要素であるかのように言うのは根拠不足だし、多分間違ってます。
ご注意くださいね。
第4位 肩を動かした方がいい・安静にしないといけない

ふんぞり男「は?動かした方がいいのか、動かしちゃいけないのか、どっちなんだ!」
ってなりますよね。
そういうアドバイスが整形外科でも治療院でもまかり通っていて、患者さんがとっても困惑している現状があるんです。
数でいうと、このアドバイスが一番多い気がします。
「前のお医者さんが動かさないとカタくなるっていうから動かしたら、痛くて動かせなくなった」
という話と、その逆で
「前の治療家さんが痛みがあるうちは動かすなっていうから、安静にしていたらカタくなった」という話。
どっちも高頻度に聞く話です。
ふんぞり男「だから、どっちが正解なんだ!?」
正解は「どっちかじゃないんですよ」

当たり前じゃないですか。
炎症があって痛いのに無理して動かせば炎症が強まるに決まっているし、痛いからと言ってまったく動かさなければ関節がカタくなる。
だから、その間でベストを探さないといけないんですね。
そのベストは診断にもよるので一概には言えませんが、例えば、五十肩で重症な凍結肩であった場合には、痛みが増えない程度にストレッチをして肩の可動域を広げていく作業が必要になります。
ふんぞり男「それが難しいから、悩んでるんじゃねぇか。」
そんな人は、こちらの動画をぜひぜひ御覧くださいね。
第3位 腕が上がるんだから腱板断裂じゃないね

これも多いアドバイスですね。
先に結論です。
腱板断裂でも腕が上がることは多々あります・・ほんと、多々あります。
なにせ腱板断裂でも無症状の患者さんだっておられるわけですから、当たり前なんですね。完全断裂でも上がる人は全然おられます。
ふんぞり男「じゃあ、腱板断裂ってやつはどうやって判断するんだ」
よっぽど重症でない限り、最終的にはMRIやエコーなどで直接腱板に穴が空いてないか判定しない限りは確定できません。
しかし、その前段階でもいろいろな診察テストや動きを観察したり、症状や痛くなったエピソードを伺うことで診断に近づけることはできます。
少なくとも、腕が上がる上がらないで腱板断裂を判定するとすれば、その専門家の方にはご注意ください。
第2位 その年だと手術しても仕方ないよ

このアドバイスも特に腱板断裂の患者さんにされることが多いんですが、本当に失礼だなって思いますね。
手術しても仕方ないとか、手術しても意味ないとか、平気で言う人の神経がわかりません。
一方で、手術のメリットよりデメリットやリスクが大きい場合にそれをはっきり伝えることは大切なので、患者さんによって手術をしないほうがいい理由を丁寧に説明すること自体は必要です。
丁寧な説明に「年だから」は該当しません。
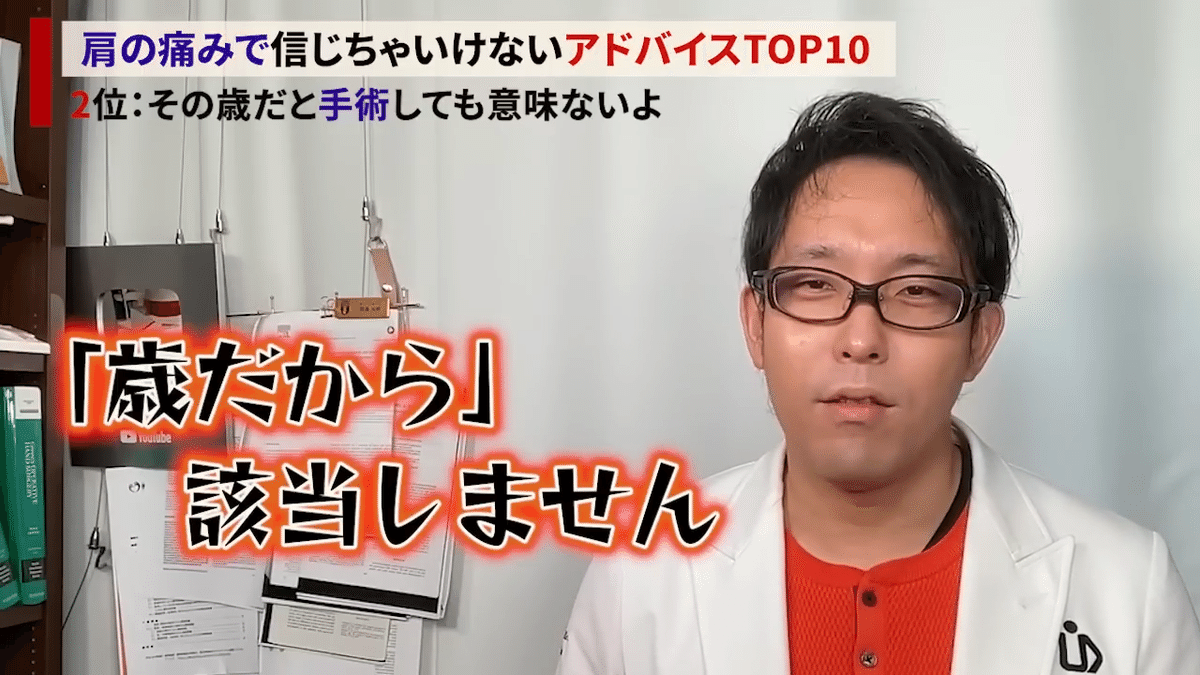
むしろ「雑で失礼な」説明です。
ふんぞり男「じゃあ、お前は100歳でも腱板断裂の手術をするのか?」
いや、流石にしたことはないですし、ご年齢が手術をするしないを決める大事な要素なのは否定しません。
例えば、100歳の患者さんが腱板断裂で来られて、もし手術を相談された場合に、おそらく僕なら
「ご年齢だけで手術をすべきか、そうでないかは決めていません。
ただ、腱板自体がもろくなっているのは事実あるでしょうから、再断裂のリスクも低くないです。
そもそも手術後に2ヶ月位装具で安静にして、片手の生活になります。
その結果、転んでしまうリスクも高まりますし、総合的に考えると手術はおすすめしません。」
って感じで説明すると思います。
これが僕が考える丁寧な説明です。
これが100歳を例にしたから、多分いくらお元気でもこういう説明をするかなぁと思ったんですが、雑で失礼な説明をする先生は、
これが60歳とか70歳とかの患者さんに対しても
「年だから意味ないよ」って言ったりするんです。

僕の場合はそのくらいのご年齢の方が、手術でよくなってくださるケースを何百回と拝見していますから、本当に信じられないんですよね。
第1位も結構、僕的には信じられないアドバイスです。
第1位 「その肩の痛みは首のせいだね」

ふんぞり男「それ、俺も言われたぞ、この間」
実際にそういうこともあるんですよ。
首から出て、肩の感覚を支配する神経がありますから。
首のヘルニアとか骨の変形とかで神経を圧迫してしまうと、神経による肩の痛みって出ることがありますし、腕が上がらない理由が首の神経であるケースもあるんです。
だから、ふんぞり男さんもそういうケースなのかもしれませんが・・
例えば、首を動かしたりして痛みが走りますか?
ふんぞり男「は?全然、首を動かしても痛くないよ。肩を上げようとすると痛くて上がらないんだよ、何回言わせるんだ!」
いや、この動画内では初めて聞きましたが、でもそうですよね。
そういう状況なのに首のせいにされちゃう患者さんが思いの外多くて、僕は信じられないんですね。
先程言ったとおり首が悪いケースもあるんです。
その場合、肩の痛みの原因が首にあるわけですから、その原因の部位を動かしたりすると、神経の圧迫が強まったりして症状が悪くなる、痛みが走るってことがあり得るんですね。
実際、そういう診察のテストもあります。
一方で肩を動かす際には、痛みの原因である首はなにも動かない、負担もかからないので、痛みが走るわけがないんですね。
首を動かすのはなんの問題もない、肩を動かすと痛みが増えるというふんぞり男さんの症状とは真逆ですよね。
もちろん、この説明はちょっと雑で、簡略化しすぎかもしれませんが、このくらいシンプルな話なんです。
首が大丈夫かどうか、厳密にチェックするになレントゲンのみならず神経を見るためにMRIが必要かもしれませんが、

少なくとも肩を動かしていたい、肩の可動域が狭くなっている理由が肩ではなく首っていうのは、信じられないんですよね。
まれに肩も悪いし首も悪いケースがあるので、首を注意すること自体は良いことだと思います。
ですが、どう考えてもメインだろうと思われる、肩を無視するアドバイスが思いの外、多くの整形外科や治療院で行われている現実があります。
なので、ご注意くださいね。
ふんぞり男「お前、今日はだいぶ敵を作ったな・・・」
やっぱりそうですかね・・。
これをご覧になって気分を害された整形外科医の先生や治療家さんがおられたら、本当にごめんなさい。

それでもここまでご覧いただいたことに感謝申し上げます。
今回のお話はかなり多分に僕の経験からくる僕の意見が混ざっています。
本来「すごいエビデンス治療」というこのチャンネルでは、医学論文などを引用しながら解説していくんですが、今回は引用論文なしとなりました。
それは医学論文を引用するまでもない当たり前すぎることを前提にしているということが主な理由です。
とは言え、僕の当たり前が他の先生の当たり前ではないかもしれません。
その可能性を否定せずに今後も情報発信をしていきますし、ご意見も真摯に受け止めていきます。
このチャンネルは整形外科医がエビデンス(論文)や医学的な知識を噛み砕いて「分かりやすさ」と「医学的な正しさ」両方を諦めない発信活動を続けております。
本日の一言

この動画も参考にしていただき、あなたなりのアドバイスの判断基準をしっかり持とう!ということになります。
🎁電子書籍「Shoulder Rule」プレゼント

肩の治療に関する渾身の電子書籍「Shoulder Rule」をプレゼント中です。
さらに特別限定動画「痛みに強くなる!-脳科学的痛み対策トップ3」を追加プレゼントします。
詳細はこちら▼
🎁治療家さん向けプレゼント
電子書籍「レッドフラッグ100選」

危険な兆候・症状・疾患を一気に学べる▼
