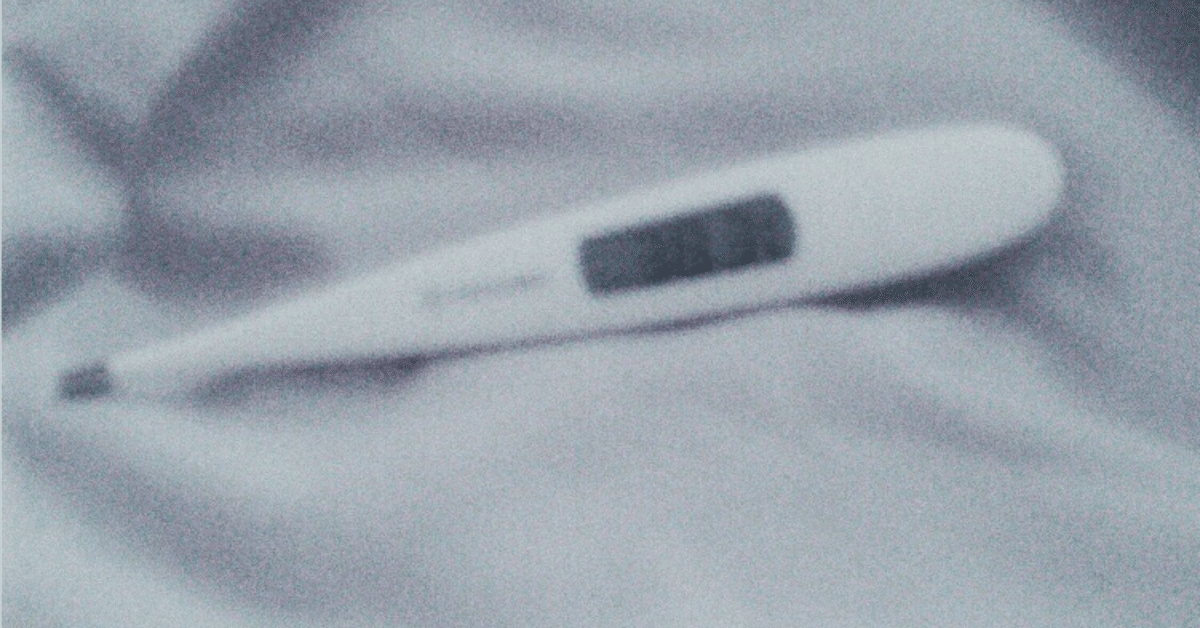
雨が止んだら -隠し事-
「あー、熱があるわね。早退する?」
「します。」
朝から雨が降っていたある日、雨衣はフラフラとした足取りで保健室に行ったきり帰ってこなかった。
後から先生に「水無月が早退するから荷物を保健室に持って行ってくれ」と頼まれた。
私は言われた通り荷物を持って保健室に向かおうとした。
すると、引き出しから一枚の紙がはらりと落ちた。それは、便箋に入った手紙だった。
「なんだこれ。」
雨衣は私の知らない間に告白でもされたのだろうか。でもそれがここにあるということは、きっと持って帰るのを忘れているし返事も忘れているだろう。
そんな妄想を勝手にして、そのときは手紙を適当にプリントの間に挟んで戻しておいた。
「というか……重っ!」
何が入っているか分からないが、雨衣のカバンは酷く重かった。
「何を入れたらこんな重さになるの。雨衣って毎日これを持って学校に来ているの?」
よくカバンが破れないものだと思いながら五キロのお米分はありそうなカバンを半分引きずりながら保健室へと向かった。
「あ、巡ちゃん!」
キラキラした表情の雨衣が保健室のベッドに座り先生と話していた。
「雨衣、あなた本当に熱あるんでしょうね?」
「あるよ!ね、先生!」
「三十八度五分、なのにこの元気なのよ。どうにかしてちょうだい。」
その姿はどこからどう見ても平熱の中、仮病で保健室に行った生徒だった。
「この子ずーっと、たこ焼きのタコはほじくって最初に食べる派ですか?とか、眼鏡をかけると少数民族になれるんだ〜とか。よく分からない事ばっかり言ってくるのよ、助けて日比野さん。」
「あー、なんかすみません。」
どうやら私が来るよりもずっと前から先生と話していたらしい。
雨衣があまりにもピーチクパーチクうるさかったものだから困っていたそうだ。それに彼女のことだ、もっと色々と先生を困らせる発言ばかりしていたに違いない。
雨衣は昔からそうだ。
熱が出るといつもの倍は喋る。いや、倍どころか三、四倍だ。
将来、お酒で酔ってもそうなりそうだなとたまに思う。もしそうだとしたら本当にやめて欲しい。介抱するのはきっと私の役目になるのだから。
あぁ、でもその時まで一緒に居られるのだろうか。最近、そのことばかり考えてしまう。まるで、この関係が無くなる事が決まっているかの様に。
何故かそれを覚悟してしまう。理由は分からない。
いつだったか、雨衣ととてつもない喧嘩をしたことがあった。その時は偶然仲直りできたけれど、また同じことが起きたらそうなるとは限らない。
でも今度はそんなことより悪いことが起きて一緒に居られなくなるのではと勘ぐってしまう。きっと私の思い違いでしかないのに、何故だか考えずにはいられない。
「水無月さん、ほらお迎え来たみたいよ。」
「はぁーい!」
私が何となく身支度している雨衣を見ていると、それに気づいたのか先生に隠れてピースしてきた。
本当に熱があるのかと疑わざるを得ない。
そして雨衣はとても重たい鞄を、さも何も入って居ない物かの様にひょいっと持ち上げた。
鞄の中身の事はあえて何も聞かなかった。
雨衣はあっけらかんとしているように思われる事が多いのだが、ここ最近は何か隠している様なそぶりがよくある。
あの手紙だってそうだ。その重い鞄だって。
単純思考なように見えて、たまに何を考えているのか分からないのが水無月雨衣という人間だ。
いつか私がそこへ踏み入れる権利を彼女はくれるだろうか。
そうしていると、高熱な上に重い鞄を持っているので今にも倒れそうだろうに、雨衣はいつも通りの笑顔でまた明日ねと言った。その声は少し鼻声だった。
「うん、また明日。」
教室に戻ると既に三時間目の授業が始まっていたので、私は小さな声で「遅れてすみません。」と教室に入った。
先生の話を聞きつつ、ふと雨衣の机に目をやる。
彼女の席は私の斜め向かいだ。
いつもは突っ伏したり、教科書で顔を隠して寝ている姿が見える机が、今は寂しそうに空席だった。
当たり前の景色が無いのはなんとも違和感がある。
そしてその引き出しには、はみ出したりクシャクシャになった大量のプリント、それには不釣り合いなあの手紙。
何が書かれているんだろう……
私は手紙の中身が少しずつ気になってきた。
何が書いてあるのか、誰から貰ったものなのか。
雨衣の引き出しに入っているということは、もちろん彼女への物なのだろうけれど、動物みたいに収集癖のある雨衣のことだ、どこかで偶然拾って後で見ようと机の中に閉まっている可能性もある。
なんにせよ、雨衣はその手紙を大事にしている気がした。でなければ、あそこまで綺麗に保管して置かないはずだ。
――次の日。
すっかり元気になった雨衣がそこには居たのだが、私に対する第一声は
「巡ちゃん、私の机の中見た?!」
だった。
「いや、特には見てないけれど、その小テストのプリントとかは嫌でも目に入ると思うよ。」
「え!やだやだ、パンツ見られるくらい恥ずかしい!」
「だとしたら、パンツ見えすぎでしょ。」
雨衣は慌てふためいていたが、どこか安堵している風にも見えた。
そんな雨衣を見て、やはりあの手紙は大事なものなのだと確信した。
私にも言えないくらい大切な秘密の手紙。
その日私はずっとモヤモヤしていた。何だかそれがとても嫌だったから。
「隠し事」それは私たちの間に無いようで、在るものになった。
いつも一緒に居るし、なんでも話せる仲なのでそんなものとは無縁だと思っていたけれど実際はそうでも無かった。
だからこそ、なんだか気持ちがソワソワしてモヤモヤした。
その気持ちと相まったのか、窓の外を見るとポツポツと雨が降ってきていた。
今日も雨か。
「雨衣、ごめんね。」
「え?」
私も雨衣に隠し事をしてしまった。
-隠し事-
~終わり~
