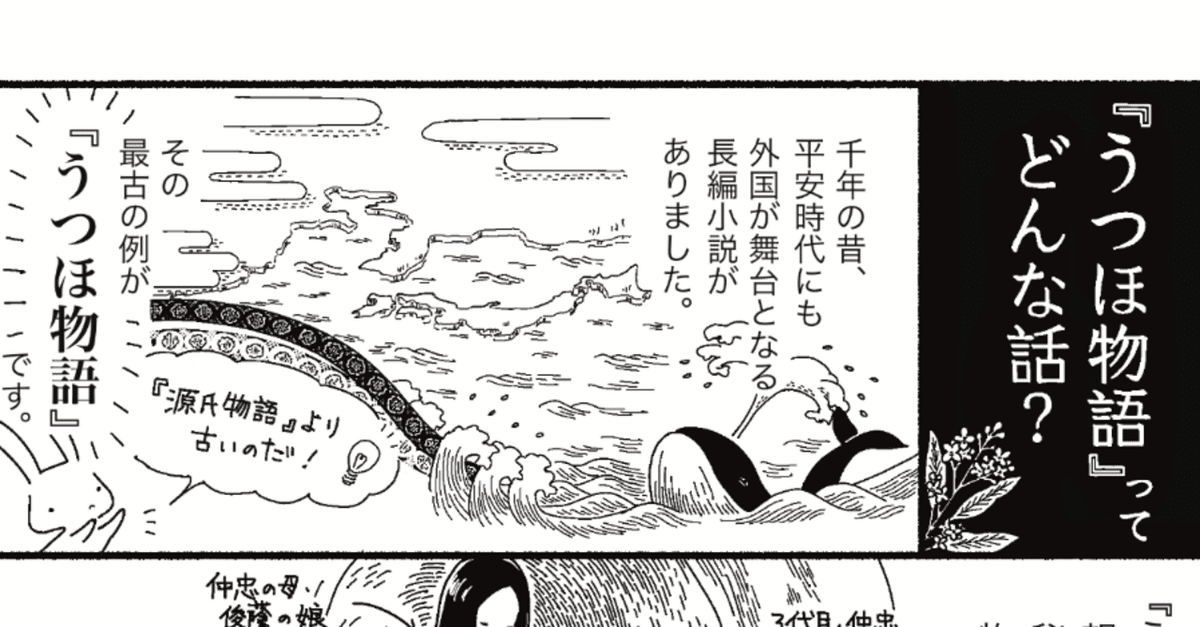
【漫画】“外国“が舞台の平安文学 ー 『うつほ物語』ってどんな話? ー

かな文字が広がり、多くの物語が生まれた平安時代。
唐との正式な外交がなくなったこの時期に生まれた日本の風土や感性を重視する文化を「国風文化」といいますが、その頃にも外国を舞台とする物語がありました。
そのうち最も古く、『源氏物語』にも影響を与えたと言われているのが『うつほ物語』です。
“うつほ“で育った貴族の秘琴伝授の物語
『うつほ物語』は親子4代にわたる秘琴伝授の物語。3代目にあたる藤原仲忠を主人公とし、貴族の求婚譚や皇位継承をめぐる対立を絡めながら話が進んでいきます。
この20巻に及ぶ日本初の長編物語がいつ、誰によって書かれたかは定かではありませんが、室城秀之氏は『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 うつほ物語』の後書きで、『蜻蛉日記』の頃(つまり『源氏物語』の少し前)に書かれたのだろうと述べています。
・
タイトルの「うつほ」を「宇津保」と書く場合がありますが、この漢字は当て字で、特に意味があるわけではありません。
ここでいう「うつほ」とは「 洞」のこと。
貧しさに苦しむ仲忠は6歳のとき、山の中で、4本の大きな杉の木が上のほうで重なり合い、根もとのあたりが人が住めるような大きな空洞になっているのを見つけました。そこにはもともと熊の一家(!)が住んでいたのですが、仲忠の孝行心に感動した熊から譲られ、母と二人この洞に移り住みます。仲忠はそこで、猿たちが運んでくる木の実などを食べながら、秘琴伝授の日々を送りますが(まるでおとぎ話のような世界!)…この洞がタイトルの「うつほ」となったのです。
『うつほ物語』における“波斯国”と実際の波斯国
さて、件の外国が舞台となるの箇所は冒頭「俊蔭」の巻にあります。
藤原俊蔭は、仲忠の祖父で、琴の一族の創始者となる人物です。
彼は天才というべき人で(”人”といっても物語内では「天女の行く末の子(天女の将来の子)」と言われているので常人とは違うのですが…)、16歳で遣唐使に選ばれ出国します。
しかし唐につく前に難破し、波斯国に流れ着きました。
ひとり泣いていると白馬がやってきて、俊蔭を栴檀の林に連れて行きます。そこでは3人の人が、虎の皮の上に座って琴を弾いており…そこから、俊蔭が秘琴を手にし奏法を会得する旅が始まるというわけです。
・
ここで”外国”として出てくる波斯国はまるでファンタジーの世界のようで、明らかに現実とは異なります。
ですが、波斯国はまったくの想像上の国というわけではありません。
『続日本紀』には、唐から帰国した遣唐使が、736(天平8)年8月に唐人3人、波斯人1人を連れ聖武天皇に拝謁したという記録が残されています。
中国で波斯国はササン朝ペルシャのことだと言われているのだそうですが…唐に行く途中で難破した俊蔭がペルシャに漂着するとは考えにくいため、物語内の”波斯国”は、東南アジアのどこかだと言われています。
いずれにしても『うつほ物語』の作者にとって”波斯国“は、実在の国として写実的に描写すべきものではなく、「唐ではないどこかの国」として名前を借りられれば十分というものだったのでしょう。
平安貴族の外国観と琴の間違った描き方 ー 神聖なものと貴ぶが、尊重はしていない?
しかし物語上の”波斯国”が「現実とは異なる世界」として描かれているとはいえ、当時の外国の書き方にはつい違和感を覚えてしまいます。
俊蔭は、異界としての”波斯国”を巡ったあと、仏の予言を受けて日本に帰国します。その際に「波斯国」へわたり、帝と后と皇太子に琴を贈るのですが、このときの「波斯国」は実在の国とみてよいでしょう。
にも関わらず、
・言葉や文化の壁がない
・国家体制が平安時代の日本と同じ様子
など、「外国」としての描かれ方をしていないのです。
なお、江戸時代のことになりますが1806(文化3)年に描かれた『うつほ物語』の絵入本では、”波斯国”で出会った人が日本の平安貴族とほぼ同じ格好をしていて…これには思わず笑ってしまいました。
・
少し話はそれますが、上の解説漫画を描くにあたり琴について調べた際におもしろい発見がありました。
『うつほ物語』で重要なアイテムである琴は「こと」ではなく「きん」と読み、いわゆる「おこと」とは別の楽器です。
平安時代に「琴」と言われる弦楽器には「箏の琴」「琴の琴」「和琴」「琵琶」の4種がありました。
箏の琴は13弦の楽器で、「おこと」として現代も私たちに親しまれているもの。和琴は6弦の楽器で、琴軋というピックで掻き鳴らすように弦を弾くのだそう。琵琶は見た目のイメージがしやすいですね。4本の弦を撥で弾いて音を鳴らします。
では問題の琴の琴はというと、こちらは7弦の楽器で、箏や和琴と違い琴柱がないのが特徴です。
箏や和琴は胴の上に柱を立てて弦を支えることで音程を決めています。それに対し琴柱がない琴の琴では、胴の表面につけられた13個の徽を目印として左手で弦を押さえ音程を調整するのだそう。そのため奏法が難しく平安時代中頃には廃れてしまったと言われています。
他にも琴の琴の特徴としてサイズの小ささが挙げられます。箏が約180cm、和琴が約190cmもあるのに対し、琴の琴の長さは125cmほどなので、だいぶ小ぶりです。中国では琴机の上にのせて弾くことが多かったそうですが、平安貴族は両膝の上に置いて弾きました。
これらのことを踏まえて絵巻物を見ると、「おや?」っと思います。
絵の中で俊蔭たちが弾いているのが琴の琴ではないからです。
これは『源氏物語絵巻』などでも同じで、琴の琴として描かれている楽器に琴柱があったり、サイズが大きすぎたり、弦の数が違ったり…琴と箏を混同しているようなのです。当時の人々(現存の絵巻は鎌倉時代以降のものがほとんどですが)は、物語の作者も含め、琴の琴がどんなものかわからないまま描いていたのでしょう。
・
こうした琴の琴の誤った描き方と、物語内の外国の描き方には少し近いものがあるような気がします。
琴の琴は、皇族系の人が弾いたと言われており、『源氏物語』の光源氏は当代一の名手でした。源氏は晩年に正妻として迎えた女三の宮(朱雀院の娘で皇族)に自ら琴の琴を指導していますが、紫の上(源氏の妻だが皇族ではない)にはそのようなことはしていません。
『うつほ物語』の俊蔭も血筋がよく、秘琴を奏でることで奇瑞を起こし人々を感嘆させます。奈良時代に唐から伝わったとされるこの楽器は、どこか特別な力を感じさせる神聖なものだったのです。
当時の人々の外国観にも似たものを感じます。
最後の遣唐使派遣が838年なので、平安時代中頃の京都には、外国に行ったことのある人も、外国経験者から直接話を聞いたことのある人もほとんどいなかったはず。太宰府や越前には外国人の渡航はあっても京に入ってくることは滅多になかったでしょう。
そのような中、貴族たちは民間貿易を通じて入手した「唐物」を好んで使用していました。異国から仕入れた唐物の所有は権威の象徴でもあったのです。『うつほ物語』の俊蔭が、出国から23年後、39歳になって帰国してすぐに式部少輔に任ぜられ東宮の学士(教育係)になったのも、彼が異国を経験したということと無関係ではなかったのかもしれません。
・
しかし、このように貴んでおりながら、外国を正確に描写しようという意識は希薄で、そのことがかえって相手を尊重していないように感じさせます。
平安貴族たちは、唐物に囲まれながらも異文化を肌で感じるような体験はなく、外国はあくまで憧憬の対象として遠くにあるものだったのかもしれません。
ファンタジー要素が強く、『源氏物語』とはまた違った魅力のある『うつほ物語』。その“外国”の描き方をとても興味深く思いました。
【参考】
川島絹江(2010)「源氏絵における琴(きん)と和琴の絵画表現の研究」『東京成徳短期大学 紀要』第43号, p.67-82
室城秀之編(2007)『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 うつほ物語』角川ソフィア文庫
室城秀之訳注(2023)『新版 うつほ物語 一 現代語訳付き』角川ソフィア文庫
川村裕子著 早川圭子絵(2023)『はじめての王朝文化辞典』角川ソフィア文庫
関連記事はこちら!

