
わかりやすすぎる均等論:均等侵害を必要以上に怖がらないために
均等侵害って何それこわい! と思ってませんか?
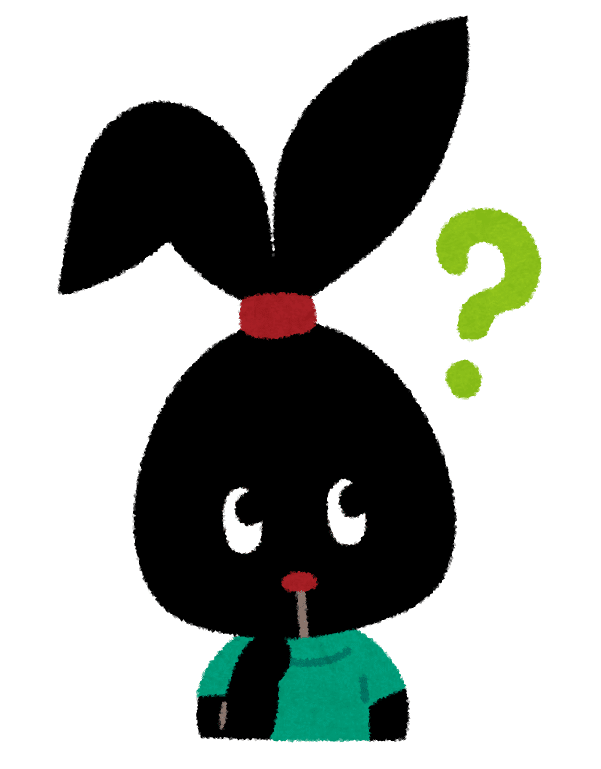
「均等論」とか「均等侵害」って、聞いたことはおありでしょうか? 弁理士や弁理士試験の受験者の方なら必ず知っている言葉でしょう。一方、特許業界以外の方にはあまり馴染みがないと思います。ただ、一般の方であっても、例えば手芸などの物作り・創作活動をされている方にとっては、まったくの無関係とも限りません。例えばある日、その手芸分野で特許を取得した人や会社が現れたり、さらにその特許権者から警告書が届いたり、といったことがあり得ます。その文面に、もしかすると「均等侵害」という言葉が書かれているかもしれません。
均等論とは特許関係の用語で、特許侵害における例外的な取扱いの一種を指します。特許というのは、原則として文章で記述された特徴によって全て決まり(後で説明します)、その特徴を言葉通りに解釈してそれを避けていれば特許侵害にはならないんですが、ごく稀に(一定の要件を満たせば)、文章に書かれた内容とは微妙に違っていても、侵害が成立すると認められることがあります。これが「均等論」であり、「均等侵害」です。
筆者は特許事務所で弁理士(特許等を扱う専門職)をしておりますが、この「均等侵害」あるいは「均等論」について、どうも皆さん誤解しがちなのではないか、という事例を最近、いくつか見かけました。一般の方が知らない、というだけではなくて、弁理士でも正確に理解していない人が意外と多いようです。その結果、均等論・均等侵害という言葉が独り歩きし、均等論について「なんかよくわからないけど怖い!」みたいな認識が広まってしまっているようです。

本記事では、この均等論・均等侵害について、可能な限りわかりやすく解説してみたいと思います。簡単に言えば、「均等侵害なんて、わかってしまえば大して怖くないよ!」といった内容です。特に、「自分の実施している技術があの特許の均等侵害になっていないか心配」「他人から、自分の製造販売している製品はこの特許の均等侵害ではないかと言われた」といった方は是非ぜひお読みください。少々長いですが、その分バチクソわかりやすく書いてますんで、きっとお役に立てると思います。また、「弁理士は均等論なんかに最初から頼るつもりで出願してちゃいけませんよ」という話でもあります。「弁理士試験の時にがんばって5要件を頭に詰め込んだけど、正直よく理解してないよ~」という弁理士の方や、その他知財関係の業界で働いている方にもわりと参考になるはずです。
†
特許権、その権利範囲とは
さて、均等論というのはあくまで例外的なものであって、例外を理解するにはまず原則を知る必要があります。そこで、均等論の前に、特許権における権利範囲の考え方について、基本を解説しておきます。権利範囲とは、つまり「どんな形の技術が特許の侵害に該当し、どんな形なら該当しないのか」ということです。特許法においては、この権利範囲は「文章」で決まります。より正確に言うと、「特許公報」の「特許請求の範囲」に書かれた文言です。特許庁から発行される特許公報には
・要約
・特許請求の範囲
・明細書
・図面
という4つの項目がありますが、言ってしまえばこの中で大事なのは「特許請求の範囲」だけです。他の項目に書いてあることは、あくまで「特許請求の範囲」(大抵、めっちゃ読みにくい変な堅い文章で書かれています)を理解するための補足に過ぎないので、あまり気にしなくてよいです。

ある製品が、その特許の侵害に該当するかどうかを判断したい場合には、特許公報の「特許請求の範囲」に注目します。中でも、そこに並んでいる「請求項」のうち、独立請求項(他の請求項を引用していない、つまり「請求項○に記載の~」などと書いていない請求項)を気にしてください。「請求項1」がそれです(他にも独立請求項があって、そちらも気にした方がいい場合もありますが、基本的には、とりあえず「請求項1」だけでいいです)。
その独立請求項には、技術的な特徴がいろいろと書かれていると思います。その特徴と、対象の製品を比較します。請求項の文言ひとつひとつと、製品の特徴を比べていって、製品が請求項に書かれた上記特徴を「全部」備えていれば、特許侵害が成立します(均等論による侵害を「均等侵害」と呼ぶのに対し、これを「文言侵害」と言ったりします)。逆に、一部でも備えていなければ、侵害になりません。基本はこれだけです。
†
恐怖の均等侵害……?
ところが、ここで安心していると、思わぬところで足を掬われるかもしれませんよ、などと巷で噂されているのが、問題の均等論です。実は例外的に、請求項の文言と完全に一致しなくても(つまり、文言侵害が成立していなくても)侵害になってしまう場合もありますよ、というんです。
これは怖いですね。上に説明したように、特許侵害は請求項の文言によって決まるんだから、それを避けていればいいんでしょ、と思って安心して商売や技術開発や創作活動に励んでいるところに、いきなり特許権者から警告書が来たりするわけです。公報(特許請求の範囲)に「この特許はこれこれこういう内容の発明です」と書いてあるもんだから、その内容を信じて、特許侵害にならないよう、自分の製品を作っていたのに、その公報に書いてあることが当てにならないというんですから、もはや何を基準に製品開発や商売をしたらいいのかわかりません。

†
実はそんなに怖くないよ
でも、「もう何を信じていいのかわからない!」と悲観して崖から身投げする前に、均等論というものを理解しましょう。そうすれば、均等論はそこまで怖くないし、胸を張って商売や技術開発や創作活動を続けていいんだ、とわかり、希望とともに明日を歩んで行けるはずです。

ここで結論を先に言っておきますと、実務上、均等侵害が認められるケースは非常に稀です。なぜなら、均等論はあくまで例外的で特殊な取扱いだからで、裁判所がこれを検討する際には実に慎重かつ厳格に判断します。特許法の運用上、均等論という例外が一部に存在してはいても、「特許の権利範囲は請求項の文言で決まる」という原則は原則として揺るがないわけです。
そして、もし特許権者の代理人弁理士などが均等侵害などを言い出してきたら、それは要するに、特許侵害の成立について自信がないか、そもそも均等論の内容や取扱いをよく理解していないからです。均等論を持ち出して依頼人の特許権を広く見せようとしたり、均等侵害の怖さをやたらと吹聴しているような弁理士がいたら、特許と対象の製品との違いがよっぽど微妙なものでない限り、あ、この人よくわかってないんだな、ぐらいにとりあえず思ってください(なにしろ、弁理士でも均等論をわかっていない人は実際多いので)。まあ、それでも均等論が成立する場合も皆無というわけではないので、心配な方は、弊山田特許事務所にご相談ください。技術鑑定(特定の製品などについて、それが特定の特許権を侵害しているかどうかを弁理士が調べ、侵害してると思います、とか、してません、といった見解を述べるというやつ)もやってますんで。
†
⚠️技術鑑定、依頼先に要注意⚠️
あ、ここでひとつご注意を。特許権者の代理人である弁理士等が、その特許権について「ご心配なら鑑定しますよ」なんて言ってくることがあります。これ、半ば罠の可能性があります。
いや、罠というと言葉が悪すぎるかな。これは別に、そういう弁理士が悪徳だとか言いたいわけではなく、特許権者の代理人としての弁理士はそういう性質のものだということです。基本的に、代理人というものは、物事を依頼人にとって有利になるよう解釈しようとするものです。それ自体は悪いことではないというか、代理人ならむしろそうするべきでもあるんですけど、その人に技術鑑定を頼んだとして、第三者的な視点で公正な判断がしてもらえるかというとまあ、そうはならない(特許権者寄りの見方をしてしまう)ことが多いと思うんですよ。当然ですよね。
つまり、皆さんが何らかの特許について技術鑑定を依頼する場合には、その特許権者の代理人ではない弁理士や特許事務所を探して依頼するようにしてください。でないと、万一、その弁理士が悪徳寄りの人物だったりした場合、「本当は侵害してない可能性が高いのに、侵害かもよ、侵害してますよ、勝手に売ったら裁判ですよ……と脅されてしまって、実施料(ライセンス)契約をさせられる」みたいなことにもなりかねません。そこまで悪徳でなくても、「侵害してるかどうか微妙だけど、特許権の行使はしないという約束で安めの実施料契約をしましょうか」ぐらいにはなるかもしれません。特許権者とその代理人からすれば、「私が御社の特許を侵害しているかもしれないのですが……」なんて相談を持ち込んでくるような人は、はっきり言って格好のカモ(というとまた言葉が悪いので、「ビジネスチャンス」ぐらいに言い換えましょうか)なんです。まあ、中には特許権者側につきながらも良心的かつ公平に判断しようとする弁理士もいるとは思うんですけども。

ともかく、「鑑定(侵害の判断)の依頼は第三者に」、これ、しっかり覚えておいてください。特に、特許権者・代理人弁理士が均等侵害に言及しているような場合は、特許権を拡大解釈して、本来なら侵害が成立しないものをあたかも成立するかのように言いくるめようという意図もあるかもしれません。ご注意を!
あ、あと、特許庁がやってる判定制度というのもありますよ。第三者の立場からの客観的な判断が期待できます。まあ、弁理士の鑑定にしろ特許庁の判定にしろ、それなりの費用がかかるんですが(すみません、我々も商売ですんで)。
†
均等論とは何か? 正体を知ろう
そもそも均等論とは何なのか、何のために生まれた概念なのか。これを理解してしまえば、均等論や均等侵害は決してむやみに恐れるようなものではありません。以下では、これを可能な限りわかりやすく、噛み砕きに噛み砕いて説明していこうと思います。
まず、日本において均等侵害の要件を最高裁が示したことで有名な「ボールスプライン軸受事件」。この判決によれば、均等侵害を認めるべき理由は次のようなものです(難しいので読み飛ばしていいです。すぐ後から説明します)。
「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」
†
どういうことかというと、例えば、金属といえばアルミニウムしかない星を仮定してみてください(あくまで仮定ですよ)。その星ではアルミ以外に金属が存在しませんから、金属=アルミです。
その星にも、日本と同じような特許制度があるとします。その星で、「アルミ製の鍋」と請求項に書かれた発明が特許になったとします。

そういう星に、ある日隕石が降ってきました。分析の結果、隕石にはアルミニウムではない金属(鉄)が含まれていました。「アルミ以外にも金属があった!」というわけですから大発見です。
で、その鉄を使って鍋を作る人が現れます。アルミ製ではないので、上記特許の侵害にはならないよね、と思って作っちゃったわけですが、いやいや、それはやっぱり侵害ですよ、というのが均等侵害です。

なぜ、このような考え方が認められるのかというと、「アルミ製の鍋」という特許を出願した時点において、アルミ以外にも金属があることなんてその星の誰も知らなかったわけです。だから、鉄とかいう金属が現れるのを予測して、それをも権利範囲に含む形で特許出願をする、なんて芸当は普通に考えて不可能でした。こんな場合にまで「請求項の文言が全て」という原則を徹底するのは特許権者がかわいそうだろう、ということで、均等論という考え方が導入されました(他にも、均等論が生まれた英語圏では、英語という言語に抽象的な語彙が少ないため、実際上、いろいろな形態を含む請求項の文章を作成することが困難、という事情もあったりしたようですが、これが日本に導入された理由はだいたい上のような趣旨、ということです)。
†
均等論が認められない場合とは?
さて、こうして鉄が発見された後、その星でも地下に鉄の鉱脈が見つかり、鉄の利用が広まります。それまでアルミで作られていた品々、刃物とか調理器具とか機械とか……を鉄で作ってみよう、という技術者が大勢現れ、その技術で特許を取ろうという人も中には出てきます。その中で、「鉄製の刃を備えたハサミ」という特許を誰かが取得したとします。そこで、鉄じゃなければ大丈夫だろう、といって、刃がアルミ製のハサミを作る人が現れます。
これは侵害になりません。具体的(専門的)に言うと、アルミ製のハサミは、少なくとも均等侵害の第4要件、「対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから前記出願時に容易に推考できたものではないこと」を満たさないので、均等侵害は成立しません。
わかりやすく言えば、その星ではアルミや、アルミでできたハサミ自体が既に知られていたので、もし仮に「アルミの刃を備えたハサミ」とか「金属の刃を備えたハサミ」という発明を特許出願していても、特許にはならなかったわけです。だから、上の特許技術「鉄製の刃を備えたハサミ」の刃をアルミに変えた形態は誰でも自由に使っていい技術であって、特許侵害にはなりません、ということです。
†
均等侵害の要件、その他
他の例も考えてみましょう。
《例1》次のような特許があった場合、製品A、B、Cはそれぞれ特許を侵害しているでしょうか、していないでしょうか。
(特許)白色の硬質材料でできた部品aを備えたナントカ装置。
(製品A)部品aが白色の軟らかい材料で作ってある。
(製品B)部品aが緑色の硬い材料で作ってある。
(製品C)部品aが白色の硬い材料で作ってあるが、表面に別の色が塗ってある。
※ただし、部品aについて、白色以外のものや、柔らかい素材のものも一般的に知られているとする。
(こたえ)製品A、Bは特許侵害ではない。製品Cは特許侵害。
専門的に言うと、製品A、Bは均等侵害の第5要件「対象製品等が特許発明の出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当するなどの特段の事情がない」が不成立で、均等侵害にならない可能性が高いと思います。特許権者は、出願の際、部品aの素材に関し、わざわざ「白色の」とか「硬質」と限定しました。この限定を入れたということは、つまり白色ではない部品aや、硬質ではない部品aも意識しており、その上で「白色の」「硬質」材料、と請求項に書いた(白色以外、硬質以外の材料を特許請求の範囲から除外した)ことになります。部品aの材質が白色でない場合や、硬質でない場合に関しては、特許出願の際、「特許請求の範囲から意識的に除外された」と言えるわけです。
製品Cに関しては、均等侵害を考えるまでもなく、普通に特許侵害(文言侵害)になるでしょうね。表面に色がついていても、白色の材料でできていることには変わりないからです。
なお、出願当時、部品aに関して世の中に硬質のものしか存在しなかったとか、白色のものしかあり得なかった、といった事情があった場合は、製品Aや製品Bによる均等侵害が成立するかもしれません。また、部品aの色が白じゃなくてベージュ、ぐらいの違いだと、これは普通に文言侵害かな(均等侵害かも)。
†
《例2》次のような特許があった場合、製品D、E、Fはそれぞれ特許を侵害しているでしょうか、していないでしょうか。
(特許)部品bの内部が空洞で、その中に入っている部品cが簡単に取り出せるようになっているカントカ装置。
(製品D)部品bの内部が硬い樹脂でがっちり固めてある。
(製品E)部品bの内部に綿が詰めてある。
(製品F)部品bの内部が柔らかい樹脂で埋めてある。
(こたえ)製品Dは特許侵害ではない。製品E、Fは特許侵害。
専門的に言うと、均等侵害の第2要件「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること」を満たしません。均等侵害が成立するには、特許発明と同じ効果がないといけないわけです。製品Dは、硬い樹脂で中を固めてあり、「部品cが簡単に取り出せる」という効果が得られませんから、これでは特許発明と同じとは言えず、侵害になりません。
製品Eに関しては、綿を取り出せば普通に部品cも取り出せますから、同じ効果が得られると言えますね。ただ、綿が詰めてあるとしても部品b自体は空洞に変わりないので、均等侵害ではなく普通に文言侵害ということになると思います。製品Fも同様です(ただ、柔らかい樹脂といってもいろいろ考えられますから、例えば樹脂が柔らかくても部品bと癒着していて簡単に取り出せないような状態なら非侵害でいいと思います)。
†
均等論は弁理士を甘やかすためのものではありません
特許侵害(直接/文言侵害、均等侵害)の考え方は、だいたいこんな感じです。ここでは説明のためにかなり単純化した例を仮定してみましたが、実際に訴訟などで均等論が検討される場合、事情はもっと複雑です。そして、その複雑な事情を背景に特許権と製品を対比し、均等侵害の要件(5つあります)を見ていくと、そのうちのどれかを満たさず、侵害は成立しないことがほとんどです。また逆に、均等侵害の5要件が成立しそうな場合、そもそも均等侵害を持ち出すまでもなく文言侵害で済むよね、というパターンも多いです。つまり、均等侵害の検討が必要になるのは文言侵害が成立しない場合ですが、文言侵害が成立せず、それでいて均等侵害は認められる、という場合は稀なんです。
なぜ、均等侵害の成立条件にこんなややこしい5要件が設定され、均等侵害が認められる場合が狭く限定されているのかというと、繰り返しになりますが、特許制度においては「特許権の範囲は請求項の文言で決まる」という原則が強固であり、また、その原則を相当強固に守らなければ不都合が起きてしまうからです。不都合というのは、「特許権が拡大解釈される」「それによって、本当なら特許侵害にならない(=自由に製造販売していい)はずの製品まで、作り手や販売者側が侵害を恐れて自主規制してしまう」「つまり、特許権者が、本来なら特許権が及ばない範囲にまで、事実上の禁止権に類する効果を及ぼすことができる」といった問題のことです。そういうことが起きないために、特許というものは、誰が見てもその権利の範囲を判断できるよう、「請求項の文章」という形ではっきり決めておく必要があるんです。
そして、特許の出願人/特許権者は、出願の際、請求項の文言を自分で自由に決めることができます(もちろん、審査で特許性が認められる範囲内に限りますが)。特許権の範囲は、こうして特許権者が自分で決めたのですから、その責任は特許権者自身が持つ(つまり、自分で決めた範囲を勝手に拡大しない)のが当たり前の道理です。特許公報は、「構成要素A、B、Cを全部含むものに限って侵害と見なしますよ」と特許権者側から文書の形で公式に明言するという性質のものと言えますが、それなのに、後から「やっぱ構成要素Aはなくても侵害ってことにするわ、失敬失敬」なんて、よほど仕方のない事情でもない限り、普通に考えて通りませんよね。「え、アンタが最初に構成要素A必須って決めたんやん!」という話です。そのために、裁判所は5要件を慎重に判断しており、結果、その「仕方のない事情」(均等論)が認められるケースは非常に稀なんです。
ふたたび上の「鉄製の刃を備えたハサミ」の発明の例に戻ると、鉄とアルミという金属が既に知られているのですから、特許を出願する際、「金属製の刃」とか「アルミ製または鉄製の刃」と請求項に書いておけば済んだだけの話です。それが可能だったのに、出願人自身が、わざわざ「鉄製の刃」と素材を限定して出願したのです。だったら、鉄でない金属(アルミ)の刃を備えたハサミが特許の権利範囲の対象にならないのは、まず第一に出願人/特許権者の責任です。均等論は、その責任を踏まえた上で、「でも不可抗力でそう書いちゃった場合(例えば上に説明したような、その技術の登場を予測・想定できなかった場合)はさすがに仕方ないよね」と例外的に認められるものであって、弁理士が作った請求項がユルユルだった場合にまで認めていいようなものではありません。
もし、このハサミのようなケースにまで均等論が認められるということになれば、単に請求項の作りがいい加減だったような場合でも、均等侵害という言葉を後出しするだけで、「請求項の文言と全部一致してなくても、だいたい一致してれば侵害」ということにできてしまいます。そんなことがまかり通ってしまうとしたら、とりあえず適当に特許を取っておいて、それと似た製品を製造販売している人を片っ端から訴える、なんていうムチャクチャなことも可能になります。だから、均等論が認められるケースは非常に少ないわけですし、だからこそ、弁理士は特許出願の際、請求項の言葉を慎重に慎重に慎重を重ねて選ばなければならないわけです。
†
誤解される均等論
均等論のあらましは上のようなものですが、実は専門家である弁理士にも「均等論や均等侵害という言葉は知ってるし、意味もなんとなく理解してるけど、中身はよくわかってない」という人や、「なんか要件とか多いし専門家でも難しいんだよね」などと思ってしまっている人は多いです。そして、わかっていない人が多いゆえに、そういう人が「均等論っていうものがあってね……」と噂を広めることで、均等論が必要以上に恐れられている現状があるように思います。でも、ここまで見てきたように、基本的な考え方は決してべらぼうに難しいものではないですし、具体的に見ていくと、均等論が成立するケースはそう滅多にありません。
では、なぜ均等論/均等侵害という言葉がこんなふうに独り歩きしてしまっているのかというと、「弁理士試験では頻出だけど、実務では滅多に扱わない」トピックだからじゃないかと思います。均等論については有名な5要件というものがあって、いかにも試験問題にしやすいんですよ。だから弁理士試験によく出るし、受験者は全員、これを頭に叩き込む。さらに、上でも説明したように特許にはそもそも「請求項の文言で権利範囲が決まる」という強力な原則があります。弁理士試験の受験者の頭には、その原則がしっかり根を張っている。そこに、「実はその原則がひっくり返る場合があるんです!」という触れ込みで「均等侵害」というものが登場するので、これは多大なインパクトがあるんですね。

で、そのインパクトと、均等5要件をがんばって覚えた体験が心に刻みつけられた状態で弁理士試験に合格するんですが、弁理士として仕事を始めてみると、均等侵害に実際に接する機会なんてほとんどない。裁判で認められる例も少ないし、したがって裁判で均等論を主張する人も多くないし、そもそも特許関連の業務をしていて訴訟沙汰になること自体がレアケースですから。だから、「均等論は難しい、恐ろしい」というイメージだけが多くの弁理士の頭に残り、それが都市伝説みたいに広がってしまうわけです。
†
均等論に惑わされるな!
ここまで均等論について長々と説明してきましたが、要するに「均等論、一見こわいけど、しょせん例外は例外」ということです。例外も認められることはたまにあるとは言え、とりあえず原則の方を気にしましょうよ、ということ。
これを前提に、少なくとも弊所では、次のような基本姿勢でもって「特許請求の範囲」の作成を行っています。
・発明品の表層的な特徴でなく、発明の根幹部分をまず把握する。
・把握した根幹部分を過不足なく表現するよう、請求項の文言を考える。
・表層的な特徴については下位請求項に記載し、請求項1には記載しない。
「特許請求の範囲」の作成は、特許の出願業務で最も重要な根幹にあたる作業です。弁理士や特許事務所は依頼人の代理で出願業務を行うわけですが、この「特許請求の範囲」の文言こそ、依頼人が将来的に取得する権利を直接的に左右する部分だからです。依頼人の利益を最大化するのが代理人の責務ですから、「特許権の範囲は請求項の文言で決まる」という大原則を踏まえ、権利範囲をなるべく大きく広く確保するために、請求項1には特許性が認められ得る限りにおいて最少の事項(発明の根幹部分を捉えるのに必要な最小限の文言)のみを記載するんです。
例えば、根幹部分が「特徴Aと特徴Bの組み合わせ」という発明があったとします。ここで、うっかり「特徴A+B+Cを備えた装置」と請求項1に記載してしまうと、「特徴A+Bのみ備えた装置」は文言上の権利範囲に含まれません。よって、「特徴Cを備えず、特徴A+Bのみ備えた装置」を他者が無断で実施していても、「権利範囲は請求項の文言で決まる」という原則に基づく限り、特許権者はこれを禁止できません。それでも禁止したい場合には、均等論を主張する、つまり「特徴Cは発明の根幹部分ではない」と主張する必要があります。
これは、上に述べた特許請求の範囲の作成における基本姿勢から考えると失策です。依頼人の特許権を広く取るためには、「請求項1に余計なこと(表層的な特徴)を書かない」のが重要なわけですが、均等論を主張するということは、請求項1に余計なこと(特徴C)を書いてしまいました、と白状するのと同じことですよね。つまり、特許侵害を主張するために均等論を持ち出さなくてはならない状況というのは、その特許の請求の範囲を作成した弁理士にとっては、結構恥ずかしいことだとも言えます(まあ、弁理士や特許事務所によっていろいろな考え方があるとは思いますが、少なくとも弊所の方針に沿って考えればそうなるということです)。
で、均等論(「特徴Cは余分でしたすみません」)を主張した結果、それが認められれば、まあ弁理士が恥ずかしい思いをしただけで、特許権者の利益は守られましたね、よかったね、で済むんですが、認められなかった場合は大変です。場合によっては、「なんで請求項1に特徴Cなんて追加したんだ!」と責任問題に発展しかねません(まあ普通は、そうならないように、「請求項1に特徴C入ってますけど、この内容で出願していいですか」って事前に確認を取りますけどね)。そして何度も書いてきたように、裁判で均等論が認められるケースは稀です。結局、均等論なんて始めから持ち出さずに済むよう、請求項1に余計な特徴を書かないのが一番いいってことです。

†
やめよう、拡大解釈
ここからは同業者(弁理士や知財部の方など)向けにちょっと小難しい言葉(職務上の通常運転の言葉遣い)で書きます。
上に見てきたように、均等論/均等侵害という考え方が問題になるのは、特許と対象製品との間に違いがあり、かつそれが背景の事情まで含めて微妙なものである場合に限られ、認められることは稀です。にもかかわらず、世間では「請求項だけ見て侵害を回避したと安心してはいけない、均等侵害という恐ろしいものがあって……」という方がいたり、さらには弁理士にまで、均等侵害の範囲を広く見てしまう人がいるようです。
筆者は一弁理士として、このような状態を憂慮しています。特に特許権者やその代理人弁理士がそのような主張をする場合、それは均等論を利用した権利範囲の拡大解釈になり得ると考えるからです。世間において、均等論というものが原理原則として確立しているのであればともかく、実際には均等侵害はあくまで例外的な取り扱いであって、しかも認められるケースは稀なんですから、最初から均等侵害を前提に権利範囲を論ずるのは拡大解釈でしかないでしょう。さらには、特許出願において最も重要な手続きである「特許請求の範囲の決定」の軽視にも繋がりかねません。
†
そもそも、特許権は請求の範囲の記載によって決まることが大前提であって、その例外的な取扱いとして均等論が導入された趣旨は、「あらゆる侵害態様に対応できるように特許請求の範囲を記載するのは容易でないこと」「発明の構成要素の一部を出願時に想定されていなかった別の要素に置き換えるなどの方法で容易に特許権を回避し得ること」であるはずです。とすれば、出願時に容易に想定し得、容易に権利範囲に含め得るような形態が、請求項の文言によって決まる権利範囲に含まれていなかった場合にまで、均等論を認めるべきではないということになります。ボールスプライン判決以降、均等侵害が主張された幾つかの裁判により、均等5要件の適用基準に関してさらに議論がなされたりもしましたが、均等論の根拠としての衡平の理念や、5要件に基づいて均等侵害の成否を判断すること自体には変わりがありません。
一般に、特許というものは「発明特定事項が多いほど取りやすい」という傾向があると言えます。特許権者の判断次第で、均等論によって権利範囲を後出しで広げるような恣意的な解釈が許されるとしたら、例えば「発明特定事項の多い請求項で権利範囲を狭く取っておき、後から各発明特定事項と対象製品との相違点について、あれも均等侵害、これも均等侵害、と主張する」といった乱暴で姑息なこともできてしまいます。こんなことが罷り通るようであれば、特許請求の範囲の考え方の基本である権利一体の原則や周辺限定主義そのものが揺らぎかねません。実施する側にしてみれば、特許公報を読み込んで侵害回避の対策をしても侵害が成立してしまうのですから、特許などはじめから気にせず製造販売をするか、製造販売自体をやめてしまうか、ということにもなってしまいます。日々、常に慎重に慎重を重ねて請求項の文言を考えている真っ当な弁理士の立場もありません。
そして、このような拡大解釈は、技術の開発者や実施者をいたずらに萎縮させ、創作活動を阻害するものであって、技術の進歩を促すという特許制度の根本的な趣旨に反するものであると考えます。これは、「特許の専門家たる弁理士が、一般の技術者や販売者等が特許制度に疎いのを良いことに、彼らにとって理解の難しい均等侵害という概念を振りかざして、特許権の及ばない製品まで規制しようとしている」という構図です(仮に弁理士本人にそのようなつもりがなくとも、そう見えてしまいかねないということです)。場合によっては、こんなことをしている弁理士とかいう連中は皆特許ゴロの仲間だ、などと思われても仕方がありません。
さらに、均等論を利用して特許権の拡大解釈を図る行為には、依頼人の利益という観点から見ても大いに問題があります。均等論の適用によって権利範囲を大きく解釈することを前提に作成した請求項は、そうでない請求項(文言通りの権利範囲を意図して作成した請求項)と比べ、文言上の権利範囲はどうしても狭くなります。その後、均等論の主張によって文意よりも広い権利範囲を主張するにしても、その主張は裁判にならなければ認められるかどうかわかりませんし、しかも認められる可能性は低いです。大抵の場合、均等論を持ち出しても「じゃあ何でそもそもあなたはこんな余計な発明特定事項を請求項に入れたんですか(=均等5要件不充足)」ということになって終わりです。均等論という例外規定による権利範囲の拡大を目論むあまり、請求項の文言に基づいて決まる本来の権利範囲を狭めてしまうようでは、依頼人にとっては不利益でしかありません。
†
マキサカルシトール事件の最高裁判決以降、均等侵害(特に第5要件)が認められやすくなった、などとはよく言われます。ただしこれは、あくまで「特許出願時、請求項の文言を注意深く選んで慎重に権利範囲を決定する」という弁理士の仕事の原則が守られていることが前提だろうと筆者は思います。そもそも、均等論の要件が認定されたのは衡平の理念によります。今後、マキサカルシトール事件の判決などをよいことに、均等論を積極的に利用し、本質的でない発明特定事項を深い考慮もなく加えるような不誠実な請求項の作り方をしつつ、特許権の範囲解釈を拡張していくような流れがもし起きるとしたら、次は均等論の適用基準を厳しくする方向の判決が出てくるんではないかと筆者は予想しています。権利範囲の予測可能性を著しく低下させ、技術の実施者に対する制限を不当に拡大するような均等論の運用は、特許権者にばかり都合がよく、均等論の根拠である衡平の理念に明らかに反しますから。
結局、依頼人の利益を最大化するため、そして技術の健全な発展のために公正を確保するため、我々弁理士がするべきは(何やらエメラルド・ソードの歌詞みたいですね)、「特許請求の範囲は、余計な限定を入れて権利範囲を狭めないよう、慎重に言葉を選んで作成する」という基本を忠実に守ることだと思います。特許制度は開発者を守って技術を保護するためにあるんですから、その趣旨に合った公正な使い方をしたいものです。
本記事によって、特許の権利範囲や均等論に関し、正しい理解と運用が少しでも広まることを願います。

