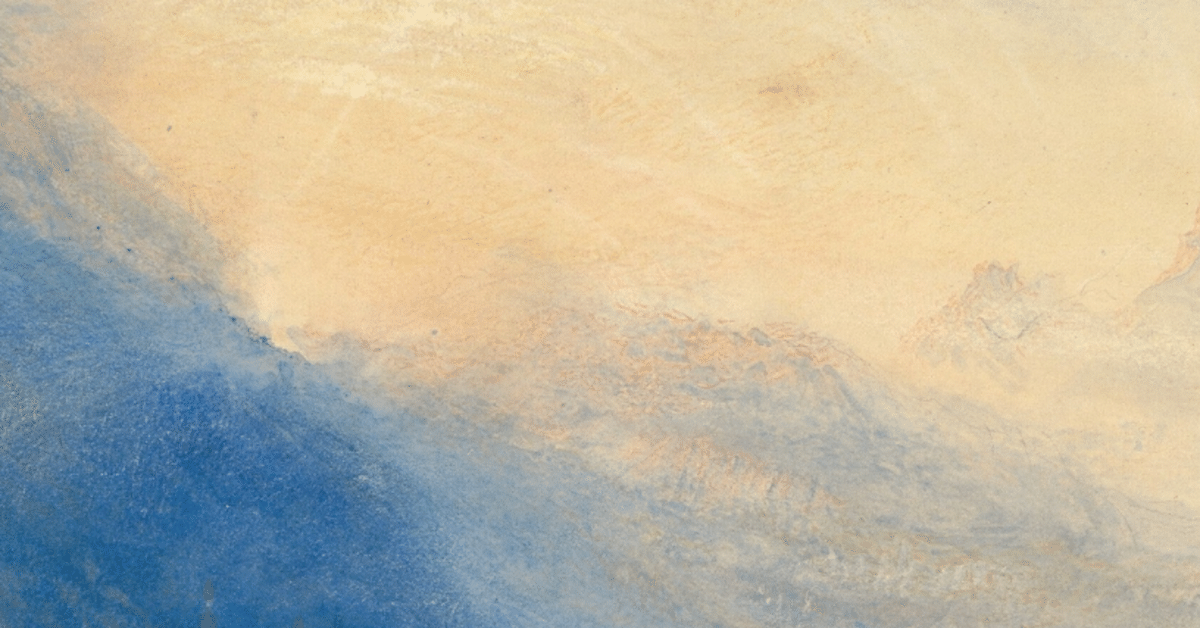
「散華」(原作:梶井基次郎『桜の樹の下には』)
散れ桜 散るな命よ若人の 母の慟哭海原に満つ
「特攻の歌ですね」
男は微笑んだ。
女は微笑みを返さず、海を見ていた。
男は短歌の会を主宰している。文学少年が年を経て、社会の波に揉まれ、またぽっかりと頭を出したかのように、文学の世界へ帰って来た。年は七十を越えた。
そんな男から見ると、近頃会に名を連ねた女は六十であってもまだ若い。ずっと独り身だということも女を若く見せるのであろうと、男は好ましく思っていた。今回の旅は吟行である。二人きりなら尚良かったが、逆に二人きりなら女は警戒して来なかったに違いない。男と女と、他に会員の女性が六名。景勝地を巡り土地の珍味に舌鼓を打ち、昔特攻へ散った青年たちの記録が残る資料館を訪ねた。その帰り、海を見下ろせる崖の上で一行は散り、各々に歌を詠んでいた。
女は旅先だというのに着物姿で日傘を差して、崖の縁に立っている。
男は、手元の歌帳を覗き込むふりをして女へ身を寄せた。
「海もいいが、もう少ししたら桜ですな。私の地元に見事な山桜がありましてな。どうです、見に行かれませんか」
他の会員がいないのを見計らって女を誘う。
「桜?」
「そうです、大きな枝垂れ桜でね。真下から眺めるとピンクの雲が広がったようで、そりゃあ綺麗ですよ」
あまり強引に誘うのもがっついているようで見苦しい。そう思う一方、
(これが最後の恋をしてもいいじゃないか)
と文学老人は開き直る。
(そんなトシでみっともないとか言う奴は、度胸がないだけだ)
男は、まだ男としての機能を失っていない。
相手の女も世間から見れば婆さんの類かも知れないが、男にとっては自分が口説くのに丁度いい位である。実は主宰の立場をいいことに、会員を口説いてきたのは一度や二度ではない。
女は歌を詠んで来ると言って身を離した。
ここで後を追えばしつこく思われそうで、男は残った。
(桜か・・・)
男には思い出がある。
故郷の山桜は男にとって格別の思い入れがあった。
それはあまり感心できるものではなく。実はその山桜は男が散々女を口説くのに使った絶好の場所だったのだ。
花より綺麗だと相手を誉め、花びらがついてると肩に触れ、そのまま抱き寄せて・・と言うのが定番の流れで、少し山の中に入った場所なのでひと目に付かず、最後まで相手をモノにしたことも再三だった。
当時はそんなことをすれば女は口堅く喋らぬもので、男の不行跡は人に知られなかった。
それだけの事をしてきた男が、七十を超えた今でも自分を色男と信じて疑わず、男やもめという自由の身をいいことに、更に女を口説こうと奮闘しているのだ。微笑ましいと見るか滑稽と見るか。
吟行に参加した他の女性からも秋波に似た視線を感じぬではないが、取り敢えず今回の獲物は着物の女性と、男は一人で決めている。
(彼女の態度は素っ気ないが、実は憎からず思っている筈・・・)
果たして、いっとき男の元を離れていた女は戻って来て、にこやかに手を振った。
「先生、歌を見てくださいな」
「ああ、勿論」
他にひと目は無い。
「どれどれ・・・」
トン。
「あ?」
次の瞬間、男は崖の下へ落ちて行った。角度と勢いと高さ。死んだのは確かだった。
女は平然と海を眺めている。
他の会員の女性たちが集まってくる。
「あらぁ。やっちゃったの?」
「私が押したかったのに」
「ごめんなさい。丁度いい場所に立ったものだから」
「誰も見てないわよね?」
「大丈夫。私たちみんなで見張っていたわ」
それはまるで、お茶会のような和やかさで・・・
「バカな先生だったわね」
「誰が通報する?」
「じゃあ私が」
一人の女性がスマホを取り出す。
着物の女は、何故か日傘を海へと放り投げた。
花柄の傘がふわりと舞った。
数十分後、駆けつけた警察に女性たちは一斉に証言する。
「なんてことかしら!あんなにいい先生が・・・」
「私が悪いんです。風に日傘を飛ばされて。先生はそれを取ろうと手を伸ばして」
「女性に優しい先生でしたもの」
「私も見てましたわ」
男の死は小さな記事になった。
それだけだった。
後日。短歌の会は解散することになり、例会で使う集会所に会員が集まった。
「写真飾る?」
「そうね。最後の会報に載せなきゃ」
「こうしてみると萎れた爺さんねぇ。若い頃は顔だけは良かったのに」
「じゃ、撮るわよぉ。笑っちゃダメよぉ〜?はい、チーズ」
「あらやだ、今でもチーズって言うのかしら」
「お豆腐が良かった?」
うふふふふ・・
笑い声が響く。
着物の女がふっと笑った。
「先生、肝心な記憶がおボケになってたのねぇ。私たちが昔捨てた女だって、分からなかったのかしら」
「こっちは恨み百万年、絶対忘れっこないのにね」
「あースッキリ。これでいつでもあの世に行けるわぁ」
「ダメよぉ、今行ったら先生に追いついちゃう」
「ずっと同じ雅号使ってくれてて良かったわよね。探し易くて」
「ねぇ羊羹食べる?上等よ」
「あら。私も甘いもの持ってきたわ。お取り寄せ奮発しちゃった」
「それ、この前の歌?」
散れ桜 散るな命よ若人の 母の慟哭海原に満つ
「先生、特攻の歌って言ったのよ」
一同がしんみりとする。
「・・私たちにとっちゃあ、あの男の為に流された水子よね・・」
「わだつみに散った若者と一緒にしちゃあいけないけれど・・・命を散らしたって意味では、私たち、ひどい親かしらね」
「私たちみんな、産める環境じゃなかったものね・・・」
着物の女が悲しく笑う。
「あの世で先生には会いたくないけど、死んだ子どもには会いたいわねぇ」
「私も・・うちはこないだ孫が産まれたんだけどね。やっぱり今でも、赤ちゃん見ると思い出すわねぇ・・」
「戦争でも何でも、命が散るのは嫌よねぇ・・・でも、自分のことだと、パッと散りたいと思っちゃう。我儘かしら」
「それとこれとはね」
「・・・・・」
「もうアッチの世界も近いってのに、私たち何やってんのかしらね」
「もうすぐ死ぬから踏ん切りを付けたかった。そういうことにしましょうよ」
「私たち、これで解散?」
「そうね。一応。こういうのは、潔くね」
無名の歌会の、無名の女たちの、泡沫に消えた、こんなお話。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
