
和田夏実/牧原依里/西脇将伍 ── 手話が街を”ハック”する
女性が安心して歩ける街、子どもが楽しく遊べる街 ──。街は今、少しずつ多様性を帯び始めています。では、もし世界から音が消えたなら、街はどのように見えるか? そんな私たちの問いに、ろう者の両親のもとで育ったインタープリターの和田夏実さん、その友人でろう者の映画作家の牧原依里さん、ろうコミュニティの活性化に取り組む西脇将伍さんと、”手話目線”のそぞろ歩きに出かけました。渋谷と原宿を結ぶキャットストリートで、身体感覚で街を読む散歩型のワークショップが始まります。「まちを読む」をテーマに、多様な視点を持つゲストを招いてお届けするデジタルZINE「まちのテクスチャー」シリーズ第5回
Photography by Yosuke Suzuki

和田夏実|Natsumi Wada
インタープリター
ろう者の両親のもとで手話を第一言語として育つ。大学進学時に手で表現することの可能性に惹かれ、視覚身体言語や、多様な人々の感覚とメディアの可能性を模索する。「たばたはやと+magnet」として、言葉と感覚の翻訳方法を探るゲーム『LINKAGE』『たっちまっち』などを発表。視覚身体言語を研究・表現するユニット「Signed」を南雲麻衣、児玉英之と結成し、美術館でのワークショップなども行う。

牧原依里|Eri Makihara
映画作家、聾の鳥プロダクション代表
ろう者の両親を持ち、小学2年生までろう学校に、3年生からは普通学校に通う。ニューシネマワークショップで映画制作を学び、2016年、ろう者の“音楽”をテーマにしたアートドキュメンタリー映画『LISTEN リッスン』を雫境(DAKEI)と共同監督。17年には「東京国際ろう映画祭」を立ち上げ、ろう・難聴当事者の人材育成と、ろう者と聴者が集う場やコミュニティづくりに努めている。

西脇将伍|Shogo Nishiwaki
大学生
ろう者の両親の元に生まれ、明晴学園にてバイリンガルろう教育を受けて育つ。高校より聴者の学校へインテグレーションし、野球部で聴者に囲まれながらプレーをしてきた。大学では「ろうコミュニティの必要性と危機」をテーマに活動。東京芸術劇場による新しい音の芸術祭「ボンクリ・フェス」で「音のないオンガク会」に出演するなど、さまざまなプロジェクトに参加している。
(7つの質問)手話の身体感覚で「まちを読む」試み
Q.1 手話をしながらの街歩きを通して、気づいたことや感じた点があれば教えてください。

西脇将伍 道や周りの状況に合わせて、身体の使い方が変わることに気づかされました。キャットストリートは人通りが多いけどクルマが少なくて道幅が広いから、手話をしながらでも歩きやすかった。
和田夏実 街を相手に「コンタクト・インプロビゼーション」(相手の身体や空間との接触を意識しながらデュエットで踊る即興ダンス表現)をやっているような、街の形に手話の空間を合わせていくような……。
牧原依里 街を歩きながらよくお喋りをするのは、ろう者の特徴だからね(笑)。その意味で今日歩いた道は、曲がりくねっていなくて話しやすかった。西脇さんが通っていた明晴学園(バイリンガルろう教育に取り組む私立のろう学校)も、廊下や道がまっすぐで奥まで見通せるようになっていたよね。
西脇 そうそう。出会い頭にぶつからないよう、できるだけ曲がり角のない構造になっていたね。
牧原 確かに……! 私たちが「まちを読む」とき、「安心して歩けるかどうか」は一つのポイントになるかもね。
Q.2 初めての街で、最初はどんなところに注目しますか?
西脇 話が逸れますが、街歩きをご一緒したみなさんから「3人とも舞台上の人物のように、必ず均等に距離を取っている」と言われたのが不思議でした。逆に、聴者の方はお互いの距離がもっと近いということ?

和田 そう、相手が見えなくても会話ができるから。そういえば、牧原さんと一緒にフランスで開催されるろう者のパフォーマンス芸術祭「クランドゥイユ」へ行ったときは、辺り一帯が大勢のろう者であふれていて、会話量がすごかった。車道を挟んだ歩道と歩道の間や、宿泊施設のベランダと地上……。遠くにいる知り合いを見つけると、会話に飛び込んでいく人もいました。手話なら騒音の中やガラス越しでも、お互いに目が届く限り話せちゃう(笑)。それだけに、ろう者が街をつくったら、また違った形になるんじゃないかな。
Q.3 手話で会話しながら街の空間を感じてみて、どんな気づきがありましたか?
牧原 おしゃれな演出なのか、お店の看板が小さいことです(笑)。郊外へ行くと、スーパーマーケットや量販店の巨大な看板が立ち並んでいますよね。でも表参道や原宿のお店は看板どころか、入口さえわかりにくい場所にあったりする。

和田 歩き方や地図の見方一つをとっても、ろう者と聴者とでは空間の把握や記憶の仕方が違う。ここは、掘り下げがいがあるところだなあ。
Q.4 視覚言語の話者だからこそできる、街への関わり方はありますか?
牧原 多様な当事者の一人として、建築の領域に入っていくことでしょうか。女性建築家が活躍するようになって、女性の暮らしやすい家が増えたように、私たちももっと参加したい。家の中で身体性がつくられるなら、それがやがて街づくりにもつながっていくはずだから。
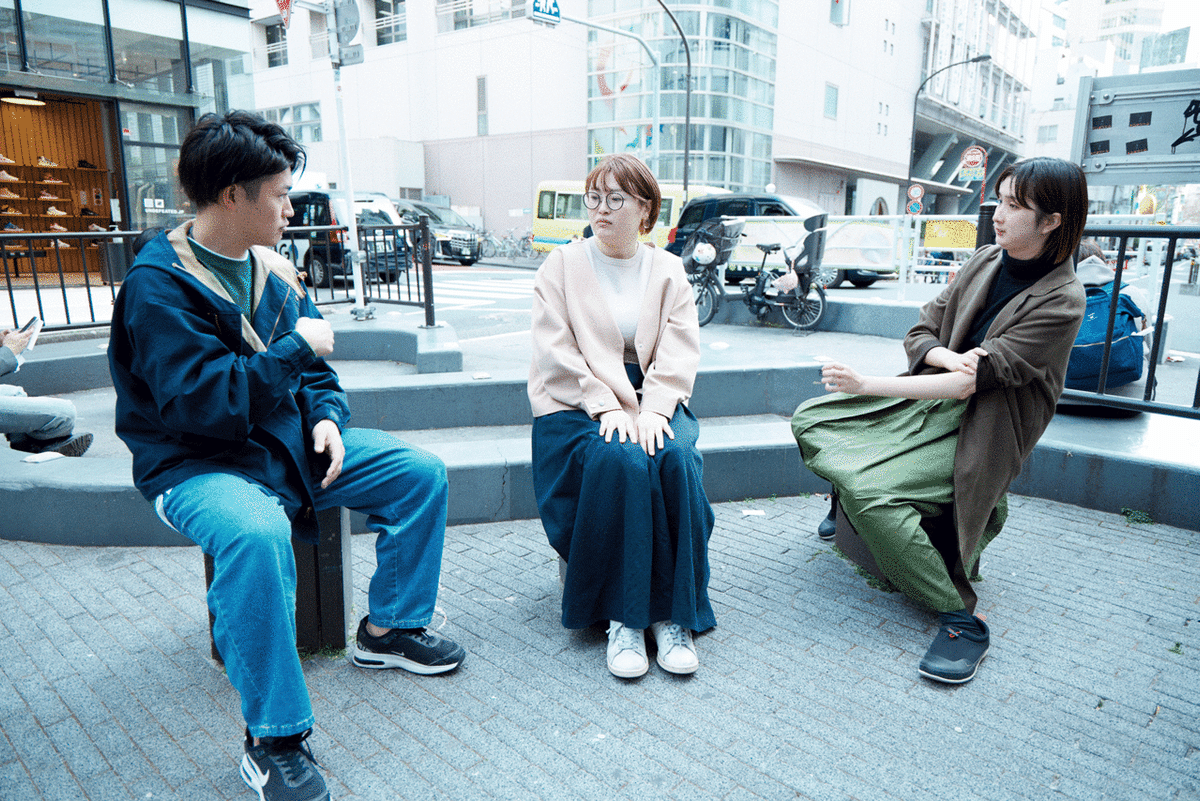
西脇 それって、今の街づくりの流れだと「ろう者が話しやすいように、公園のベンチを三角形に配置しよう」という発想は出てこない、ということだよね?
和田 うん。ろう者が街に溶け込みながら、よりよいあり方を見つけていく。イメージとしてはスケートボーダー。彼らは段差や手すりを見て「ここで技を決めよう!」とか、独自の目線で街をハックしているでしょう。別の身体感覚を取り入れることで、街との関係も変わると思う。今日、会話しながら2人の前を後ろ向きに歩いていて、背中で街を感じてるようなイメージがあった。身体の前にある「会話空間」と、後ろにある「街」に挟まれて、間にいるような感覚。
Q.5 視覚言語話者が使いやすいという観点から、気に入った場所はありましたか?
牧原 特定の場所ではないけれど、今日のエリアは建物が低くて視界が広いのがよかった。ふと思い出したのは、前に住んでいた団地の部屋で家族がドアを開けっぱなしにしていたこと。とにかく見通しを確保して、夜は人感センサーですぐ照明がつくようにしたり、リビングのドアにもガラスをはめて向こうが見えるようにしたり。

和田 低層の建物が多ければ、屋上同士でも話ができて、にぎやかになりそう。窓ガラスも大きくして、プライベートな話をするときはブラインドを下ろせばいいし。
西脇 手話なら、よそから見えなくすればひそひそ話ができるからね(笑)。
Q.6 街の未来に望むこと、取り組んでいることがあれば教えてください。
和田 私が参加している「めとてラボ」(視覚言語話者が主体となり、異なる身体性や感覚世界を持つ人々とコミュニケーション創発の場をつくるプロジェクト)では、ろう者の家で育まれている空間「デフ・スペース」をリサーチしています。調べてみると、壁を取り払ったり、大きな吹き抜けを設けたりと、家ごとに工夫があって面白い。これまではそうしたアイデアを共有する場がなかったので、共通のフォーマットを見つけて活用していきたいなと。
牧原 そういえば、廊下がないワンフロアの家を建てた友人がいますよ。ろう者にとって廊下は単に音を遮る空間だから必要ない。ダイニングの目の前にトイレがあっても、音が聞こえなければ大丈夫だしね(笑)。
西脇 ろう者一人ひとりの工夫を集めて、新しい身体や空間の使い方を発見する……いろいろ可能性が広がりそう。
Q.7 そうした観点もふまえて、ずばり、街にはどんな個性が必要だと思いますか?
牧原 まずはターゲットを絞ること。例えば、視覚障がい者の暮らしやすさに特化した街をつくれば、それ以外の人にも必ず発見があるはず。

西脇 いろんなことに手を出しすぎると、一つひとつの要素が薄まってしまう。特定の人に特化したほうが、街の価値も上がるはずだよね。個人的な住みやすさの話になってしまうけど、例えば僕なら、駅のできるだけ近くに住みたい。夜中まで電車が走っても、音はぜんぜん気にならないので(笑)。
和田 自分と違ういろんな身体が社会にはある。そういう人たちと一緒に暮らしていることが感じられたら、誰にとっても面白い街になるんじゃないかなあ。
自分の体を乗りこなし、街を面白くハックする
──幼いヘレン・ケラーの手に、家庭教師のアン・サリバンが水を注ぎながら指文字で「water」と書いたことで、水のイメージと実像がつながったという逸話があります。同じように、ご自身のなかで建築や街のイメージと実像がつながった経験はありますか?
和田 オーストラリア先住民のアボリジニには、世界観を絵画や音楽、ダンスなどで表現する「ソングライン」という文化があります。地理や道筋を歌で伝えていくのですが、中心に自分がいて、移動しながら世界を捉えていく感覚です。同じように私も今日、目の前の会話空間が拡張する一方で、街がぐっと後ろに引いていく感じがしたんです。景色をシャットダウンして、空間が自由に広がっていくというのか……。

牧原 そうやって自分たちだけの空間をつくれてしまうのは、ひょっとして「ろう者あるある」なのかな?
西脇 日頃やっていることに、すごい効果がある気がしてきた(笑)。
──手話では身振りだけでなく顔の表情も重要ですが、仕草や表情によって自分以外のものを「演じる」ことが、世界の認識にも影響している気がします。
牧原 手話には「CL(Classifier/類辞)」や、現在の自分以外の人物の役割や様子を表現する「ロールシフト」など特有の表現があって、手話言語学的に「演技とは違う」と定義されているんです。でも、確かに面白い表現がたくさんあります。聴者は「黙って」と言うとき、口の前に人差し指を立てて「しーっ!」とやるけれど、ろう者は手をチョキンと切る動作をしたりする(笑)。

西脇 例えばCLなら、「クルマ同士が勢いよく衝突して、一回転して逆さまになった」と言いたい場合、手をくるりと返してクルマの動きをそのまま表現できるよね。
和田 街について考えるときも、手話だと音声言語よりもAR(拡張現実)っぽい感覚になる気がする。建物や道の形を手で表現しつつ、そこに”イメージを重ねる”感じ。
牧原 面白いね! こういう議論がもっと広がって、普通のことになってほしい。異なる人同士がそれぞれの世界に想いを馳せたなら、そこはもっといい街になっていくだろうから。
渋谷・表参道リサーチ取材:2023. 3/1
主催&ディレクション
NTT都市開発株式会社
井上 学、權田国大、吉川圭司(デザイン戦略室)
梶谷萌里(都市建築デザイン部)
企画&ディレクション&グラフィックデザイン
渡邉康太郎、村越 淳、江夏輝重、矢野太章(Takram)
コントリビューション
深沢慶太(フリー編集者)
