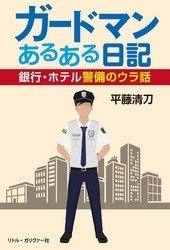フリーライターはビジネス書を読まない(41)
スーパーで売られている惣菜の正体
1週間くらい通ったら、まわりの様子が見えてきた。
惣菜売り場でもフライ担当と寿司担当がはっきり分かれていること、寿司以外は揚げ物はもちろんサラダや弁当などすべてフライ担当の仕事になっていること、寿司担当のおばちゃんたちは一見和気あいあいやっているように見えて、じつは足の引っ張り合いが凄まじいことなど。
もっとも、おばちゃんたちの派閥争いに巻き込まれたらロクなことにならないのは分かっていたから、積極的に打ち解けることをわざと避けていた。
それとは別に、裏側に立ってみて、はじめて見えてくることもある。
スーパーの惣菜のつくられ方である。
一言でいってしまうと、業務用の冷凍食品やレトルト食品を揚げたり蒸したり焼いたりして、解凍しているだけ。
例えば「やきとり」は、すでに焼調理されタレまで塗られている完成品が冷凍で搬入される。それをコンベクションで再び焼いて、業務用のタレをべったり塗り、平皿に移し替えて売り場に出す。
「赤飯」は、1パック分ずつ個包装された冷凍品を蒸し器で戻して、ご飯粒をほぐしながら容器に盛り付けると、あたかもホカホカできたての赤飯に見える。
「松茸ごはん」も似たようなものだ。こちらは、味付けされて1kgで真空パックされたご飯だけを蒸して柔らかくし、6パックに等分する。その上から山菜の具材をのせ、さらに仕上げに小指の先ほどの大きさの、松茸のスライスを2~3枚のせるだけ。
「鶏のから揚げ」や「コロッケ」「ミンチカツ」「白身魚フライ」は冷凍のまま160℃の油に放り込んで、油の熱で解凍しながら揚げるという荒ワザ。「お好み焼き」と「たこやき」は、完成品の冷凍を油で揚げてソースをたっぷり塗れば、鉄板で焼いたように見える。
素材から調理される商品は、天ぷらのほかごく一部だった。
仕事に慣れていくにしたがって「このつくり方で許されるんだ」という新しい発見があり、一方でスーパーで惣菜を買う頻度が極端に減った。買うとすれば自分がバックヤードでつくった商品だけになり、よそのスーパーでは買わなくなった。というより、買えなくなった。
そんなことを思いながら、スーパーの裏話は絶対にネタになる確信を得たのである。問題は、どんな媒体に、どんな形で出すか。
もうちょっとネタを溜めてから、企画書をつくってみようと考えていた。
(つづく)
―――――――――――――――――――――――――――
◆最近の記事/まいどなニュース
どの魚を先に出すか検討中→「これは“あにき”か?」「そっちは“おとうと”です」…<お寿司屋さん編>
「この温泉には『ワニ』が出ます」「ワニ対策にお水をお持ちください」…!?<銭湯・温泉編>
山が燃えている→「今回は山火事ではありません」「発火した原因で呼び方が変わるんです」…<消防署編>
◆電子出版