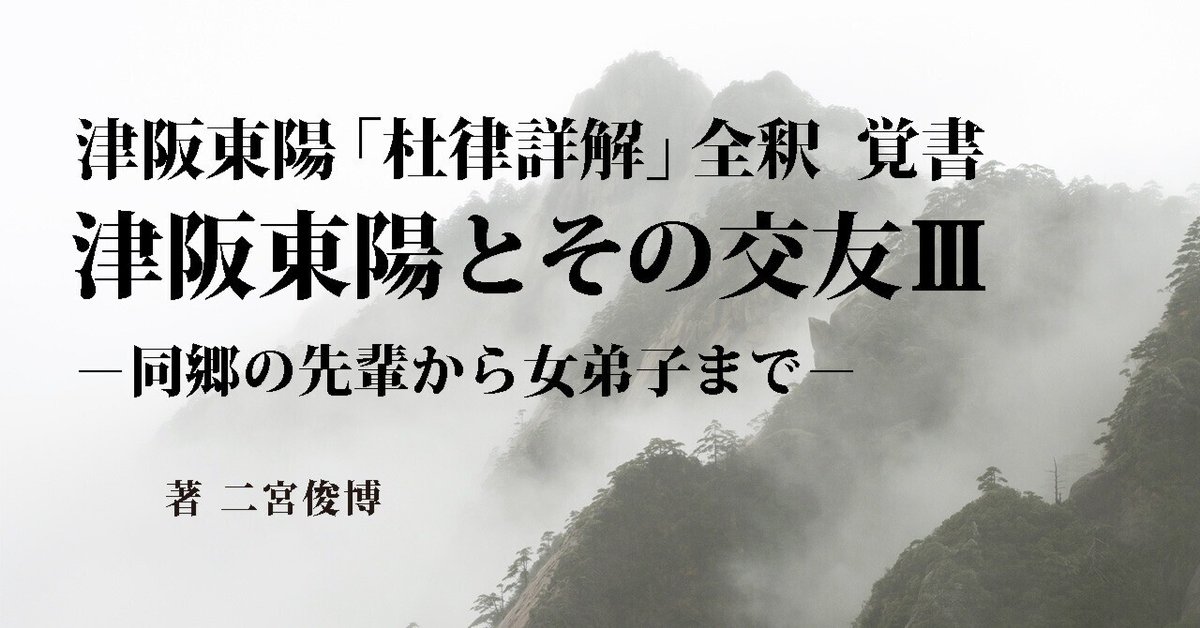
覚書:津阪東陽とその交友Ⅲ-同郷の先輩から女弟子まで-(7)
著者 二宮俊博
画人―十時梅厓・大原雲卿・岡田米山人
岡田米山人(延享元年[1744]~文政3年[1820])
名は国、字は士彦。通称は彦兵衛。安永ごろは大坂で米屋を営み、臼を踏みながら読書に励んだという逸話がある。寛政2年に津藩の大坂蔵屋敷の下役として召し抱えられて以降、藩との関係が生じた。東陽より13歳上。
七絶に「席上、米山人に贈る」詩(『詩鈔』巻九)がある。この詩は米山人が津にやってきたときに詠まれたのであろう。詩の配列からすれば、文化13、4年頃の作。当時、東陽には大坂へ出向いた形跡がないことからして、この詩は米山人が津にやってきたときに詠まれたのであろう。時に東陽は58か60歳、米山人は72か74である。
心跡相忘混酒徒 心跡相忘れ酒徒に混じる
醉郷爛漫是仙都 酔郷爛漫是れ仙都
豪來揮霍龍蛇筆 豪来揮霍す龍蛇の筆
寫出名山大澤圖 写し出す名山大沢図
◯心跡 心情・行為。六朝宋・謝霊運「斎中読書」詩(『文選』巻三十)に「昔余京華に遊ぶ、未だ嘗て丘壑を廃さず。矧んや乃ち山川に帰り、心跡双つながら寂漠」と。◯酒徒 酒飲み連中。李白の雑古「草書歌行」に「八月九日天気涼しく、酒徒詞客高堂に満つ」と。◯酔郷 気分のよい酔い心地。西晋・劉伶に「酔郷記」がある。◯爛漫 存分に酔うさま。畳韻語。杜甫の五律「高滴に寄す」詩に「定めて知る相見るの日、爛漫として芳尊を倒すを」と。◯仙都 仙人の住むところ。晋・孫綽「天台山に遊ぶ賦(『文選』巻十一)に「陟降信宿、仙都に迄る」と。◯揮霍 手を速く動かすこと。双声語。◯豪來 興來と同じ。六如の『葛原詩話後編』巻四に「興シ来ルヲ又豪來ト云フ。放翁往々喜デ用之ヲ」云々と指摘する。◯龍蛇筆 雄勁で生動する筆勢。北宋・黄庭堅の五律「文安国の挽詞二首」其二に「龍蛇の筆を見ず、新たに乾く研滴の蜍」と。◯名山大沢 『左氏伝』襄公21年に「深山大沢、実に龍蛇を生ず」と。
自注に「山人は本と飲を解さず、年古稀を過ぎて始めて酒中の趣を識る。婆娑として寄傲し、自ら酔仙と称す、画品神妙、酔筆尤も逸なり」と。〈婆娑〉は、酔ってふらふらするさま。畳韻語。〈寄傲〉は、自由気ままな思いを託す。東晋・陶淵明「帰去來の辞」(『文選』巻四十五、『古文真宝』後集巻一)に「南窗に倚りて以て寄傲し、膝を容るるの安んじ易きを審かにす」と。
今挙げた東陽の詩および自注は、森銑三「米山人のことども」(『森銑三著作集第四巻人物篇四』)にすでに紹介されているところであるが、東陽にはこのほか「米山人の枯木竹石に書す」と題する一文(『文集』巻七)がある。
此浪華米山人戲墨、醉興槃礴揮灑。殊見天眞爛漫、殆是神來之筆。余擊節喝采。山人曰、唯吾亦覺勝平時、然不知者必大笑耳。余曰、然哉。抑不笑不足以爲道。唯我與爾有是也夫。山人稱快、引杯滿酌。遂書以識之。時丁卯九月十日、山人訪宿草堂、劇談豪吟、夜漏下三刻矣。
(此れ浪華米山人の戯墨、醉興槃礴揮灑す。殊に天真爛漫を見はす、殆んど是れ神来の筆。余、節を撃ちて喝采す。山人曰く、唯だ吾れも亦た平時に勝るを覚ゆ。然れども知らざる者は必ず大いに笑はん耳。余曰く、然る哉。抑そも笑はれざれば以て道と為すに足らず。唯だ我と爾と是れ有る也夫。山人快と称し、杯を引いて満酌す。遂に書して以て之を識す。時に丁卯九月十日、山人草堂に訪宿す、劇談豪吟、夜漏下ること三刻なり矣)
◯槃礴 両足を投げ出して坐る。双声語。『莊子』田子方篇に「衣を解き槃礴して臝」になって一心不乱に描いている画師の様子を聞いて、宋の元君が「可なり、是れ真の画者なり」と讃えた話がある。◯揮灑 筆をふるう。◯神来 インスピレーションがおりてくる。清・高士奇『江村銷夏録』巻三、「李龍眠維摩演教図巻」の条に「真に神来の筆、後世の丹青手を視るに直だ土苴なる耳」と。◯撃節 拍子をとる。◯喝采 ほめそやす。もとは博奕の時、掛け声をかけて骰子を振ること。宋代以降の近世語。◯不笑不足為道 この表現、『老子』第四十一章に「上士 道を聞けば、勤めて之を行ふ。中士道を聞けば、存るが若く亡きが若し。下士 道を聞けば、大いに之を笑ふ。笑はれざれば以て道と為すに足らず」と。◯唯我與爾有是也夫 『論語』述而篇に「子、顔淵に謂ひて曰く、之を用ふれば則ち行ひ、之を舎つれば則ち蔵る。唯だ我と爾と是れ有る夫」と。なお、『論語』には〈也〉字がない。◯劇談 大いに論じ合う。西晋・左思「蜀都の賦」(『文選』巻四)に「劇談戯論、腕を扼し掌を抵つ」と。◯豪吟 意気盛んに大声で詩を吟ずる。◯夜漏下三刻 夜が明ける一時間ほど前をいうか。中唐・張籍の七古「沙塘行」に「宮中の玉漏下ること三刻」とあり、元・倪瓚の「絶句四首、九成の韻に次す」詩(『倪雲林先生詩集』巻六)の自注に「倪瓚、高斎に留宿し、篝灯して為に春林遠岫図を写し并せて四詩に次韻して画上に題す。時に夜漏下ること三刻なり矣。佩韋斎中に書す」と。
米山人が東陽のもとに訪宿したのは、〈丁卯〉とあるから文化4年(1807)64歳のときのことで、当時51歳の東陽はまだ伊賀上野にいた(津に召還の命が下るのは同年の11月23日)。このとき米山人は多少なりとも「飲を解」するようになっていたのであろう、ただそれまでは酔って筆をとったことはほとんどなかったのではあるまいか。ところが、東陽宅で酔余の一興として戯れに描いた枯木竹石の画が自分でも驚くような出来ばえで、山人にとって新たな境地に達した得難い体験であったようだ。
なお、後から気がついたのだが、河野元昭氏に「米山人小伝」(「美術史論叢」20、平成16年)がある。それによれば、米山人の文化12年作「携酒遊景図」に七絶の賛があり、
日日遊惰興叵窮 日日遊惰 興窮め叵し
桃花探尽又紅楓 桃花探ね尽くして又た紅楓
南北東西一瓢酒 南北東西 一瓢の酒
酔醒醒酔蹣跚翁 酔いては醒め醒めては酔う蹣跚の翁
◯叵 不可の合音字。◯酔醒醒酔 北宋・黄庭堅「酔落魄」詞の自注に「旧と酔醒醒酔一曲有り云ふ、酔いて醒め醒めて酔ふ、君に憑って会取す皆滋味」云々と。◯蹣跚 よろめきながら歩くさま。千鳥足。畳韻語。
と詠じられ、それには「向に蘿月亭に遊ぶの約有りしも、果たさず。東陽君小集を催して余を促す。余、之に赴く。是れ老懶興情の致す所。因りて其の意を賦し、漫に山水を写す」という前書きが附されているという。
とすれば、先に示した「席上、米山人に贈る」詩は、文化12年の作であろう。
※米山人については、森銑三「米山人のことども」のほか、神山登「岡田米山人・半江の生涯」(「古美術」53、昭和52年)、藪本公三「岡田米山人年譜考」(同上)および神山登氏執筆にかかる『近世大坂画壇』(大阪市立美術館。同朋舎出版、昭和58年)の本論篇「文人画」第三章「画壇の精華―米山人と半江」参照。さらに中村真一郎『木村蒹葭堂のサロン』(新潮社、平成12年)の第三部第一章第十節「岡田米山人」がある。米山人は前掲、大槻幹郎著にも取り上げる。
附㈠ 清客程赤城
東陽の『詩鈔』には、時に思いがけない人物が登場する。次に挙げる清国人程赤城はその一人である。両者の接点や介在する人物が具体的にわかれば、意外でもなんでもなくなり、それを探究するのが研究ということになろうが、両者の結びつきは今のところ不明。
程赤城(雍正13年[享保20年、1735]~嘉慶12年[文化4年、
1807]~?)
名は霞生、号は相塘。赤城は、その字。蘇州の人。長崎にたびたび来航した清国の海商で、書法にすぐれ揮毫をよくした。明和7年(1778)、豊後国東の三浦梅園が起稿した『贅語』に書目・題言を揮毫したのをはじめ、天明元年には『詩轍』(刊行は天明6年)の日出藩儒喬維嶽序、同7年には『梅園詩集』(天明7年刊)自序の文字をそれぞれ書いている。
東陽の天明期在京中の作に七絶「清客程赤城の西帰するを送る」詩(『詩鈔』巻七)がある。
幾年瓊浦住為家 幾年瓊浦住みて家と為す
歸去齊州絶海邈 帰り去る斉州 絶海邈かなり
知對東風來日本 知んぬ東風の日本より来たるに対して
春雲望斷白櫻花 春雲望断す白桜花
◯瓊浦 長崎の雅称。◯斉州 中州。中国を指していう(『爾雅』釈地)。中唐・李賀「天を夢む」詩に「遙かに斉州を望めば九点の煙、一泓の海水杯中に瀉ぐ」と。◯絶海 陸地から遠く離れた海。◯望断 見えなくなるまでながめる。
「春風が吹くころになると日本恋しさにいつまでも東の空に浮かぶ桜色の雲を眺めていることでしょう」。
この詩には「明人貝瓊の詩に、唐風日本より来たり、北斗玄枵を辟す」との自注がある。貝瓊は、元末明初の人。詩を楊維楨(字は廉夫、号は鉄崖)に学んだという。『元史』編纂に与った。東陽が挙げるのは、その五排「丁未の除夕」詩(『清江詩集』巻九)の第一、二句。〈玄枵〉は、星座の名。北方にあり、子の方角にある。
先にも述べたように東陽と程赤城との接点は分からないものの、東陽の畏友で若くして亡くなった小栗明卿(宝暦13年[1763]~天明4年[1784])の弟、十洲は長崎に遊学しているし、東陽と交友が深かった橘南谿は天明2年の九州遊歴中に長崎で程赤城に会っている。南谿の『北窓瑣談』巻一には「程赤城は廿歳ばかりの頃より六十余に及ぶまで、年々渡り来」たという話を載せる。老年まで来航する理由を問うと、「第一日本の飯を食し馴ては、彼国の飯は食しがたく、第二酒、第三味噌汁なく香の物なし」と答えたという。我が国の食べ物や酒がよほど口に合ったらしい。
さらに、程赤城の名は意外なところにも見える。尾張の岡田新川が「清人程霞生、君山先生の敝帚集を読み、節を撃ちて称嘆す。之が為に序し、其の帰るに及んで、諸を橐中に載す。余、長句を作りて其の盛事を賛す」と題する七言古詩(『朝陽集』巻一)を作っている。ちなみに、松平君山の『弊帚集』は、明和7年(1770)の刊。
当時、長崎に遊んだ文人墨客は必ずといってよいほど程赤城と面談するか、そうでなくとも話題に取り上げている。天明8年の春木南湖(宝暦9年[1759]~天保10年[1839])、司馬江漢(延享4年[1747]~文政元年[1818])、文化元年(1804)の市河米庵(安永8年[1779]~安政5年[1858])らいずれもそうである(南湖の『西遊日簿』、江漢の『西遊日記』、米庵の『西遊折瓊』)。その一人に大田南畝(寛延2年[1749]~文政6年[1823])がいる。南畝は文化元年6月に、長崎奉行所詰を命じられ、9月に着任し、翌年10月まで長崎に滞在したが、文化元年の作に「清人程赤城の七十の寿詞、賦して文庵に示す」と題する二首(『南畝集』巻十四)がある。文庵は幕府から長崎に派遣された医官で、南畝に同行した。さらに森鷗外『伊澤蘭軒』その三十三に、文化4年、蘭軒が長崎で交流した清国人の一人としても登場している。
※程赤城の略歴については、吉村永吉「来舶唐人と迂斎」(「長崎談叢」第三十輯、昭和17年)および小曽戸洋・町泉寿郎「梁田蛻巌撰・程赤城書『張仲景図賛』」(「漢方の臨床」四六ノ一、1999年)参照。なお、南畝の詩は、岩波『大田南畝全集』第四巻に収める。詩題に見える文庵については、濱田義一郎[江戸文人の歳月―蜀山人大田南畝に於ける](「大妻女子大学文学部紀要」15)に言及されている。
◀覚書:津阪東陽とその交友Ⅲ-同郷の先輩から女弟子まで-(6)
▶覚書:津阪東陽とその交友Ⅲ-同郷の先輩から女弟子まで-(8)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
