
たとえ死の影の谷を歩いても、私は悪を恐れない

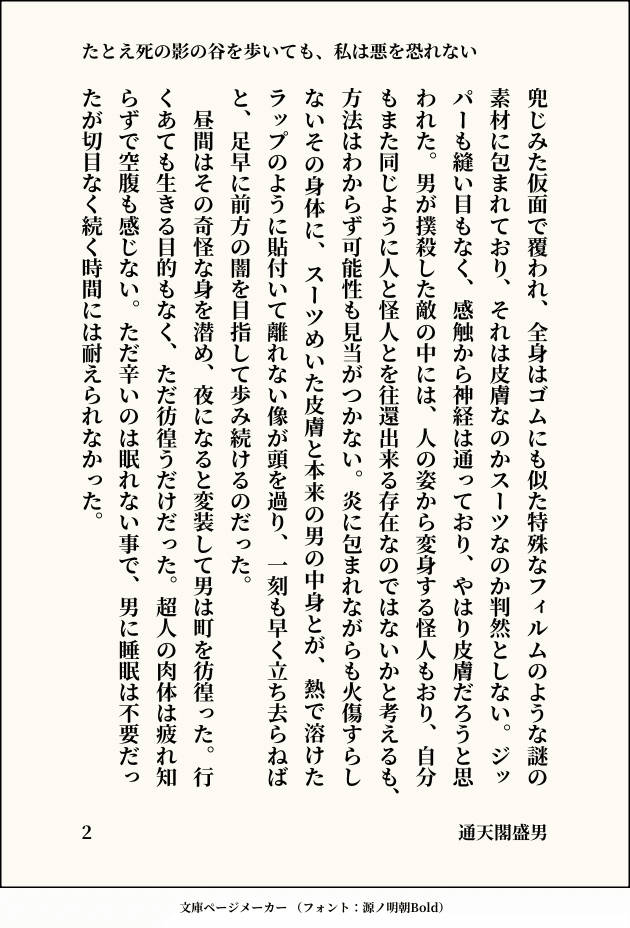




たとえ死の影の谷を歩いても、私は悪を恐れない
夜の森の中、血に塗れた手を見つめ立ち尽くす男を、燃え盛る炎は照らし、まるで男の心のように激しく揺らめく火炎は勢いを増して、巨大な爆発と共に辺りを真昼の明るさに変えてしまった。逆光の中に男の影が浮かび上がる。影はただ真直ぐ前へと進んでいく。
男は曾て人間だった。今はある組織に拉致され改造された改造人間である。その力は組織の中枢を担う筈だったが洗脳されるより前に男は抵抗し、皮肉にも彼らの科学力を結集したその力によって組織とアジトは今壊滅したのである。彼らは世界征服を企む悪の組織で男は世界を救った訳だが、それを証明する痕跡も全て炎の中で燃え尽きようとしていた。
男は昆虫の遺伝子を組込まれた怪人であり超人で、頭部は触角の付いた兜じみた仮面で覆われ、全身はゴムにも似た特殊なフィルムのような謎の素材に包まれており、それは皮膚なのかスーツなのか判然としない。ジッパーも縫い目もなく、感触から神経は通っており、やはり皮膚だろうと思われた。男が撲殺した敵の中には、人の姿から変身する怪人もおり、自分もまた同じように人と怪人とを往還出来る存在なのではないかと考えるも、方法はわからず可能性も見当がつかない。炎に包まれながらも火傷すらしないその身体に、スーツめいた皮膚と本来の男の中身とが、熱で溶けたラップのように貼付いて離れない像が頭を過り、一刻も早く立ち去らねばと、足早に前方の闇を目指して歩み続けるのだった。
昼間はその奇怪な身を潜め、夜になると変装して男は町を彷徨った。行くあても生きる目的もなく、ただ彷徨うだけだった。超人の肉体は疲れ知らずで空腹も感じない。ただ辛いのは眠れない事で、男に睡眠は不要だったが切目なく続く時間には耐えられなかった。
このような日々の中でも、生きてさえいれば良い事があるのではと、そんなふうに思えた事もあった。男にはある女の事が思い出された。女は一人で小料理屋を営む年増で、夫を事故で亡くし子供も無かった。母性本能からであろうか、路地裏の、店の勝手口の前にうずくまる男を女は招き入れた。二人は共に暮らすようになり、男も人目につかぬよう陰ながら店を手伝った。いつしか夫婦のように互いを労り合うようになっていた。だがそんな蜜月も長くは続かない。所詮男は異形の者である。女の幸せを考えれば留まり続けて良い筈はない。身勝手な正義感から、男はある日別れも告げぬまま女のもとを後にした。そうして男は死のうと決意したのだった。死ねば全て諦めがつくだろうと、誰の人生に関わる事もなく自分という存在に思い悩む事もないのだとそう思った。男は死に場所を探して旅をする事にした。何故だろう、男は内心微笑していた。これから死のうというのに、目的が出来た事に心を弾ませていたのである。
男は旅を通して世界の美しさを知った。山や海を眺め、川の流れの滑らかな曲線に見入る事が今迄あったろうか。花の名前を知りたいと思った事が、鳥や虫の鳴き声に耳を澄ませた事があったろうか。この美しい世界を自分は救ったのだと、そう思うと幾らか心は満たされもしたが、その自然の中にも人の営みの中にも男の存在出来る場所は見つからなかった。そして男は死からも拒絶されていた。屈強な男の身体に首吊りも飛降りも効果はなく、服毒しても健康を害する気配すらない。
ある日男は浜辺で夕暮れを眺めていた。するといつの間にか白髭古老の男が傍らの岩に腰掛け同じように海を見ていた。里の老人だろうか、人目を避けなければならない男は戸惑った。老人は海を眺めながら男に話しかけた。「今日もまた太陽が沈む、単純な繰り返しじゃ。人生もしかり、難しく考えるとわからなくなるものじゃよ」男は老人の言葉に耳を傾けた。「お若いの、道に迷うとるようじゃの。道に迷う事こそ道を知る事になる。だが旅をしても自分からは逃げる事はできん。人生とは変化し移りゆくものじゃ、変化に抵抗してはならん。そして全てを知り尽くしたなどとは思わん事じゃ。儂もこの歳になってまだ知る事も多い。例えばドナルド・トランプ前大統領の事じゃ。彼が軍を率いてディープステート(闇の政府)と戦っておるのはご存じかな。奴らは小児性愛の悪魔崇拝者で世界を支配しておる闇側の勢力じゃ。光側のトランプ氏はプーチン氏と共に銀河連合と協力し奴らと戦っておって、その事は銀河連合高等司令官ソーハン氏が明らかにしておる。彼はプレアデス星団アシャラ星系のエラヘル族で銀河連合を創設した種族でもあっての……ところでお主、妙な風体をしておるな、まさか、レプティリアンではなかろうな!」そう言って男を凝視する老人の険しい表情が日没と共に、海辺の浜の闇の中へ吸い込まれるようにゆっくりと消えてゆくのだった。
そこは人が暮らす世界から離れた場所のようだった。暗闇を駆け出し辿り着いた先は月明かりも届かぬ山の中で、立ち込める夜明けの霧の合間に鬱蒼とした樹々が見え隠れする。その狭間で男が見たものは一頭の巨大な熊だった。予期せぬ邂逅に驚き襲い掛かる熊。男にとっては容易な敵だが、抵抗はしなかった。ここが死に場所を探した終点のように思えたからだ。このまま大自然の食物連鎖の中に飛込む事が孤独を弔う唯一の方法だと思った。熊の激しい打撃を浴びながらも男は幸福だったのである。しかし熊は空腹ではなかった。そもそも雑食性の熊は小食で主に草食なのである。攻撃は熊の防衛本能から来るものだった。絶命し完全に機能停止した男の身体は、望み通りこの地で朽ちるのか。だが科学の粋を尽くして造られた身体は土に帰る事はなく、特殊な皮膚は動物の牙をも通さぬ強度で微生物の分解も許さない。肉体の死を超越した科学の勝利である。男の身体はまるで捨てられたビニールや不法投棄された廃棄物の如く、ただ環境を破壊し地球を汚染するよりほか、その死がもたらすものは何もない。
