
45機目「共同体の基礎理論」
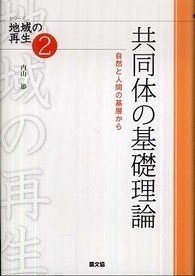
「共同体の基礎理論」(内山節 農文協)
「アイデンティティ(自分らしさ)」を考えるうえで、「共同体」っていうものに対する理解が外せないかもしれない。
そんな風に思えました。
~~~ここからメモ
わずか半世紀の間に、共同体は克服すべき前近代から未来への可能性へとその位置を変えたのである。
「近代化」とは何であったのだろうか。第一に、国民国家の形成があった。国民国家とはそれまでの地域の連合体としての国家を否定し、人々を国民という個人に変え、この個人を国家システムのもとに統合管理する国家システムのことである。
第二に市民社会の形成がある。個人を基礎とする社会の創造である。第三に資本主義的な市場経済の形成があった。
さらにこれらの動きを促進するためには、科学的であることや合理的であることに依存する精神を確立する必要があったし、歴史は進歩し続けているのだという「共同幻想」を定着させる必要もあった。
外来語の「共同体」は人間の共同体を指していて、自然と人間の共同体を意味する日本の地域社会観とは違う概念である。
たとえば村とか集落とかいうとき、日本の村や集落は伝統的には自然と人間の里を意味している。自然もまた社会の構成者なのである。
「私」をもっているとは、仏教的にいえば「煩悩」をもっていることと同義である。ヨーロッパの思想では人間は自己をもち、欲望を抱くからこそ文明が発展するというように、「私」があることを肯定的にとらえる。
テンニュスによる「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」・
ゲマインシャフト:地縁、血縁などで結ばれた有機体
ゲゼルシャフト:利害関係や目的意識などでつくられた人間の社会
ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへの移行が
歴史の発展としてとらえられていた。
それは近代形成過程の理論だといってもよい。
マッキーヴァーのコミュニティとアソシエーション
コミュニティ:共同的な生活が営まれている場であり、社会のあり方や文化などが共有されている結合体
アソシエーション:コミュニティの内部にある、ある目的を達成するための組織
「コミュニティは、社会生活の、つまり社会的存在の共同生活の焦点であるが、アソシエーションは、ある共同の関心または諸関心の追求のために明確に設立された社会生活の組織体である。アソシエーションは部分的であり、コミュニティは統合的である。」(「コミュニティ」(中久郎・松本通晴監訳 ミネルヴァ書房)
真理は1つではなく、多層的である。なぜなら真理はある磁場のなかに成立しているのだから、磁場が異なれば真理も異なる。
真理はそれを切り取った断面のなかにあるのであり、切り取られた断面が異なれば真理も異なってくる。
それは共同体を生きた人々が自然とともに存在していたからであろう。
共同体とは共有された世界をもっている結合であり、存在のあり方だと思っている。共有されたものをもっているから理由を問うことなく守ろうとする。あるいは持続させようとする。こういう理由があるから持続させるのではなく、当然のように持続の意志が働くのである。
この共同体のなかにいると、自分の存在に納得できる。諒解できるからである。自分の存在と共同体が一体になっているから、共同体への諒解と自己の存在への諒解が同じこととして感じられる。共同体とはそういうものである。
とすれば共同体の中にいくつもの共同体があっても何の問題もない。自己の存在を小さな共同体の中で諒解し、同時に大きな共同体の中で諒解する。さらにはそれらが組み合わさって、自己の存在が諒解されるのである。しかもその共同体はひとつだけでは成り立たない。いくつもの共同体があるからこそ、ひとつひとつも共同体の性格をもち、全体としても共同体でありうるからである。
故に共同体は多層的共同体なのである。おそらく「アソシエーション」を積み上げても共同体は生まれないだろう。理由のある組織を積み上げても、理由がある社会がつくられるだけだ。それはそれでよいかもしれないが、私はそれを共同体とは呼ばない。
トクヴィルにとって健全な社会とはさまざまな精神の習慣が併存している社会だった。逆に述べれば、ひとつの精神の習慣が覆っているような社会を、トクヴィルは危険な社会とみなした。ひとつの理念が支配するような社会をよい社会だと考えてはいなかったのである。なぜならひとつの理念が支配すれば、その理念だけが正義になり、それとは異なる精神の習慣を圧迫する抑圧的な社会が生まれてしまうからである。
いくら制度が民主的でも、圧倒的な多数派が同一の精神の習慣をもっていれば、それが当たり前のように正義になり、それと異なる意見をもっている人は葬り去られる。ここに制度は民主的でも、実態は強権的、抑圧的、全体主義的な社会が生まれる。それがトクヴィルのみたアメリカだった。
では多様な精神の習慣はどうしたら生まれるのか。小さな集団が多様に存在することだと彼は考える。人間の精神の習慣は自分でつくっているように見えるかもしれないがじつはそうではない。そのグループに加わっていることによって、そのグループの精神を身につけるのだと。
いくつかの精神の習慣を1人の人間が身につけるようになると、どれかひとつの精神の習慣に絶対的な真理があるわけではないことに、人々は気づくようになる。
日本の共同体にはどのような前提基盤があったのだろうか。そのひとつは自然である。
日本の共同体の特徴のひとつはその自治力の高さである。
豊臣秀吉が検地、刀狩りを実行しようとしたのも、武装した自治する共同体が統一国家を形成するうえで壁になっていたからである。
江戸期の社会は、武士が城下町に住み、農村から都市に移動したことが大きな意味を持っている。幕府は武士を農村から引き上げさせることによって、武士と農民のつながりを断ち、検地、刀狩りを実現することによって、自治する共同体を支配する共同体に変えようとしたのである。
中世後期以降のヨーロッパの農村のように、死後のことはキリスト教の神が受けもち、共同体も人間だけの共同体としてつくられていれば、共同体の管理、維持の仕方はわかりやすいかたちが可能になる。ところが自然や死後の世界を含めて共同体をもとうとすれば、人間同士の取り決めだけでは十分ではなく、自治の方法のなかに祭りや年中行事が大きな意味を持つものとして入ってくる。
村人が守ろうとしたのはこういう世界である。だから、それが守れれば、ときには案外簡単に妥協する。武士が強い命令をだせば、とりあえずしたがってみせたりする。壊してはいけない世界を守るためには、そこに手を突っ込まれない限り、平気で「服従」もするのである。それは村人たちの自身である。どうせ武士は農村の直接支配はできないのである。
~~~ここまでメモ
共同体を「多層化」し、それぞれが異なる「精神の習慣」をもっていること。これを、個人レベルでやれば、8機目の出てきた「レイヤー化する世界」のように、個人のアイデンティティは多層化された出てくるプリズムになっていくということ。
もうひとつ。共同体には「自治」があったということ。守るものを守るために、自分たちの暮らしに根差す哲学を持っていたこと。これは強いなと。
ラストは、村人たちの「強さ」の秘密がわかる一言で締めくくられる。
「村人は自分の一生だけがすべてだとは思っていない」
熱いなあ。
