
【音楽雑記】おれはアボイドノートをやめるぞー
こんにちは、ピアニストの塚本です。
やめるぞシリーズ第二回は「アボイドノート」についてです。
一応補足ですが、タイトルは「ジョジョの奇妙な冒険」第一部のディオ様のようにテンションMaxで読んでいただけますと幸甚でございます。こんなこと言ってたらジョジョが読みたくなってきましたが、がんばって話を続けます。
アボイドノートって?
さてみなさん、アボイドノート(avoid note)って言葉をご存じですか?
日本語直訳すれば「避けるべき音」です。よく音楽理論書や理論講座などに触れると出てきます。大丈夫、知らなくてもこの回はためになるので、どう
かブラウザを閉じないでください。
アボイドノートというのは、そのコードに対して不協和になるような音のことを指します。
短9度(b9、フラットナインス)音程を作る組み合わせは不協和になる、とか、トライトーン(減5度音程)をドミナント以外で作るな、とか。
説明用に簡単な動画を作りました。
まあこれだけ聴くと気持ち悪いですよね。「避けなきゃ!」って気持ちになるかもしれません。
さて「アボイドノート=避けるべき音」を「やめる」ということは「避けるのを止める」つまり「避けぬ!」となります。

まさにアウトフレージングというのはこの聖帝のような心意気がなければできません。
アボイドの呪い
私が音楽理論を学び始めたとき、いろんな人との会話の中で「それアボイドじゃね?」とかそういう話を聞いてる中で、「なんかいけないことらしいぞ」と呪いのワードとして意識に強く残ることになりました。

音楽にはやっちゃダメなことがあるんだ、と委縮した記憶があります。アドリブのときも作曲のときも例えばトニックのときに4度を弾くのは悪いことに感じました。
アボイドする必要あるのか?
結構前に受講したFernando Silvaというアルゼンチンのベーシストのオンライン講座で印象的だったのが、「フラットナインスが普通に気持ちいいんだよ、ほらこんな感じ」とかまあ弾いてくれるわけです。まったく避ける気がないです。
別にアボイドノートでなくても短9度音程は発生します。またアボイドノートだとしても、前後関係や曲調にもよるとは思いますが悪くない響きになります。こちらも簡単な解説動画を作ってみました。
私の好きな音楽家達はフラットナインスやトライトーンも別に忌避することなく美しく使っている気がします。動画最後には我が師 Vardan Ovsepianの曲の冒頭フレーズを例として弾いてます(注:自分の和声感覚が特異かもしれないので、きもいと思ったらそっとブラウザの戻るボタンを押して、アボイドノートを勉強すると良いと思います笑)。
今でこそ、経過的に使う4度、意図的に使う短9度、いまいちなケースも含めて、いろんな響きやコンテキストの中で理解が進んだので、アボイドの呪縛はないです。そして、この「いまいちなケース」を言葉で表現してくれたものなのだろうとは思いますが、「ルール」や「ガイドライン」のように杓子定規に機械的に避けられるような簡単なことではないと感じています。
否定ルールは何も生まない
よく子供とか部下とか同僚とかに「それはいまいちだ」「それはダメだ」「それはやってはいけない」と否定だけするケースはあると思います。このとき「どうすればよいのか?」という行動を促すとっかかりがないと、ただ何かを止める/止めさせるだけになりますよね。
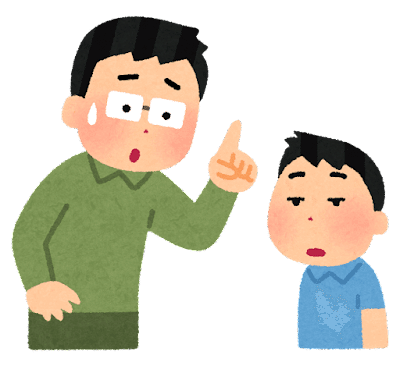
多くのアボイドノートを説明する記事は、「やってはいけない」「避けるべき」「不協和を生む可能性がある」というものの、「何をやればよいか」については語りません。
音楽を作ること、即興演奏をすることは「やってはいけない」の否定ルールから導かれるものではなく、「こうしたらよさそう」の肯定的な経験・感覚の集合だと思うのです。
特に即興演奏してるときにこれはダメ、あれはダメ、なんて考えてるヒマないですよね。
で、どうしろと
アボイドノートは、そんな呼び方があるんだな、くらいに眺めておけばいいような気がしてます。こういう風に音を積み上げると、こういう風に響くのか、という理解のためにはよいと思います。
しかし、せっかく思いついたものを取り下げたり、捻じ曲げたりする「やってはいけない」ルールではない、という意識を持っていた方がよいかなと思います。
ともかく、先人の音楽に耳を傾けて、いろいろ試してみて、経験し、自分なりのポジティブなルールやパターン、プラクティスを見出していくに尽きるかなと思いますけど(それがめんどっちいので、理論とか安易なhow toに飛びつくのでしょうが)。
まとめ
「アボイドノート」はあくまで捉え方・考え方の一つ。ルールではないし、何かを生み出すための考え方ではない
何かを生み出すには「やらない」ためのルールではなく、「やる」ためのルールや考え方を定着させていく方がよさそう
とえらそーなことを言って終わりとします。ありがとうございました。(了)
