
オラファー・エリアソンがだいすきになった@「ときに川は橋となる」展 その1
東京現代美術館で開催されていたオラファー・エリアソン「ときに川は橋となる」展。

7月末に訪れた際、まさかの«ビューティー (1993)»という作品を見逃して帰ってくるというぽんこつぶりを発揮してしまったため、先日再度訪れてきました。

せっかくもう一度行くのならば、と「論理的美術鑑賞(堀越啓【著】)」を実践してみることに。
それほどの知識なく訪れた1回目と、知識を備えて訪れた2回目について比較しながら、オラファー・エリアソンについて書いていきたいと思います。
今回、その1としてまずオラファー・エリアソンという人について触れたいと思います。
なぜ「ときに川は橋となる」展にいこうと思ったのか
そもそもなぜこの展覧会に興味をもったかというと、日曜美術館(NHK)を観た母からの薦めでした。オラファーさんがアイスランド系の方だと聞き、絶対に行きたいと思いました。というのも、数年前にアイスランド旅行へ行ってから、アイスランドがすごく好きな国になり、気になり続けているのです。
オラファー・エリアソン(53)とは
ここで、論理的美術鑑賞の1つであるアーティストの人生を読み解く「ストーリー分析」のフレームワーク(STEP1-5)を使って、私が思うオラファーさんについてご紹介したいと思います。
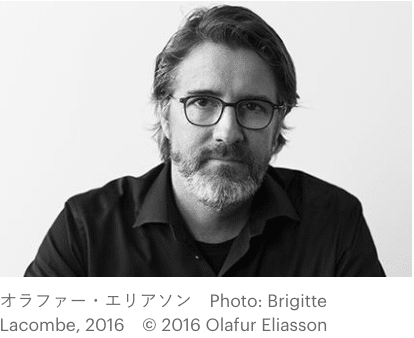
STEP1:どうやってアーティストとしての人生が始まった?
オラファーさんは、コペンハーゲン(デンマーク)生まれのアイスランド育ちです。

アーティストであり料理人である父、エリアス・ヒョルリーフソンさんに、オラファーさんは小さい頃から刺激を受けてきました。
たとえば一緒に山をみて「あの稜線は何に見える?」とエリアスさんが問いかけます。すると、オラファーさんは「あそこが鼻で、巨人が寝転がっているようにみえる」と答えてその絵を描くと、エリアスさんはすごく喜んだそうです。そうやって今、目の前に見えている現実をあなたの想像力で違うものにしてみなさい、とエリアスさんから喜びをもって問われ続けたことが、オラファーさんがアーティストになるきっかけになったのではないでしょうか。(日曜美術館(NHK)参照)
STEP2:どんな出会いがあった?
出会った人の影響を受けながら、アーティストは描く力や技術を向上させていったり、(中略)いろいろな思いを胸に宿らせ、自己の表現へと変換していきます。そして自分の才能が徐々に多くの人の目に触れるようになっていき、アーティストとしての実績を重ねていきます。
論理的美術鑑賞(堀越啓【著】)
父であるエリアスさんは、オラファーさんの師匠でありメンターであったように思います。また、オラファーさんは幅広い人材(技術者・建築家・研究者・美術史家・料理人等)からなるチーム、スタジオ・オラファー・エリアソンを設立し、作品制作を行っています。
STEP3:人生最大の試練は? & STEP4:その結果、どうなった?
オラファーさんのご両親は、オラファーさんが小さい頃に離婚されています。そのため、福祉に厚いコペンハーゲンでお母様と生活しながら、週末や夏休みは大自然アイスランドで父エリアスさんと過ごしていました。この2つの地を行き来していたことによって、日常生活の気づきを地球規模で作品化していくことになっていったのではないでしょうか。
STEP5:使命は何だった?
私は3つあると思っています。
・未来が求めるものに従って、現在を形作る
・「観客」に委ねるアート作品の制作(体験することの意味を問い直す)
・アートとのつながり方を民主化する

まとめ (その1)
オラファーさんは、こんなことをおっしゃています。
アートとはひとつの言語であり形式です。より重要なのはそのアート作品がなぜ作られて、なにを伝えようとしているのかです。伝えることによって使う言語も変わってくるでしょう。ただわたしの場合より詩的な言語を使いたいと思っています。 日曜美術館(NHK)より
オラファーさんの作品をみているとたしかに、一体これはなんだろう...、と作品の前に立ち止まってずっと考えてしまう、流し見ることができない力を感じ、それは詩を読んでいる感覚と似ているように思いました。
次回以降、1つずつの作品について、1回目と2回目の鑑賞を比較しながら書いていきたいと思います...!
