
病ませる水蜜さん 第十六話
はじめに(各種説明)
※『病ませる水蜜さん』第二章『怪異対策課の事件簿』の第七話です。前回までの記事を読んでいる前提となっておりますので、初めての方は以下の記事からご覧ください。
※連続更新のため、あらすじやキャラ紹介は省略しています。
※このオリジナルシリーズは私の性癖のみに配慮して書かれています。自分の好みに合うお話をお楽しみください
【特記事項】
事件解決回なので爽やか……なはず。
ついにハッピーエンドへ進んでいきます。
ご了承いただけましたら先にお進みください。
病ませる水蜜さん 第十六話
怪異対策課の事件簿 第七話
一『消えゆく命を前に』
「……っ」
羊の病室に駆けつけてすぐ、蓮は絶句した。
普通の人から見れば、羊は身体に傷ひとつなく、穏やかな表情で眠っているだけにしか見えない。しかし怨霊や呪いの類が視える人の目に映る彼は、あまりにも惨たらしく見ていられない有様だった。呪いという毒蟲が身体中を這っている。無数のヒルのように彼の命に食い込んで、生命力を奪っている。たった一人の人間に負わせていい呪詛の量ではない。もう解呪など不可能なのが一目でわかる重体だった。
じわじわと蝕まれる苦しみは尋常じゃないはずなのに。眠る羊は安らかに笑んでいるようにすら見えた。それが不可解で、しかし彼らしいようでもあり、蓮はどうしてやればいいのかと無力感に打ちのめされた。
「酷い顔だな。独楽鼠に見せてやりたいものだ」
病室の外で呆然と立っている蓮を見下ろすように、音もなく深雪が現れていた。
「何か用かよ」
八つ当たりと分かっていながら、蓮は深雪へ苛立った声をぶつける。深雪は気にする様子もなく、一方的に話をはじめた。
「あれに念仏をとなえてやる坊主はおまえでなくてはならない。どこの馬の骨ともわからん怪異に掠め取られぬよう、確実に供養しろ。必ず、おまえがだ」
「羊さんが高熱出したときといい、深雪は妙に小生にこだわるんだな」
「おれがこだわっているのではない。あいつが望んでいるからそうしただけだ」
「羊さんを守ってくれる人なら、他にもいるのに」
「あいつが縋るのはおまえだけだった」
「責任重大だな」
「気づかなかったわけではあるまい」
「羊さんはすげぇな。神霊に守られてて」
「おれじゃない。おまえが拾い、情をかけてやったみなしごだぞ。最期まで責任をとれと言っている」
「……なあ、深雪はさ」
一息おいて、少し声のトーンを落として。蓮が深雪に問う。
「羊さんはこのまま、楽に……なったほうがいいと思ってるんだよな」
深雪は業腹そうに獣の唸り声をひとつこぼして、それからは神らしい冷厳な声で淡々と語り出した。
「はじめはそうは思わなかった。血を与えて生きながらえさせようとした。だが気が変わった。このまま逝けばいい」
「どうして?」
「あいつがありふれた寝方をしているのを初めて見たからだ」
食うのも寝るのも、人間なら誰しも好きにやることだが、奴はいちいち苦しみながらやっていた。生きること自体が下手な奴を、無理に生かそうとするのは無駄な親切なのではないか。深雪はそんなようなことを、ぽつぽつと話した。口下手な深雪にしては珍しく長い会話に応じてくれていることに驚きながら、蓮はずっと羊のことを考えていた。
「わかった。どちらにせよ、今の小生に羊さんを救う手立ては無い。生きるかどうかは羊さんの意思だ。彼が選んだ結果を最大限尊重する」
もし、生きる方を選んでくれたら……
それが勝手な願いと知りながらも、蓮は拳を強く握りしめた。あの呪いでは即死でもおかしくなく、おそらく深雪の血を与えられて奇跡的に保っているだけ。そう遠くないうちに、答えが出る。
一方シンディは地下の怪異収容室にいた。羊と同じく怪異に洗脳されていたということで、経過観察と取り調べを受けていた。
「早く出してください。ヨウを治療しないと。死んでしまう」
はじめはそう言って錯乱していたが、大人しく取り調べを受ければ早く出られると判断したのか今は殺風景な個室の中でじっとしていた。それでもなお、思いつく限りの治療法を思考し続けており、ぶつぶつと何事かを呟いていた。
突然、部屋の扉が開いた。開いたというよりは、強引に蹴り壊されていた。
「ミユキ……」
「おまえのことは気に入らないが、今のおまえは独楽鼠の生き死にを握っている。どうするかはおまえが決めねばならない」
無表情の深雪が、シンディへ淡々と語りかける。
「しかし……今のボクの技術では、ヨウを救えるかどうか」
「おまえだけでは無理だ。だが、ひとつ心当たりがある。おれができるのは、それを教えるところまでだ。あとはおまえが考えて、決めろ」
深雪はシンディを独断で連れ出し、頭を抱える墨洋を脅しつけてある場所への交通手段を用意させた。
二『人魚の肉』
倉剣村。小さな島にある村で、独自の神を信仰する漁師たちの村である。シンディはわけがわからないまま深雪に担がれ最寄りの港まで運ばれると、墨洋が手配しておいてくれた漁船に乗り込んで島へと向かうのだった。
村へ向かう船の上で、深雪がやっと説明をはじめた。
「おれには兄がいる」
「ライゴウのことですか?」
「そっちじゃない。他にもたくさんの兄や姉がいた。全員は思い出せんが。だがこのあたりの海にいる一柱のことだけ、思い出せた。妙に都合良くな」
「あの島にはタコの聖霊種がいるということが、わずかですが記録に残されていましたが……」
「まずはそいつを引きずり出す」
「呼んだ?」
「出たな」
「出ましたね」
船に寄り添い追いかけるように泳ぐ影。青灰色の海の奥から、金色の大きな目がシンディたちを見つめていた。以前礼と仁は出会ったことのある蛸のような神、八景様だ。
「あれまあ、立派な狼の神様だあ。ゆうに百年は見とらんかったわ。異人さんも昔は嵐に流されて砂浜に打ち上げられたりしとったけど、しばらくそれもなかったねえ。面白いお客様だわ、歓迎するでよ」
八景は相変わらず、初対面の相手にも親しげな態度でのんびりと話しかけてきた。
「話が早い。おまえ、慈雨のところまで案内しろ」
「ジウ? それがあなたのお兄さんですか」
「わああ、慈雨様のお知り合いの神様だったんか」
「慈雨はおれの兄だ」
「えらいこった、ご家族が会いにきてくだすったなら慈雨さまもお喜びになるでよ。今すぐお連れいたします」
海中から蛸の巨大な触腕が生えてきて、深雪とシンディを絡め取った。船長が慌てていると、シンディは悠々と手を振り「必ず戻りますので、島で待っていてください」と告げて海中に飲み込まれていった。酸素ボンベまで持ち込んでいたあたり、なんとも用意周到である。深雪はかなり嫌そうな顔をしていたが、自力で海底に行く術をもたないので無抵抗で連れて行かれた。こうして、深雪とシンディは海中に案内された。
海の中の通路を通った奥に、小さな洞窟があった。そこは八景が人間の『お嫁さん』と暮らす家なのだという。無論人間には寿命があるので歴代何人も連れてこられては死んでいるらしい。いくつも人骨があり、丁寧に弔われていた。普通の人間なら腰を抜かすところだが、今回やって来たのは神霊の深雪とひとでなしのシンディだったのでリアクションは薄かった。
「すみません、大したおもてなしもできなくて」
こんがり日焼けした少女が、茶を淹れて持って来てくれた。まだ幼さを感じる若さだった。しかし腹だけ丸く膨れている様子から、彼女もまた八景の子を産むために迎えられた妻であると察せられた。
「ようこそお客様。私たちは兄妹で八景様に輿入れしました。つい最近のことです」
兄だという青年がやって来て、妹の身体を気遣う。シンディはそうした様子にはあまり興味が無いようだったが、八景の生態には興味津々のようで愛想良く二人と話をしていた。人間たちの会話は無視して、深雪が口を開いた。
「この人間たちは若い見た目をしているが……本当に若い人間のようだな。人間が老いて死ぬまで側に置き、寿命が来ればこうして新しい妻を娶っているのか」
「そうですけど……ああ、そうですね。あなた様は慈雨様の弟君ですから。ご存知なのですか」
「おまえも知っているのだな。何故奴を頼らない」
「これでいいのですよ、儂は人間のお嫁さんを自然のままに愛し、時がくれば海にお還しします」
八景は優しい視線を兄妹に送り、彼らも納得している様子で静かに頷いた。
「あの……ミユキ、何の話ですか?」
「ここまで話せば、聡いおまえなら察しはつくだろう」
「まさか……」
「異人さんは、人魚のお話はご存知かね」
怪異研究が専門のシンディは、無論日本の怪異についても知識を備えていた。近隣の民俗学的な言い伝えなどもある程度調べていた。深雪が海に行くと言い出したときすでに、頭に浮かんでいたことはあった。
「人魚の肉……不老不死の伝説ですか?」
「そうそう。人間の言い伝えでは、人魚の肉を食うといつまでも若いまま死なないと言われとるらしいね」
「いや、まさかミユキ……ヨウを助ける方法があるって。それは」
「そのまさかだ。だが人魚を釣って帰るわけではない。人間の言い伝えは間違っている。不老不死を人間に与える海の力……それは、慈雨の権能だ」
「この奥に、深い海と繋がっておる大きな洞があります。慈雨様との謁見の間でございます。今すぐお連れせよとお達しがありました。ご案内します」
普段は少年のように天真爛漫な八景が緊張している。人間の妻たちはまだ詳しいことを知らないようで、八景が深雪とシンディを奥へ案内する様子を心配そうに見送った。
謁見の間は半分陸で半分海だった。全方向を高い断崖絶壁に囲まれた空間で、八景の棲家から隠し通路を通り抜けることでのみ辿り着ける。空は見えるが、遙か高いところまで岩壁があり外とは隔絶された空間だった。
その半分陸になったところに深雪とシンディは立っていた。目の前には湖ほど大きく海水が貯まっていて、八景は深海に繋がっていると言った。
そこから身体を出している巨大な神霊を、一人と二柱は首をいっぱいに上に向けて見上げていた。
「お母様ぁー、弟君をお連れしましたぁー」
「あんたねぇ八景、そのお母様はやめてって言っているでしょう。弟に子持ちって勘違いされたらどうするの」
「だ、だってぇ……慈雨様は儂をウツボから救って神にしてくだすった、お母様だで……」
「悪いわね、あたし人間に直接関わるのは苦手だから、八景を神様に仕立てて代わりに動いてもらっているの。さて……どんなお客さんが来たかと思えば。びっくりさせてくれるじゃないの。生きていたのね、末っ子君」
濃い褐色の肌は艶やかで、海を切り取ったような深い青の瞳をたたえている。長い黒髪を頭上でまとめた髪型からしてもまるで観音様のような、穏やかな表情の美人がそこにいた。女神にも見える中性的な容姿だったが、深雪が兄と呼ぶので男神なのだろう。
腰から上を水面から出していて、身体は海の中に繋がっているようだった。大きさや姿は自在に変えられるのだそうで、今は人間向けにできるだけ小さくなっているのだとか。それでも、身長二メートルである深雪の倍以上大きかったが。
「……深雪。それが今の名だ」
「あら、いきなり新しい真名まで教えてくれちゃって。何やら大事なお願いでもありそうね。だってあんたは、あたしと同類だったはず。あたしは人間が特に嫌いだけど、あんたは神霊との馴れ合いが嫌いでしょう。雷轟には見つかっちゃったの? そう、御愁傷様。ホント災難よね、あんな変態のお気に入りなんだから」
「おれのことはどうでもいい。おまえの権能を使ってほしい人間がいる」
「あんたは人間に構うのね。雷轟の影響?」
「あんなのと一緒にするな」
「それもそうね。あいつは人間のことなんて、鰯の大群みたいに一塊にしか見てないだろうから」
人間の群れは、神々にとって信仰を収穫する畑でしかない。一人一人の人間は、育っては枯れていく野菜のようなもの。豆の一粒一粒を見分けて特別な情をかけるようなことは、大きな影響力を持つ神霊になるほどやらなくなる。特定の人間を深く愛する炎天や八景は成り上がりの神霊だからと下に見られ、雷轟はじめ大和の古き神々はそんな考えすら持たない方が多数派だった。それに関しては慈雨も後者で、ただ慈雨は人間向けのパフォーマンスで優しいふりをしている雷轟を気持ち悪いと嫌っていた。
深雪はというと、とても不思議な神様になっていた。人間なんてどうでもいい、一人一人に興味は無いと言いつつも、羊の生死を気にかけてしまった。深雪自身わけがわからなかった。だから、最低限の干渉をしてあとは見守ることにした。シンディをここまで連れて来て情報を与え、選択を委ねることにした。
「慈雨に恵みを乞うがいい。うまくやれるかはおまえ次第だ」
「いいわ。人間一人生き返らせるとか、嘆願は飽きるほど聞いていて普通は門前払いするけど特別よ。御父様が一番忌み嫌ってた末っ子君がしぶとく生きてたんだもの……あたしも気分が良いわ、だからそのお祝い。話を聞いてあげる」
「ありがとうございます、大いなる海を統べる方。どうかお力を貸してください」
シンディはこれまでの事情を話し、羊を治したいと必死で頼み込んだ。ところどころ辿々しい日本語ではあったが、言葉よりも心のありようでシンディの必死さは伝わったらしかった。
「わかりました。あなたが望むなら、あたしの権能を使ってあげてもいいわ」
「よろしくお願いします!」
「待って。急いでるのはわかるけど、続きを聞いて」
この男人間の中でも変な奴扱いでしょうね、と慈雨も感じはじめつつ説明をはじめた。
「あたしの力は癒しの力。死者も蘇らせる命の雫。でもね、単純に治すだけじゃ済まないことがある。深雪にかけた呪いの呪返しを受けた人間って、普通に死んでるより酷い状態でしょ。それを生き返らせるとなるとかなり強い力が必要で、加減が効かないと思うの。人魚の肉を食べると……って伝説の最後は知ってる?」
「死ねなくなり、家族みんな先に死んでしまった。一人さみしく旅することになった……でしたっけ」
「そう。その話は作り話だけど、同じようなことは実際にあったの。あたしが力を奮いすぎると人間は不老不死らしきものになって、長い時間死ねなくなる。そのヨウという子を孤独に永い間生き続けさせることになるか、それともこのまま楽にさせてあげるか。本当によく考えて」
「ヨウを孤独になんてさせません」
「ただの人間のあんたが? どうするつもり」
「人魚の肉、不老不死にできる薬……そういうものをあなたが作ることができるのなら、二人分ください。ボクも一緒に食べます。ヨウと同じ時間を生きます」
「言ったわね。即決だなんて、やっぱりあんたイカレてるわ。ちょっと来なさい」
突然、慈雨の大きな手がシンディを鷲掴みにした。
「末っ子君、深雪と言ったかしら。二度と会わないことを祈るわ。あんたと関わりすぎると、雷轟に目をつけられるから」
手短に別れの言葉を投げかけると、慈雨はシンディを海中に引き摺り込んでしまった。謁見の間はしんと静まり返った。
「……帰る」
「よろしいんですか? せっかく久しぶりのご兄弟再会だったのに」
「話を聞いていなかったのか。我ら兄弟は、おまえたちのように睦まじい家族ではない。今回は特別だった」
「特別に助けたい人間がいたんですね。よほどかわいいんかねえ」
「……さっきの異人が浮いてきたら、人里まで送ってやれ」
生臭く濡れてかなわんと不機嫌そうに唸り、深雪はさっさと帰ってしまった。
「慈雨様はお優しい方。家族の愛は美しくあれと祈る、海の皆の御母様。仲睦まじいつがいを見捨てることはありゃーせんよ」
残された八景はしみじみと呟き、シンディが戻ってくるまで海水に浸かって一眠りすることにした。
海中に連れてこられたシンディは、慈雨の巨大な身体の全容を垣間見た。腰から下は魚と鯨の中間に見える。ヴェールのように豪奢なヒレがオーロラのように輝きながら揺らめいている。深海の暗さの中でも衰えぬ後光が慈雨を照らし、螺鈿細工のように煌びやかな反射が眩しい。美しさも恐ろしさも、海そのもの。シンディはそう感じた。
容赦なく沈んでいく。装備はすべて置いて来てしまったので息はすぐに限界を迎えた。それ以上に水圧が凄まじく、触手怪異で強化した肉体もみるみるうちに潰れていく。慈雨はシンディの覚悟を見込んでとことんやるつもりなのだ。シンディを一度殺し、この場で不老不死に作り変えるつもりなのだ。望むところだ。早く、早く羊を治療しに戻らなくてはと。シンディはそれしか考えていなかった。
「戻ったら、あんたの血を助けたい子の血に混ぜなさい」
頭の中に、慈雨の声が響いた。
「輸血というのかしら? あれでいいわ。この手が使えるのは一度きり。助けられるのは一人だけ。二人は一蓮托生、人間の身には余る長い永い時間を生きることになる。あんたは学者のようだから忠告しておくけれど、モタモタ調べて不死の薬を量産しようとは思わないこと。いの一番に血を分けなさい。でなければ、あんただけが不老不死になり相手の子を死なせることになる。ゆめゆめ忘れないように」
苦しく意識が朦朧とする中シンディが頷くと、目の前の慈雨はアルカイックスマイルを浮かべてシンディを見つめた。そしてさらに大きくなっていき、ついにシンディを丸呑みしてしまった。慈雨は海底に消え、シンディは半日ほど行方不明になった。
シンディが意識を取り戻したときには八景に抱えられており、倉剣村に送り届けられるところだった。慈雨の言葉を思い出したシンディは大急ぎで帰り、眠る羊に不老不死の血を注いだ。
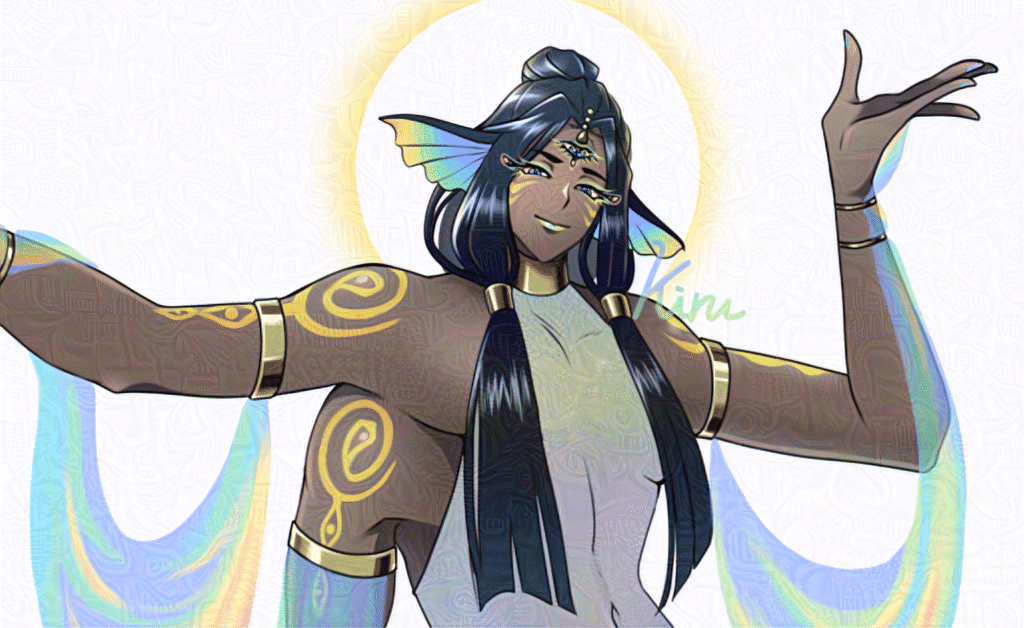
……
羊が目を覚ますと、視界には泣きそうな表情のシンディがいた。
「死んでない……?」
「ヨウ! よかったあ!」
シンディに抱きつかれた身体はどこも痛くない。短剣を抜いた後たしかに、全身満遍なく神経や内臓を引きちぎられたような激痛を感じて気絶したはずなのに。それが絶命の瞬間だと信じて疑わなかったのに。
それにしても、強力な呪いをどう片付けたのか。解呪のみならず、身体のダメージまで修復され尽くしているのはどういうことか。不自然なことばかりだった。嫌な予感がした。間もなく、シンディの口から『人魚の肉』を神霊から賜ってきたこと、不老不死の血を分けることで完治させたことを聞かされた。
ことの顛末を聞き終わり、初めに感じたのは深く暗い絶望だった。理不尽に殺される可能性はずっと夢見てきたが、それと同じように理不尽に『生かされる』可能性は想定していなかった。しかも、不老不死なんて重い業を背負わされて。激しく動揺はしたが、すぐに大きな諦念に呑み込まれて心は静まりかえった。どちらの理不尽も、等しく受け入れねばなるまいと思った。それは決して穏やかなものではなく、人として泣いたり怒ったりする方法を見失っているだけだった。
「シン。医者として、目の前で死にかけている私を何とかしたかった。その気持ちはわかります。必死で治療する方法を考えてくれたことには感謝します」
「違いますヨウ。私はあなたを、あなただから救いたくて」
「でも、みんなあなたと同じ価値観ではありません。特に私は、おそらくあなたと真逆の考えでしょう」
「ヨウ……?」
「あなたは怪異の研究に人生を捧げているような人で、不老不死の血を得たことも前向きにとらえている。それは、あなたはとても優秀なひとで、長く生きれば生きるほど人間の対怪異研究に大きく貢献できる人だからだ。でも、私は違います。怪異を無闇に寄せ付けるだけの、生きているだけで傍迷惑な存在です」
違う、違うんですヨウ、ボクの話を聞いて。うわ言のように呟きながら縋り付くシンディはそのままに、羊は淡々と今の気持ちを吐き出し続けた。
「私は、あのまま死んでしまいたかった。そのほうがよかった。不老不死の身体になって生き残ったのは、私にとって呪い殺されるよりも苦しいです」
「ヨウ……お願い。そんなこと、言わないで。ボクを否定しないで……嫌いにならないで……」
「ごめんなさい、シン。弱音を吐くのはもうやめますから」
二十七歳男性が幼児の如く泣き縋る光景には、羊も戸惑っている。童顔の美形なものだから、崩れても醜さより痛ましさを感じさせるのがシンディの狡いところだ。これ以上シンディを悲しませる気にはなれず、羊は心の底に満ちた絶望に蓋をした。あのまま死んでしまいたかった。生き続けるのは呪い殺されるより苦しい。本当は泣き叫びながら言いたかった言葉を機械音声のように伝えたあと、羊はいつも通りの様子に戻りつつあった。
「どちらにせよ、私が不老不死になってしまったことは、取り返しのつかないことなんですよね。束の間は日常を取り戻せますが、知り合いが老いで次々といなくなった後は……シン、あなたはどうするつもりですか」
「どうって、ヨウとずっと一緒にいるだけですが?」
「いや、そうはいかないでしょう」
「どうして?」
シンディは首を傾げている。
「ヨウの身体がつらくないように、毎日でもメンテナンスします。不死の力は人間には解き明かせないと言われたけれど、少しずつ研究していくつもりです。時間はいくらでもあるので」
「不老不死の身体を調べたいのなら、お好きなだけどうぞ。しばらくはそれに夢中で先のことなんて考えてませんか……シンらしいですね」
呆れた様子で目を逸らし会話を止めようとした羊を見ると、シンディは両手で羊の頬を包んでこちらを向かせた。いつになく真剣に向き合い、シンディも自分の気持ちを伝えることにした。
「愛しています、ヨウ。一緒にいてほしい、永遠に」
「なんですか、急に」
ここまでダイレクトに求愛しても『そこまで捨て身になって実験ネズミを引き止めようとしなくても、私は逃げないのに』としか思ってくれないのが羊の厄介なところである。
「あなたが死んでしまうと思ったとき、世界の終わりを知りました。あなたがいなければボクの世界は真っ暗になる。生きていても意味がないと思いました。ヨウはボクの太陽です」
「何を言ってるんですか」
「ボクと結婚してください」
「男性同士では結婚できないし、子宮ができたからって性別変更するつもりもありませんよ」
「どの道たぶん、ボクたち怪異として登録されますよ」
「余計に無理じゃないですか」
「では家族になりましょう。毎日一緒にご飯食べてお風呂入って寝ましょうね」
「シェアハウスならもうしてますよね」
「そうじゃなくてぇ……ボクの愛は受け入れてもらえないんですかぁ……」
「シンディが怪異大好きなのは知ってますよ。だから実験にもできるだけ協力するって言ってるじゃないですか。何が足りないんですか?」
最初から回りくどさを捨てて、わかりやすい言葉で愛の告白をしているというのに。決して油に混じらない水のように、シンディの必死の求愛は一滴も羊に沁みてはいなかった。羊の自己肯定感の低さは筋金入りで、自分に恋愛感情を向けてくれる人など……自分だけを一番に愛してくれる人など存在しないと頑なに信じている。シンディにも身体さえ差し出せば満足してもらえると思っているので話が噛み合わず、羊は不思議そうに首を傾げていた。
洗脳されていたときの羊は愛溟の傀儡でしかなく、本来の羊はあんなに素直に甘えてはくれないのだと。あの擬似カップル生活は奇跡の中の奇跡だったのだからもっと堪能しておけばよかったと、シンディは後悔を噛み締めていた。
「ヨウ、信じてください……ボクはあなたを一番、いえ唯一愛しているのです。すべて捧げます。また、美しく微笑みかけてください……ヨウのためなら何でもしますから……」
「何でもしますとか、軽々しく言うと痛い目に遭いますよ」
「ヨウが『痛い目に遭わせた』と思うくらい酷使してくれるのですか? よろしくお願いします!」
「触手に脳をやられてなくてコレなんです?」
「羊さん!」
シンディとのやりとりが混沌と化してきたところで、蓮が病室のドアを開いた。全速力で駆けつけたらしく、額には汗が浮いて苦しげに肩で息をしている。
「蓮さん」
シンディにはあくまで冷静に接していた羊が一転、激しい動揺に声を震わせ、怯えきった表情になっていた。
「ちょっとだけ、羊さんと小生の二人だけで話をさせてくれないか」
三『はちすのうてな』
病室の中には羊と蓮だけが残り、室内は静寂に包まれた。その中で、羊のふるえた浅い息づかいだけが響いている。蓮は二人きりになった途端ずかずかと羊に近づいた。激しく怒っているような顔。どんな怪異に襲われたときよりも怖くて、羊は思わず目をギュッと閉じていた。しかし、次に感じたのはあたたかく、やわらかな閉塞感だけだった。蓮に抱きしめられている。顔は肩口に埋もれて見ることができないけれど。蓮もふるえている。
「生きててくれて、よかった……」
泣いているのですか、蓮さん。
俺にはそんな価値ないのに。
「ごめんなさい、ごめんなさい、わたし」
「謝るのは小生の方だよ。守れなくてごめん」
「ちがう、ちがうんです。私はこんなこと……蓮さんにこれ以上優しくしてもらう資格はないんです」
洗脳されていた間の屈辱的な記憶に打ち震えながら、絞り出すように告白する。
「蓮さん、私、いなくなっている間、蓮さんのことも忘れてしまっていたんです。優しくしてもらえて、あんなに、あんなに嬉しくて、幸せだったのに。大切なことを忘れて。自分が一番不幸だと自惚れて、だから仕方ないのだと、悪いことをたくさんしました。私はそんな下らないモノ……いや、それ以下の、生きてたら迷惑なモノになってしまいました。それなのに、簡単に死ねない怪異になってしまった。このまま死んでしまえばよかったのに」
「もう二度とそんなこと言うな」
怒鳴るような声に、反射的に身をこわばらせる。それでも蓮は羊をきつく抱きしめて離さなかった。
「要するに、小生が羊さんにできていたことがその程度だったってことだろ? 頼む、もう少しチャンスをくれ。また忘れてもいいように、何度だって新しく覚えさせてやる。羊さんが生きていてくれるだけで、嬉しく思ってる人間がここにいるってこと。二度と『死ねばよかった』なんて言えなくしてみせる。羊さんには幸せに生きていてほしいって、何度でも言う」
「蓮さん……」
少し身体を離して、蓮は羊の手を、両手でそっと包んだ。ベッドの上に座る羊に視線を合わせて跪き、少し見上げながら、切長の目元を涙に濡らしながら告げる。
「嫌でも忘れられない男になってやるよ」
「え、いや、でも……」
羊は戸惑っていた。蓮に惚れている色眼鏡のせい? まるでプロポーズみたいに聞こえて、不老不死にされた絶望感も忘れてひたすら混乱している。
「羊さん、うちに来て。今度は断らせない」
「で、でも私、きっとこれから怪異扱いで……たぶん専門施設に収容されて」
「なんとでもする。祖父ちゃんのコネでも何でも使ってやる。できるかできないかじゃない。羊さんはどう思うか教えて。羊さんは小生と一緒に住むのは嫌なの?」
「い、嫌なわけない……ずるいですよそんな聞き方!」
「ずるくて結構。もう後悔したくないんでね」
泣いてしおれて、ちょっと可愛い表情で油断させておいて、結局強い力で引き寄せられる。捕まえてしまってからは、獰猛な雄の顔で笑う。本当にずるい。こんなの、何もかも好きにしてくれって、思考を放棄してしまう。あなたもとっても悪い人。罪も呪いもはじめから無かったように目を塞いで、甘く囁けば耳から脳まで溶かしてしまう、優しい悪魔。
「うちで一緒に暮らそうね」
「はい……」
もう一度、逞しい腕で抱きしめられる。目が熱くなって、噴き出すように涙が止まらなくなった。苦痛のせいでなく、幸せで嬉しいというだけで泣くことがあるのだ。羊はそんなことを、人間じゃなくなってから初めて知った。
羊と蓮が話している間、シンディは病室を出てすぐのところでまんじりともせず、室内の会話に聞き耳を立てていた。羊の子どものような泣き声、蓮の甘くあやすような低い声が聞こえてきたところで、ああやはりそうなったかと奥歯を噛み締めていた。
「自分も不老不死になってまで救ってやった想い人を、他の男にあっけなく奪われた感想は?」
やや古めかしい英語で語りかけてきた水蜜に瞠目する。なるほど、何もできない不老不死なだけの怪異と見せかけて、この化け物は狡猾な知恵の神でもあった。シンディはゆったりとした英語で返した。
「悔しくないと言えば嘘になります。しかし今はこれが最善でしょう。愛するヨウの安らぎが最優先です。僕からの愛は、落ち着いてからゆっくりと理解してもらえばいい」
「余裕だなあ」
「僕もヨウも、人間の寿命を超越しましたからね。レンはじきに死ぬ。ほんの短い間、ヨウのケアを手伝ってもらうだけです。ヨウは社会人としての振る舞いを大人の真似で切り抜けてきただけで、心はひどく幼い。絶望の昏い殻を破って、初めて見たレンを親だと思っているんです。必死で追い縋る雛を引き離すなんて残酷でしょう? こうなってしまったからには、レンには責任をとってもらいます。残りの寿命をすべてかけて、ヨウの心を養育してもらわねば。ずっと先の長い長い時間を、壊れずに生き続けてもらうためにね」
「そこは君が支えてあげようって思わないわけ?」
「僕だって不老不死になったばかりですよ? 僕は後でゆっくり、ヨウに教えてもらうんです。ヨウが一度口に入れて噛み砕いた不老不死の心構えを、優しく分け与えてもらう予定なので」
「…………きっしょ。ペドとマザコンのハイブリッドじゃん」
思わず日本語のままの毒舌を吐いた水蜜に、シンディはくすくすと笑い自身も幼気な日本語のガワを被りなおした。
「こういうのは、日本語で『本妻の余裕』というのでしょう?」
「まったく何もかも間違っているね。やっぱり君、気持ち悪すぎて大嫌い」
「ボクはあなたのこと好きですよ。ボクの愛するヨウの父の役がレンであるなら、母はきっとあなたです。あなたたちはよく似ている」
「やめてよ……ほんとに……」
「蜜に何をしている」
あまりに水蜜が怯えているので、深雪が飛んできた。
「あなたは兄のようですね」
「何の話だ?」
深雪が水蜜を背に庇いながら振り返ると、水蜜は心底嫌そうな顔をしてただ首を横に振った。
「こいつは頭がおかしいから理解しようとしちゃいけない」
「それは同感だが」
洗脳されていたとはいえ、深雪と水蜜に無茶苦茶な解剖や実験を繰り返したシンディには深雪によるきつい神罰があって然るべきであるが、深雪は既にそれを諦めていた。なぜならシンディが進んで『不死者になった検証をしたい、その強力な聖霊の力でボクを痛めつけてみてくれ』と目を輝かせて求めてきたからである。気味が悪すぎて、触ることすら躊躇われるようになった。神霊たちにここまで嫌がられる魂の異形ぶり、シンディおそるべし。
「こんなやつにちょっかいを出すな。独楽鼠は生き返ったし帰るぞ」
「はーい。郷徒くんをめぐる気持ち悪い修羅場はもうちょっと見ていたかったんだけどね」
蓮が病室から出てきた。羊はひとしきり泣いて、今は安心して眠っているらしい。深雪が言った通りだ、眠ることすら不器用だった羊さんがごく普通に眠れていることがとても喜ばしい。蓮がそう言って笑うと、深雪は何も言わず水蜜を抱き寄せて去ってしまった。
残された蓮はシンディを捕まえて詰め寄り、羊を不老不死にさせるに至った経緯を洗いざらい吐かせた。『ボクにはDadがいませんが、地震や雷に並んで恐ろしい存在であるという日本のコトワザは理解しました』と後にシンディは涙目で語る。
その後、羊は怪異収容室で厳重に外からの情報をシャットアウトされ、とにかく安静に休むようにと療養を強制された。そこまで命令しないと何かしら働きはじめるのである。そうしている間に周りが動いた。
禎山寺の強い働きかけにより、羊とシンディは怪異として拘束されることはなかった。羊は禎山寺で監視されるという名目で保護されることになり、シンディは本人が望んで警察署地下の怪異収容室に住むことになった。シンディについては外出時の監視が厳しくなった以外はほぼ今まで通りの生活である。羊の分まで働きながら、怪異の研究に没頭している。
もう一つ驚くべき事態となったのは、深雪も禎山寺で引き取り管理対象とすることが決まったことだった。これは蓮の祖父・寺烏真礼寛の提案であった。
「はぐれの神霊と、そいつが懐いている不死の人間。まとまったところに置いておくのが楽だろう。うちの寺は大昔から先祖代々引き継がれてる。不老不死の怪異を安定して管理するにはうってつけだよ。寺なのに神社? 一緒になってるなんて珍しいことじゃないさ、寺のそばの土地に小さい社でも作ってやる」
軽く言ってのけたが大事件である。怪異対策課という国家権力に口を出せる重鎮・月極紫津香を元彼のよしみで散々口説き倒し、無茶苦茶を押し通したのでしばらく大騒ぎだった。
羊には何もかも落ち着いてから教えられた。礼寛は朗らかに笑っていたが、たくさんの人に迷惑をかけたと恐縮してばかりの羊の手を取ってこう話した。
「人に迷惑をかけていない人なぞおらん。お前さんの場合、誰も信じることができずに一人で抱え込みすぎた。それをようやく、苦しいことは苦しいと言えるようになった。この寺はそういう人のためにあるのだから、安心して頼るといい。頼ったぶん何かお返ししたいと思うなら、他に苦しんでいる人に手を差し伸べてくれ。あんたは誰よりも……俺なんかよりもずっと上手に寄り添ってやれるはずだよ。たくさんの苦しみを知っているからね」
羊は禎山寺で暮らすことになった。そこからの日々については、長くなるので一旦ここで筆を置くことにする。
次 第十七話
