
A Thousaund Suns完全解説
リンキン・パークはどんなバンド?
リンキン・パークは1996年に結成されたSuper Xeroというバンドを前身としていて、メンバー・バンド名の変更を繰り返しながら活動を行った後、2000年に大手事務所のワーナーと契約、メジャーデビューを果たします。
メンバー構成は、
メインボーカル:・チェスター・ベニントン
サブ・ラップボーカル:マイク・シノダ
ギター:ブラッド・デルソン
ベース:フェニックス
ドラム:ロブ・ボードン
DJ:ジョー・ハーン
の6人となっています。
音楽性を様々に変化させながら順調に活動を続けていましたが、2017年にチェスターが自ら命を絶ち、バンド活動が停止してしまいます。各々はその後ソロ活動などを行っていましたが、ついに今年7年ぶりに再始動!メインボーカルに、Dead Saraというバンドに所属している女性シンガー、エミリー・アームストロング、そしてドラムにコリン・ブリテンを新たに起用し、新たな道を歩み始めています。


彼らはラウドロック、もしくはミクスチャーロックと呼ばれる様々なジャンルを混ぜ合わせたロックを主体とした音楽のジャンルに分類されます。リンプ・ビズキットのようなあたりが近縁バンドになりますが、彼らよりもずっとスマートで様々な種類の音楽に取り組んでいる印象ですね。昔は「ロックは不良がやる音楽」みたいな話がありましたが、特に初期リンキン・パークは、
「スーツを着てやってる激しいロック」
という印象が近いので、人に説明するときはこの文言を使うようにしています(笑)
一般的にリンキン・パークのアルバムだと、デビュー作であり、ラウドロックの金字塔とも言える"Hybrid Theory"、そしてその流れを受け継ぎ、よりメロディックなサウンドを導入した2作目の"Meteora"が、代表的で評価が高い名盤として挙げられる機会が多いと思います。
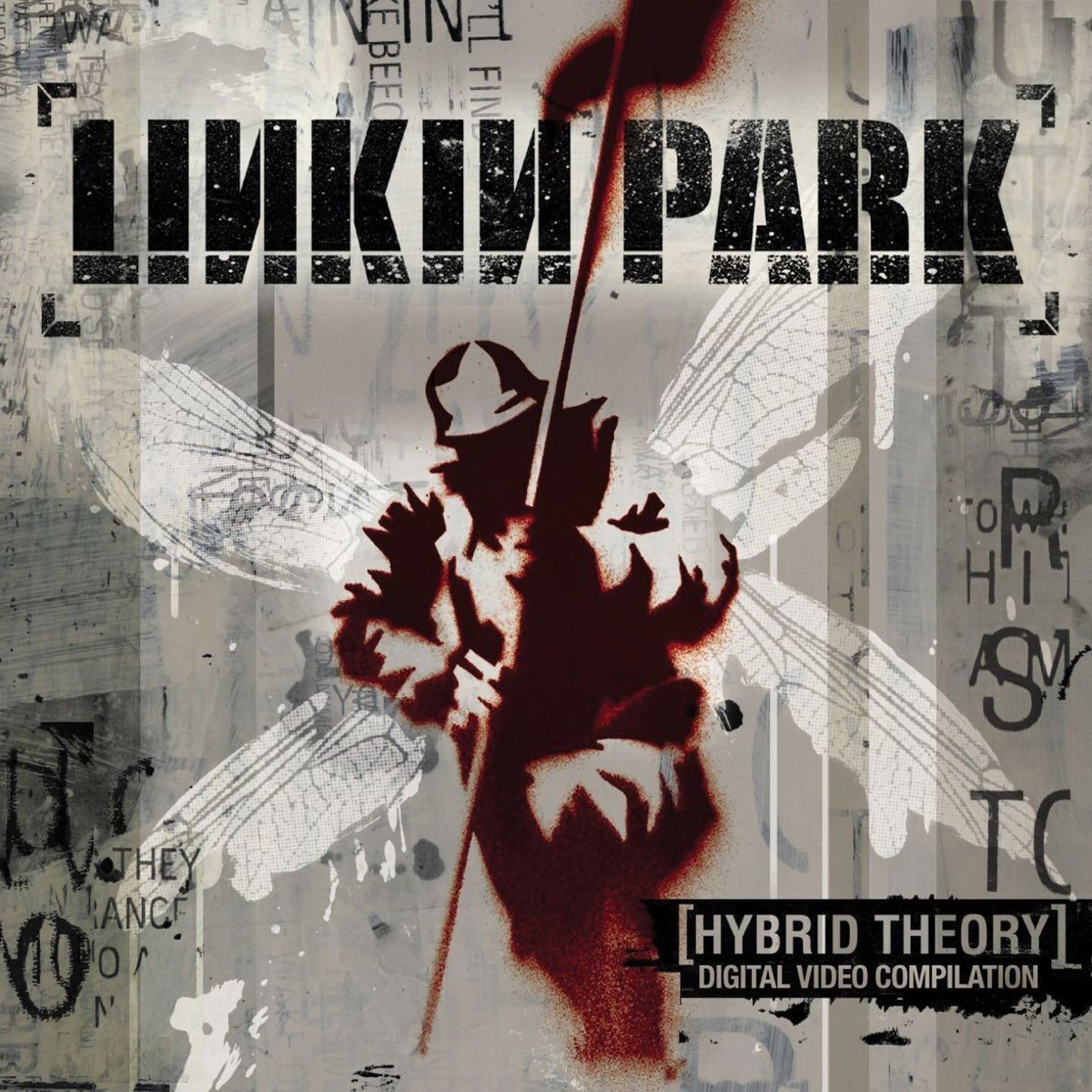

このバンドの音楽性に変化が見られ始めたのは、3作目の "Minutes To Midnight"。DJ担当のジョー・ハーンが繰り出すスクラッチは鳴りを潜め、ラウド中心だったサウンドもメロウなアレンジに。マイク・シノダのラップボーカルも減り、チェスター・ベニントンの純粋な歌唱力がフォーカスされています。かなり大きなモデルチェンジにも関わらず、アルバムは全世界で2000万枚を超える莫大なセールスを記録してしまうところが彼らの凄いところというか、過去2作で築き上げたブランドというか…(笑)
何はともあれ、この辺りからバンドの風向きが変わり始めたのは明らかで、リンキン・パークの新章の幕開けを予感させました。

A Thousand Sunsとはどんなアルバム?
まず、この "A Thousand Suns"は、ロックコンセプトアルバムです。テーマは「核戦争」で、タイトル・歌詞などにもその要素があることは何となく見てとれると思います。
アルバムタイトルは、
"If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one"
訳:"もしも千の太陽の輝きが空に向かって一気に飛び出すようなことがあるなら、それは力のある聖なるものの輝きのようになるだろう"
という、ヒンディー語の経典「バガヴァット・ギーター」の一節から取られたものです。
(一見すると核戦争とは関係のないように思える一節が、なぜ元ネタになったのかというのは、後ほど解説致します)
そして音楽性の面では、過去3作とはかなり趣が異なっていて、「Pro Tools」というコンピューターソフトウェアによる打ち込みを多用し、積極的にエレクトロニクスを導入した形式をとっています。メロウな仕上がりだった前作よりも、チェスターのシャウトやジョー・ハーンによるスクラッチという代名詞的なボーカルスタイル、サウンドは増えた印象ですが、打ち込みを導入した分、ドラム・ヘヴィーなギターなどの楽器系のバンドサウンドは薄まったように感じられます。
個人的には、「リンキン・パークがレディオヘッドの"Kid A"的な作品を作ってみました」みたいな感覚が近いような気がしますね…
結果的にこのアルバムは先述の大胆な路線変更で大きな論争を呼び、バンド地位的にも世界に衝撃を与えるキャリア最大の問題作となりました。
ということで、次のパートからは収録曲を1曲ずつ詳細に解説していきたいと思います!
全曲徹底解説
1. The Requiem
このアルバムの幕開け。初期作品を聴いたことのある方は、イントロの時点で何やら様子がおかしいという印象を抱く方も多いでしょう(笑)
空気を切り裂くような音から始まり、途中からピアノの音が聞こえ始めます(ピンク・フロイドの"Echoes"という曲のイントロに感覚は似ていますかね…)。
そして1:16付近から、女声の人工音声によるボーカルが始まります。
"God save us, everyone. Will we burn inside the fires of a thousand suns? For the sins of our hand, sins of our tongue. The sins of our father, the sins of our young"
訳:神よ、我々をお救い下さい 我々は千の太陽の烈火の中で焼かれるのでしょうか? 有する罪悪、言葉、父の罪、若かりし日の罪のために…
という歌詞が繰り返され、非常にスピリチュアルな印象を受けます。
「許されないと分かっていながらも、許しを請い続ける少女の叫び」というシリアスなシチュエーションが読み取れてくるのではないでしょうか…?
2. The Radiance
"The Requiem"からシームレスで繋がるこの曲では、何やら男性のインタビューのような音声が聞こえてきます。
これは、「原爆の父」として有名な科学者、ロベルト・オッペンハイマーの音声のサンプリングです。ここでオッペンハイマーは先ほど少し取り上げた「バガヴァット・ギーター」の一節を口にしています。
"Vishnu is trying to persuade the Prince that. He should do his duty, and to impress him. Takes on his multi-armed form and says, ""Now I am become Death, the destroyer of worlds."" "
訳:ヴィシュヌ神は、王子に義務を果たすよう説得しようとした。彼の心を動かすために千手の姿に変わり、「我は死なり、世界の破壊者なり」と告げた。
トリニティ実験という史上初の原爆実験が1945年に行われたことは非常に有名ですが、この言葉はオッペンハイマー自身がその時に頭に浮かんだものだそうです。核という強大な武器を手に入れてしまった人間がこのままだと世界の破壊者になってしまうという罪の深さを痛感した、彼自身による悔恨ともとれる文章と言えます。
ここまでが、物語が始まるまでのプロローグだと思ってください。次の曲から本編の開始です!
3. Burning In The Skies
お待たせしました!この曲から、ようやくマイク・シノダとチェスターの歌声を聞くことができます(笑)
空を戦闘機が飛んでいるような音から始まり、そこから打ち込みのドラム、暗めのギターへ続くというイントロの形式。そこから、マイクの歌声、チェスターのサビへと繋がっていきます。
この曲のハイライトは、2:35付近から始まるブラッド・デルソンのギターソロ、そしてロブ・ボードンによる生のドラム音の出現。これまでのヘヴィーなギターサウンドや強く叩く強烈なドラムとは少々異なり、少し内側に入り籠ったような音を両者共に出しています。
歌詞で印象的なところと言えば、
"I'm losing what I don't deserve."
訳:自分にはふさわしくないものを失っているところだ。
という部分ですが、「核」という人間にとって上手に扱いきるには限界があるものの、その扱いの維持性を失っているというような意味ではないかと僕は推測しています。
また、ここで覚えておいてもらいたいのが、
①打ち込み・楽器音少ない
②間奏でギター、ドラム出現
③出現した楽器音とチェスターの声の調和によるクライマックス
という順番で行われる演奏パターンが、このアルバム内の重要曲という位置付けの楽曲で行われることです。
今回、重要曲として僕が置いているのはシングルカットされた曲で、
1stシングル "The Catalyst"
2ndシングル "Waiting For The End"
3rdシングル "Burning In The Skies"
4thシングル "Iridescent"
の計4曲。
それぞれの曲のパートで再び解説しますが、このパターンを覚えておくと、彼らがこの作品で特に注目して聞いてほしい曲として考えている(すなわちシングル曲)この4曲の解像度がとても上がって聞こえてくるはずです!
4. Empty Spaces
"Buring In The Skies"からシームレスにつながる20秒にも満たないインストゥルメンタル曲(インタールード的なやつです)。
タイトルの意味から考えると、「大空で燃えた」後に、「何もない空間」が来る。つまり、爆弾の投下などの戦火でそこには何もなくなってしまった、と物語に連続性を持たせるような役割をこの曲に持たせているということになると思います。
5. When They Come For Me
ここまでの4曲とは打って変わって、民族の太鼓系の打ち込みドラムサウンドの中にヒップホップを混ぜたスタイルの楽曲です。ここではマイク・シノダのラップパートが強くフィーチャーされていて、素晴らしいライミングを見せてくれています。
曲の終盤では、チェスターのボーカルが入り、そこから壮大な展開へと発展していきます。
民族の太鼓の音は古くからある音楽の一部として認識されていると思いますが、今その辺で様々な人たちがやっている音楽にこのエッセンスが含まれているものは少ないでしょう。
この原始的な音、すなわち環境に戻りたいけれど、現代の人々の利便性・先進性を求める社会でそうするのは難しい。タイトルの"When They Come For Me"というのは、その瞬間を待ちわびていることを表しているのではないでしょうか…?
6. Robot Boy
ピアノ(キーボード)のイントロから始まる、エレクトロニックなサウンドの美しさがこのアルバム中で最も前面に出ている楽曲です。
ジョン・レノンが、ビートルズ期の楽曲、"Tommorow Never Knows"で「数千人の僧侶がお経の詠唱をしているようなボーカル」を実現するためエフェクトを用いたように、少しリバーブ系のエフェクトを掛けたチェスターのボーカルが、この曲をより神秘的でスピリチュアルな仕上がりにしていますね!
この"Robot"という言葉は調べると、「機械的に生きる人間」のような意味を表すものでもあるそうです。
"You say, you're not gonna fight, cause no one would fight for you"
訳:あなたは言う、「戦うつもりは無い。自分のために戦う奴なんて誰もいないから。」と。
"On the weight of the world will give you the strength to go"
訳:世界の重さはあなたに立ち向かっていく強さを与えてくれるだろう
という2種類の歌詞が印象的ですが、この言葉が機械的に生きる孤独な人間に生きる意味を与える神からの囁きのようにも感じられますね。
7. Jornada Del Muerto
マイク・シノダがエフェクトの掛かった声で、
「持ち上げて、解き放して」
と日本語で語りかけるボーカルは日本人にとってはより印象的に感じるでしょう。
これもエレクトロ要素が強く押し出される楽曲ですが、曲の終盤では重く沈み込むようなエレキギターの音が聞こえてくるなど、少々これまでの楽曲とは変化が感じられるシーンもあります。
タイトルにもなっている「ヨルナダ・デル・ムエルト」は、アメリカのニューメキシコ州にある砂漠盆地、ないしは「死者の道」と呼ばれるそこを通る全長160kmのルートの名前です。ここは、先述のトリニティ実験が行われた場所です。正に核戦争というテーマだからこそ付けられたタイトルだと感じますね…
8. Waiting For the End
全米最高42位、オルタナティブソングチャートでは1位を獲得した、このアルバムからの最大のヒットを記録した楽曲。
コンセプトや曲との繋がりを中心としている今作の中では、単曲でも良さが理解できるベストソングの一つです。
ビリビリとしたギターにも似たノイズ、そして"The Requiem"と同様のピアノイントロでスタートし、マイクによるレゲエから影響を受けたラップが始まります。チェスターの鮮明さ・美しさが際立つメロディアスなボーカルは非常にクオリティが高く、後にライブの定番ソングとなったのは納得の出来です!
歌詞の内容は、苦悩をしながらも希望を拠り所にして行動に移していく人間の様子の描写が中心となっています。非常に詩的な歌詞になっているので、じっくりと読み込んでどのようなことを言っているのかを理解して楽しんでみるのも面白いでしょう。
3曲目の"Burning In The Skies"で紹介した通り、
前半の打ち込み中心のサウンド、マイクの2回目のラップパート付近からハード目なドラムの生音が入り、間奏でブラッドのギター、そして楽器音・ラップとボーカルの掛け合いが入るクライマックス
というお決まりのパターン。
前半に集中しがちなキラーチューン的な曲をアルバムの真ん中で放り込めるところが、リンキン・パークのアルバム構成の素晴らしいポイントの一つであることをこの曲を聴いて感じることが出来ると思います。
9. Blackout
チェスターのキャリアトップレベルの強烈シャウトが聴ける1曲。正に"Blackout(昏倒)"しそうなくらいのものすごいシャウトをしてくれてます!
この曲も電子音が生かされてる曲ですね。ボン・ジョヴィの"Livin' On a Prayer"を彷彿とさせるフェードインから、後に"Burn It Down"などの彼らの作品でも使用される電子音リフでイントロが構成されています。ラップとシャウトの交互掛け合いとデジタル音の衝突は、無機質でアンバランスとも思えますが、そこに味わい深さのようなものが見出せますね。クライマックスでのチェスターのハイトーンの安定感は抜群で、ここでも彼のボーカル能力の高さが分かります。
歌詞はどこかサイケデリックな感じを持った意味の分からない文章の羅列で、少々難解で理解が難しいものになっています。
10. Wretches And Kings
このアルバムでは珍しくヒップホップの影響が色濃く出た1曲で、マイクのラップパートに焦点が当てられています。そして終盤のジョー・ハーンによるスクラッチは圧巻で、ハイライトとも言えるシーンです。この曲は80年代中盤~90年代前半に活躍をしたヒップホップグループ、パブリック・エネミーに大きな影響を受けていて、マイク自身も「チャック・D(パブリック・エネミーのメンバー)のオマージュ」とこの曲について語っています。
しかし、最も注目すべきはマリオ・サヴィオの演説のサンプリングです。マリオ・サヴィオはアメリカの政治活動家で、カリフォルニア大学バークレー校でのフリースピーチが有名です。その際にした演説の一部がこの曲ではサンプリングされています(「演説の一部」をクリックしてご覧ください)
。歌詞の内容もこれに関連し、「力を持つ組織との闘争」がテーマになっています。
11. Wisdom, Justice, And Love
人工音声によって紡ぎだされるこの言葉は、キング牧師によるベトナム反戦運動をテーマにした演説のサンプリングです。
「戦争や紛争によって人々に害を与える行為は、"Wisdom, Justice And Love"(知恵、正義、愛)では埋め合わせが出来ないものである」
と彼はこの演説で語っていて、差別や争いの無い平和な時代の到来を常に祈り続けていたことがよく分かります。このアルバムの「核戦争」のテーマとも被る、良いサンプリングの選択のように個人的に思います。
12. Iridescent
2011年の映画、「トランスフォーマー / ダークサイド・ムーン」の主題歌として起用された4thシングル。「トランスフォーマー」の"What I've Done"、「トランスフォーマー / リベンジ」の"New Divide"に続くリンキン・パーク3回目の主題歌起用です。
ピアノで始まるイントロで始まり、マイクの物悲しいボーカル、優しく絞り出すようなチェスターのサビへと繋がります。2番の前の間奏から、内側で響くようなブラッドによるギターを始めに少しずつパーカッションが増え、ロック曲の様相を呈してきます。
そして2番終了後の間奏でブラッドのギターリフ、メンバー全員によるサビのコーラス、その後にロブの強烈なドラムが入り、楽器の生音がはっきり聞こえるロックサウンドをクライマックスで迎えます。これもパターンが現れる曲の一例ですね。
この曲は個人的にアルバムでも1,2を争うレベルで好きな曲なんですよ。うるさくもなり過ぎず、軽すぎもしないちょうどいい塩梅の中でさらに素晴らしいメロディを聞かせてくれますから、そりゃいいに決まってるんです(笑)。メンバー全員でのコーラスも大波のように押し寄せて盛り上げてくる感じが最高ですね!
13. Fallout
このアルバムの最後の仕上げにかかる前のインタールード的な曲です。前曲の"Iridescent"から繋がるような形で始まり、人工音声→マイク・シノダの声に変化しながら3曲目の"Burning In The Skies"のサビの歌詞を刻んでいきます。
そしてシームレスでクライマックスとなる次曲、"The Catalyst"へと続いていきます。
14. The Catalyst
さあ、このアルバムのクライマックス、そしてキャリア最大の問題作と言っても差し支えない1曲の登場です。
2010年の8月に1stシングルとして発売されたこの曲は、リンキン・パークのファンはもちろん、様々なリスナーから衝撃と困惑をもって迎えられました。今までの彼らからは考えられないサウンド、詩的で複雑なパート構成など、違和感を感じるのにはあまりにも十分すぎる内容でした。
それでもUSビルボード・ロックソング・チャートで歴史上初めて初登場1位を獲得するヒットになるなど、批判意見が多い中でも一定の成功を収めることに成功します。まさにこれまで彼らが積み重ねてきた地位によるものと言えますね。
内容の解説ですが、まずこの曲はアルバムの総決算的な曲なのでここまでポイントとして解説してきた様々なサウンド・パターン・歌詞が登場してきます。
まずはサウンド。エレクトロニクス色が強く、打ち込みが多用されるのと同時にジョー・ハーンの強烈なスクラッチが響きます。楽器音もこれまでの通り、内側に閉じこもりなかなか表に出てきません。終盤にかけては、ロブ・ボードンのパワフルにぶっ叩くドラムを中心に今作で最も激しいバンドサウンドが展開され、その中でもコーラスの重なりによる美しさを表現した部分も混ざり合う複雑な構成を成立させています。
次にパターン。打ち込み→楽器音出現→チェスター&マイクのボーカルと楽器音のコンビネーション、という重要曲でのパターンを忠実に守り、そのパワーを極限まで発揮しています。
そして歌詞。1曲目の"The Requiem"の歌詞の繰り返しや再構成の歌詞で、そこにサビのオリジナルの歌詞が重なりあうように歌われています。なんと言っても、2番のサビ終了後の一旦テンションが落ち着いた時、マイクの優しい声で
"Lift me up. Let me go."
と聞こえてくるシーンでフラグ回収が行われた時のスッキリ感は抜群!
そう、7曲目の"Jornada Del Muerto"で出てきた「持ち上げて、解き放して」という謎の歌詞は、実はこの部分の和訳だったんですね~。
"Catalyst"は英語で「触媒」という意味ですが、ここまで解説してきた様々な要素が触れ合いながら化学反応を起こすように曲が進行していく様に、まさにこのタイトルはぴったりですね!
15. The Messenger
物語本編が終了した後のエピローグ的な曲。アコースティックギターを中心とした優しいメロディとゆったりしたリズムに乗りながら、チェスターが最後の力を振り絞るように熱のこもったエモーショナルな歌唱を披露してくれています。
「労い」や「安心できる世界」を中心としたメッセージを戦い終えた人々に対して伝えながら、このアルバムは幕を閉じます。
最後に
ここまで全曲の解説を行ってきましたが、いかがでしたか?
このアルバムは、今までのような良い曲を単純に並べて聴いていくだけではなく、ストーリー性やテーマ性、そしてどのようにフラグが回収されて1枚のアルバムが完結しているのかということを考えながら聴いてほしいというメッセージが込められているように今回細かく分析を行った上で強く感じました。
この記事を読みながら、改めてこのアルバムを咀嚼しながら聴いてみると新たな発見が得られるかもしれません。ぜひ一度聴いてみてください。
最後にYouTubeのプレイリスト、各サブスクでのリンクを貼っておきますので、興味がある方はこちらをクリックしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
Link
YouTube
Spotify
Apple Music
