
けテぶれフェスにいけないので、勝手にポスターセッションやってみた
主題は「今年度の“空振り”3選!!!」
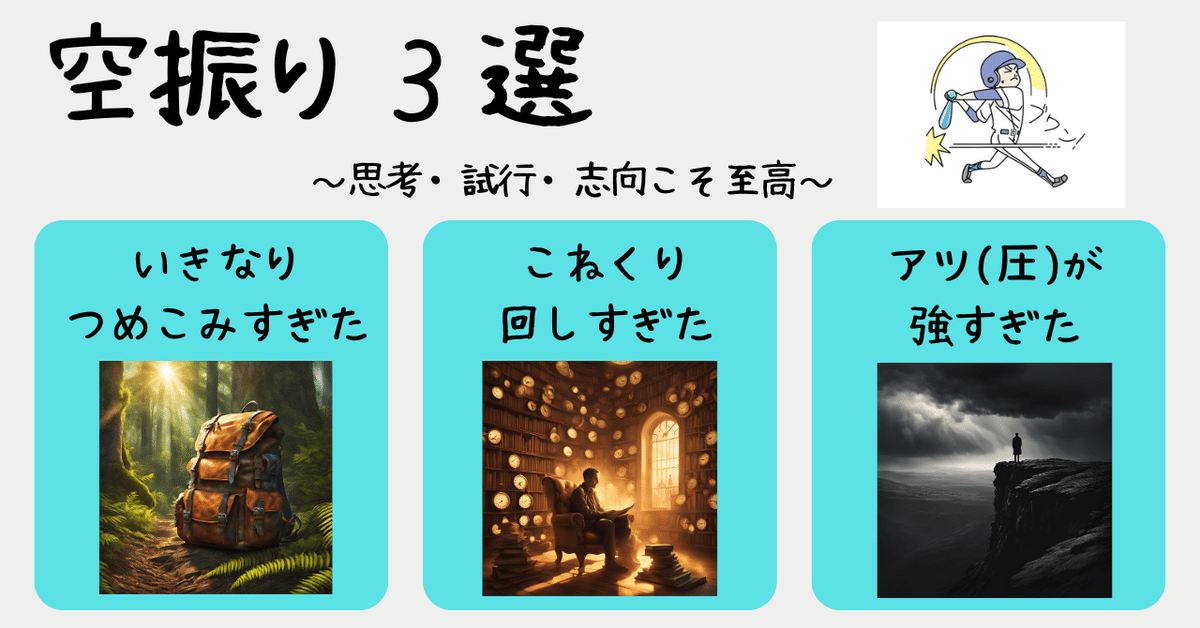
はじめに
お久しぶりです。とんです。明日8/9(金)は、けテぶれFestaがありますね。とても魅力的な催しになっており、本当は行きたくて行きたくて仕方がなかった…。だけれども、生まれたばかりの息子と過ごせるのは、この一瞬だけ。そのため今回は見送り…。
ということで、勝手ながらポスターセッションを行いたいと思います!!笑 1学期の振り返りも兼ねて、気をつけることをまとめてみました。よければ、最後まで読んでいただけると嬉しいです。
空振りその1-いきなり、つめこみすぎた…-
今年度、今までないほど学級スタートの準備をし学級開きに臨みました。「けテぶれロードマップ」なるものを書き出し、4月~7月までの段階に分けて、導入すべきものを考えました。そして、子どもたちとの出会いの日から、どんどん導入していきました。「心マトリクス」「漢字けテぶれ」「生活けテぶれ」「あのね日記」などなど…。
前向きな姿で溢れると思っていた教室がGW前になると、どこか疲弊しているように見える子どもたち。「慣れないことが多すぎるよ…」といった悲痛な叫びのようなものが、聞こえた気がしました。
このままでは…と思いGW明けからは、導入したものを定着させるために継続に重きを置いて、指導していきました。その結果、子どもたちはスキルとして慣れていき、少しずつ身につけていきました。
導入したものを継続する(強化する)ことにより「余白が生まれ、子どもの創意工夫が生まれやすい」という良さがあることに気づきました。
少し具体を交えて話します
①「心マトリクス」…月と星の間に『ノリノリ』 下がりすぎると『ダメダメ』になる。(子どもの発見)
②「漢字けテぶれ」…家庭学習で、自らけテぶれを行う児童がでてきたこと。『丸つけを丁寧にしないと、自分の成長を見逃すから。』こちらの想定を超えてきた瞬間でした。
③「生活けテぶれ」…夏休みの宿題とは別に生活けテぶれをやりたいという児童が25名いました。無意識だったものを意識化することで、自らの行動に変化が出ることが楽しいようです。また、持ち帰らなかった児童も、自己選択ができていて『ゆるさ』を担保できていたように思えます。
このように、「必要な指導」と「ほどよい余白」は、子どもたちの創意工夫を生むものだと実感しました。
空振りその2-こねくりまわしすぎた…-
けテぶれ、QNKSの良さは、共通言語化やプロジェクト化されていることだと考えています。この前提を知らずに「けテぶれをより伝わりやすく」「QNKSを細分化して…」とした結果、サイクルとしては回しやすさは生まれましたが、汎用性に欠くものとなりました。特にけテぶれは、ドラクエの文脈に合わせて説明・図化したことにより、漢字を学習するスキルとして認識しているように思いました。メタファーは、言葉で説明ぐらいで押さえておく方がいいのかな…?
2学期は、「けテぶれ=できるを増やす」「QNKS=考えること」というそのものの良さを、改めて子どもたちが理解できるよう学習に位置付けていく予定です。
空振りその3-アツ(圧)が強すぎた…-
今年度、「ゆるアツ」を大切に学級経営を行っていこうと意気込んでいました。(挿入:ゆるアツについて個人的な解釈)
しかし、子どもたちの前に立つと、良いと思った実践を子どもたちにおしつけてしまっている自分がいました。以前noteに「導入する実践は教師が良いと思っているもの。子どもの心に刺さる導入、継続をする必要がある」のような文章を書いていましたが、自分が実行できていませんでした…。
やはり、「ゆる」と「アツ」のバランスの成果は、子どもたちの姿で返ってきます。特に「アツ(圧)」が強いと、子どもたちは抜け道を探そうとしたり、窮屈ゆえに反発的な行動(直接的でないものを含む)を取ったりしました。今年度は、この時点で気づくことができたことが幸いでした。
その結果、意識的に「アツ(圧)」を減らし、「ゆる」の中に「アツ(熱)」を含め、子どもたちと笑顔で接し、励まし背中を押すような空間づくりを意識し続けることができました。
2学期は、「より子どもたちが気持ちよく過ごせる空間」を作れるよう、提案カードやクラス会議、学級アンケートを取り入れていこうと思っています。
思考と試行と志向こそ至高
では、まとめに入ります。1学期に行った実践は、子どもたちの姿を通してたくさんのフィードバックを受けることができました。
① 心地よいクラスは、ほどよい余白から生まれる
② どんなに優れた実践も、その本質を見極める必要がある
③ 教師の理想は、押し付けるものではなく、語るもの
簡単に3つにまとめてみました。これらを感じることができたのは、志向の上に試行と思考があったからです。このような姿は、まさに至高と言えるなぁと思います。(なんかすみません。言いたくなりました。)
2学期は、子どもたちの試行と思考と志向を引き出せるよう、ゆるアツをより意識し、実践をこねくり回さず、余白を持って、取り組んでいきたいと思います。
最後に…
けテぶれFestaでポスターセッションをされる皆様、すでに頑張って準備されていると思いますので、発表そのものや出会いを楽しんできてください。そして、ぜひどこかで発表をお聞かせください。笑
