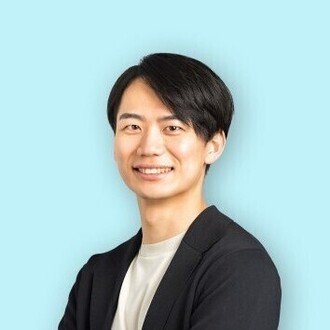創業者のセカンダリー売却とFuck you money
Fuck you money
Fuck you money(略してFYM)という言葉を耳にしたことがあるだろうか。
「クソ上司に耐えられなくなったら辞められるための資金」という意味らしい(私も最近ある人に教わって知った)。経済的独立 (Financial Independence) に近い概念だが、より柔軟に「当面困らない程度の資金」という意味で用いられる。スタートアップの創業者にとっても実はこの概念は重要なのではないかと思った。ただ創業者の場合、自分のビジョンで会社を立ち上げ、経営に深くコミットしているため、単純に「辞める」という選択肢は現実的ではない。
ここでは辞めるという意味ではなく、「経営判断において外部からの不当な圧力や短期的な資金ニーズに振り回されず、創業者自身が自社のビジョンに沿った意思決定を維持できる状態」という解釈をしてみたい。つまり、創業者にとってのFYMとは単なる「辞めるための資金」ではなく、戦略的な自己防衛手段であり、精神的・経済的な余裕を確保することで、企業の長期成長を支えるための基盤となるものである。
近年、スタートアップのIPOまでの期間が長期化する中、セカンダリー売却により一部の持分を流動化するケースが増加している。しかし、現状では創業者が持分を売却する事例はまだ少なく、VCの間でも創業者が先にキャッシュを得ることは忌避される傾向にあるように感じる。しかし、創業者が経済的に安定した状態、すなわちFYM状態にあることは、短期的な資金調達に振り回されず、真に大胆なビジョン実現に専念できる環境を整えられる点で、VCや投資家にとっても大きなメリットであり、創業者によるセカンダリー売却はもっと増えるべきだと考える。
IPOまでの長期化とセカンダリー売却の重要性
近年、創業からIPOまでの期間はかつてないほど長くなっている。実際、米国のテックスタートアップでは平均7〜10年、日本ではさらに長期化するケースも散見される。この長い期間において、起業家は自社の成長と同時に自身や家族の生活基盤を維持しなければならず、経済的なプレッシャーは非常に大きい。
このような状況下で、セカンダリー売却は単なるエグジット手法ではなく、起業家が早期に経済的基盤を固め、FYM状態に近づくための重要な戦略ツールとなる。たとえば、創業者が保有株式の一部を市場に売却することで得た流動性により、外部からの短期的な利益要求や不当な圧力に左右されることなく、長期的なビジョンに沿った経営判断が可能になる。
資金のゆとりが支える経営のエネルギー
どれほど情熱を注いでも、家族を養いながら生活費や将来の不安に頭を悩ませる状況では、精神的な余裕を失い、経営判断が短絡的になりかねない。セカンダリー売却によって現金が確保されれば、家族の生活資金や将来の備えが整い、経済的な不安から解放される。結果として、起業家は冷静に事業に専念できるようになるだろう。
また、同一事業に5年以上取り組むと、どうしても「飽き」やモチベーションの低下が生じる。実際、直近でExitを果たした知人の起業家や他の事業を手がけた経営者からは、「同じことばかり続けると情熱が薄れ、疲弊する」といった声が聞かれる。ここで一定規模の現金化が実現すれば、新たな視点で事業を見直すきっかけとなり、再び情熱を燃やす「燃料」として機能する。これは、精神的余裕がもたらすプラスの効果であり、長期戦における起業家の持続可能なモチベーション維持に直結する。実際に創業してから5年以上経っていた知人の起業家は、傍から見て少し息切れしているように見えていたが、セカンダリーにより数千万円規模の現金を確保した結果、リモチベーションが回復したのか、新たな事業投資を積極的にやるようになったと感じる。
さらに、VC側の視点からも、創業者がキャッシュ不足に陥り、早期の小規模M&Aオファーで利益確定に走るリスクが軽減される点は大きなメリットである。創業者が経済的な不安から解放され、真に長期的なビジョンに基づいて事業に専念できる環境は、結果として企業価値のさらなる向上につながる。これは、VCと起業家双方にとってwin-winの関係を築くための重要な要素である。
VC目線でのセカンダリー売却のガイドライン
セカンダリー売却には多くのメリットがある一方、注意すべき点も多い。以下に、VCの視点も踏まえた基本的な考え方と注意点を示す。
タイミングの目安:例えば、設立後5〜7年目、または企業評価が数十億円規模に達したタイミング(SaaSの場合、ARRが5〜10億円規模に達するフェーズなど)が目安となる。IPOまでの長い期間に備えて、早期に流動性を確保することが肝要である。
シグナリングリスクへの配慮:創業者が自ら低いバリュエーションで流動性を求めると、「企業価値の大幅な伸びを狙っていない」と市場に受け取られるリスクがある。たとえば、10億円のバリュエーションで株式を売却した場合、1,000億円以上の成長を期待する投資家からは、企業の将来性に疑念を抱かれる可能性がある。そこで、創業者としては、無理に売却条件を主張するのではなく、まずはVC側からのオファーを待ち、その提示内容を慎重に検討することが望ましい。
売却割合は極力抑える:売却する株式の割合は、総保有株式の数パーセント程度に留めることが望ましい。過度な売却は、「全力で事業に取り組んでいない」というシグナルとなり、企業価値向上へのコミットメントに疑念を抱かせる可能性がある。
無理に売却を進めるべきではない:セカンダリー売却は自然な流れの中で実施されるべきであり、創業者が焦って「早く売らなければ」とするのは逆効果である。周囲からのオファーを受け入れる形で、自然発生的に進むことが理想である。
ホットな資金調達ラウンドの場合の注意:多くのVCが出資をしたがるような過熱したディールでは、VCが自らの規律を緩めてセカンダリーに多額の資金を投入するケースもある。しかし、その場合でも売却金額が過大にならないよう慎重に進める必要がある。過大な売却は、後続の投資家から不信感を招く恐れがある。
常に会社の利益を最優先に:セカンダリー売却はあくまで流動性確保の手段であり、本来の目的は事業成長や企業ビジョンの実現に専念することである。売却が主目的となってはならず、常に会社の将来や経営戦略を最優先に考慮すべきである。
まとめ
ガイドラインと銘打ったものの、セカンダリー売却に関する正解は一律には存在しない。各企業の事情、創業者個々のライフステージを考える必要があるし、さらには株主をはじめとするステークホルダー全体の合意が不可欠である。セカンダリー売却は単なる短期的な現金化イベントではなく、長期的な経営戦略の一環として、そのタイミングや規模を慎重に見極める必要がある。最終的に、創業者がFYM状態を実現し、経済的・精神的余裕を手にすることが、企業の持続的成長とVC・投資家双方にとってwin-winの関係を築くための鍵となるのではないかと思う。
P.S.
個人的にも創業者のセカンダリー売却はもっと増えたほうが良いと思う出来事がいくつかあってこのnoteを書いていたところ、ANRIの中路さんが同様のnoteを投稿されて完全にタイミングが被ってしまった。
世に出すべきか迷ったものの、ご了承を得た上で、供養の意味でもこの記事を出させてもらうことにした。優しい中路さんに感謝。ぜひ☝️のnoteも読んでください!

いいなと思ったら応援しよう!