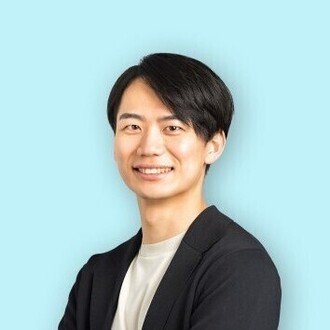規制改革を動かすナラティブ:Uberの日米比較に学ぶ戦略
2024年の規制改革の進展を見ていると、ライドシェアなどの分野では活発な議論があった一方で、全体としては規制緩和が思ったよりも進んでいないように感じる。この背景には、時の政局や一時的なトレンドの影響もあると思うが、根本的な足りていないピースがあるのではないかと思った。それはルールや既存の枠組みを動かすに足るナラティブだ。
ナラティブとは?
ナラティブという単語自体はここ数年でビジネスシーンにおいて使われるようになったが、改めてその意味を聞かれてみるとパッと答えるのが難しい。Perplexityに聞いてみると、わりとしっくり来る以下の答えが返ってきた。
ストーリーには通常、起承転結のような明確な構造があり、作り込まれたシナリオに沿って物語が進行します。対してナラティブは、終わりのない継続的な物語であり、語り手によって常に変化し続けます。
要するにナラティブの場合は、語り手(=主語)次第でその解釈や語り口も変わるものであり、物語の受け手へのメッセージ性がより強いものだと個人的に解釈した。
スタートアップとナラティブの関係性
スタートアップは本質的に、既存の秩序に挑戦し、新たな価値を創造する「アンダードッグ的存在」である。
既存の枠組みが固定されたシナリオだとすれば、スタートアップは自らを、あるいは社会的弱者などの他のステークホルダーを主人公として、社会を変革する物語を紡ぎ出すことをその存在意義としている。ナラティブは、この変革のビジョンを効果的に伝達するための重要な手段の一つだ。
分かりやすい例として、小売業者が自社のオンラインストアを構築できるECサービスを提供するShopifyのナラティブ「Amazonは帝国を作っていて、Shopifyは反乱軍に武器を与えている」は、eコマース業界におけるShopifyの存在意義を明確に示している。このナラティブは主語である「反乱軍=小規模事業者/起業家」の共感を呼び、Shopifyの急成長を支える重要な要因となった。
米国Uberの成功例:タクシー業界の差別問題を活用したナラティブ
ナラティブを効果的に構築した代表例として、米国のタクシー業界における人種差別問題を自社のストーリーに組み込んだUberの事例が挙げられる。
筆者は2010年代半ばまで米国に住んでいたが、Uber以前の米国では、既存のタクシーサービスの信頼性は低く、特に繁忙時には配車が困難になることが頻繁にあった。さらに有色人種、中でもアフリカ系アメリカ人がタクシーを利用する際に直面する人種差別は深刻だった。
2015年にシカゴで行われた調査では、アフリカ系アメリカ人の66%が、タクシー運転手による意図的な差別を認識していることが分かった。また、48%は、タクシーを呼ぼうとしても無視される可能性が高いと感じていた。
興味深いのは、この問題に対する認識が人種を超えて共有されていたことだ。通常、差別に関する主張では白人とマイノリティの間で認識に大きな隔たりが生じるが、白人回答者の55%が、貧困層やマイノリティのコミュニティではサービスが行き届いていない可能性が高いと答え、47%が黒人客に対するタクシー運転手の意図的な差別に同意している。
筆者が住んでいたワシントンD.C.も地域によって住民の人種が完全に分かれており、シカゴと同様、この問題は社会的不平等の象徴として広く認識されていたと記憶している。
当時の米国各州では、日本の現状と同様に、既存のタクシー業界の抵抗によりライドシェアの合法化が進んでいなかった。しかし、Uberはこの差別問題を自社のナラティブに巧みに組み込むことで、単なる配車サービスとしてではなく、人種に関係なく誰もが簡単に利用できるサービスとして位置づけ、社会的不公平を是正する手段としてアピールした。
日本におけるUberの失敗
Uberは日本にも2014年に進出しているが、米国のような成功は収められていない。これにはいくつかの要因や説明があるが、主に日本社会の法律やコンプライアンスを重視する性質が影響している。
まず、日本では「法律を破ってはいけない」という意識が非常に強い。米国では、罰則金がコンプライアンスのコストより低い場合、自社やユーザー、社会の便益を考えてプラスしかないと確信できるとき、「法を破ることが経営者の責務」とさえ考える風潮がある。しかし、日本ではこのような考え方は受け入れられず、コンプライアンスの軽視は即座に社会的批判の対象となる。
米国でUberは「グレーゾーン」のまま各地でサービスを開始して一気に普及させた。既成事実を作った上で、先述の通り、差別問題のナラティブを構築してロビイングの調整を行うという展開を進めたわけだ。
日本に上陸した際も、グレーゾーンを駆け抜けようとした。2015年2月に福岡で始まった実証実験「みんなのUber」では、運賃を徴収しないため許認可が不要だと考えた。しかし、道路運送法では「有償運送」が定義されており、無償でも結局有償にする可能性が高いと見なされた。これにより、サービスは国交省からの指導を受け、シャットダウンされた。
日本では先にサービスを普及させて既成事実を作るといった米国的な破壊的なやり方ではルールを動かすことはできない。事前に規制当局と対話し、社会にとって必要だというコンセンサスを築くことが重要だと分かる。このためには、ステークホルダーが納得できるナラティブが不可欠だ。
ナラティブにおける主語の選択
誤解を恐れずに言うと、法律やルールというのは普遍的なものではなく、時代や場所によって変わっていく相対的なものだと思っている。個々の人々やグループが対話を通じて納得できるルールをアップデートしていくことが自然だ。そのためには、多くの人々が動かされるナラティブを活用する必要がある。
日本では多くの分野で既得権益が強く、規制や業界団体の抵抗が根強い。一般的に米国以上に規制改革のハードルが高く、グレーゾーンで既成事実を作る戦略は通用しにくいことはUber Japanが証明している。規制を動かすには、粘り強くステークホルダーの支持を得ることが不可欠であり、「誰をナラティブの主語にするか」という問いが重要になる。米国のUberは、アフリカ系アメリカ人という社会的弱者をナラティブの主語に据え、ステークホルダーの賛同を得ることで政治的圧力をかけ、ルールを動かすことに成功した。
Uberの米国での成功、そして日本での失敗には、現状「規制大国」である日本が「ルールメイキング大国」へと進化するための重要な学びがあるのではないかと思う。既存の秩序に挑戦するスタートアップという存在が社会に大きな影響を与えようとすると、自ずとルールメイキングの領域にも染み出すことが今後増えるだろう。
規制領域に挑戦しようとしている起業家がいれば、VCとしてぜひその挑戦にご一緒できたら嬉しい。
参考文献
いいなと思ったら応援しよう!