
#3 最近読んで面白かった本10選
はじめに
年末に書いたNote#2で和Vizを題材に思い出トップ5を作った後、ランキングものを書きたいと思い、試してみました。ここ3年(2022-2024)くらいの間に読んで面白かった書籍を順番に並べました。世間の評判とか、売れ筋とかはガン無視で、自分にとってツボったかどうかの観点だけで書いています。
世の中には素晴らしい書籍やベストセラーは沢山あると思いますが、自分にとってビビッときたってだけ選んでいます。なので、そんな視点もあるのかと生暖かい目で見て頂けると幸いです。というより、半分はこのテイストで記事を書きたかったという単なる創作意欲がモチベーションです。
トップ10
1位 店長はCDO
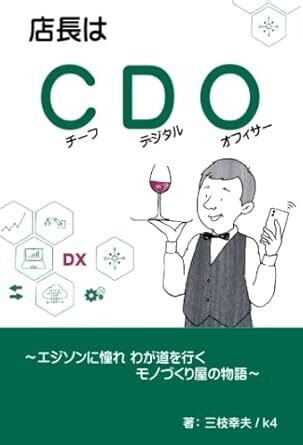
第1位は「店長はCDO」。IT協会主催の研究会で三枝幸夫さんの講演を聞いたのが購入のきっかけ。DXの成功には「Agile+デザイン思考」が重要。という考えが基礎にあり、その基礎に至るまでの実話に基づく変革の物語です。
顧客に距離を近づけるとか、プロセスを理解するとか、なるほどという学びが色々あります。そして、国を跨いだ時に出てくる面倒な人間模様など笑いあり、学びありの一冊です。これを読み終えると、ハードのプロジェクトを任されるのも悪くないなという気分にさせられる一冊です。
ちなみに著者の三枝さんは、国分寺でAoyuzuというイタリアンレストランを経営されており、そのレストランに行くと、書籍に登場するモデルとなった方もいます。私も2度ほどお邪魔しましたが、料理も美味しいし、雰囲気も良いお店です。
2位 ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか -日本版BRP2.0-

第2位は、村田総一郎さんの「ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか」です。これも学びが多い。SAP JAPANのディレクターをされている方だけあって、日本企業内のどったらこったらが一冊に凝縮されている感があります。
ビビった来たワードを1つ取り上げると、以下になります。
情報の価値は、その情報そのものよりもその情報の受け取り手の状況によって圧倒的に左右される。実は、情報そのものには価値はない。
<4つの大事な問い>
①適切な受け手に渡るか?
②受けての行動に有意な影響を与えるか?
③その結果として何かしらの経済的・社会的価値が生まれるか?
④情報が渡るタイミングが適切か?
この4つの問いがすべてYesとならないと、情報の価値はゼロだそうです。
会社の中で、見える化、見える化ってやっているけど、イタタタと思うこと多々あり(笑)
3位 問いのデザイン

第3位は、安斎勇樹さんの「問いのデザイン」。序章で述べられている、
"「認識」と「関係性」の固定化による病い"というフレーズから一気に引き込まれました。日常において、多くの時間を与えられた課題をどう解くのか(How)に全力に注いでしましいがちですが、本来解くべき課題は何だ?そもそも問題ってなんだっけ?と問い直す切り口を知ることができます。この本を下敷きにワークショップを1本作ったりもしたので、課題発見系のワークショップをやる時に読むと良いかもしれません。「足場の問い」とか使いだすと、モヤっていた思考がどんどんクリアになったりもします。
4位 リフレクション 内省の技術

第4位は、熊平美香さんの「リフレクション 内省の技術」です。この本との出会いは"価値観のアップデート"というフレーズでググったのがきっかけでした。そして見つけたサイトから辿り着きました。何を調べてんだと思ってしまうが、その頃、壁にぶち当たっていたかメンタルが落ちていたんでしょう(笑) 人は認知の4点セット「意見」「経験」「感情」「価値観」というメンタルモデルで物事を見ているのですが、環境変化やなにがしかの躓きを経験したとき、従来のメンタルモデルでは物事をうまく処理できない。つまり自分の行動や思考や感情を司る価値観をアップデートしないと"沈む"という感覚が、この本に出会わせてくれました。読んだからと言って、すぐに何かが良くなったわけでないですが、暗闇の中の中であれやこれやと試しながら、気が付くと、開き直って以前より図太いメンタルモデルを手に入れました。 最近好きなアンラーンという言葉も入っていますが、自分を変えるには、これまでの意見、経験、感情、価値観で評価判断することを保留して、そういう考え方もあるんだ?と受け止めることがスタートです。
5位 Give&Take

第5位は、ADAM GRANTさんの「Give&Take」。彼については、YouTubeに上げられているTEDの動画が面白いと思い、何度も見ていました。そして、ある日地元の図書館でこの本を発見したのが、出会いでした。
GiverやTakerという単語はいろんな文脈で語られることがあります。自分のルーツを考えると、Giver的な思想を与えられ、育った気がしています。一方でGiverというのは、結構危険です。なぜなら、Takerに食い物にされたり、燃え尽き型のGiverになって終わっちゃうケースが少なくないからです。
ですが、統計的に分析すると、最も成功するのもGiverです。燃え尽き型のGiverか成功するGiverか?その違いは何なのかが語られています。
自己犠牲型のGiverと他者志向型のGiverという2つがありますが、シンプルに言うと、お互いの利益に貢献できるGiverが成功するってものです。
この本も好きだったので、調子乗って社内LTで引用しました(笑)
6位 右脳思考

第6位は、内田一成さんの「右脳思考」。この本も会社で他部門からデータドリブンの先駆者みたいな扱いで、講演頼まれた時に引用しました(笑)
端的に言うと、データドリブンと言っても、KKDを否定しちゃいかん!ってことです。何かを動かしたいときは「①右脳-②左脳-③右脳」で伝える!
①右脳=KKD
②左脳=論理+データ
③右脳=情熱
みたいな順番で考えないと、動ける範囲は狭くなるし、人の心を動かすことはできないってのが骨です。若干、自分のフィルターで歪んでいるかも(笑)
なぜなら、データが捉えられるのは世界の一部でしかない。すべてをデータに頼ると、動ける範囲がとても狭く、そして初動に時間がかかる。KKD(勘・経験・度胸)には人間の英知が詰まっている(間違っていることもあるけど)。
だから、閃きは右脳(=KKD)に頼り、その正しさを左脳(データと論理)で証明し、最後は右脳(情熱)で訴えかける。
7位 新時代を生き抜く越境思考

第7位は、沢渡あまねさんの「越境思考」です。2024年11月のDATA Saber Conferenceに参加した後、どうも越境という言葉が頭に残り、越境て何だ?と思い、ポチった本です。自分自身について言うと、既に2018年あたりから越境モードで活動してきたから、改めて新鮮という感覚はしなかった。学びが少ないとかではなく、自分の中で越境が常態化しているという意味です。だから、特徴的な部分を抽出することが難しいのだが、VUCAの時代には、必要不可欠な行動様式です。
越境、越権、隣の芝生に足を踏み入れ、オーダされた仕事の裏側にある背景や人の価値観を覗き見たり、メタレベルで合意形成したり、ビジネス変革をリードするには越境は絶対必要。越境モードにギアを入れると、嫌がられることもあるかもしれないけど、力強く味方になってくれる人も現れるはず。
いろんな越境テクニックは書かれていたが、特に嵌ったワードは以下です。
・「~だからできない」これは悪魔の言葉
小さいからできない
地方だからできない
・「~だからこそやれる」これは魔法の言葉
小さいからこそ短期間でできた
地方だからこそ注目される
8位 V字回復の経営

第8位は、三枝 匡さんの「V字回復の経営」。弊社の幹部が勧めていたって理由で手にした本。経営者が好きそうな内容なだけあって、学びも多い。
大企業あるあるですが、組織が機能別に分かれ、それぞれが部分で行動して、一見うまくいっているよう見えるが、全体を俯瞰して見るとダメダメで、最終的なアウトカムに責任感の欠片もない企業風土になった会社をV字回復させるお話です。
3日間の合宿で、会社の問題点を付箋に張りまくって、分析し、方向づけしていく。誰かがやってくれるではなく、自分自身が当事者意識をもって会社を変えていく胸熱の物語です。こういう視点で見ると、少なからず、よくない空気が身近な所にもあるので、ちょっと真似したくなる内容でもある。
9位 組織にいながら、自由に働く。

第9位は、仲山進也さんの「組織にいながら自由に働く」です。
働き方を4ステージで分類しているのが、非常に学びのある考え方でした。
ステージ1 +加
・できることを増やす、苦手なことをやる、量稽古
・仕事の報酬は「仕事」
ステージ2 -減
・好みでない作業を減らして、強みに集中する
・仕事の報酬は「強み」
ステージ3 ×乗
・磨き上げた強みに、別の強みを掛け合わせる
・仕事の報酬は「仲間」
ステージ4 ÷徐
・(因数分解して)一つの仕事をしていると複数の仕事が同時に進む
・仕事の報酬は「自由」
キーとなるページをそのまま書いちゃいましたが、その通りという感じ。
ちなみに私はステージ4に瞬間的に入ることがある。ステージ3あたりだと、強みがバリューネットワークを作り出すので、別分野のステージ1をやりづらくなる。なので、環境変化の中で自分が劣化しないようにアンラーンして時間を作って、新しい領域に自分を放り込むことを大事にしている。
10位 最後はなぜかうまくいくイタリア人
第10位は、宮嶋勲さんの「最後はなぜかうまくいくイタリア人」。これも、図書館でタイトルを見たとき、ビビっときた一冊です。普段はつい小難しいビジネス書を手にしがちですが、段々と脳が疲れ、たまに緩い書籍を読みたくなります。「店長はCDO」も小説風でかなりゆるいですが、入りと出は、ゆる系で締めたいと思います。
この本の魅力はイタリアの文化を違う視点から捉えている事です。時間に縛られてあくせくしなくていい。その場、その場を楽しむことを大事にする。全体の調和の中で、ズレることや、何に価値観を置くかが共有されていればOKとする。日本社会は完璧であることが目的化されがちだが、結局幸せとは何か?コネを使ってネットー枠を広げていくことは大事。
と、イタリア文化をちょびっと垣間見れる一冊です。学びはというと、全体の系を見ずに、部分だけを捉えて、自分の価値観や提案を当てはめようとしても、うまくいかない。それより人生楽しもう!

さいごに
最後まで読んで頂きありがとうございます。この3年(2022-2024)、読んだ本の中で気に入ったもの?あるいは自分の行動に影響を及ぼした本をレビュー付きランキング形式でピックアップしてみました。
やってみた感想は、自分自身の頭の中を整理できますね。自分がなぜその本を手にしたか、何に共感したか、その後どんな行動をしたか。楽しいので、3年と言わず毎年振り返り的にやってもいいかな。
