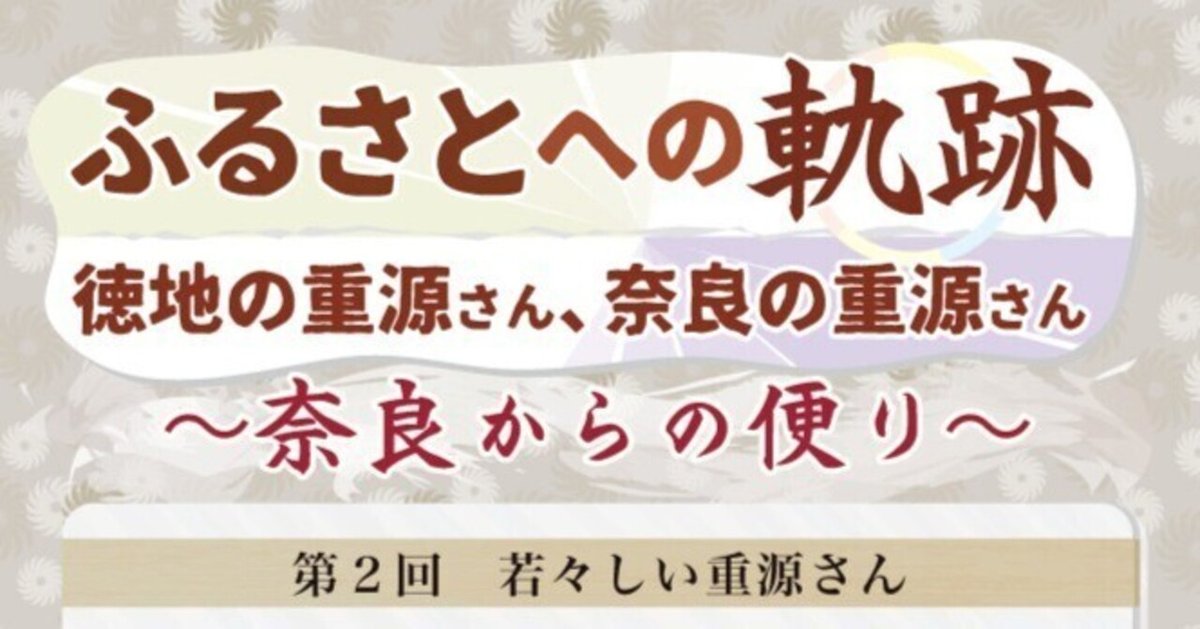
徳地の重源さん、奈良の重源さん(第2回 若々しい重源さん)

ふるさとへの軌跡 徳地の重源さん、奈良の重源さん 〜奈良からの便り〜文筆家 倉橋みどりさんによる寄稿記事です。
東大寺再建を成し遂げた俊乗房重源上人の足取りを奈良と徳地の二つの地から紐解きます。

奈良国立博物館では、「大勧進 重源」展が2006年に、「頼朝と重源」展が2012年に開催された。展覧会の目玉は「俊乗房重源上人坐像」(国宝)。少し前かがみで数珠を繰っておられる。一般的に、重源さんといえばこの姿を思い浮かべる人が多いと思う。私もそうだった。2019年2月、里帰りに合わせ、徳地にある重源さんゆかりの地を巡った。佐波川沿いに車で走っていると、いきなり「重源上人像」が現れた。没後800年忌に造られたという。あれ、この重源さんは若々しい。東大寺再建の大役を任されたのが61歳、その数年後の姿のはずだが、筏に乗り、背筋を伸ばし、前を見つめる姿はたくましく、頼りがいがある。佐波川には重源さんにまつわる史跡や伝説が多く、川の名前からしてそうだ。東大寺再建に使う材木を採るため、多くの人々がこの川の上流の奥地で汗を流していた。奈良から来た人もいて、「故郷を離れて一度も魚を食べていない」とこぼすので、重源さんが木片に「鯖」と書き、祈祷した上で池に投げ込むと鯖に変わった。同じように川に投げてもやっぱり鯖に変わったので、「さばがわ」と呼ぶようになったというのだ。甘柿渋柿の話も面白い。徳地の重源さんは、まるで神様仏様のように不思議な力を持つ存在として語り継がれている。奈良ではそんな言い伝えを聞いたことはなかった。 (執筆:倉橋 みどり氏)
