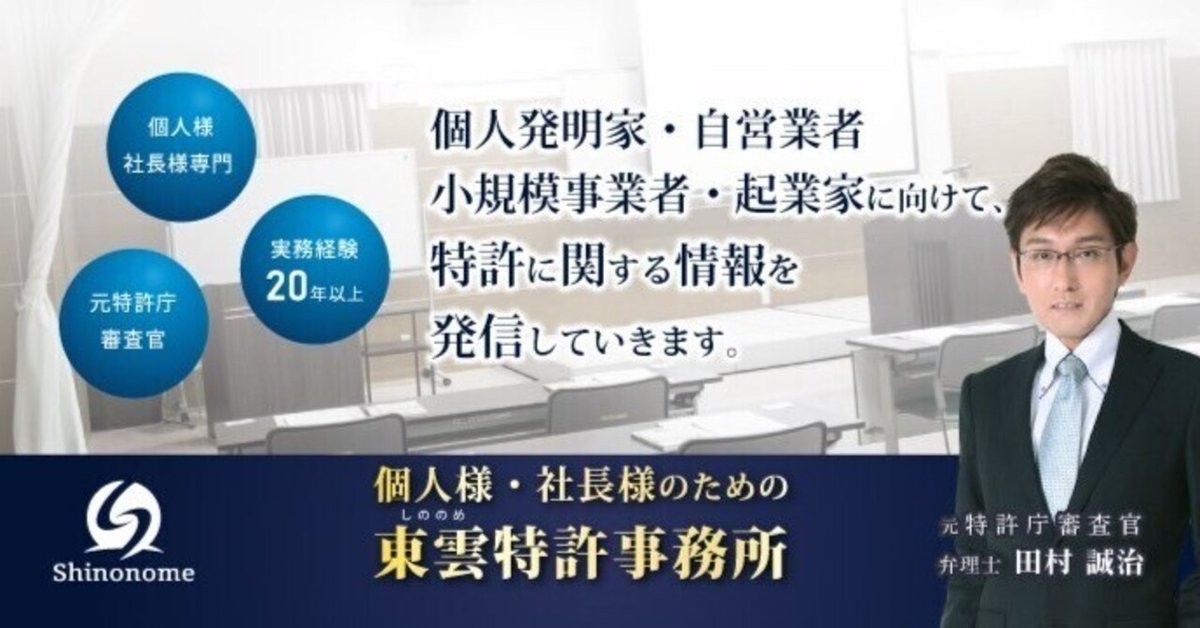
特許法第36条の拒絶理由は審査官のアドバイス!【リライト版】
(Q)特許を出願し審査を受けたところ、拒絶理由通知が届きました。
特許法第36条を理由に、特許が拒絶されるということです。
これはどういうことでしょうか?
(A)特許法第36条の拒絶理由は、審査官からのアドバイスです。
審査官の意図を把握して、適切に対応しましょう。
■特許法第36条の拒絶理由=不備を解消してくださいというアドバイス
特許法第36条が指摘されるのは、主に次の2つの場合です。
・特許請求の範囲の請求項の記載が不明りょうである。
・書類に開示した内容よりも、特許を求める内容の方が広い。
一言で言えば、出願書類の記載に、不備があるということです。
別の言い方をすれば、審査官のアドバイスです。
✔特許になる前に記載不備を解消しておいた方がいいですよ!
ですので、審査官の指摘に従って対応しましょう。
(審査官からの指摘が明らかに誤解でない限り)
■発明を正確に表現できていますか?
最もよくないのは、36条の指摘に感情的になってしまうことです。
「出願書類の記載不備?審査官はわたしの発明を理解してくれない!」
あなたの発明は、あなたの頭の中では当然に明確です。
しかし、書類上では、発明を正確に表現できていないかも知れません。
そうすると、出願書類は明確ではないとされる場合もあります。
■記載不備のまま特許になると・・・
また、こういう考え方もあります。
本当は記載不備があるのに、審査官から指摘されないとしましょう。
そのまま特許になったとしましょう。それで本当にいいでしょうか?
記載不備を残したままの特許は、無用な争いになるおそれがあります。
その争いの時点では、書類の記載不備を解消できないかも知れません。
最終的には、次のようなおそれがあります。
✔特許が無効とされる
✔きわめて限定的な権利になる
✔特許権を行使できなくなる
■審査官はあなたの発明をきちんと理解しています
36条の指摘は、
✔出願書類の記載不備を事前に解消することができる
✔あなたの特許を適切なものにすることができる
よい機会なのです。
ちなみに、審査官が発明を理解してくれないということはありません。
審査官が発明を理解できないとしたら、36条の指摘もできません。
このことは例えば、学校の授業と同じです。
✔わからないところがわかる子→先生に質問できます
✔授業がまったく理解できない子→質問すらできません
審査官は、あなたの発明をきちんと理解してくれます。
その上で、記載不備があればそれを指摘してくれるのです。
「拒絶理由」という言葉の響きはよくないですね。
ただ、指摘してくれた審査官に、感謝してもいいくらいなのです。
■拒絶理由を否定的に考えるべきでない
いかがでしたでしょうか。
36条の拒絶理由通知に対して、否定的に考えるべきではありません。
このことがご理解頂けたと思います。
実は、36条よりも指摘されることの多い拒絶理由があります。
特許法第29条第2項(いわゆる発明の進歩性)です。
これについても、36条と同様の考え方をすることができます。
この点については、別の記事で述べたいと思います。
<元記事>
【Q&A】特許法第36条の拒絶理由を指摘されたのですが →審査官のアドバイスです(2015年07月06日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/88734837.html
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************
