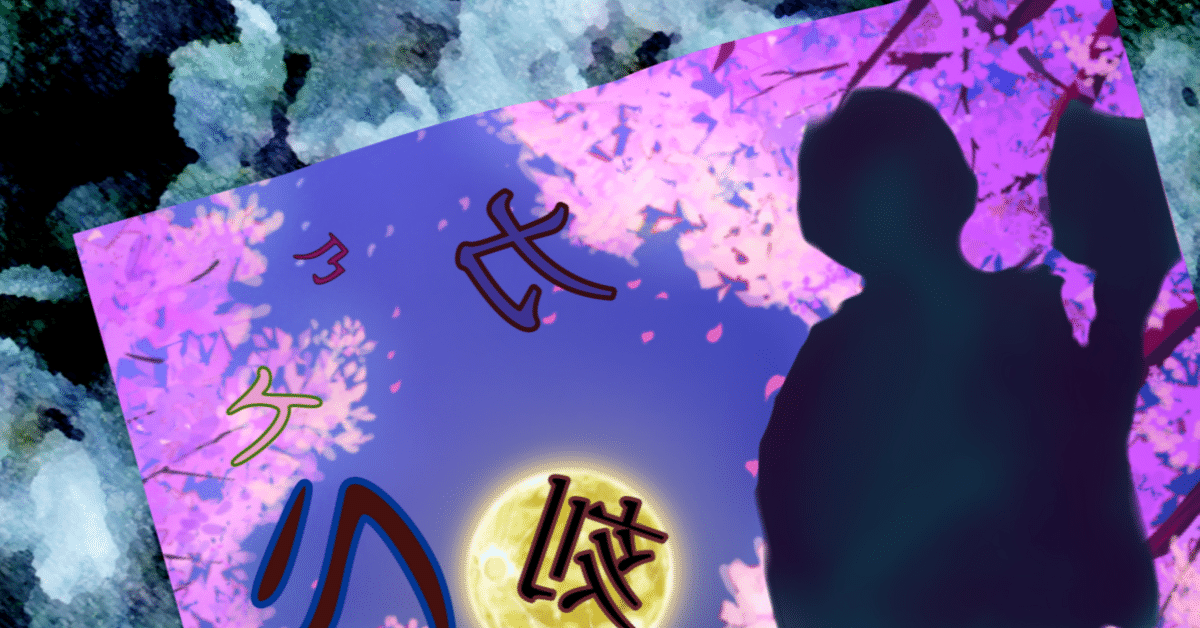
刻乃カケラ
その日は帰りが遅くなった。帰りの電車でついウトウトしてしまい、降りる駅を乗り過ごしてしまったのだ。
眠い。人間生活って大変だよ、ホント。
春乃舞は、花びらの妖精だ。
七月七日の夜空から落ちてきた流れ星。そこにあった一枚の花びらが人の姿になったのだ。
それからまぁ色々あったのだけれど、人間社会で、大変ながらに楽しく暮らしている。
「とはいえ……ふわぁ~」
普通のご飯じゃ、妖精の力の栄養にはならないのだろうか。今日も一日欠伸がとまらない。最寄駅から、重たい身体を引きずるようにして歩く。帰ったら、とりあえずちょっと寝ようかなぁ。
と、視界の端に、街灯に照らされた何かが鈍く光った。
「……時計?」
近くまで歩みよれば、それは時計だった。鈍い色の懐中時計。普段の生活であまり見ることのないものだ。
誰か落としたのかな? 芝居の小道具などでなければ、アンティーク品や誰かの形見といった、大切なものかもしれない。交番に届けた方がいいかな。
そう思って、拾い上げる。見た目よりも軽く感じる。傷やヒビも見えるそれは、ひょっとしたら部品が欠けているせいで軽いのかもしれない。
「……え、これって」
そこに。手の中の懐中時計に、ふっと何かが見えた。時計のヒビから滲み出し、夜の中へと溶け込み消える。
……これ、記憶?
「え、ちょ、ちょっと待って!」
慌てて時計を両手で包む。それでも指の隙間から、誰かの記憶がすり抜け消えていく。時計、本、手帳、手紙、友、心、花、色。それらの記憶が消えていく。
「いや、まってってば!」
それはほとんど無意識に、両手の平からあふれて、壊れた懐中時計を包み込んだ。
これって……私と、おんなじ?
自分が花びらから生まれたように。
妖精の力が懐中時計を包み込み、それは徐々に人の姿を形どり。
「……えっと……大丈夫ですか?」
手の平から離れて、街灯の下に立ち尽くすその人に恐る恐る声をかける。自分でしたこととはいえ、初めてのことなので戸惑いが先行して、どうしていいかよく分からない。
「あ、ええ、私は大丈夫です」
「あ、そうですか。よかった」
生気のない瞳に見つめられ、どう考えても大丈夫そうには見えなかったけれど、本人が大丈夫と言っているのだから……まぁ、いいか。
「あのー……」
「え? あ、はいはい?」
「私、何してるんでしょうか?」
「……さあ、ちょっと分かんないです」
嘘ではない。分からないものは仕方ない。
「えっと、私は春乃舞っていう名前なんだけど、あなたは?」
「なまえ……名前?」
そう首を傾げるのを見て、そういえば先程消えていった記憶の中に、名前があったことに思い当たる。ただ一瞬で、一文字しか確認できなかった。
「こく……とき? 刻って、覚えてたりしないかな?」
「いえ……でも、刻って私のことなんですね」
その時、夜の中から染み出すように、記憶の欠片が落ちてきて、それは名も無きその人の手の中の、壊れた懐中時計に染み込んで。
「欠片……私の、カケラ」
「ときの、かけら?」
口からこぼれた言葉に、生気のない瞳がわずかに輝いた。
「そうですね。きっと私は、刻乃カケラなんでしょう」
「……違うんじゃないかな」
壊れているはずの懐中時計から、カチリと、針の進む音が聞こえた気がした。
