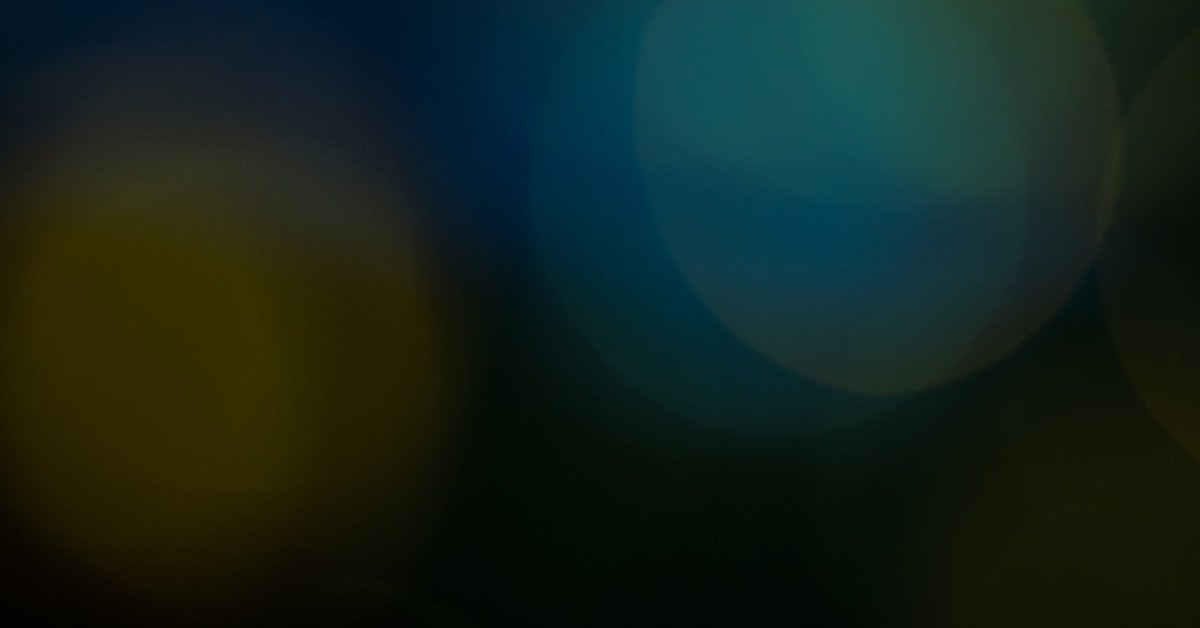
「新月色を撮りに行く」
谷水春声さんには「月の見えない夜だった」で始まり、「そう小さく呟いた」で終わる物語を書いて欲しいです。できれば7ツイート(980字程度)でお願いします。
#書き出しと終わり
https://shindanmaker.com/801664
月の見えない夜だった。
わざわざ新月の日を選んだ甲斐があった。この闇は私によく似合っている。
誰に咎められる訳でもないのに玄関の扉をそっと開けて、街の電灯から逃れるように公園へと走る。ジャージのポケットには、部長に渡されたデジタルカメラが入っている。走り方がぎくしゃくしてしまう。
もう写真部に転部したというのに、体を動かしておかなければならない強迫観念がどこかにあって、今でも定期的に走りこんでいる。
遊具は滑り台と鉄棒が二つだけ、ボール投げ禁止と看板の立っている、目的を見失った公園だ。
到着するまで部活のことを考えていたせいで異変に気が付かなかった。
新月の暗さではない。
街灯に明かりがないのだ。
息を整えながら辺りを見回すと、道を挟んだ民家にも光がなかった。一軒だけではない。隣もその隣も、数軒先まで見渡す限り真っ暗だ。
思わず笑いだしそうになってしまった。
遂に夢が叶ったのかと思ったのだ。
私以外の人間が消え去ったのかと。
或いはこの世から光が失われて、二度と誰かに顔を見られずに済むのかと。
勿論そんなことは起こるはずがない。この時代には珍しく、公園の辺り一帯が停電しただけで、二時間後には復旧したのだと翌日には知るが。
その時は、何か人智を超えた力によって救われたのだと思った。
だから。
低い唸り声が近くで響いたのも現実感がまるでなかった。振り向いて、その塊をじっと見据えて、大きな黒い犬が座っているのだと気付いた。
動物に敵意がないのだと伝えるには、目を逸らしたほうが良いのだったか。
途端、肌が粟立つ。
例えば目の前にいるのが血に飢えた野犬で、なす術もなく喉を食い千切られるのだとしたら。
憎んでいた元の部活の人間関係や、愛のない家族、自分の容姿に何のけりもつけられないまま終わってしまうのだとしたら。
嫌だ。
せめて部長に何か言葉を掛けて貰ってからがいい。
ここで頭に浮かんだのが、言葉を交わすようになってから日の浅い同級生だったことに苦笑する。
これまでどれだけ多くの人間関係を破綻させてきたのかと。
世界に誰もいなくなったと一旦は勘違いをして見せたが、そんな空想に乗り切れるほど、自分も子供ではなくなった。
私はカメラを取り出して、犬に向かって構えた。映るのは暗闇で、イメージ通りのものだと確認する。
「生き延びられたら、この写真を部長に渡せますように」
私は縋るようにそう小さく呟いた。
(980字)
(拙著『新月色、セーフライト、』の導入部分のようになりました)
