
オピオイドのいま~主人公は誰だ
先日行われた講演内容について、スライドをシェアします。医療者向けです。一部有料(マガジン購読者は無料)です。
僕としては珍しく、疼痛緩和をテーマに講演依頼を受けました。
僕自身、緩和ケア医ではありますが専門とするところはどちらかと言えば「社会的苦痛」や「スピリチュアルペイン」に関連するところや緩和ケアシステム論であって、これまでの講演依頼もAdvance Care Planningや早期緩和ケア、社会的処方などが多かったのです。
疼痛緩和については、僕よりも話が上手な専門家が何人もいらっしゃり、まあ僕の出番は無いかなと思っていたのですが、ある製薬企業さんの方々と「オピオイドをドラ〇エに例えたら」みたいなノリで話していたら「ぜひその話を講演にしてくれませんか」と依頼を受けたのでした。
まあ、そんなノリで受けた依頼でしたし、Webセミナーということでしたから、せいぜい50人くらいを相手にした講演だろう、と思っていました。
しかし当日、配信会場で担当の方に
「ところで、今日は何人くらいの方がご視聴しているのですか?」
と尋ねたところ
「そうですね、1000人を超えるくらいです」
「なん・・・だと・・・」
背中に冷や汗が流れる。
いやいや、きっと勉強熱心な看護師さんとか薬剤師さんとかが大半に違いない。こういうテーマは看護師さんたちも興味あるしな!
「えーと、医師が7割を超えています」
「なん・・・だと・・・」
画面の向こうに700名超の医師。もしかしたら、僕よりも高名で経験のある緩和ケアの先生方もずらり?
「素人質問で恐縮ですがああああ」
とか来たら爆死する自信ある。
ということで、僕の軽いノリから始まった講演企画は、緊張で青ざめた僕の顔が大写しになるところから始まったのでした(恥ずかしいのでマスク着用でお願いしました)。

では、講演パートを始めていきます。もちろん、ここで書いている内容は講演で話した内容そのままではないですし、スライドも一部変更しています(逆に言えば製薬協のプロモーションコードに引っかかって講演で使えなかった部分が原本のままになっています)。

まず、緩和ケアが受けられることは患者の「基本的人権(Access to palliative care is a human right.)」であることを宣言したプラハ憲章をご紹介します。これは2013年のヨーロッパ緩和ケア学会(EAPC)で採択されたものです。
「EAPCは,発展途上国か先進国かにかかわらず,すべての世界各国の政府に対し,病院であれ,自宅であれ,そしてその他の場所であれ,必要なところで患者中心の緩和ケアを受けられるための健康政策と社会保障政策の確立,および人々を苦悩から解放する施策の実行を促す」ことがうたわれ,参加者に賛同の署名を要請した。そうして政治的な実行責任を問うものとして各国政府に向けて発信された4つの中心的課題は,以下のとおりである。
[4つの中心的課題]
1)致死的な疾患あるいは終末期の患者の必要性に応える医療政策を策定する
2)必要とするすべての人に,規制医薬品を含む必須医薬品が使用できるように保証する
3)医療従事者が大学の学部以上のレベルで,緩和ケアと痛みのマネジメントに関する適切な研修を確実に受けられるようにする
4)緩和ケアを医療制度のあらゆるレベルに確実に組み入れる
医学界新聞「人権としての緩和ケア:ヨーロッパ緩和ケア学会第13回大会報告(加藤恒夫)」より引用

この、Lancetに掲載された図では、想定されるオピオイド必要量に対しどの程度の量が使用されているかを表現した図です。オピオイドが不足している国は細く、過剰な国は太っているように表現されていますね。
これを見て分かるように、アジア圏およびアフリカなどにおいては未だ、苦痛緩和に十分なオピオイドが供給されていないのが現状です。一方で北米やヨーロッパは必要量以上にオピオイドが使用されていることで、むしろ濫用が問題となっています。
例えば、ベトナムではオピオイド処方は10日間までに制限され、本人にし対してしか処方できないというルールがある一方で訪問診療は充実していないため、終末期になって本人が通院できなくなった場合はオピオイドが届かない、ということになります。また、10年前までは都心部にあるがんセンターでしかオピオイドを処方できなかったので、何十㎞も遠方の患者さんだとしても、ホーチミンまで来るしか方法はなかったのだそう。
もともとフランスの植民地として、麻薬を生産する拠点とされてきた歴史的背景もあり、ベトナムの市民および医師・薬剤師でも、オピオイドへの忌避感が強いことも特徴です。仮に、医師がオピオイドの処方箋を書いたとしても、薬局で拒否される事例などもあると伺いました。
現在では北米から医師が派遣され、現地の教育や啓発にあたってきたことで、医療者の偏見もおさまってきているようですし、処方も各県レベルでできるようになって、改善はしているそうですが、まだまだ不十分であるとのことでした。
一方で北米においては20年以上も前から、オピオイドの過剰使用が蔓延していたとされ、「抜歯後の鎮痛にオキシコドン」が日常であり、がん性疼痛のみならず、非がん性の急性・慢性疼痛に対してもオピオイドを濫用してきたのだそうです。その結果、依存症の発症やオピオイドによる死亡事故も多数発生してきました。あるとき、米国から講演に来る緩和ケア医師が「オピオイド蔓延は国内病。日本はまだこの病に侵されていない。我が国の轍をふまないことを願う」と述べていたことが印象的でした。
変更になった「痛みの定義」や「がん疼痛治療5原則」
2020年、国際疼痛学会は1979年以来41年ぶりに「痛みの定義」を変更しました。
具体的には、
(改定前)
実際に何らかの組織損傷が起こったとき、あるいは組織損傷が起こりそうなとき、あるいはそのような損傷の際に表現される不快な感覚体験であり、情動体験である
であったのを、
(改定後)
痛みは実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た感覚かつ情動の不快な体験
と変更になりました。つまり、疼痛に組織損傷が伴わない場合もあることが明記され、より複雑な疼痛への対応が期待されるようになったということです。
また、僕ら世代が慣れ親しんだ「WHOがん疼痛治療5原則」も変更になりました。

上記のような5原則から、3番目の「by the ladder」が抜け、4原則となりました。これは、1段階目のNSAIDsから順番に3段階目の強オピオイドまで増やしていきましょう、という内容から「痛みの程度によって最初から強オピオイドも使おうよ」とのメッセージかと思います。緩和ケアの専門家なら、強オピオイドに抵抗感は無いと思いますし、また実際の臨床でも「最初から強オピオイド」は普段から行っていたかと思いますが、一部ではトラマドール(弱オピオイド)がダラダラと使用される例も散見されますので。

では、今日のテーマ「主人公は誰だ」について見ていきましょう。これは、つまり「自分の軸となる薬をひとつ決めて、他の薬剤はその特徴に応じて使い分けていきましょう」というメッセージです。ドラ〇エで言えば、誰をパーティーメンバーにするのか、とかまあそういう話です(ちなみにジョブの分け方は完全なる個人的見解です)。

まずは「戦士」モルヒネ。
使われてきた歴史も長く、剤形も豊富。応用範囲も効果も高く、ぜひともパーティーに迎えたいジョブですね。また、散剤や速放錠剤はとても安く、薬価をできる限り抑えたい、というニーズにも応えられます。
ただ、腎機能障害がある方には使いにくく、その意味で使用に制限があるのがネックです。
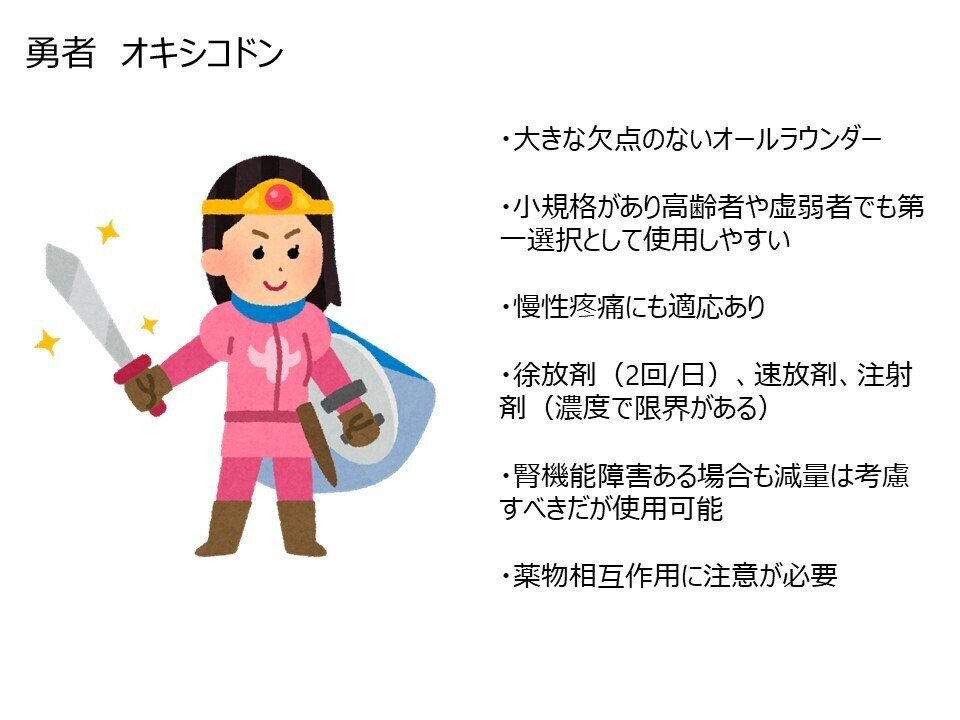
次に「勇者」オキシコドン。
「究極の普通」「オールラウンダー」の名を冠するにふさわしい、欠点が少なく使いやすい薬。なので、僕個人的には「初心者がまず最初にパーティーに入れるべきジョブ」としてオキシコドンを推したいです。

CYP3A4の影響を受けるために薬物相互作用に注意が必要ですが、その影響を受ける中に頻用薬は少なく、日常的にはあまり気にするべきことは多くありません。
唯一の使いにくさは、濃い注射剤が無いことで在宅での使用がしにくい点です。在宅で経口摂取ができない患者だと、モルヒネ皮下注や次に紹介するフェンタニルパッチが中心に活躍することになります。

さて、その「風の魔法使い」フェンタニル。
貼付剤であるがゆえに、「どうしてもフェンタニルが必要な場面」が存在します。経口摂取が難しい患者はもちろん、「できる限り内服薬を減らしたい」ニーズにも応えられます。
一方で、貼付剤であるがゆえに扱いにくい面もあります。
その第一は、用量調整がしにくい点です。貼付してから安定血中濃度になるまでに時間がかかるため、「いまここにある痛み」へは対応が難しい。また、患者によって吸収の個人差や限界があり、「フェンタニルパッチでは全く痛みが取れない人」もしばしば経験します。なので、僕個人としては「最大規格量」を超えた貼付はしない、とルールを決めており、例えば商品名でフェントステープだと8㎎まで増量しても疼痛が緩和しない場合は原則として別の薬剤を検討しています。

また、フェンタニルパッチを貼付した場合は、レスキューもフェンタニルにしなければならない、と考える方がけっこういますが、フェンタニル速放剤はROO製剤(rapid onset opioid)といって、そもそも使う目的が異なります。ROO製剤は、モルヒネやオキシコドンの速放剤と違い、「とにかく早く効く」薬です。いや、モルヒネやオキシコドン速放剤も早くは効くのですが、もっと早く効く、という特徴です。なので、ROO製剤の出番は突出痛(breakthrough pain)、つまり「普段は全く痛みなくコントロールされているが、急激な痛みが1日2回くらいある人」が典型的な使用対象となるわけです(図の赤ライン)。図を見ていただければわかるように、この突出痛の山さえ消せれば、この方の痛みの閾値は黒点線のところまで上げるだけで済むわけですからね。それに対し、黄色ラインのような「普通の疼痛」の場合はオキシコドン速放剤で山の部分を抑えるか、またはオキシコドン徐放剤の量を増やして、全体の痛みの閾値を上げる、という戦略になります。
ROO製剤をオキシコドン速放剤と同じように使わない理由のひとつは「依存症の発症を防ぐため」という面もあります。依存症は一般的に「効果発現が早くその効果が高い」ほど発生しやすい、とされていますがROO製剤はオキシコドン速放剤と比べると依存リスクが高いのです。
では「内服不可能な患者へのROO製剤は使用してはいけませんか?」との質問には、「限定的に使用してよい」とお答えします。できれば、モルヒネ座薬を優先して使用したいですし、それでコントロール困難なら早めに注射剤としてほしいところです。それもできない特殊な事情がある場合はやむを得ずに使用することはあります。

そして次が「剣士」ヒドロモルフォン。
ヒドロモルフォンの特徴は1錠の力価が小さく、1日1回投与で済むため認知症のある高齢者などでもコントロールしやすい点です。また大きな欠点も無く、使いやすい薬ですのでオキシコドンと並んでパーティーのメインとして考慮してよい薬ですね。

そして最後は「炎の魔法使い」メサドン。
使いにくい印象を持たれている炎魔法ですが、実際には「メサドンでしか取れない痛みがある」のも事実で、パーティーの一人として後衛にいてくれると心強いです。
その一番の要因は、NMDA受容体拮抗作用、セロトニン再取り込み阻害作用を持ち、鎮痛補助薬としての効果も併せ持つことです。メサドンが登場する以前では、骨盤内腫瘍などが原因となる難治性疼痛は神経ブロックでしか緩和できない、という場面がしばしばありましたが、登場後はほぼメサドンだけで緩和可能な患者ばかりとなっています。
薬物動態の個人差が大きく換算表が使いにくいため、それまでに投与されていたモルヒネやオキシコドンなど他のオピオイドにプラスして使っていく場面も時々あります。
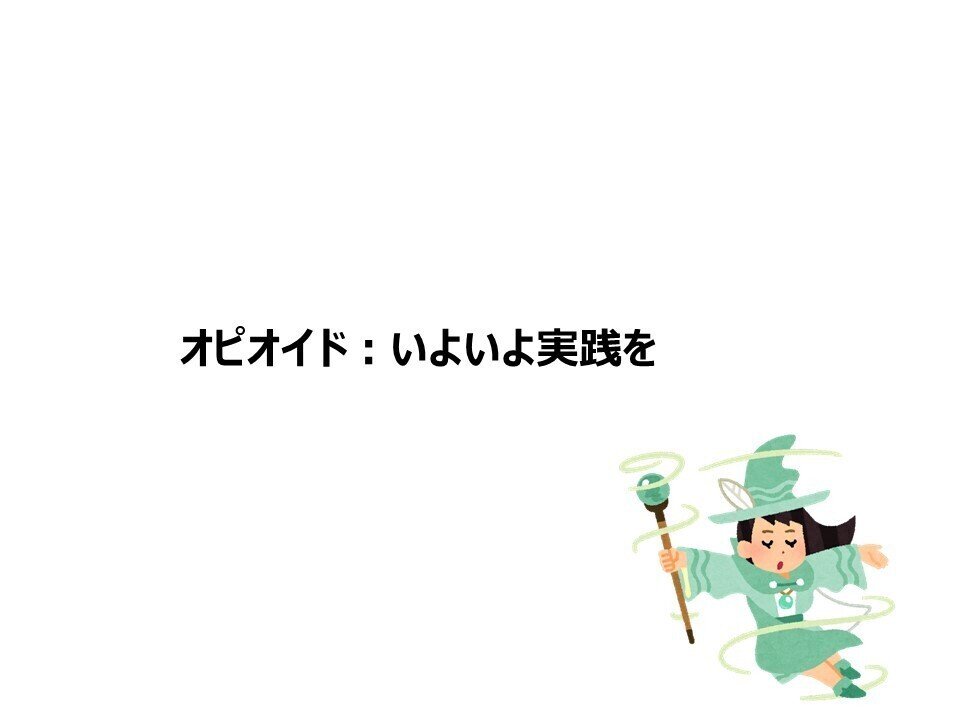
では、実践においてどのように使っていくのかを見ていきましょう。


もし医療現場でがん性疼痛やがんに関連した呼吸苦を見た場合、緩和ケアの専門家に紹介する前に、これくらいの処方は非専門医でもできた方が良いですね。
便秘の副作用対策に用いるナルデメジンは、保険上は予防投与不可なのですが、それを守るとしてもできる限り早めに開始する方が良いです。便秘がひどくなってからナルデメジンを開始すると、急に腸が動くことによって腹痛に襲われる患者が少なくありません。
吐き気止めのプロクロルペラジンは、以前は「オピオイド導入時は予防的に5日前後投与」と習ったかもしれませんが、最近の研究では必ずしも吐き気止めは必要ないとされており、若い女性や乗り物酔いしやすいなど嘔気のハイリスク患者のみ考慮、で良いかと思います。
またオピオイドと併用するNSAIDsは何でも良いのですが、効果時間の短いロキソプロフェンは避けるのが無難です。朝方になって効果が切れて「痛い」と言われる原因となります。

がん性疼痛に立ち向かう時に、軸となる薬剤は何なのか。僕はオキシコドンを中心に据えることをお勧めしますが、これは人に寄りけりでしょう。オピオイドはそれぞれのキャラクターをつかみ、自分なりのパーティーを考えることが大事です。
ではここから(仮想)事例を見ながら検討してみましょう。
ここから先は
¥ 100
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
スキやフォローをしてくれた方には、僕の好きなおスシで返します。 漢字のネタが出たらアタリです。きっといいことあります。 また、いただいたサポートは全て暮らしの保健室や社会的処方研究所の運営資金となります。 よろしくお願いします。
