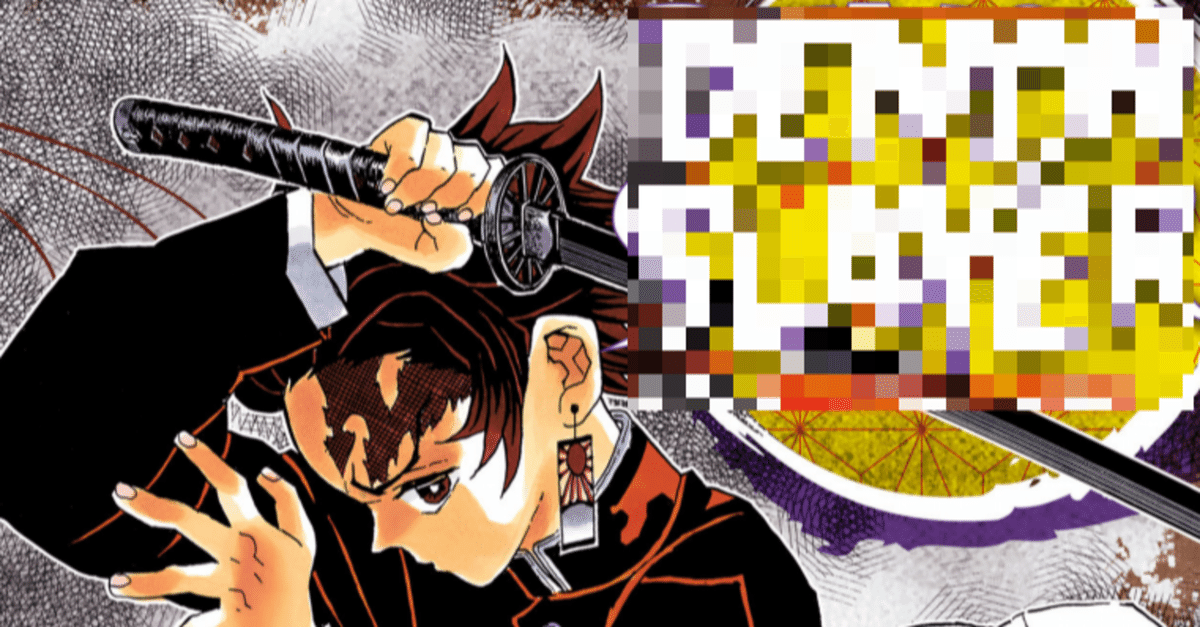
鬼滅の刃で中学英語#11~鬼滅英単語①『鬼滅の刃』はどう訳された?~
最近英文法の話ばっかりで若干ハードだったので、今回は軽めに、鬼滅の刃用語の英語バージョンをご紹介&解説していきますよ!
今回はマンガのタイトル『鬼滅の刃』英語タイトル『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba』について。
最初はこの訳、「どうなの?」と思いましたけど、色々調べていくと、「なかなかピッタリじゃん!」ということがわかってきました。
鬼は「Demon」で大丈夫?
鬼滅の刃は、先ほどご紹介した通り「Demon Slayer」です。
意味は、以前チラッと紹介しましたが、改めて。
西洋でも見た目が「鬼」というのは、ファンタジーRPGに登場する、人を食うけど頭が悪く大して強くもない「Orga(オーガ)」や、一つ目の巨人「Cyclops(サイクロプス)」などもありますが、『鬼滅の刃』に登場する鬼は、人型のサイズで、残忍で、狡猾で、人を食すという意味で、ちょっと違いますね。
「demon(デーモン)」は一般的な「鬼」の翻訳語ですが、「demon」は「悪霊」という意味もあるように、「悪」の存在者という意味合いが強いので、「鬼滅」での鬼も「demon」となったのでしょう。
ちなみに同じように「悪魔」と翻訳される「devil(デビル)」ですが、こちらは神と敵対する悪の存在を意味するので、ちょっとイメージと違いますね。
鬼滅の刃の世界は「神vs悪魔」ではなく、「人間vs鬼」なので、人にとっての悪魔という意味でも「demon」が正解でしょう。
では、「slayer」の方はどうでしょうね?
英語は、動詞を「動詞+er」の形にすることで、「~する人」「〜する物」という「名詞」にすることができます。
例
work(労働)→worker(労働者)
play(プレー)→player(プレーヤー)
speak(話す)→speaker(話者、スピーカー)など
鬼滅の刃の場合は、「slay(殺す、滅ぼす)」という動詞に「-er」をつけて、「slayer(殺す人)」にしてるんですね。
なお、「殺す」に相当する英単語は「slay」の他にもよく知られている「kill」、殺人者に使う「murder」などもありますが、採用されなかったのは、それぞれこんな意味の違いからでしょう。
slay=人や化け物などを「殺す」
kill=動物や人間、物、時間*などを「殺す」
murder=殺意を持って人間を「殺す」(意図的)
*kill time=ヒマをつぶす
こうやって見ると、「slay」が一番しっくり来る表現ですね。
「刃」はどこ行った?
じゃぁ『鬼滅の刃』の「刃」はどこいったって話になりませんか?
英語で「~の刃」は「blade of~」なので、『鬼滅の刃』を直訳すると、『The Blade of the Demon Slayer』となりますね。
「of」を使った創作ものに、映画化もされた『ロード・オブ・ザ・リング(The Load of the Rings=指輪物語)』がありますが、そんな感じです。
ちなみに英語版ウィキペディアでは、『鬼滅の刃』の日本語そのものの意味として、「Blade of Demon Destruction*」だとするブログ記事を紹介しています。
*破壊、絶滅、駆除、大量殺人
原作では「鬼を滅殺するのが鬼殺隊」という使われ方をするので、「滅ぼす」という意味のある「Destruction」が確かにピッタリな気がしますが、でも、実際のタイトルにはそれが採用されなかったわけです。
なんででしょうね?
それは、「slayer」という言葉に秘密があります。
「Slayer」に隠された意味
先ほど、英語は「speaker(話者、スピーカー)」のように、「動詞+er」が、人でも物でも使えるんですよね。
この辺、日本語は、人にするときは「○○者」、物にするときは「(例えば)○○車」のように、人と物では違う表現になるので、ちょっと違和感があるかもしれませんが、これが英語の特徴といえば特徴でもあります。
たとえば、「slayer」という言葉を使ったものに、「Dragonslayer」という言葉があります*。
*英語版Wikipediaにも項目がちゃんとあります。
Wikipediaによると、古来から、姫をさらった凶悪なドラゴンを英雄が倒す「竜退治」の話が各地に300種類もあるそうです。
そして、そのストーリーの中で、ドラゴン(竜、龍)を退治する英雄、またはその武器が「Dragonslayer(ドラゴンスレイヤー)」と呼ぶそうで、それをタイトルにしたお話も数々あります。
たとえば、40年くらい前に、あのディズニーとパラマウントで共同制作された「Dragonslayer」というまんまのタイトルの映画がありました(日本では上映がなかったようですが、DVD化はされています)。
YouTubeでも一部視聴でき、フルCGの映画もたくさんある現代人からするとショボく感じますが、CGなんてほとんどなかった時代に作られた画期的な作品だったようで、アマゾンレビューでも評価が高いです。
つまり、何が言いたいかというと、西洋の人からすると「○○Slayer」という表現は、割と受け入れられやすい表現だってことですね。
タイトルを「○○Slayer」とすれば、「○○退治の話」というのがよくわかるのです。
そして、
西洋で「○○退治」と言えば「竜退治」ですが、
日本で「○○退治」と言えば「鬼退治」なんです。
だからその「竜退治のお話」を「鬼」にした結果、「DragonSlayer」ならぬ「Demon Slayer」になった、ということがよくわかっていただけるかな、と思います。
「刃」に込められた意味とは?
それにしても、この、「人」もしくは「武器」を「ドラゴンスレイヤー」と言うという感覚は、日本人にはなかなかなじみがないですよね。どっちかにしろよと。
でも、これはあくまで個人的な意見ですが、この、どっちにも解釈できる言葉が、いかにも「刃」を表しているような気がするんですよね。
というのも、『鬼滅の刃』には、鬼を殺せる唯一の武器としての刀(日輪刀)が出てくるのですが、『鬼滅の刀』というタイトルにはしていませんよね。
タイトルに「刀」を使ってしまうと、「武器」そのものをイメージしてしまいますが、「刃」にするとどうでしょう?
色んな意味が出てくるような気がしませんか?
広辞苑(第七版)でも、「刃」については、
①火に焼き、水に浸して鍛えた刃物
②焼き場のついたもの。刃物
③刃のように鋭いもの、威力あるもののたとえ
であるとしています。
『鬼滅の刃』に使われている「刃」というのは、明らかに③の意味でしょう。
それは、武器としての刀だけではなく、鬼殺隊という鬼を殺すことに生命をかける集団も指し、また、その鬼殺隊の隊士の想いもそこに込めて、そういうのもひっくるめて、鬼を滅ぼすことができる刃としているのではないでしょうか?
鬼を殺すのは武器だけじゃなくて、人の想いも必要だと。
ややネタバレになってしまいますが、今、週刊少年ジャンプ本誌では、「鬼滅」のクライマックスシーンに向かって突き進んでいる状況ですが、まさにそれを体現しているかのような展開ですし、単行本4巻で、「刃になれ!!」とというシーンがあるので、「鬼殺隊士=鬼滅の刃」ということなんでしょうね。

ちなみに、これも広辞苑からですが、「刃(やいば)」とはもともと「焼刃(やきば)」から来ている読み方だそうで、物語中盤で出てくる「焼ける刃」というのも、ひょっとしたら計算してタイトルに込めていたのでは??
・・・という作者の恐ろしい伏線を想像したりしちゃいました。
おまけ
余談ですが、西洋の「ドラゴン」はこのような「悪の化身」として描かれますが、日本などのアジアでは神社に像があるように「竜(龍)=神もしくは神の化身」として描かれます。
これは歴史的背景による違いで、興味がある方はこちらを読んでもらうとわかりやすいかもしれません。
本日のまとめ
・『鬼滅の刃』≒『Demon Slayer』は、「DragonSlayer」の鬼(Demon)バージョン
・英語は「動詞+er」で「~する人」「~する物」の両者を表すことができる

