
【トークレポート】負の世代間連鎖を生き延びるために(前編)──メニコン シアターAoi「芸術監督トークシリーズ vol.1」〜映画『プリズン・サークル』〜
「芸術監督トークシリーズ」は、作品とトークセッションをワンセットにてご覧いただくことで、作品を通じて一緒に学び、考え、楽しむ企画です。ゲストの方と芸術監督の山口茜がさまざまなトークを交わします。
第一回目はテーマを「負の世代間連鎖」とし、映画『プリズン・サークル』監督の坂上香さんと、モラハラ加害者変容のための当事者コミュニティ・GADHA(ガドハ)を運営する中川瑛さんをお招きました。
本記事は、当日のトークのようすを要約してお伝えいたします。
*記事の後編はこちらからお読みいただけます。
(取材・文・写真: 河野桃子)

刑務所のプログラムに、演劇的な要素をみつけて
山口 「芸術監督トークシリーズ」第1回目として演劇ではなく映画を上映することにしたのは、シアターAoiができてまだ1年なので、ご近所の方が「演劇だとちょっと腰が重いけど、映画だったら行けるかな」と気軽に来ていただけるきっかけになればと企画しました。
そこでなぜ『プリズン・サークル』を選んだかというと、私自身、恐ろしいほどの暴力性と被害者意識を持っているのですが、そのことを、40代後半になってようやく客観的に見つめられるようになってきたからです。今振り返ると、30年ほど演劇を作り続けることによって「この加害性は一体どこから来たのか」を探ってきたようなところがあります。

『プリズン・サークル』のなかでも演劇が出てきました。刑務所にいる受刑者たちが物語を作ったり、被害者の役を演じたりする「TC(ティーシー)(*1)」というプログラムを受けていましたが、それは、ぜんぶ演劇ですね。TCのようなものがあれば、世の中に、傷つけたり傷つけられる人が減るんじゃないかなと感じたんです。この映画がきっかけになればと思いました。
大川 中川さんは映画をご覧になっていかがでしたか?
中川 ふたつのことを、映画を見ても思いました。ひとつは、多くの人がTCのように、自分の考えを正直に言葉にできる場を求めているだろうということ。もうひとつが、TCのような場は社会にすごく少ないということ。刑務所でTCを受けても、出たあとに社会で正直にいようとして傷ついてしまえば、また鎧を着こまなければいけなくなってしまう。TCのような考え方や、ケアの文化や空気が社会全体に広がっていく必要があるのかなと思いました。
「負の世代間連鎖」をトークテーマに
大川 おふたりとも、映画をご覧になって、社会の中にセラピー的な環境がもっと必要じゃないかと思われたのですね。山口さんは『プリズン・サークル』を上映すると決まった当初から、トークテーマは「負の世代間連鎖」にしたいと仰っていました。なぜですか?
山口 私の両親もとても暴力が多く、私は常にビクビクしていたんです。映画のなかである受刑者のエピソードとして、相手が何かを取ろうとしただけなのに「あっ、殴られる」と体が反応してしまう、というのが出てきましたが、私もそうでした。映画に出てくる受刑者の方々は、子どもの時の自分のようです。人を信じることも難しかったし、「万引きに罪悪感がない」という気持ちもわかる。他者と自分の区別がつかないとか、すべてが自分の視点からでしか見られないとか……そういう感覚ですね。
けれども20~30代は、自分が被害者だったこともわかっていませんでした。ただ、社会を憎んでいることは確かでした。それが演劇を作るなかでどんどん紐解かれていき、ようやく最近になって辿り着いたことが、母の父……つまり私の祖父が傷痍軍人(*2)だったということなんです。
祖父は、第一次世界大戦で頭に銃弾が入った状態で帰国し、よくお酒を飲んで暴れていたので精神病院に強制入院させられ、そこでリンチを受けて植物人間になったのですが、母親が「これでやっと動かない」とホッとしたそうです。そういう状況で育ってきた母の暴力性は生き延びるために仕方がなかったんだということと、戦争がとても大きな原因であることがわかってきました。全部、繋がっていたんです。
坂上さんは刑務所をよく撮影されていますが、個人的な体験と繋がっているんでしょうか?
坂上 私は刑務所という場所に特に関心があるわけではないんです。むしろ無くなればいいとすら思っています。刑務所に行き着いたのは、アリス・ミラーという精神分析医の番組を作ったことからでした。アリス・ミラーは『魂の殺人~親は子どもに何をしたか~』という本を書いていて、80年代のはやい時期から「暴力の連鎖」という考え方を提唱していた人です。それは単純に、暴力を受けたら暴力の加害者になるということではなく、また、個人的な暴力もあれば社会的な暴力や、紛争、戦争に発展するケースもある。今まさに世界で起こっているウクライナとロシアや、ガザのこともそうです。とくにガザについては、かつてユダヤ人たちがホロコースト(*3)で受けた被害へのケアや社会的対応が不十分だったことや、そうした彼らの被害感情に加担する人々が、イスラエルの領土拡大のためにパレスチナの何千人もの子どもたちや民間人を殺しています。
やはり元(もと)をちゃんと見なければいけない。何が起きて、どんな傷を負っていて、その傷をちゃんとケアできていない、ということに目を向けなければいつまでたっても暴力の連鎖が繰り返される。日本の社会にもいろんな暴力があり、受刑者たちの話からわかるのはサバイバルしてきている人が多いということです。

私も被害者であり加害者でした。母親からの暴力や学校でのいじめによってうまれた憎しみで、力のない弟をいじめていたんです。「お前なんか生まれてこなければ良かった」のような言葉の暴力で尊厳を傷つけていました。暴力を弟に連鎖してしまったんです。
その後、「誰も私のことを助けてくれない」と日本の社会を憎んで18歳でアメリカに留学し、南米にも行き、言葉にできないほど凄まじい拷問の被害者に会うこともありました。そうして日本やアメリカの暴力的な構図を客観的に見られるようになりました。
20代初めには日本に帰ってきて、テレビ番組を作る制作会社に入りました。当時は性暴力や暴力が当たり前の業界で、歯を食いしばって、夜もうなされて、自分が自分じゃないような9年間を過ごしました。それから大学に9年勤めました。大学にも暴力がありましたが、テレビ番組業界のようなあからさまな暴力ではなかったので、転職当初は「日本にもこんなまともな職場があるんだ!」と感激しました(苦笑)。暴力が当たり前になっていると、諦めがでてきて、耐えてしまう。外に出てやっと「すごく痛かったんだ」と気づいたんです。

こうした過程で、暴力の連鎖にとても関心を持ち、刑務所に行きついたんです。受刑者には凄まじい暴力に遭っている人たちの割合が高い、ということは海外の調査でもわかっています。おかした犯罪が凶悪になるほど彼らが受けてきた幼少期の暴力は凄まじい。でも、そのことはずっと隠されてきた。TCのようなプログラムがあれば受刑者に何があったかがわかるけれど、日本のほとんどの刑務所のようにただ閉じ込めているだけだと、彼らがなぜこんなことをしでかしてしまうようになったのかがわからないですよね。
私はアメリカのテレビの仕事で何回かTCプログラムを扱ってきたので、日本でもTCを通して受刑者の受けた被害が見えてくるはずだと確信し、この映画を撮りました。
大川 中川さんは、「暴力の連鎖」に関連して、モラハラ・DV加害者変容のためのコミュニティ「GADHA(ガドハ)」を立ち上げた経緯などを教えていただけますか?
中川 僕がGADHAを始めた経緯は、自分が加害者だという自覚を持つ時があったからです。基本的にはお二人とかなり近く「自分はこれは当たり前」と思っていた関わりが、暴力的だったことに気づいた。励ましているつもりがかえって追い詰めていたり、「普通こうするだろう」と相手をコントロールするような暴力を振るっていたんです。それに気づいた自分も、それを親からされていたということと、愛や優しさや自分のためを思ってくれていたと信じていたことがまったくそうではなかったことに気づいてしまった。それはショックなことでした。
これが暴力ならば、世の中のどこにでもあるし、たとえば、相手のためを思って相手をコントロールしようとする行為は本当に優しさだろうか?……そんな疑問が生まれてきました。

被害者も加害者も無自覚ですから、まずは自分たちで「これは暴力なのかしら」「じゃあ何をすればケアなんだろう」と話せる場所があればとイベントをやりました。3年間で1,100人くらい集まり、男性7割、女性3割ほどです。学び変わりたいという人がこんなにいる。そうして溜まってきた知見をまとめて学べるプログラムを作っています。

やっていると、パートナー関係の話をしていたはずが、だんだん親子関係の問題と繋がっていくことがあります。自身が親からの被害者であり、同時に、子どもへの加害者であると急激に自覚していった事例がすごく多い。そこで、親子関係について学べる場所を作ろうとPaToCa(パトカ:変わりたい毒親のためのコミュニティ)を作りました。
あと、職場でも被害・加害は多く、CoNeCa(コネカ:変わりたいと願う「怖い職場を作ってしまう人」のためのコミュニティ)という場所を作りました。
それらのなかでいろいろな先行研究を読み、坂上さんの考え方にも出会いました。今日は坂上さんとお話できるとワクワクして来ました。
TCと映画について──「じゃあ俺たち証人な」の意味
大川 TCという仕組みについて、映画を見ると「これは絶対にやった方がいいな」と思うのですが、実際に現場で撮影をされていかがですか?
坂上 日本の刑務所でのTCはいまだに、映画で取材した「島根あさひ社会復帰促進センター」ひとつだけしかない。どうやら法務省は「オープンダイアローグ(*4)」という手法を矯正施設に導入しようとしています。そちらも悪くはないんですが、TCの場合は、徹底的に自分の過去の被害者性について語ると同時に、自分がやった犯罪について考える。映画の中で「修復的司法」という考え方を使ったワークショップが出てきますが、犯罪を「損害」だととらえて、人間関係においてのなんらかの損害を与えてしまった相手(被害者)に対して、加害者(受刑者/自分)は何らかの責任を追わなければいけないと考える。実際に効果が出ていて、明らかに再入所率も低くなっているし、出所後も支え合っている。
ただ、この映画では、彼らが関係を作っていた「余暇時間」という休憩時間にはカメラをほとんど入れられませんでした。その「余暇時間」でお互いに「今日は思ったことをちゃんと言えなかったんだ」「じゃあ続き話そうよ」などの話ができていて、大切なかけがえのない時間だったんです。「TCを通して作った関係性を外では一生作れないんだ」と断言する人がいるぐらいです。ご本人たちからは「坂上さん、何も映っていないじゃないですか」と言われるほど、彼らにとっては意味のある場だったんですよね。

TCは、やはりしんどいんですよ。徹底的に自分の過去の被害者性について語ると同時に、自分がやった犯罪について考える。
映画で、出所した人達が集まった会話のなかで、(なかなか仕事が続かない)一人が「(これ以上みんなに「ちゃんとしろ」と責められるのは)もうギブギブ、ギブアップ」と言っていましたが、あのシーンはすごく難しくて…。専門家の方はあのシーンを見て「(追い詰められていて)キツすぎる」と言われますが、私は、TCがあったからこそあの会話が成立していると思います。その人はみんなに「ちゃんとしろ」とかいろいろ言われるけれど構ってもらえているし、みんなは関心を持って彼と付き合っている。
そして次のシーンで、他の一人が「じゃあ俺たち証人な」と言うんですよ。この「証人」というのはとても大事な言葉です。アリス・ミラーの言葉で『助ける証人』と『事情をわきまえた証人』というものがあります。『助ける証人』とは子どもの虐待に介入して助けてくれる大人のこと、『事情をわきまえた証人』とは助けるまではできなくても「大変そうだな」「声をかけてあげようかな」と思っている大人のこと。そういうことを彼らは学んでいるので、「証人」という言葉が出てくるんですね。
つまり「俺たち証人な」という言葉は、彼らは3ヶ月に1回しか会えないので「次に会う時までその3ヶ月頑張れよ」と励ましている。私はあのシーンがとっても大好き。
山口 すごく象徴的な場面だったと思います。負の世代間連鎖をストップさせるには、まず自分が沸き上がってくる感情にブレーキをかけられるようになることは重要ですが、それが自分だけじゃなくて仲間に対してもおこなっている、という場面ですね。
坂上 やはり刑務所の中と違って、社会にはいろんなハードルがある。「人間関係の作り方をここ(島根あさひ社会復帰促進センター)で学んだ」と言う人もいて、出所後に周りの人から「そのコミュニケーション能力はどこで身につけたの?本当に刑務所?」と驚かれる。
彼らが社会に出た後で危険なことが起きそうなときに「これはまずい」と踏みとどまれるのは、TCの仲間たちが刑務所を出てからも良い人間関係を作ってくれているからなんですね。もちろんなかにはズルズルと悪い方に進んでしまう人もいますが、そういう危険性はここにいる私たち全員にとっても常にある。だから、仲間を作ることがとても大事なんだと思います。
後編はこちら
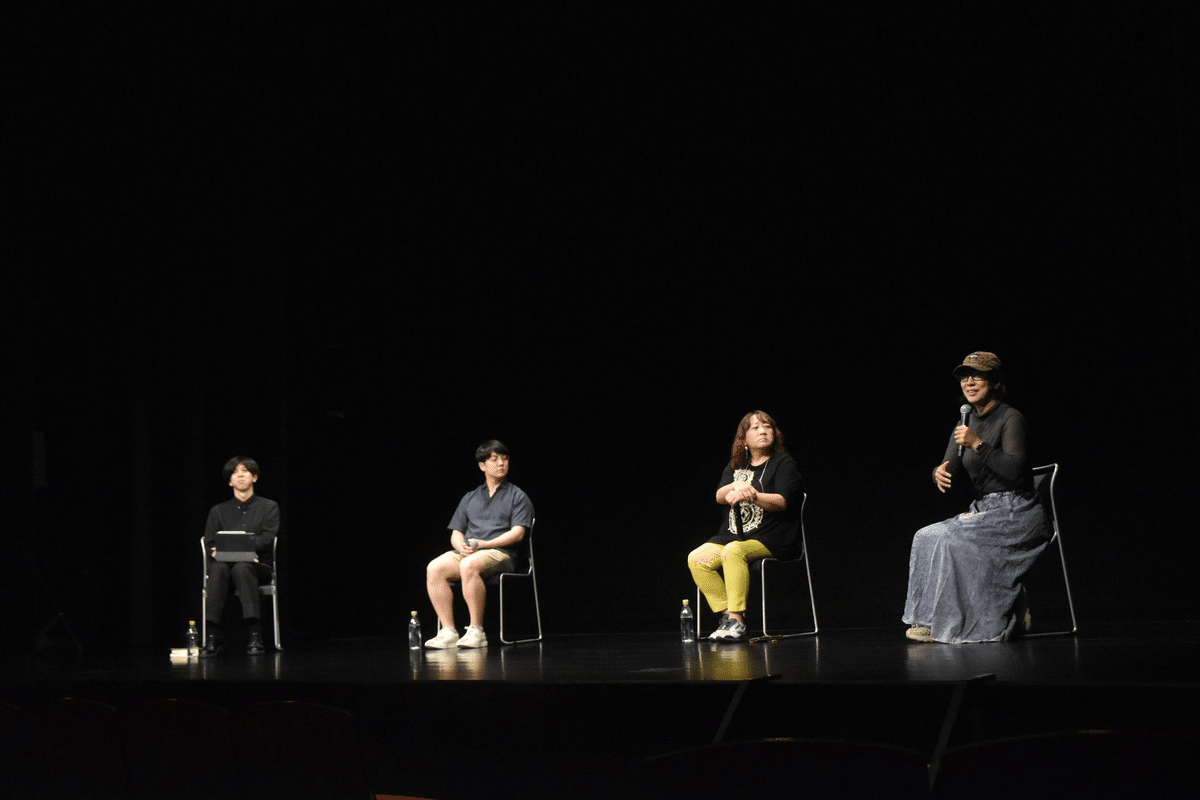
脚注
TC……Therapeutic Communityの略。受刑者同士の対話をベースに犯罪の原因を探り、更生を促すプログラム。
傷痍軍人……戦闘によって負傷した軍人
ホロコースト……ナチスドイツ政権とその同盟国などによって行われたヨーロッパのユダヤ人約600万人の迫害および虐殺
オープンダイアローグ……「開かれた対話」を意味する、フィンランド発祥の精神医療で用いられる治療的介入手法。日本の刑務所でも、オープンダイアログの手法や考え方を取り入れた「対話」が行われている。
▼登壇者プロフィール
坂上香
ドキュメンタリー映画監督。NPO法人「out of frame」代表。一橋大学客員准教授。高校卒業と同時に渡米・留学、ピッツバーグ大学で社会経済開発学の修士号を取得。南米を放浪した後、帰国後TVドキュメンタリーの道へ。「被害者」による死刑廃止運動、犯罪者の更生、回復共同体、修復的司法、ドラッグコート(薬物裁判所)など、暴力・犯罪に対するオルターナティブな向き合い方を映像化。ATP賞第1回新人奨励賞を皮切りに、ギャラクシー賞大賞、文化庁芸術祭テレビ部門優秀賞、ATPドキュメンタリー部門優秀賞等、数多くの賞を受賞。2001年TV業界を去り、大学専任教員に転職。メディア教育に従事しながら、薬物依存症の女性やその子どもたち、刑務所等に収容される人々を対象に、映像やアートを使ったワークショップも行う。2012年、映画制作に専念するためインディペンデントに。劇場初公開作品でアメリカの刑務所が舞台の『ライファーズ 終身刑を超えて』(2004)で、New York International Independent Film and Video Festival海外ドキュメンタリー部門最優秀賞を受賞。2作目の『トークバック 沈黙を破る女たち』(2013)はLondon Feminist Film Festivalのオープニングに選ばれる。「暴力の後をいかに生きるか」をテーマに、「希望」や「成長」に着目した作品をこれからも作り続けていきたいと考える。主な著書に『癒しと和解への旅』(岩波書店)、『ライファーズ 罪に向きあう』(みすず書房)、「プリズン・サークル」(岩波書店)、「根っからの悪人っているの?」(創元社)。絵本の翻訳に『ねぇねぇ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと』、『きょうのわたしは ソワソワ ワクワク』(偕成社)。
中川瑛
モラハラ・DV加害当事者団体GADHAを主宰し、ミクロな「加害者個人」の変容や、その背景にあるマクロな「加害者を生み出す構造」の変容に取り組む。近著に『別居・離婚後の「共同親権」を考える(分担執筆 第五章担当)』(明石書店)、『ハラスメントがおきない職場のつくり方』(大和書房)、『孤独になることば、人と生きることば』(扶桑社)、コミック『99%離婚』(KADOKAWA)シリーズ原作など。
山口茜
劇作家・演出家。龍谷大学文学部日本語日本文学科卒業後、自らでプロデュースし演劇を上演する団体、トリコ・Aプロデュースを設立。京都を拠点とし、東京・大阪などでも演劇を上演。関西では演劇ワークショップの講師などもつとめる。2007年9月〜2009年9月までの2年間文化庁新進芸術家海外留学制度研修員としてフィンランドに滞在。帰国後、活動を再開し、利賀演劇人コンクール2015に参加したメンバーでサファリ・Pを立ち上げ。2010年からは龍谷大学非常勤で講師も務める。2021年~メニコン シアターAoi芸術監督。
▼『プリズン・サークル』概要
ぼくたちがここにいる本当の理由
「島根あさひ社会復帰促進センター」は、官民協働の新しい刑務所。警備や職業訓練などを民間が担い、ドアの施錠や食事の搬送は自動化され、ICタグとCCTVカメラが受刑者を監視する。しかし、その真の新しさは、受刑者同士の対話をベースに犯罪の原因を探り、更生を促す「TC(Therapeutic Community=回復共同体)」というプログラムを日本で唯一導入している点にある。なぜ自分は今ここにいるのか、いかにして償うのか? 彼らが向き合うのは、犯した罪だけではない。幼い頃に経験した貧困、いじめ、虐待、差別などの記憶。痛み、悲しみ、恥辱や怒りといった感情。そして、それらを表現する言葉を獲得していく…。
監督は、『ライファーズ 終身刑を超えて』『トークバック 沈黙を破る女たち』など、米国の受刑者を取材し続けてきた坂上香。日本初となる刑務所内の長期撮影には、大きな壁が立ちはだかった。取材許可が降りるまでに要した時間は、実に6年。この塀の中のプログラムに2年間密着したカメラは、窃盗や詐欺、強盗傷人、傷害致死などで服役する4人の若者たちが、新たな価値観や生き方を身につけていく姿を克明に描き出していく。
▼「芸術監督トークシリーズ」について
劇場がインクルーシブな場所であるために
メニコン シアターAoiの目指す姿を「自分が主役と思える場所」と定義し、常にマイノリティに寄り添う場所でありたいと志す芸術監督の山口茜が自ら発案・企画するトークシリーズを、2024年度より始動します。
山口が掲げる劇場の目指す姿を見据え、山口が、劇場が、そして作り手・観客をはじめとして、この社会を構成する全ての人が、他者に寄り添い、インクルーシブであるために考えるべきこと、知っておく必要があることを、共に学ぶためのトークシリーズです。
各回、映画もしくは演劇の作品鑑賞とその後のトークセッションをワンセットでご覧いただきます。トークについては、作品に関係する様々な要素から、トークホストも務める山口が、劇場がインクルーシブであるために考えを深めたいテーマを選び、各作品のクリエーターに加えて、そのテーマに知見を有するゲストを招き、山口が来場者とともに学ぶことのできる場づくりを行います。
トークセッションの内容は社会的な共有知と考え、後日レポート記事をWEB上で公開し、インクルーシブな劇場、そして社会が実現に繋がることを目指します。
