
【解説】アメリカにおけるアファーマティブアクション「違憲」判決!
ゆっくりしていってね!
アメリカの最高裁でアファーマティブアクションに違憲判決が出たわよ!(※後述するけど、この言い方はやや語弊があるわ)

え? アファーマティブアクションって何って?
アファーマティブアクションってのは……アレよ。被差別層を救うために一種の優遇措置を採ることを指すわ。
最近、日本でも東京工業大学が女子枠を作って話題になっていたわね。これも女子へのアファーマティブアクションよ。
東京工業大学は、2024(令和6)年4月入学の学士課程入試から、総合型選抜および学校推薦型選抜において女性を対象とした「女子枠」を導入します。
2024年4月入学者の入試では4学院(物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院、環境・社会理工学院)で新選抜を開始し58人の女子枠を導入、2025年4月入学者の入試では、残りの2学院(理学院、工学院)で新選抜を開始し85人の女子枠を導入します。
アファーマティブアクションっていうのは、上記のように特定の属性に違う選抜コースを用意して枠を作ったり、あるいは黒人さんなどのマイノリティにマイノリティ加点をして、ちょっとテストの点が悪くてもウチの大学に入れてあげよ~ってやるやつよ!
……うん。まあ言いたいことは分かるわ。
瞬時に思いつくこととして、「かえって不公平では……なんで点数が高い人が落とされるの?」「逆差別じゃない?」というツッコミがあるわよね。確かに下駄なしで受験戦争やらされる側はたまったもんじゃないわ。
とはいえ、アメリカでは長らく大学入試制度におけるアファーマティブアクションが裁判所に認められていたわ。かなりの不満はあったけどね。一応は持続してきた仕組み。
それが覆ったのが2023年6月。ハーバード大学とノースカロライナ大学で行なわれていたマイノリティ優遇の入試制度に「それやっちゃダメ!!」と違憲判決が下ったわ。
もちろん世界的な大ニュースになったけれど、日本での浸透ぶりはいまいち。知らない人も多くて、さらに知っている人の中でも誤解が散見されるから、本記事ではそこを整理していくのだわ。
先に言っておくと、違憲判決といっても、あらゆるアファーマティブアクションを禁じるようなクソ広い判決が出たのではないわ。
相当やりにくくなったのは確かだけれど、「アファーマティブアクションを認める条件をより明確にした上で、ハーバード大学とノースカロライナ大学の入試制度はアウトにした」と表現した方が適切でしょう。
ただ、メインの判決の説明に入る前に、アメリカにおけるアファーマティブアクションの歴史的な位置づけをまとめておくわ。
かったるい人は見出し機能でスキップしてもいいけれど、もともと日本人には馴染みが薄いテーマだし、「これまでの経緯」が分からないとけっこう難しいと思うわ。
では、いってみましょう!
アメリカにおけるアファーマティブアクションの歴史
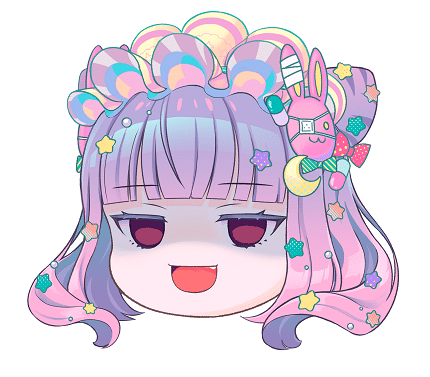
まずアメリカ、お前、差別やりすぎ。
奴隷制度からの流れで、白人以外はゴミのように差別されていたわ。黒人専用バスとか、黒人入学拒否の学校とかの時代ね。
ちょっとずつ改善していくのだけども、1960年代に入って「さすがにやりすぎたので、優遇してでも戻しましょう」と言い出したのが当時のジョン・F・ケネディ大統領さんよ。
実はこの時からアファーマティブアクションは「平等」の理念に反するから、法的に正当化できないはずだと批判はされていたのよ。アファーマティブアクションが提唱する「人種を基準にして特定層を優遇する」という行為は、その本質的な部分からして差別性を抱えているの。
でも、そんなお行儀のいいことを言うには、そもそもやってた差別の方が度を越していたのよね……。「平等」の理念に反するってどの口でほざくねん、と。
いささか気まずいものがあったので認められやすかった――のかもしれないわね!(文章化して残すような話じゃないから憶測になるけれど。)
Bakke裁判(1978年)で入試制度のアファーマティブアクション承認
アファーマティブアクションにアメリカ最高裁が法的な正当性を与えたのは、1978年のRegents of Univ. California v. Bakke裁判よ。
カリフォルニア大学医学部と、その入試制度のせいで不合格にさせられた白人男性・バッケさんの間の裁判ね。アメリカのアファーマティブアクションを語る上で絶対に欠かせない歴史的にも超重要な判例よ。アメリカでアファーマティブアクションを推進しているリベラル派が大好きなやつ。
バッケさんは白人男性で、テストの点数もすごく良かったんだけど(ほぼ満点に近かった)、それより劣る点しか取っていないマイノリティの人たちが「マイノリティ枠」で合格して、彼は2年連続で不合格にさせられていたのよ。
不公平、不平等! ――と憤るのもごもっとも。アメリカが全体として酷い差別をしていた経緯があっても、バッケさん個人が貧乏くじ引かされるのは率直に何か違うしね。
でも、アメリカ最高裁は「マイノリティを優遇する措置を採る権利が大学側にはある」と認めたわ。
さて。アファーマティブアクション推進派の人たちはこの裁判が大好きでよく引き合いに出すのだけども、実はこの判決では、そんなにアファーマティブアクションを「善いもの」とは述べていなかったりするわ。
実際、同判決の中で、カリフォルニア大医学部の定員100人中の16人までをマイノリティ固定枠にするという方法に関しては「それはやりすぎ」と中止させたりもしているのよ。……ヘイ、「固定女子枠」を作った東工大? 聞いてる?
人種を考慮したアファーマティブ・アクション・プログラムは、大学入試のプロセスにおいて引き続き役割を果たすことができる。 多様性のある教室環境を作ることは、憲法修正第14条の下で認められる州のやむを得ない利益追求だからである。しかし、州立大学がマイノリティの入学者数に一定の枠を設けるのは行き過ぎである。
Affirmative action programs that take race into account can continue to play a role in the college admissions process, since creating a diverse classroom environment is a compelling state interest under the Fourteenth Amendment. State universities go too far, however, when they set a certain quota for the number of minority students who enroll.
人種で加点を行う権利は「多様性を追求したいという大学側の自由を尊重する」という意味で認めたものの、次のような注文をつけているわ。かなり念入りよ。
特定の人種を指定した固定枠の設定は駄目。
「固定枠でなければいいんだな?」と入学志願者や人口統計上の比率を用いて「割合枠」に直したとしても駄目。
マイノリティと非マイノリティで異なる入学選抜ルートを使う行為は駄目。
人種が入試を左右する役割は、適切に制限されていなければならない。人種が決定的な要因となるような配点は駄目。
非マイノリティの利益を不当に害する仕組みは全部駄目。(「不当に」と付けていたらそりゃ駄目でしょうって話ではあるけど)

つまり、日本で東工大がやってる「女子固定枠」は、アメリカなら、アファーマティブアクションが勝利したと言われる判決内ですら否定されているほどアウト!
まあ別にアメリカの判決に従う理由はないけれど――日本はアファーマティブアクションの本場ですら認めていないほど「強烈な」アファーマティブアクションをやっているというのは、事実として知っておいて良いでしょう。
さて。ここまで縛りが厳しいと、じゃあ逆に何が大学側の自由なアファーマティブアクションとして出来るのよ? って話よね。
答えを言うと、「非マイノリティにもマイノリティにも共通の評価システムを用いた上で、人種を書類評価の1つの"部分的な"要素として、かつ"加点にだけ"用いること」が許されたわ。
アメリカでは平等保護条項を極めて重視するという憲法論的な観点から、アファーマティブアクションは元より危険視されていたのよ。
とはいえ、このBakke裁判は意外と綺麗にまとまったのよ。当時の新聞でも「全員が勝者となった画期的判決」として賞賛されたわ。理由としては次の3つが主よ。
①行き過ぎたマイノリティ優遇措置(固定枠)は廃止させた。
②アファーマティブアクションで人種に加点することは認められた。
③大学を告訴したBakkeさんも入学できた。
Bakkeさんはマジで優秀な人だったから、良かったわね!
(全米優秀奨学生に選出、海兵隊に4年勤めて大尉に昇進。名誉除隊後、NASAでエンジニアとして勤務。なお、念願の医学部に入学できた後も医師として活躍したわ。)
Grutter裁判(2003年)での再承認
少し時代が飛ぶけど、入試制度のアファーマティブアクションが次に最高裁で争われたのは2003年のGrutter v. Bollinger裁判ね。ロースクールの入試制度を巡って法廷闘争になったわ。
ここから先は
¥ 350
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
