
【TeSHコラム企画 vol.04】 新株予約権
Tech Startup HOKURIKU(TeSH:テッシュ)は、北陸先端科学技術大学院大学と金沢大学を主幹機関とし、北陸3県の10大学、3高専を共同機関とする北陸地域の大学・高専発スタートアップ創出プラットフォームです。
TeSHでは、スタートアップ支援のスキル・ノウハウなどのナレッジ共有や、活動実績の記録のためにコラム企画を毎月更新しています。
過去の記事については、TeSHのクリエイターページよりご覧ください。
第四回は、TeSHプログラム代表の内田先生に執筆いただきました。
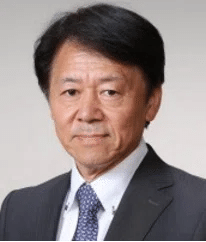
内田 史彦 氏
Tech Startup HOKURIKU(TeSH)プログラム代表
北陸先端科学技術大学院大学特任教授、未来創造イノベーション本部スタートアップ推進室長
-
日立中央研究所主任研究員、企画室部長を経て2012年同社研究開発本部CIO。2014年筑波大学教授、国際産学本部審議役、2021年お茶の水女子大学イノベーション創出環境強化事業統括を経て現職。
新株予約権
10年ほど前になりますが、民間の日立から筑波大学に移った2014年に、筑波大学発ベンチャー“CYBERDYNE”は、創業後10年で株式上場を果たしました。上場時の時価総額は、1,400億円でした。頭の中がまだ民間であった私は、『仮に大学が大学保有特許の対価として、わずか1%の株を持っていたら14億円が大学に入っていたはずだ!』と考えたのでした。しかし、当時の大学には新株予約権の規則そのものがありませんでした。そのことを大学の財務部門に話をしても一向に埒があきません。いたずらに時間が過ぎていきました。
そこで、2016年12月27日に、筑波大学の財務部長と財務制度企画課長とともに、文科省の法人支援課、大臣官房会計課を訪問したのでした。そこで、新株予約権をはじめ、私が大学に移ってきて疑問に思っている4項目について質問したのです。
(1) 大学発ベンチャーの大学構内への登記はできないのですか?
(2) 大学発ベンチャーの新株予約権を大学が取得することはできますか?
(3) 大学発ベンチャーが上場した際に大学に入る収入を基金化できますか?
(4) 政府調達に半年もかかると国際競争に負けてしまう。短縮化できませんか?
回答は、『(1)は、問題ありません、どうぞやってください。(2)は、まさに準備しています(2017年:文科省通達)。(3)は、運用できますが、基本計画期間を跨ぐのは難しい。(4)は、外務省管轄のWTOに絡み、簡単ではありません。』というものでした。
そこで、翌年、江戸川公認会計士の指導のもと、新株予約権の学内規則を制定しました。そして、2019年には、筑波大学発ベンチャー“ピクシーダストテクノロジーズ”ともう一社、2社の新株予約権を筑波大学は取得しました。この一連の取組みによって、ピクシーダストテクノロジーズの落合陽一社長と私は、大学発ベンチャー表彰のアーリーエッジ賞を2019年にいただきました。その後、2023年8月にピクシーダストテクノロジーズは、NASDAQに株式上場を果たしたのでした。
しかし話はまだ続きます。今年の10月25日、ピクシーダストテクノロジーズが、NASDAQ上場を廃止するとのニュースが飛び込んできました。この世界は、とても厳しいのです。また、大学の新株予約権も、簡単ではありません。法律事務所の指導では、『大学の産学連携部門が株式の取得を財務部門が管理をやる仕組みでは、完全な情報断絶(チャイニーズウォール)は無理である。取得した株式の売買は信託に任せるべきである。』という指導を受けました。そこで、筑波大学では、信託銀行に預ける規則を追加したのです。しかし、そのためには、新たに信託銀行に支払うお金がかかります。つまり、一定の規模の株式売却益が得られる大学発ベンチャーでなければ、大学にお金は入らないどころか、持ち出しになってしまうというわけです。
このように大学が社会・金融業界の荒海に漕ぎだすには、様々な経験が必要です。しかし、漕ぎ出さなければ、学びはありません。今年、北陸のアカデミアも、荒海に漕ぎ出したのです。だからこそ、今後、得られる経験を糧としていきましょう。
コラム企画は毎月第4木曜日に更新。
次回は2025年1月30日(木)に、金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任准教授 佐々木 淑貴 先生のコラムを公開予定。
