
生放送番組「生徒会ライブ2024」 準備の裏側
皆さん初めまして。N高等学校の川邉哲平(TEPPei)と申します。
今回は先月学園のYouTubeチャンネルにてライブ配信した番組「生徒会ライブ2024」の準備の裏側を、大量の画像と共に振り返っていければと思います。
※この記事は私の自慢が4割、生徒会の自慢が3割、ノウハウ共有が2割、良い意味での愚痴が1割です。
その前に、まずは簡単な自己紹介を。
川邉哲平 - Teppei KAWABE(17歳・高校3年次)
N高等学校 7期生で通学コースに所属しており、現在は週3でキャンパスに通う。特技はドラム演奏、趣味は映像制作・グラフィックデザイン・茶道(表千家)。
高校在学中は第1期生徒会の役員をさせていただいたり、磁石祭2024(N高S高N中等部合同の文化祭)の実行委員としてクリエイティブを担当したり、通学コースキャンパスにてイベントの実行委員をしたりしている。
続いてN高の生徒会の紹介も。
N/S高では、生徒主体の活動を盛り上げて学校生活をより充実させることを目的として「生徒自身が決めて本当に実行できる生徒会」をコンセプトに、2022年11月、生徒会を設立しました。
N/S高生徒会は国内最大規模となる生徒数26,000名の代表として、生徒自身が学びたい課外学習・特別授業の企画、卒業式や文化祭等に招待するゲストの選定、学校生活におけるルールの制定・変更などさまざまな決済権限を持ち、活動します。各活動の実現のために、年間1,000万円の運営予算が用意されています。
番組の概要
「生徒会ライブ2024」は、第2期生徒会の1年間の活動の振り返りを主な目的として、生徒会役員自身が中心となって制作した番組です。今年は「あなたと生徒組織をつなぐ、つなげる。」というテーマで、在校生・入学検討者・支援者などの方たちに、日々進化する新しい生徒主体組織への関心を持ってもらいたいという思いで内容を組みました。
「今年は、ということは昨年(第1期)も番組を配信したのか?」と思われた方、そうなんです。私が役員を務めていた1期でも同様の番組を作っていました。
生徒会の活動を通して学園の魅力を発信📷
— N/S高生徒会 @生徒会ライブ2024アーカイブ公開中! (@kdg_seitokai) October 2, 2023
「N/S生徒会ライブ」 アーカイブ配信中📷コンテスト・歌舞伎/お笑いツアー・ひろゆき氏とのディベート対決など、数々の企画の裏側を第1期役員が語り尽くす!
最後には感動のフィナーレが📷N予備校でどなたでもご視聴いただけます📷https://t.co/LrwMEsDaOH pic.twitter.com/soKrr0TfYw
(絵文字が全部📷になってしまっているのはお見逃しください…)
この2つの番組をザッと見ていただくと、今年は昨年よりも内容、演出、クリエイティブ等々の面で大幅にクオリティが上がっていることがお分かりになるかと思います。
それこそが、1期役員である私が2期の「生徒会ライブ2024」の制作を手伝った最大の理由です。
プロジェクトの始まり

番組制作のプロジェクトは嘘みたいに早くキックオフしました。実に放送の9ヶ月ほど前です。
それ以前に、後にプロジェクト代表(番組で言うとチーフプロデューサーの立ち位置)となる役員の方とは、1期が配信した「N/S生徒会ライブ」について、楽しかったこと、大変だったこと、しんどかったこと、悔しかったことなど、かなり密に話をしていました。

上品なラーメンをすすりつつ、こちらを向いて真剣に聴いてくれていたことを覚えています。期待した成果が出なかった1期の姿を見てもなお番組の価値を感じ取ってくれたことが、早期のキックオフにつながったのだと勝手に思っています。
構成

どのような内容の方向性でいくかはプロジェクトの立案時点でおおよそ決まっていたので、具体的にどの施策・企画を取り上げるか、どこをVTRにしてどこをスタジオのトークにするのか、全体を通して情報の密度のバランスをどう取るか、などを細かく詰めていきました。構成が確定したのは6月中旬(!?)。放送1ヶ月前くらいまで何度も何度も修正をしていました。
こちらが、何を何秒でどのような形式で伝えるか、そして担当ディレクターや制作ステータスをまとめたスプレッドシートのキャプチャ。

細かすぎて見る気が失せそうですが、実はもっと縦横に長いです。
どのような写真・動画素材が必要なのか、その使用許諾はどこから取れば良いのか、スライドやVTRは誰がいつまでに作成するのかなど、一つのコーナーだけでも取り扱う情報は莫大になります。
それらを記憶・議事録・Slackのメッセージ・Zoomのレコーディングでバラバラに管理すると、都度情報の収集や整理をする必要が出てきますよね。そこになるべくリソースを使わないよう、多少細かくなってでも一つのシートに一覧化しておくのは大切だと考え、そうしていました。
デザイン
様々なクリエイティブ(VTR・テロップ・スライド・広報画像等)を作り始める前に、デザイン・デザインシステムを作っていきます。デザインやクリエイティブと言うと、よく“センス”とか“感性”という言葉が聞こえてきますが、私が制作に関わる案件では見た目のスゴさ(抽象的)よりもロジック(客観的)を重視しています。見た目のスゴさでは校内にいる“スゴイ人”に絶対負けますしね…
キービジュアル
まず何をしたかというと、デザイン担当の役員を集めて付箋ワークをしました。


これまで生徒会が作ってきたクリエイティブはどんなものか
それぞれどんな意図でそのデザインになったのか
生徒会に対して持たれているイメージ(アンケート結果)と自分たちが出していきたいイメージ、そして現状はどう違っているか
その上で番組の雰囲気はどうするべきか
その雰囲気を実現させるためのデザイン要素とは?
など、2時間ほどかけて一つ一つの「なぜ」を潰すように丁寧に言語化していきました。“言語化”は、普段から大量の資料を作ったりプレゼンをしたりしている役員の得意分野です。


次は付箋ワークで出た断片的な要素を、具体的な色・形に落とし込んでいく作業。(一人でやってしまいましたが、複数人で進める力も身につけたいです。)
殴り書きのメモを見返すと、形は円で広がり・繋がりを、色はカラフルにしたい気持ちもありつつどこかで共通点を持たせたかったのだろうな、というのをなんとなく感じます。
そうして出来上がった初稿がこちら。

無理矢理個性を出そうとして無個性になってる感!!(?)
はい、ロジックロジックとは言いつつも、うまく言語を落とし込めなかったためにこのような違和感を感じるものが出来上がってしまいました。
担当役員から3通フィードバックを受け、もう少し“色”を前面に出し、形に2期生徒会の基幹デザインに使われている扇を取り入れて完成したのがこちら。
#生徒会ライブ2024 放送のお知らせ
— N/S高生徒会 @生徒会ライブ2024アーカイブ公開中! (@kdg_seitokai) June 28, 2024
生徒会のこれまでの成果を発信!
🧲#磁石祭2024 初協賛獲得!波乱の8ヶ月間
㊗️#日本生徒会大賞2024 特別賞!挑戦の舞台裏
📣実行委員代表が語る!生徒組織の魅力
など盛り沢山でお届け〜
7月19日(金) 18時〜ライブ配信
絶対お見逃しなく✨https://t.co/5bWfKrOlio pic.twitter.com/kE2cCrqw7y

少なくとも初稿よりかは、すんなり目に入ってくるものになったと思います。
デザインガイドライン
そのキービジュアルのデザインをいろんなところに展開していく上で必要なのがガイドライン。一つ一つのデザイン要素の意図や使用方法を説明し、番組デザインの利用促進と制作物のクオリティ担保を目的として作成しました。





結局このガイドラインは使われたのか、という話ですが、そもそも実務面でのデザインを担当したのが私くらいだったので、ほとんどの役員はファイルを開きさえしなかったと思います。
・・・そういうとこだぞ川邉。
テロップ
視聴者にとって重要なテロップも作成しました。今はどんな場面なのかをわかりやすくするサイドテロップ(左上)、VTR中で誰が話しているのかをわかりやすくするネームテロップ(左右)、スタジオトーク中にお知らせなどを出す帯テロップ(下)の3点は、番組のデザインに合わせて作成しました。



少しデザインとは逸れますが、テロップの文言にもこだわりました。新聞のラテ欄(番組表)を参考にし、決められた文字数の中で魅力的なフレーズを作るためにどのように単語を組み合わせるか、ギリギリまで練りました。

スライド
MCブースのところに表示していたスライドは、極力文字を入れず、写真やグラフィックを大きく配置するようにしました。Zoomで画面共有をするのとは違って、カメラが頻繁に切り替わったり、そもそも視聴者に文字を読むというある種の“ストレス”を与えないようにしたかったり、というのが理由です
各コーナーの担当役員に作ってもらったスライドは、はじめは文字が多く写真が小さい、番組で使うにはあまり適していないものでした。これは担当役員のセンスがないという話ではなく、スライドの制作を依頼した際に「いつ・どこで・どのように映されるか」を伝えなかったのが原因だと思っています。今回は伝える以前に、そういった細かな話し合いができていませんでした。
ちなみに後から「スライドはこういうレイアウト・情報量で作ってほしい」と伝えた際、「もっと早く言ってよ!」「川邉の方針じゃなくてちゃんと総意取ってよ!」と怒られてしまいました。そりゃそうだ。
VTR
番組の肝であるVTR。今年は番組尺に占める割合を、1期の27%から9ポイント増やし36%にしました。(だいたいの数値です)
私が担当したもので特にこだわったのが、番宣CMと自己紹介中のモーショングラフィックス(VTRとはちょっと違うかも知れませんが)。
📺7月19日(金) 18:00~ 生配信⚡️#NS高生徒会 活動成果を生徒自らが発信📢
— N高等学校・S高等学校【全国69キャンパス】 (@nhigh_info) July 12, 2024
【N/S高 #生徒会ライブ2024 】
🧲#磁石祭2024 協賛獲得💪波乱の8ヶ月間
㊗️#日本生徒会大賞2024 特別賞の舞台裏
👥実行委員代表が語る💬生徒組織の魅力
…など盛り沢山でお届けします‼️
🔻番組URLhttps://t.co/rWLljgw497 pic.twitter.com/dECBAwjzEm


他にもコーナーのVTRを制作しましたが、生徒会外の8人の方に編集を手伝っていただいたのでとても助かりました。ただ、おおよその構成だけ伝えて残りの細かな部分は編集者の方に任せっきりになってしまったため、こちらが伝えたい内容とできあがったVTRに相違が出てしまい、かなりの部分を修正しました。こちらは大きな反省点です。

限られた時間の中で伝えたい情報を過不足なくいれつつ、 あとのスタジオトークを活かせるようなVTRを作るのは難しい作業です。また、合宿や磁石祭パートのように、何十時間の映像と何百枚の写真を見てどのシーンにどの素材を入れ込むかを考えるようなものは、どれだけ頭がさえていてもかなりの時間がかかります。
台本

台本というと台詞が書かれている紙、というイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、実際は台詞に加えてどのカメラが何を写すのか、スライドを切り替えるタイミング、VTRやBGMを流すタイミング、各マイクをオン/オフにするタイミング、テロップを表示させるタイミングなど、いろんなことが書かれています。カメラ、音声、スイッチャー、テクニカルディレクター(?)など、配信の技術面をサポートいただく方(外部会社のスタッフさん)に配信中どう動いてほしいのかは、こちらから詳しく要望を出さないといけないのです。
それほど大切な台本にもかかわらず、全ての台詞の書き込みが終わったのは、実は当日の朝でした。担当役員に作成を依頼したのが本来の締切2週間前、放送日の3週間前ということもあってタイトだったのもあるかと思いますが、その期間で対応できるだろうとリソースを誤算してしまいました。
放送前日の夜にZoomでリハーサルをやったのですが、そこで「スゥ〜、書いてませんでしたね(汗汗)」「明日の朝まで書ける?」「無理」「まあそうだわな」というやりとりもあったため、もう諦めようと思いました。
しかし朝起きて台本を見ると、なんと前日の夜まで真っ白だったページが綺麗に埋められているではありませんか!
なんだ書けるんじゃないか、と思ったのと同時に、、、、、、
一晩で書けるなら期限までに書けよ!!!!!!!!!!と。
アドレナリンが出て書けちゃいましたじゃねえよ!!!!!と。
…すみません、口が悪いですね。ちょっとムカついてしまいました。
終わったことですし、タイムスリップして過去に戻ったところでこのギリギリ体質はすぐには改善できないだろうと思うのですが、昨年の自分がまさにアドレナリンに頼り切ったピンボール人間だったので、その精神的な反省点と改善策を引き継げなかったのはとても反省しています。
広報
完全なる私の主観ですが、2期は大規模な施策を動かしている割には在校生への発信をマメにしない、そして労力をかけている割にはそこから生み出された成果の“自分たちからの”アピールに消極的な印象があります。複雑な事情があるのかもしれませんが、もったいない!!!
そういった背景があるからか、生徒会ライブの広報もスムーズにはいきませんでした。担当役員のキャパシティが足りなかったというのが一番の原因ではあるのですが、一度に多くの依頼を投げてしまったことにより、優先順位をつけて作業してもらえなかったというのもあると思います。VTRといい広報といい、私には指示力がないなと痛感しました。ないというか、情報量の良い案配を見つけられないというか。

迎えた当日
東京の某社オフィスから配信しました。私も現地に出向き、タイムキーパー兼フロアディレクターをしていました。

放送直前まで本当にバタバタしていました。
胸元につけるネームプレートやコサージュを用意する人、スクリプター(台本を表示するモニター)に映すドキュメントを作る人、放送中のXへの投稿文を作る人、台本の細かな言い回しを修正する人、お土産を配る人、職員さんに絡む・絡まれる人など…

当日朝まで徹夜して台本を書いた人もいたでしょう。無理難題な要求をずっと浴びせられ続けて、逃がしようのないストレスを抱えていた人もいたと思います。そういうこともあって、役員のみんなが楽しく過ごしてくれるかが一番心配でした。
しかし、そこは2期のチームワーク。リハーサルも本番もずっと笑っていてくれました。本当に良かった…
振り返り
もちろん放送して終わりではありません。ちゃんと振り返りをしました。
視聴データや制作関係者へのアンケート結果を分析したり、それぞれのセクションごとにKPTを付箋に書き出したり… 自分たちでやってきたことの幅が広すぎる分、振り返りもなかなか経験しないほどの細かさでやっていきました。

最後に
最後まで読んでいただきありがとうございました。
いろいろ書きましたが、イチ高校の生徒組織にここまで全力を捧げている人がいること、役員のみんなは本気で物事に取り組んでいるということ、ネットの高校でもこういう類の青春を送ることができること。
こういったことが伝わっていれば幸いです。
また、捉え方次第では自己満の世界だとか、組織を私物化していると思われても仕方がない部分があるかもしれません。そこには反論できません…
しかし、根底には本当に学園が好きで仕方がない気持ちがあるということや、生徒会を活用して本気で学園をよりよくしていきたいと思っていることを知ってもらえたら嬉しいです。
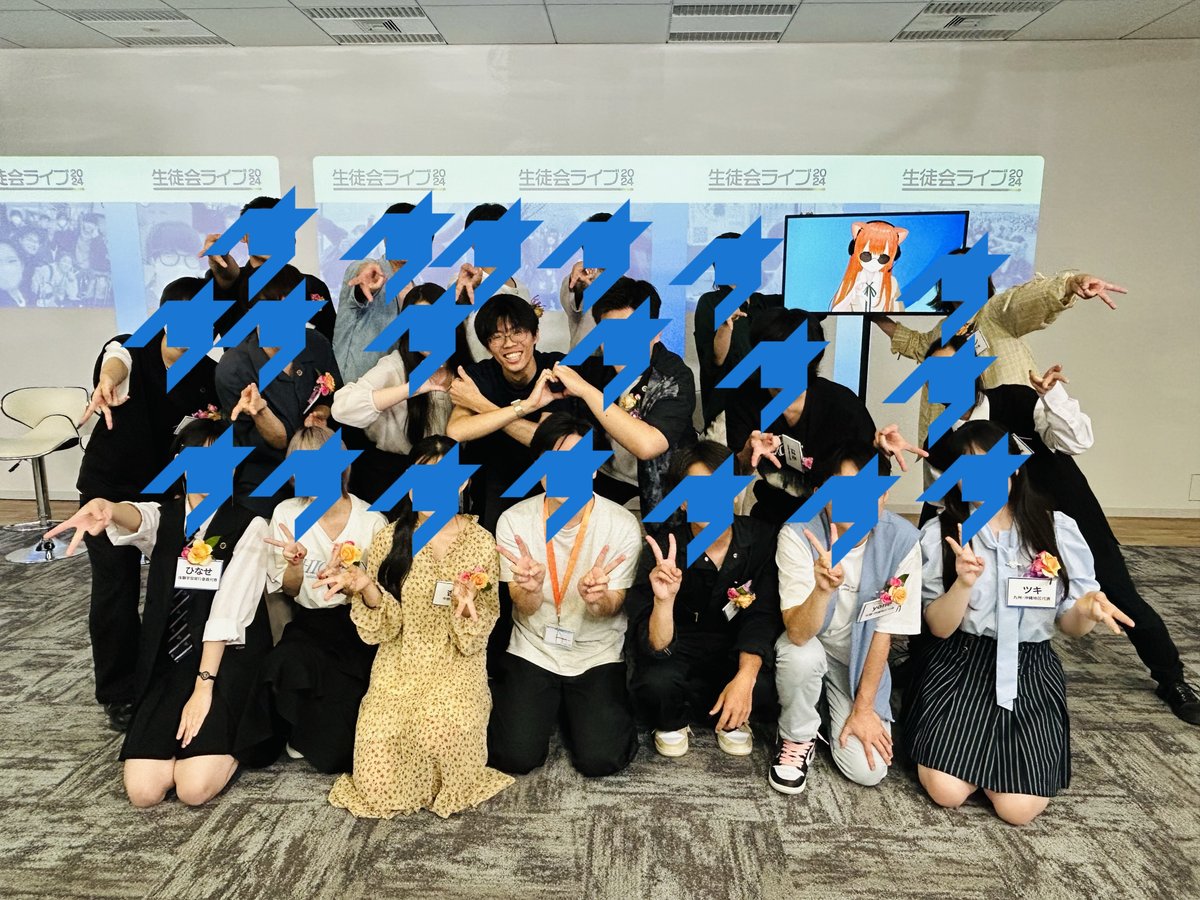
次はどんな楽しいことをしようかな。
※記事中の全ての画像は、生徒会役員会から成果発信としての使用の許可を得た上で掲載しています。
