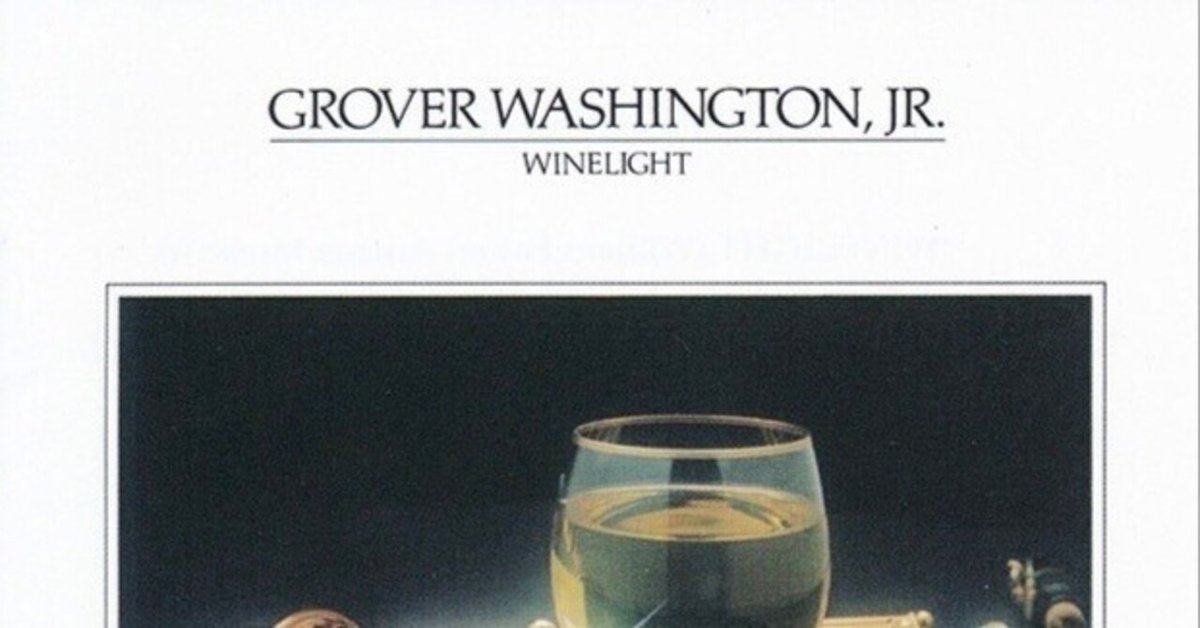
ワインライト/グローヴァー・ワシントン・ジュニア
サックス奏者グローヴァー・ワシントン・ジュニアの80年録音作品『ワインライト』を取り上げましょう。
録音:1980年6月、7月
スタジオ:ローズバッド・レコーディング・スタジオ、ニューヨーク
エンジニア:リチャード・オルダーソン
プロデューサー:グローヴァー・ワシントン・ジュニア、ラルフ・マクドナルド
レーベル:エレクトラ
(as, ss, ts)グローヴァー・ワシントン・ジュニア (Fender Rhodes)リチャード・ティー (clavinet)レイ・チュー、(clavinet, Fender Rhodes)ポール・グリフィン (Oberheim)エド・ウォルシュ (Oberheim, arr, conductor)ビル・イートン (g)エリック・ゲイル (b)マーカス・ミラー (ds)スティーヴ・ガッド (conga, perc, Syndrums)ラルフ・マクドナルド (steel drums)ロバート・グリニッジ (backing vocals)ヒルダ・ハリス、イヴォンヌ・ルイス、ウランダ・マックラフ (lead vocals)ビル・ウイザース
(1)ワインライト (2)レット・イット・フロウ(フォー・”Dr. J”) (3)イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ (4)テイク・ミー・ゼア (5)ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アス (6)メイク・ミー・ア・メモリー (サッド・サンバ)

グローヴァー・ワシントン・ジュニア、11作目のリーダー作に該当し当時のフュージョンブームもあり、アルバム自体空前の大ヒット、ビルボード・トップ・ジャズ・アルバム1位を記録します。
収録曲ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アスも全米ポップチャート2位、そして82年のグラミー賞ベストR&Bソング賞を受賞する快挙を遂げます。
もともとグローヴァーの作品制作は、R&Bのテイストを基本にジャズ・フレーヴァーをスパイス的に含ませ、取り上げる楽曲は心地よさを最優先としながら、緻密なアレンジ、構成をさり気なく織り込み、高度な音楽性を潜在させつつも耳に自然に入るように作られています。
演奏する本人たちは意識していないでしょうが、スムース・ジャズというカテゴリーで括られています。
制作スタッフやグローヴァー自身はアルバムのセールスの事を当然考えているでしょう。ビジネスも大切ですが、兎にも角にもナチュラルな音楽を演奏し、レコーディングしよう、アルバムを作ろうという姿勢を感じます。
演奏者が楽しまなければ、オーディエンスにアピールすることは出来ません。例えばレコーディングの休憩時、スタジオブース内ではさぞかし笑い声が聴こえ、快活な会話がなされていた事でしょう。自分の経験からも現場の雰囲気の大切さ、その延長線上にバンドの一体感、良い音楽の礎が作られるのを知っています。
本作の豊かで明るい、仄暗さも隠し味で加えられた、上品でおおらかなムードは、グローヴァーともうひとりのプロデューサー、ラルフ・マクドナルドの持ち味に由来します。
グローヴァーのプレイ自体はホットに、盛り上がるところはひたすら大胆にテンションが上がりますが、実際は大変クールに、演奏を俯瞰しながらイメージを確実に織り込むべく、計算尽くで臨んでいるように感じます。
演奏は決して破綻をきたさず、ひたすら予定調和を歩みます。そのためプレイに意外性を望むことは出来ませんが、そこはカテゴリーとしてのスムース・ジャズ、その創始者とも言われるグローヴァーの演奏ですから。
聴き心地がよく、家庭で寛ぐ際のイージーリスニング、ドライヴ中の車内でのBGMとして打って付けの内容を表出してます。
彼はテナーがメインのサックス奏者ですが、スムース・ジャズのサックス奏者全般と同様にアルト、ソプラノも使い分け、異なったカラー、ニュアンス、サウンドを聴かせます。しかもそのいずれもが艶のある素晴らしい音色、特にテナーの極太感は他の奏者から抜きん出ています。
音色に対する大変なこだわりを感じますが、使用楽器、セッティングを紹介しましょう。
テナーの楽器本体はコフのゴールドプレート、マウスピースはベルグ・ラーセンのハードラバー130/0、リードはリコーロイヤルの5番。ソプラノもコフのブラックニッケル・プレート、マウスピースはラニヨン8番に同じくリコーロイヤル5番、アルトはセルマー・マークⅥ、マウスピースはニューヨーク・メイヤー7MM、同様にリードはリコーロイヤル5番、これは流石にワールドクラスのハードなセッティング、それ故のオーディエンスを惹きつけてやまないサウンド・プロダクトです。
ウェイン・ショーター、ベニー・ゴルソン、チャールス・ロイド、ジョー・ロヴァーノたちも引けを取らないハード・セッティング・テナー奏者、アルトがメインの奏者ではまず考えられないマウスピース・オープニングの広さ、リードの硬さです。
グローヴァーの演奏を映像で観ると、身体を揺れ動かしながらもタフな仕様のサックスを確実にコントロールしています。ただソプラノで時折ピッチが上擦るのを感じるのは、コントロールの難しい高音楽器ソプラノで、どうしてもアンブシュアに力が加わってしまうからです。
オープニングの広いマウスピースを吹奏時に力を入れる、それこそ噛んで吹いてマウスピースのオープニングを狭めるのでは意味がありません。
彼はテナーではアウト・オブ・コントロールに陥る事はなく、安定した奏法に起因する腹式呼吸の確実さ、脱力感から得られる常にリラックスしたプレイにより、豪快で艶っぽい音色を提供しています。
そしてテナー・スタイルですが、テキサス・テナーの流れを汲むホンカー・スタイルに属します。
ホンカーの定義については以前にも紹介しているので、ここでは簡単に。
イリノイ・ジャケー、アーネット・コブ、バディ・テイト、ウィリス・ジャクソン、エディ・”ロックジョー”・デイヴィス、デヴィッド・ニューマンらに代表される、太く豪快に、熱くアーシーなブロウを信条とするテナー奏者の事を指します。
スタンリー・タレンタイン、ジーン・アモンズ、ウィルトン・フェルダー達はホンカーの中でもジャズ寄りのプレイを行い、ジョージ・アダムスやジェームズ・カーターは、フリージャズ寄りのホンカーと言えましょう。
今までに挙げたテナーマンは全員が黒人ですが、白人ユダヤ系のマイケル・ブレッカーのプレイにもホンカーの要素を十分に見出す事が出来ます。
グローヴァーもジャズ要素が強いホンカープレイを行いますが、ホンカーの条件としての「委細構わず熱くブロウを行う」において、一歩退いたプレイを行うため他とは異なるテイストを表出します。ハードなプレイとド派手なパフォーマンスで、オーディエンスを興奮の坩堝に誘うウィリス・ジャクソンとは、真逆の立ち位置と言って良いでしょう。
参加ミュージシャンも本作のようにスティーヴ・ガッド、マーカス・ミラー、リチャード・ティー、エリック・ゲイル、ラルフ・マクドナルドたち当時のスタジオ、ライヴ・シーンで活躍中のオールスターズ、フュージョンやスムース・ジャズの演奏を任せたら右に出るもの無し、共演者の人選にも配慮がなされています。
これらが作品発表を経るごとに洗練され、より良いアルバム作りを重ねる事が出来、本作に於いては時流に合致したことで彼の代表作となり、最大のヒットを収めました。

それでは収録曲について触れて行く事にしましょう。
1曲目表題曲ワインライト、本作の全曲アレンジとコンダクトを担当したウィリアム(ビル)・イートンのナンバーです。
冒頭エレクトリック・ベースにフランジャーをかけたスラップ・サウンド、ギターのパターン、オバーハイム・シンセサイザー、印象的なバスドラム、パーカッションが織りなすイントロが既に心地良いです。
アルトによるテーマが開始されますが、印象的な音色です。アルトサックスとは思えない太さ、これはテナープレイがメインなサックス奏者ならではの特徴であります。ソニー・スティットしかり、カーク・ウェイラム、ウィルトン・フェルダーも同じです。
ダークさと相反するブライトネス、付帯音とコク、ハスキーさ、複雑な鳴りの成分が絶妙なバランスで一体化しています。そこにベンドやグリッサンド、音量のダイナミクス、様々なニュアンスが織り込まれ、楽曲自体の素晴らしさもありますが、アルトのメロディ奏、リズムセクションとのブレンド感は申し分ありません。
アドリブソロに入り、グルーヴが変わります。マーカス・ミラーのベース・ワークが要となり、バンドを牽引しています。
マーカスはこのレコーディング時21歳になったばかり、そうとは信じられない熟練と成熟ぶりを聴かせますが、彼の叔父が名ピアニスト、ウィントン・ケリーです。音楽一家に育ち、幼い頃から良い演奏に触れつつ英才教育を受けていたのでしょう。以降もずっと第一人者としてミュージック・シーンに君臨します。

次第にサックスソロは熱を帯び、音量が大きくなり始め、フラジオ音も含めて音域も上がります。にも関わらずリズムセクションは淡々とグルーヴを繰り出すのみ、ガッド、マーカスのコンビならばソロイストのフレーズに機敏に反応するはずですから、これは予めリズムセクションを録音し、サックスソロを後からオーヴァーダビングした演奏に違いありません。
そう考えるとリズムセクションも同時に演奏していない可能性があります。ギターやキーボードはオーヴァーダビングでも全く問題ありませんし。
グルーヴを合わせるために、少なくともドラムとベースは同時に録音している可能性はありますが、ガッド、マーカスの二人はどのような状況下でも求められるベストなプレイを提供出来るミュージシャンなので、実際のところは分かりません。
後テーマを迎えリズム隊は一度音量を下げ、エンディングに向かいますが、マーカスはアウトロ中にフィルインを縦横無尽に挿入しつつプレイ、しかしグローヴァーの方はそれを意に介さず自身のストーリーを吹き続けます。
2曲目レット・イット・フロウ(フォー・”Dr. J”)、Dr. Jとはニューオーリンズ出身のピアニスト、ヴォーカリスト、ドクター・ジョンの事、彼に捧げられたはグローヴァーのナンバーです。
ここでもマーカスのベースがアクティヴに動き、楽曲のムード、サウンド、グルーヴを決定付けます。対してガッドはシンプルにリズムを刻み続けますが、シャープさと安定感、時たま繰り出すフィルインが音楽的で、小粋な印象を受けます。
マクドナルドのパーカッションはまさに音楽を色付けするが如きセンスで、楽曲をゴージャスに飾り付けます。
ゲイルのギターも職人芸的な巧みさを隠し味として表出させ、音楽を豊かにしています。
グローヴァーは再びアルトサックスを用いてテーマを奏でますが、ここでは涼しげで哀感漂うブロウから始まり、展開部では力強さとパッションを感じさせるプレイへと変化します。
今一度主題部に戻りその後ソロパートへ、マーカスのスラップが次第に白熱しますが、ガッドのプレイも随所にテンションを感じさせます。
日野皓正氏80年作品『デイドリーム』収録の名曲スティル・ビ・バップ、そこでのデイヴ・リーブマンのアドリブソロについて、アルバムで演奏したガッドの雑誌インタビューを読んだことがあります。
リーブマンのソロはオーヴァーダビングだったそうで、ガッド曰く「ここのソロは誰が演るんだい?デイヴね、オッケー、彼が盛り上がるところをイメージしてプレイするよ」のような発言だったと思います。
誰かがソロをオーヴァーダビングするに際し、恰も同時演奏のクオリティを出すべく、イメージしてベーシックなトラックを録音しておく。この事はスタジオミュージシャン誰しもが出来ることではありません。
ガッドならではの、百戦錬磨で培った彼の音楽性が成せる技、力量であると思います。ここでのガッドのプレイもグローヴァーの演奏をイメージして叩いているに違いありません。
噛み合っていない部分も無くはありませんが、何ヶ所か二人がアクティヴに動く部分が合致しています。この事はラストテーマ後のプレイでさらに顕著になり、マーカスもグローヴァーのアドリブ想定に加わっているのか、ガッドに合わせて同じベクトルを描いてプレイしているのか、いずれにせよスリリングな展開を聴かせています。

3曲目イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴは、ラルフ・マクドナルドとウィリアム(ビル)・ソルターの共作、ソルターはマクドナルドの曲作りのパートナー、長年コンビを組んでいます。
このふたりに加えて時に作曲し、主にアレンジやオーケストラの指揮を手掛けるのが、1曲目の作曲者ビル・イートン、60年代初頭ハリー・ベラフォンテのグループで一緒になった3人は意気投合し、アルバム制作、プロデュース等の共同作業を手掛けるチームを組んだのだそうです。
米国にはこのようにシーンの裏方で活躍し続けるミュージシャンが大勢存在します。表舞台に出るミュージシャンの多さ、アクティヴさは言うまでもありませんが、彼らの様に有能な裏方の貢献があってこその、米国音楽シーンと言えましょう。
リチャード・ティーのフェンダー・ローズによるイントロ、そこにエリック・ゲイルのギターが絡みます。
グローヴァーはソプラノでテーマをプレイ、楽器の特性上メロウさが深まります。
歌詞が付いているかの様なメロディアスなナンバー、冒頭のメロディ・ラインはきっと曲名を歌っているのでしょう。
「歌の無い歌謡曲」とはよく言ったもので、楽器にヴォーカルの部分を演奏させる形態は古今東西ありましたが、歌っているが如きグローヴァーのサックスにメロディを演奏させれば、ヴォーカリストとは違った説得力を発揮する事でしょう。
テーマ奏後はガッドのドラミングがアクティヴになります。ソプラノはステイしつつ次第にヒートアップしますが、ラストテーマに向けて山場を設けた後、緩やかにディクレッシェンド、インタールード・セクションを経てラストテーマへ入ります。
ガッドの潔いフィルインの後は再びムーディなソプラノソロが始まります。フラジオ音はソプラノでは難しい奏法ですが容易くヒットさせつつ、華麗にプレイします。フェードアウトが始まる頃、ガッドのフィルインにグローヴァーが反応しています。

4曲目テイク・ミー・ゼアはグローヴァーのオリジナル、ここではテナーサックスが登場します。威風堂々とした音色は極太にしてハスキー、テナーサックス奏者の系図を確実に辿れる、伝統的にして、しかし誰もなし得なかったタフで極上なトーンです。低音域でのサブトーンの充実感が堪りません。
やはり彼のメイン楽器であるテナーは、排気量の多いアメ車の如く、どっしりとした安定感と確実なコントロールが成されています。
アーバンでありながら長閑さと哀愁を漂わせるテイストのナンバー、リズムセクションとのキメもナイスな佳曲、グローヴァーはレイドバックしつつ、ヴィブラート、ベンドを多用し、情感たっぷりに歌い上げます。
続くソロでは一転してストロングなグルーヴの上で益荒男振りを発揮、押し寄せる豪快なテナー・サウンド、オルタネート・フィンガリング使用から、音域も次第に上がり、通常音域よりも高いレンジを多用した、フラジオ祭りに突入します。
中低音域のチューニングに比べてフラジオ音のピッチがかなり低いのが、同業者の私には些か気になるところではありますが。
マクドナルドが率先して提示したクラーヴェをきっかけとして、サンバにリズムが代わり、疾走感溢れる展開へ。引き続き彼のカウベルやティンバレスが効果的にサポートします。
グローヴァーのソロは激しさを増し、ほど良きところで再びクラーヴェがプレイされ、元のリズムに落ち着きます。
ラストテーマへはごく自然な流れで収束しますが、先ほどの盛り上がりが嘘のように、たっぷりとレイドバックしたメロディ・プレイが心地よく耳に入ります。
アウトロは再び躍動感みなぎるプレイを聴かせ、じわじわと盛り上がりを感じさせます。マクドナルドがもう一度クラーヴェを提示しますが、ガッドは笛吹けども踊らず、再度のサンバ展開はくどいと判断したのでしょう、却下されました。その後フェードアウトです。
5曲目は本作のハイライト、ビル・ウイザースのヴォーカルをフィーチャーしたジャスト・ザ・トゥ・オブ・アス。ウイザース、ソルター、マクドナルドの共作になります。
印象的なイントロではさり気無くも美しいティーのフェンダー・ローズのメロディ、またここで聴かれるガッドのバスドラムの音色と的確なタイミングに、今更ながら心惹かれます。
演奏中継続して演奏される、作曲者マクドナルドによるコンガのプレイが、さりげなくとも楽曲に豊潤さを与えています。
マーカスのプレイもスマートなフィルインを交えながら、ツボを押さえた「まさにココ!」と言うビートの位置を提供しています。
その後ヴォーカルが登場、技巧派ではなく、派手さも特に感じられませんが、実直で味わいのある歌声、的確なタイム感には好感が持てます。
またコンパクトな声質のウイザースは、グローヴァーの重量感あるテナーサウンドともバランスが取れています。
女性コーラスの輪唱が入り、その後テナーによる印象的なメロディを持つインタールードが、オバーハイム・シンセサイザーの対旋律を伴い、オクターヴ下げて2度奏でられますが、サックス奏者の作品で、ヴォーカルをフィーチャーするに相応しいアレンジを聴くことが出来ます。
その後に控えているのが意外性に富んだスティール・ドラムのソロと、その後ろでの女性コーラスですが、これは斬新です!プロデュース力にしてやられました!
続くテナーソロへのクッションとしてワークし、哀愁を帯びたヴォーカル・ナンバーでの、テナー間奏の呼び込みに相応しい構成です。裏方3人組のプロデュースの妙と言えましょう。
スティール・ドラムの最後のフレーズを受け継ぎ、グローヴァーのソロがスタートします。女性コーラスはそのまま暫く継続しますが、テナープレイの盛り上がりと共に次第に消えて行きます。ソロは曲想とアレンジに合致しつつ、熱いスピリットをクールに表現しており、プレイの長さも加わりこれは歌伴の域を超えた、インストルメンタル演奏の範疇です。
マクドナルドは途中でカウベルを主体としたパーカッションで、コンガとは違った色付けを施します。
その後インタールードが再び演奏され、ダ・カーポしイントロに戻り、あと歌が始まります。
このままフェードアウトしFineする展開が通常ですが、3人組のアイデアは巧みです。この後に男性ヴォーカルの低音コーラスでタイトルが歌われますが、密かにこのコーラスは裏方3人組が歌っているのでは、と睨んでいます。男性コーラスのクレジットが特に無いことからも推測出来ますし、遊び心がありそうな面々ですので。
低音コーラスのメロディを引き継ぎ、グローヴァーの後奏が始まります。先ほどのスティール・ドラムのソロを受け継いだ事に韻を踏んだかのように。
その後もモチーフとしてメロディを2度ほど引用しソロを続けています。男性の低い声はまさにグローヴァーのテナーの音色、一貫した流れを感じました。
全米ヒットチャートに躍り出るだけの、キャッチーで緻密な構成を持つナンバー、様々な要素を織り込み、隠し味を加え、プロデュースという名の推敲、校正を行い、主体であるアーティストを映えさせるべく、裏方たちが楽しみながら音作りに励んでいる様を、この演奏から知る事が出来ます。

6曲目メイク・ミー・ア・メモリー (サッド・サンバ)はラストを飾るグローヴァーのナンバー、ここでは再びアルトをヴォイスに選びました。
イントロではゲイルのギターが必要最小限の音使いによる、テイスティなフィルを聴かせます。
エピローグに相応しい曲想はやはり哀愁路線、アルトの音色と音域が相応しいメロディ・ラインは、確実にソロのコンセプトにも反映されています。
ソロパートではパーカッションの持ち替えが常のマクドナルド、全体を見回しながらのカラーリングを怠りません。
グローヴァーのソロはジャジーなアプローチをスパイスとして交えながら、クールなホットさを存分に発揮、加えて表題曲の演奏よりも深い音色、スムースなプレイを聴かせていると感じ、この曲がアルバム冒頭に位置しても良かったのでは、とも思いました。
アルトソロ後には再びギターの「渋い」フィルインが聴かれ、ラストテーマへ。
イマジネイティヴなアウトロでのアルトソロは、やはりこの曲を作品冒頭に位置させても良いと感じましたが、表題曲の持つキャッチーさには一歩及びませんでした。
