
John Patittuci / John Patitucci
今回はベーシストJohn Patitucciの87年リリース、初リーダー作「John Patitucci」を取り上げてみましょう。GRP Label
b)John Patitucci ts)Michael Brecker p)Chick Corea synth)John Beasley synth)David Whitham ds)Dave Weckl ds)Vinnie Colaiuta ds)Peter Erskine vo)Rick Riso
1)Growing 2)Wind Sprint 3)Searching, Finding 4)Bajo Bajo 5)Change of Season 6)Our Family 7)Peace and Quiet Time 8)Crestline 9)Zaragoza 10)Then & Now 11)Killeen 12)The View


ジャケット写真の表面にはエレクトリック・ベースを、裏面ではアコースティック・ベースを携えたレイアウトが印象的です。ジャズベース奏者でエレクトリック、アコースティック両方を演奏するプレイヤーは少なくないですが、Patitucciのように両者のレベルが拮抗するプレイヤーはほんの一握り、文字通り両刀使いの先駆者にして現在も最先端のベース奏者です。しかも6弦という多弦エレクトリックベースを自在に操り、正確なタイム、グルーヴで超絶技巧のフレージングを繰り出すスタイルはギタリストの演奏を超えるほどのインパクトを与えます。ギターよりもずっと音が太いですからね。本作での登場はありませんでしたが、Akoustic Bandで聴かれるようなアップテンポでのアコースティックベースのスイング感の巧みさは他の追従を許しませんし、9曲目で聴かれるようにアルコソロも絶品です。05年Herbie HancockのDirections in Music来日コンサート時に楽屋を訪ね、Michael Breckerの紹介でPatitucciと話をしたことがありますが、明るく快活でフレンドリー、人を思いやる話しぶり、スマートさにはなるほどと、ファーストコール・ミュージシャンのオーラを感じました。
59年NY Brooklyn生まれ、10歳でエレクトリック、15歳でアコースティック・ベースを始め、早くからスタジオ・ミュージシャンとして活躍していました。85年Chick CoreaのElektric Band、89年Akoustic Bandと両方に参加し、Coreaの寵愛を受けその才能を開花させ、プレイヤーとして急成長を遂げました。Elektric, Akoustic Bandの間87年にCoreaの全面的サポートで本作品をGRPレーベルでレコーディング、収録12曲中10曲が自身の作品、1曲がCoreaとの共作になり、そのいずれもが佳曲です。参加メンバーもCoreaをはじめとして以降も度々共演を重ねることになるMichael Brecker、そしてDave Weckl, Vinnie Colaiuta, Peter Erskineという素晴らしい3人のドラマーが参加したドラム祭りでもあり(笑)、曲によって異なった色合いを出して作品のクオリティ向上に貢献しています。
Patitucciは現在までに14枚のリーダー作をリリース、いずれもが高いクオリティの作品で音楽性の幅の広さ、様々なジャンルを巧みに演奏する懐の深さ、作品を重ねるごとに深まる表現の度合い、常に進化を遂げているミュージシャンですが、本作でのフレッシュさはまた格別に心に響きます。初リーダー作は演奏家の原点と言えますが、ここではコンポーズ、サウンド作りとそのアイデア、ベース・ソロプレイとバランスの良さを提示、以降一貫したテイストを聴かせることになります。
それでは収録曲に触れて行きましょう。1曲目Growing、グルーヴが気持ち良いファンクナンバー、オーヴァーダビングによるベースのメロディが印象的ですが途中からRick Risoのフェイザーが掛かったヴォーカルが加わり、キャッチーでダンサブルな雰囲気を醸し出すことに成功しています。Patitucciのソロを大フィーチャーしたナンバーですが、それにしても上手いですね、この人!フレージングはギタリストを研究した節が窺われますが、むしろサックス奏者からの影響が顕著です。随所に聴かれるシンセサイザーが効果的に曲想をバックアップしています。
2曲目はよりテンポアップしたファンクナンバーWind Sprint、イケイケのドラムフィル、ド派手なスラップベース、これでもかと互いに呼応しつつバトルするベースとテナー、リズムセクションとのインタープレイ、入魂の演奏から我々はこういったタイプの楽曲を「ど根性フュージョン」と呼びました(笑)。ジャズ史上Michaelのテナーにバトルを挑んだベース奏者はこの人くらいかもしれません(爆)、憧れのサックス奏者との共演にそれまで描いていた夢を実現すべくバトルを提案したのでしょう、実に功を奏しています!ちょっと気になるのはテナーの録音、音像がやや引っ込み気味な点です。反してベースの音像はクリアーに聴こえます。Michaelのただでさえ凄まじいソロ、ベースと同じ定位ではバトルというシチュエーション上勝敗が確定してしまう(?)のを避けるために敢えて行われたのかも知れません。
91年出版された楽譜集「The New Real Book Volume Two」に、この曲の譜面が掲載されています。当時バンド仲間で嬉々として共有し「ど根性」の演奏を繰り広げた記憶があります(笑)

エンディングはDave Wecklの壮絶なドラムソロが聴かれますが、当時のドラムキッズ達の憧れのフレーズ満載の演奏です!みんなこぞってコピーしましたね!聴き覚えのあるフレーズのオンパレードですから(笑)
Dave Weckl

3曲目はへヴィーなダウンビートのスイング・ナンバーSearching, Finding、モーダル〜Coltrane Likeな曲想なのでColtraneが生涯追い続けた探求、発見という事でしょうか、Patitucci自身の音楽観にもオーヴァーラップさせているのでしょう。ドラマーがPeter Erskineに替わりますが、本作中ジャズ系のナンバーでは彼が起用され、フュージョン系はWeckl, Colaiutaと役割分担がなされています。曲中のベースラインはシンセベースでも演奏されているようで、リーダーはソロイストとしての参加、ギタリストのようにメロディをMichaelと演奏、さらにカッティング?やフィルインを入れ捲っています!Erskineのシンバルレガート、フィルイン、グルーヴ、どれも何て的確なんでしょう、あまりにもハマり捲りです!ソロの先発Michael、気持ちが入っています!2’15″あたりの、ぐ〜っと後ろに引っ張ったフレーズのレイドバックにその入魂ぶりが現れています!本物のテナー奏者は演奏に入れ込めば入れ込むほどタイムをタメるものなのです。Michaelの最後のフレーズを受け継いで続くPatitucciのソロもBurning!その後のCoreaのソロは超人的なタイム感を駆使した演奏、ピアノの音色が実にキラキラして音の粒だちが尋常ではありません!さりげにオルガン系音色のシンセサイザーのバッキングがオイシイです。この曲でもエンディングでドラムが大暴れ、Coreaも呼応してユニークなバッキングフレーズを連発、さぞかし演奏終了後メンバー同士で盛り上がったことでしょう。オーヴァーダビング無しでの演奏、かつTake OneでOKだったに違いありません。
Peter Erskine

4曲目はPatitucciとCoreaの共作によるBaja Bajo、共作とはいえ曲想としてはCoreaの方のテイストが強いのは致し方ないかも知れません。速いテンポのラテン〜サンバ、ドラマーはColaiutaに替わります。Wecklと比べるとColaiutaの方がビートがずっしりとしていて音符が長いように感じます。でもこれはどちらが良いという優劣ではなく、表現の仕方の個性の違いです。さらにWecklの方はフィルインやソロでしっかりとフレーズを叩いているので形が比較的明確ですが、Colaiutaはその都度のイマジネーションでドラミングしておりスポンテニアス、良い意味で不定形な表現スタイルです。Philly Joe JonesとRoy Haynesの違いと言うと分かり易いでしょうか、厳密なものでは無くあくまで雰囲気的にですが。Colaiutaはこの演奏中オーヴァーダビングでパーカションも演奏しています。ピアノとシンセサイザーによるテーマ演奏はシャープかつリズミック、とってもカッコ良いです!ソロの先発Corea、期待に違わぬハイパーな演奏でColaiutaもここぞとばかりに煽っています。CoreaとColaiutaの相性は抜群だと思うのですが、Coreaがリーダーでの共演は何故か92年Blue Note TokyoでのChick Corea Trio(ベースはPatitucci)ライブ等、ごく一時期限定に留まりました。Patitucciのソロも実に巧みですがCoreaのバッキングも全く聴き逃せません!Coreaの傑作「Friends」でのJoe Farrellのソロ時のバッキングにも匹敵〜主役を食ってしまうほどインパクトのあるバッキング!ラストテーマ〜エンディングはまさにCoreaサウンドのオンパレード、パーカッションもイケてます!
Vinnie Colaiuta
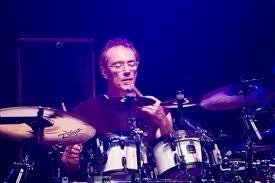
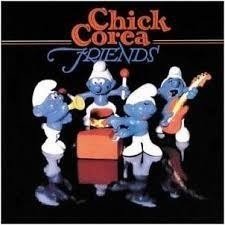
5曲目はChange of Season、ドラマーは再びColaiuta、ピアノがテーマを演奏しますがCoreaではなくここではDave Whitham、プロデュサーにしてマエストロCoreaの前で演奏するのはやり辛かったと思います(汗)、Whithamのピアノも素晴らしいですが、Coreaと比較するとどうでしょう、タイムの安定感や音色、フレージングにややぬるさを感じるのは仕方がないのかも知れません。ここでのベースソロはイってます!ColaiutaとJohn Beasleyのシンセベースのサポートと共に、リズムを細分化して微積分した(爆)ような緻密な演奏です!
6曲目Our FamilyはPatitucciとCoreaのDuo演奏、Coreaは全編Synclavierでパーカッションを担当しPatitucciが縦横無尽に6弦エレクトリックベースを演奏しています。よく聴くとCoreaは遊び心満載、巧みにラテンのリズムを繰り出しており、二人の楽しげな雰囲気が伝わってくる対話に仕上がっています。
7曲目はバラードPeace & Quiet Time、Michaelがここぞとばかりに歌い上げます。ドラマーはErskine、2, 4拍に入るスネアやシンバルのアクセントがオイシイところに入ります!Patitucci〜Michaelとソロが続きますが、やはりテナーの音像が引っ込み気味なのが気になります.
8曲目Crestline、Colaiutaのドラムが水を得た魚状態、適材適所です!Coreaのソロはどうしてこんなにも毎回イマジネーションに富んでいるのでしょう!素晴らし過ぎです!Colaiutaとのコンビネーションもバッチリでタイムの捉え方がまるで一卵性双生児のようです!Patitucciのソロ、ピアニシモからメンバー一丸となってジワジワと、ウネウネと、遠くから津波が押し寄せる如く、これでもかと盛り上がります!それにしても丁度良いところで次のセクションに行くものですね。
9曲目Zaragoza、この曲のみCoreaのナンバーです。Beasleyのリズミックなシンセサイザーのイントロが印象的です。アコースティックベースのアルコでのメロディ奏、ピチカートでの超絶ソロが聴きモノです!適度な小部屋内で録音された感が美しいベースの音色も、とても魅力的です。Patitucciの全編フィーチャー、作曲者自身のソロはありません。
10曲目Then & Now、Michaelのオンステージになりますが、彼のフィーチャーを想定して書かれたかのような、Michaelにまさにうってつけのナンバーです。この人のソロは実に様々な技や高度な音楽理論を駆使して行われていますが、淀みなくしっかりとウタ、ストーリーに仕上がっている点が驚異的、ジャズ的なテイストのフレージングもスパイス的に散りばめられ、そのバランス感にいつも感心させられます。
11曲目KilleenはPatitucci, Corea, Erskineのトリオによる演奏、本作中最もジャズテイストを感じさせるワルツナンバーです。アコースティックベースで初めにトリオ演奏を録音、その後エレクトリックベースによるテーマをオーヴァーダビング〜ソロプレイ、Coreaのソロの後にエレクトリックで再びソロを取っていますが、後ろでアコースティックが聴こえつつ、ここでは3者のインタープレイが行われているのでこの部分は初めにエレクトリックでソロを収録し、その後アコースティックをオーヴァーダビングしたと考えるべきでしょう。録音技術を駆使しつつアコースティックなジャズサウンドを自然に表現しています。
12曲目ラストを飾るのはThe View、アルゼンチンタンゴをイメージさせるリズムの上でBeasleyがシンセサイザーでソロを取り、ひとしきりあった後Patitucciのソロ、ラストもBeasleyのシンセサイザーでFineとなります。
