
スプリング/トニー・ウィリアムス
ドラマー、トニー・ウィリアムスのリーダー作1965年8月録音『スプリング』を取り上げましょう。
録音:1965年8月12日
スタジオ:ヴァン・ゲルダー・スタジオ、イングルウッド・クリフス、ニュー・ジャージー
エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー
プロデューサー:アルフレッド・ライオン
レーベル:ブルーノート BST-84216
(ts)ウェイン・ショーター (ts)サム・リヴァース (p)ハービー・ハンコック (b)ゲイリー・ピーコック (ds)トニー・ウィリアムス
(1)エクストラ (2)エコー (3)フロム・ビフォー (4)ラヴ・ソング (5)ティー

/トニー・ウィリアムス
鮮やかなオレンジ色と白のコントラスト、使用される文字にも橙色系を用いてこだわりを感じさせる統一感、極めてシンプルにして尚且つ効果的なジャケット・デザインは、ブルーノートの諸作を手掛けたリード・マイルスによるものです。
ブルーノートのレコード裏面に、ほぼ必ず掲載される米国ジャズ評論家によるライナーノーツが本作では省かれたのか、敢えての非掲載か、代わりにリーダーの写真が大きくレイアウトされています。
アルバム・タイトルが『スプリング』にも関わらず録音は夏に行われ、収録曲にも同名曲は含まれません。もっとも季節を表すとは限らず、ドラマーとしての動きの意味にも感じます。
ブルーノート諸作品中ジャケット、演奏内容共に異彩を放つ本作はトニー・ウィリアムス第2作目のリーダー・アルバム、録音当時若干19歳です。
18歳時の初リーダー作『ライフ・タイム』は前年64年4月録音されました。両作共に全曲トニーのオリジナル・ナンバーから成ります。

/トニー・ウィリアムス
ふたつの作品の仕上がりから、ドラミングは元より作曲、編曲の才能、そしてバンド・リーダーとしての素養をトニーが持ち合わせている事を物語っています。
当時のジャズ・シーンの猛者たちにして、ブルーノート・レーベルに不可欠なアーティストをサイドマンに迎え、自身の音楽をクリエイトしています。

本作の演奏形態としては60年代半ばの時代背景があり、モーダル、フリー、アヴァンギャルド、現代音楽からなります。
故に表現には高度な音楽性と理解力、演奏に関しては楽器を操る能力の高さ、優れたハーモニー感、リズム感、メンバーとのコラボレーション能力が必要となります。トニーには有り余る音楽的才能があり、年齢と経験からは信じ難いジーニアスを発揮し、プロディジー(神童振り)を見せつけます。
参加サックス奏者ウェイン・ショーター、サム・リヴァース、異色のツー・テナー・フロントに興味が惹かれますが、ジャズ作品の多くに存在する同一楽器によるバトル形式は用いられず、大きく異なる個性の発露によるコントラストを生かしたアンサンブル、アドリブソロの応酬となります。
またピアニストにはトニー生涯の盟友ハービー・ハンコックを迎え、ベーシストにはブルーノート・レーベルには珍しい人選、前作『ライフ・タイム』からの付き合いになるゲイリー・ピーコックが加わります。
このレコーディングの前後にマイルス・デイヴィス・クインテットがニューヨークのジャズクラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードに出演します。
その際マイルスとメンバーのロン・カーターがインフルエンザに罹患し、ライヴを欠席しました。
御大抜きでハンコック、トニーを擁したショーター・カルテットでの演奏になった訳ですが、ベーシストのエキストラにはピーコックが参加、本作のリヴァース抜きのメンバーです。恐らくトニーの推薦があったからでは、と睨んでいます。
因みにその時の演奏曲目にはハンコックのジ・アイ・オブ・ザ・ハリケーン、スタンダード・ナンバーのジャスト・イン・タイム、ショーターのオリジナルからオリエンタル・フォーク・ソング、ヴァーゴ、マイルスのフラン・ダンス等がチョイスされ、うるさ型のいない分メンバーそれはそれは伸び伸びと、且つクリエイティヴに演奏を楽しんでいます。

トニーのバイオグラフィーを紐解いてみることにしましょう。
1945年12月シカゴに生まれ、マサチューセッツ州ボストンで育ちます。多くの門下生を輩出しているドラム奏者、アラン・ドーソンに11歳で手解きを受け、早くも13歳からボストンの老舗ジャズクラブ、コノリーで音楽活動を開始します。
その際の共演者としてはオルガン奏者ジョニー・ハモンド・スミス、本作のテナーサックス奏者サム・リヴァースらが挙げられます。

ジャズクラブ・コノリー
転機が訪れます。62年11月彼が16歳の時にジャッキー・マクリーンに誘われニューヨークに移住します。翌63年4月マクリーンの代表作『ワン・ステップ・ビヨンド』を録音し、そのフレッシュで革新的なドラミングをジャズシーンに周知させます。
未成年のミュージシャンを自分のバンドに雇い入れるため、マクリーンはトニーの実家にまで行き、両親を説得したそうです。彼にとっては自己の音楽を遂行させるに相応しいドラマーを得た訳です。

/ジャッキー・マクリーン
しかし新たなサウンドを求めていたマイルスの目にトニーが留まり、間も無く彼のクインテットに抜擢されます。
マイルスの自叙伝にはトニーとの出会いが書かれています。
「そのすばらしさに一発でまいってしまった。ものすごい奴だと思った。聴いた途端、一緒にカリフォルニアに連れていきたくなったが、ジャッキーとの仕事が残っていた。だがそれさえ終わればこっちのものだった。ジャッキーも、オレのバンドでしっかりやってこいと言ってくれたということだった。オレはこのたいしたチビを聴いただけで、久しぶりにたまらなく興奮してきたのがわかった。」とまで述べています。
一方マクリーンにとっては好事魔多し、これから音楽を創造して行こうとした矢先です、さぞかしトニーの喪失に落胆し、ぽっかりと大きな穴が空いてしまった事でしょう。
マクリーンの音楽にはシャープでレスポンスの良い、センシティヴなドラマーが必要でしたから。
私見ですが、マイルスのバンドでしっかりやってこい、と言ってマクリーンがトニーを送り出したとは到底思えません。
想像するにマイルスは半ば強要して、トニーを自分のバンドのメンバーに引き抜きます。そしてメンツに拘るマイルスは対面上トニーがマクリーン・バンドを円満退職したかのように体裁を整えます。
マイルスはウェイン・ショーターを参加させる際にも、当時ショーターが在籍していたアート・ブレイキー・ジャズ・メッセンジャーズ、リーダーのブレイキーにかなり強引に圧力をかけて彼を獲得した経緯があります。
欲しいものはどの様な手段を使っても、何としてでも手に入れる、文字通り帝王学を身につけたマイルスならではのやり方に違いないと睨んでいます。

以降マクリーンのレコーディングにはロイ・ヘインズやビリー・ヒギンズ、クリフォード・ジャーヴィス、一貫したセンスを持つドラマーがチョイスされ、そしてジャック・ディジョネットに辿り着きます。

裏ジャケット
トニーのマイルス作品へは63年5月14日録音『セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン』が初参加になります。

/セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン
この時ハービー・ハンコック、ロン・カーター、ジョージ・コールマンたちクインテット・レギュラーも初参加、同メンバーでタイトル曲を含め3曲がレコーディングされます。
トニーのプレイは以降の壮絶さと比較すれば多少の硬さを感じますが、十二分に帝王マイルスの音楽に追従し、かつ自己表現を行っています。
8分音符がイーヴンに近いグルーヴでのトップシンバルのレガート、シャープにしてビートに喰らい付きつつのスピード感が堪りません。
フィルインやドラムスソロに於いて決まった形を敢えて排除したかの不定形さ、フレッシュなアプローチを常とするクリエイティヴさが際立ち、60年代以降のドラマーのプレイ・スタイルの礎を築きます。
50年代の実に多くのドラマーが様式美を追い求めてプレイを行い、定形を表現する喜びさえ彼らから感じ取れました。例えてみれば日本の夏祭りの太鼓演奏の如しですが、トニーのドラミングは真逆の立場に位置する不定形の極みです。
それにしてもこの時トニー17歳!何という早熟なミュージシャンでしょうか。
斬新で自由な発想、アプローチ、寄り添い感、音楽の展開方法、躊躇なき自己表現の発露、更にはいちドラムス奏者としてだけで無く、トータルなミュージシャンには不可欠な要素である作曲、アレンジ、そしてバンドを率いてメンバーに采配を振う統率力の素晴らしさ。新時代のリーダーの登場です。
この事は後に展開するパーマネント・メンバーによるレギュラー・バンド活動に顕著になります。
トニーに宿るイーヴンなグルーヴに派生したのでしょう、演奏形態は次第に刷新されロック・フォームに至り、その後フュージョンを経て、ピアノトリオ編成やクインテットによるジャズ演奏に一巡します。
作曲、編曲の才能は一段と冴え、85年6月録音トニーの作品『フォーリン・イントリーグ』収録の名曲シスター・シェリルやライフ・オブ・ザ・パーティの鮮烈さには、メロディ・メーカーとしての力量を痛感します。

/フォーリン・イントリーグ
95年12月録音『ウィルダーネス』、マイケル・ブレッカー、パット・メセニー、ハンコック、スタンリー・クラークたちが参加、シャイなトニーが心置き無く演奏を共に出来る精鋭を配したと言える作品です。
意欲的なトニーのオリジナルは更に進化し、多岐に渡るコンポーズのセンスはクラシカルなオーケストラ・アレンジにまで及び、その才能の発露に歯止めが効かない状態です。
当時トニーはクラシックのオーケストレーションを勉強中だったそうです。

/トニー・ウィリアムス
これから更に煌びやかなトニー・ウィリアムス・ワールドが開けて行くであろう、その矢先の97年2月23日、ひょっとしたら何か手違いがあったのかも知れません、胆嚢手術後に心臓麻痺で亡くなります。享年51歳でした。

それでは作品の内容について触れていく事にしましょう。前述の通り全曲トニーのペンに寄ります。
1曲目エクストラは急速調ブラシワークから始まります。蠢くようなツーテナーの咆哮と同時にベースも加わり、暫くの間テナー両者のソロが同時進行します。
フォームとしてフリーではあるものの、単に「せーの」で演奏を始めたのではなく、ここでは具体的なサジェスチョン、明確なモチーフの提示がトニーからあったように感じます。
テナーはリヴァースが退きショーターのソロがスタートします。リズムを様々に感じつつアップテンポのスイングに大きく乗り、巧みなラインを奏でます。
色々なモチーフ、フラグメントを提示しながらストーリー、彼なりの唄を感じさせるインプロヴィゼーションを披露します。タイムの揺れを設けながらのプレイにはリズム隊が一触即発でレスポンスを行います。
ドラムス、ベース、サックスのトリオ演奏、尚且つインテンポでのフリー・フォームには、オーネット・コールマン60年12月録音リーダー作『フリー・ジャズ』の手法に則っているように思います。
形態としてはフリー・ジャズではありますが、単なるフリー演奏ではオーディエンスを放置する事に成りかねず、メソッドを設けたプレイを行う事の重要性をトニーは熟知していたと思います。
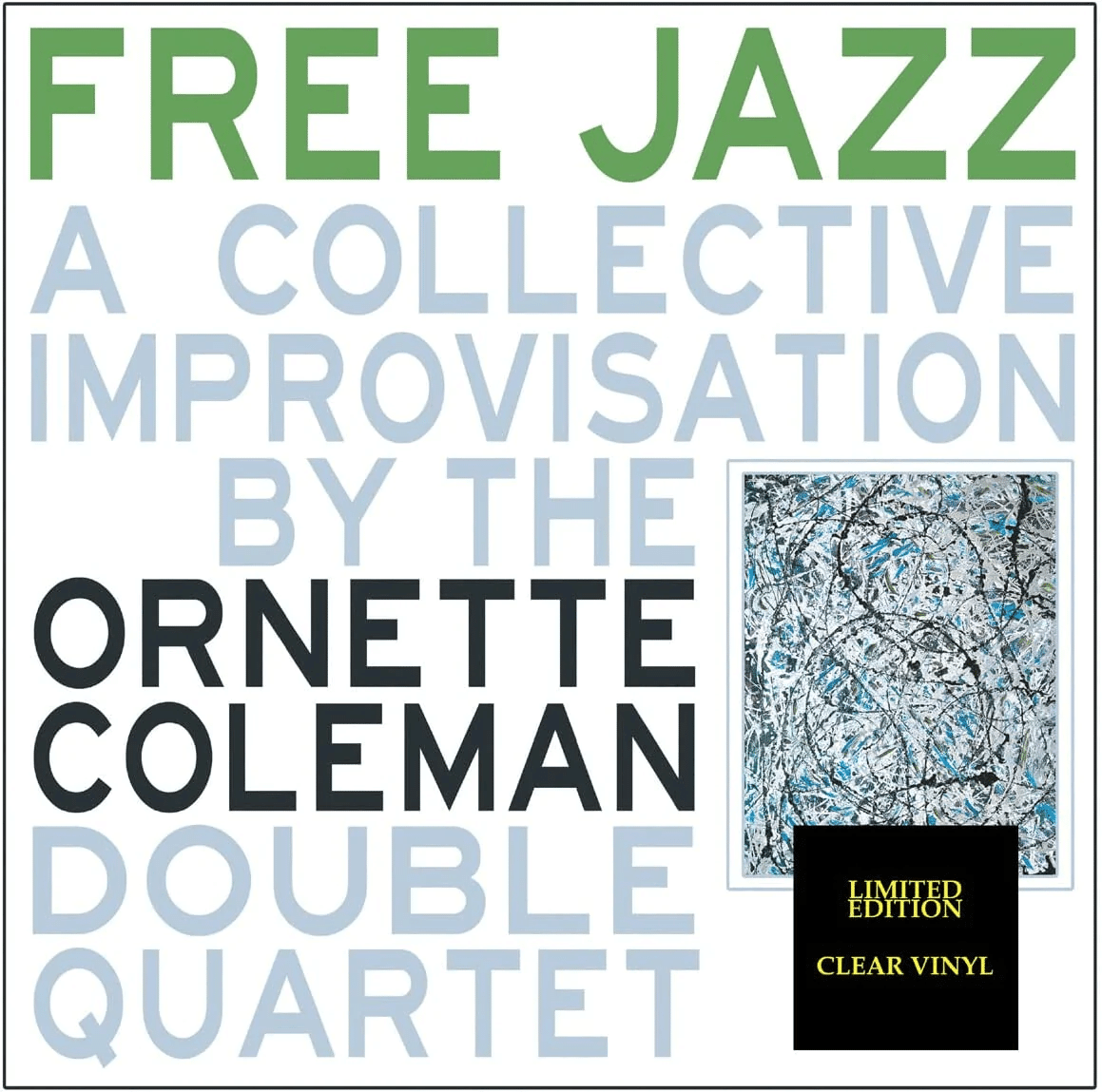
/オーネット・コールマン
ショーターはオーネットと同じくフレーズを用いるスタイルでのフリーへのアプローチ、オーネットのアルトに瞬時に反応するチャーリー・ヘイデンがここでのベーシストであったら、とんでもない展開になった事でしょう。
トニーと抜群のコンビネーションを聴かせるピーコック、彼のソロに続きます。
ショーターのソロ中ブラシでキープしていたトニー、場面を変えるべくここでスティックに持ち替えます。
ピーコックとトニーの対話にある程度の決着が付いた頃、リヴァースのオブリガートが聴こえ始め、彼のテナーソロへ、再びトニーはブラシに持ち替えます。
テンポは半分になり、その後ワルツに転じます。ここでのリヴァースのソロははじめからフリーク・トーンを用いてインパクトある表現を行います。
ショーターがフレーズを中心にソロを展開していたと述べましたが、リヴァースは効果音的、情念を繰り出す手法が中心となり、言わばアルバート・アイラー的な演奏スタイルと捉えていますが、ピーコックはアイラーのバンド在籍経験者、相性的に良きものを感じます。
テナーソロのラストにマルチフォニックス(重音奏法)をプレイし、クライマックスを迎え、そのまま独奏に転じます。更なるフリーク・トーン連発ののち、テナー最低音域をプレイしたのを見計ったトニーが徐に高速ブラシワークを繰り出し、エンディングに持っていきます。
ショーターが加わり、再びツーテナーの咆哮、そこにベースラインが加わります。ブラシだけが残り、様々なアクセントを用いながらFineを迎えます。
ここではメロディらしきラインは一切演奏されませんでしたが、リーダー、トニーのバンド采配の巧みさ、そして彼のディレクションに基づいた各人のアドリブ・ソロを鑑賞する演奏と捉えています。
2曲目エコーは全編ドラムスのソロです。
ジャズのドラミング、ソロにはある種のモチーフを用いながら構築して行く手法、美学が存在します。と言うよりもそれこそがジャズドラム、耳馴染みのリック無しには成り立たない筈ですが、ここでのトニーは純粋にその場での即興をエンジョイしながらプレイしている様に聴こえます。言ってみればお決まりの手捌きを用いずの、スポンテニアスなドラミングです。
ドラムス・セット=バスドラム、スネア、タム各々の打面パーツの音色、シンバル、ハイハット、金属系の音色のエッジー且つシャープさが彼の場合特に魅力的、しかも多彩な音色を操りながら変幻自在にフレージングを繰り出します。ここに前人未到のフレッシュさを感じます。
トニーのプレイを敬愛するジャック・ディジョネットが影響されたのでは、と思える場面を随所に確認する事が出来ました。
3曲目フロム・ビフォー、不安感を煽るかのツーテナーのダークなラインから始まります。そしてこの曲からハンコックが参加し、5人全員の演奏になります。
ピアノのカラフルなバッキングが加わる分、全く異なるアカデミックな世界が表現されます。ピアノレスとの対比を敢えて行った曲配置と考える事も出来ます。
印象的なリズム・キックが演奏され、テナーふたりが何やらボソボソと会話をするかのパートが設けられ、続いてハンコックが両テナー奏者の間にカーテンを下すかの打鍵を行います。
その後ベースソロが開始されます。ベースのプレイには全く関係ないかのピアノのバッキングが施され、しかもソロを奪うかの激しい調子で進みますが、ピーコックは一歩も譲らず両者同時進行、トニーの猛打を伴っていよいよハンコックの独壇場と思われる場面で予想を裏切り、ツーテナーがプレイし始めます。
参加者全員によるコレクティヴ・インプロヴィゼーション、その後は結局ピアノ一人裸になり、独奏が開始されます。
打鍵はまだまだ続いていたように思いますが、トニーないしはプロデューサーの意向でしょうか、余韻を残しながらFineとなります。

4曲目ラヴ・ソングは本作中随一メロディラインが明確なワルツ・ナンバー、激しさを伴うナンバーやフリージャズ・アプローチの中にあって、ムーディさが際立ちます。
テーマ・メロディ、ソロ担当はリヴァース、旋律の歌い方、コード進行に対するアプローチ、メロディアスな楽曲に対する美意識に関して比較的一辺倒なものを感じるため、個人的には表現の多彩さが際立つもうひとりのテナー奏者、ショーターに任せても良かったのではと思います。
とは言えソロの盛り上がりには、彼ならではのものを認める事が出来ます。リズム隊、特にトニーとは最初期からの共演歴を持ち、彼のサポートの巧みさを伴いながらピアノソロに続きます。
マイルスのテナー奏者ジョージ・コールマンが脱退し、ショーターが参加する束の間にリヴァースを加えたクインテットが64年7月来日します。この時の演奏を収録した作品が『マイルス・イン・トーキョー』です。

リヴァースは元々数週間のみでの参加契約の臨時メンバー、日本ツアー終了後米国で幾つかの公演に参加した後に脱退しますが、リヴァース参加にはトニーの推薦があったそうです。

ハンコックのプレイには知的さ、明確なストーリー性と意外性、魅力的なタイム感、適度な遊び心を認める事が出来、曲の有するコンセプトをダイレクトに表現しています。
ピアノ打鍵後リヴァースが再登場、短くソロを取った後ラストテーマに繋がります。
5曲目ティーは再び参加ミュージシャン全員による演奏です。幾何学的なメロディラインと複雑な構造美を有する短くもユニークなナンバー。
難易度高いリフゆえでしょう、リヴァースがラインを吹き切れておらず、アンサンブルに乱れが生じているため、ショーターの孤軍奮闘を感じます。
テーマ後誰が最初にソロを取るかを決めていなかったのか、元々のアレンジか、暫くカオス状態が続きますが、次なるソロイストの助走となるべくのインターミッション的に存在します。ピアニシモでテナーふたりがお互いを聴きながらプレイしますが、主導権は次第にショーターに渡ります。
テーマのメロディ、ムードを携えながらフレーズを繰り出すショーター、テナーの音色は演奏の濃密さ同様カラフルにして多くの成分を含みます。
楽器のセッティングですが、テナー本体が米セルマー社製バンディないしはマークⅥ、マウスピースはオットーリンク・メタル、オープニング10番、リードはリコ4番、極めてハードな仕様です。
ショーターのプレイは能弁ですがミステリアスです。明確なメッセージ性を確認出来そうでいて極めて高いハードルを有し、はぐらかされているかの、まるでジャズの持つ神秘性を彼ひとりが担っているかの如く、圧倒的な存在感をアピールします。

ハンコックのバッキングはショーターの音楽性の良き理解者として、全くの相応しさを表し、トニーのレスポンス、カラーリングにも同じ事が言えます。
続くハンコックのソロも軽やかにして含みを持ち、壮大な世界観には天から舞い降りるインスピレーションに対して全身全霊を以て、自身のイメージに反映させている様に感じるのですが、豈図らんや脱力感に満ちています。
ピーコックのソロが始まります。後年のキース・ジャレット・スタンダーズの演奏とは明らかに異なり、弦高の高さを十二分に感じるエッジーさ、撥弦の際の入魂ぶりが伝わる深くダークな音色を携えます。
巧みなピチカート・プレイには透徹なヴィジョンを感じ、アグレッシヴにしてデリカシーさも含むテイスト、時折パーカッシヴにも撥弦します。
トニーが超ピアニシモでレガートを続けていましたが、いつの間にかディミヌエンドし、そしてピーコックのソロも3曲目のピアノ独奏でのアウト同様、カットアウトされ、Fineとなります。
両曲のエンディングはプロデューサーのガイドラインか、トニー自身によるアイデアか、興味が尽きないところです。
