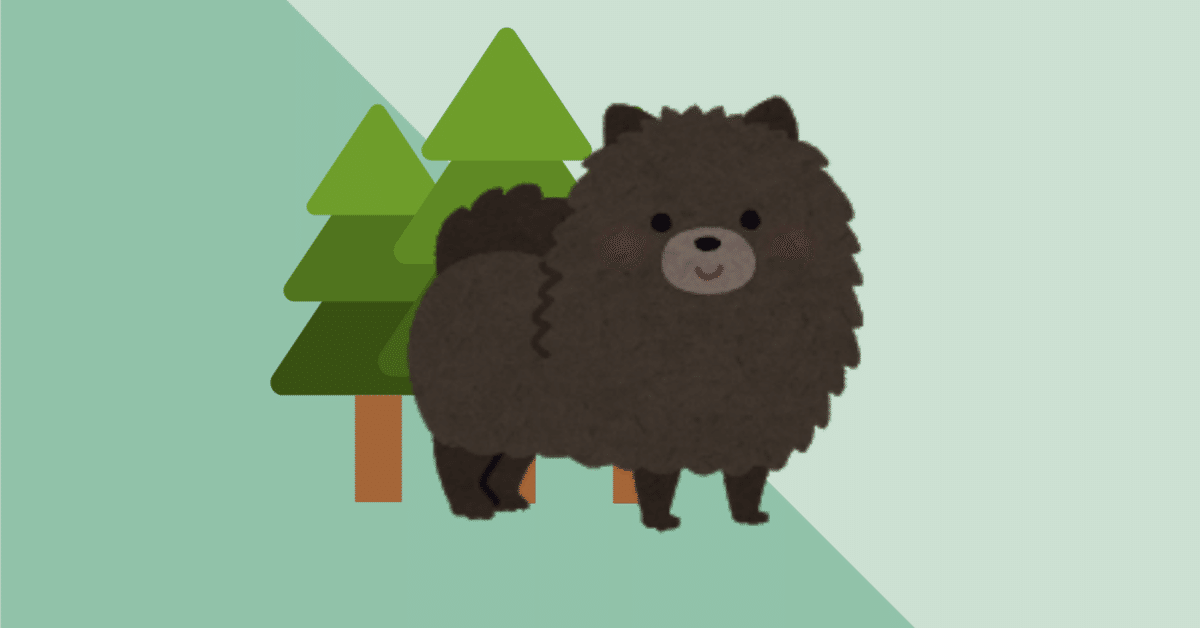
第20話 イタイノイタイノ しょうちゃんのところに飛んでいけ~
ボクは毎晩、寝床を作るために穴掘りをする。
寝床を掘るのは、オオカミ時代からの習性のひとつだよ。
だから、寝る時、ボクはソファに乗ってクッションに穴掘りをしたくなっちゃうんだ。
これをするとなんか安心するんだよね。
寝床がちゃんとあるのに申し訳ないいんだけど。
そしてね。
ここはボクのおやつの隠し場所でもあるんだよ。
クッションとクッションの間のミゾが隠し場所にちょうどいいんだ。
隠したのを忘れちゃうこともあるけどサ。
ママが片付けの時に見つけて、ポイしちゃうこともあるから注意が必要だね。
ママはボクがソファを掘るのがイヤみたい。
ソファーの布が傷むからだよ、きっと。
だから時々、ソファーの布が傷まないように、伸びたツメをチョッキンするんだ。
ボクはこれが大嫌い。
いくらママでも、これだけは勘弁してほしい。
今日も、ボクがソファーを掘ってると、ママは、はさみを持って近づいてくる。
そして、ドサッとボクの隣に座ると、ボクを膝の上にのせて、爪切り体制に入るんだ。
きたー!
ボクは、押さえつけようとするママの腕をすり抜けて逃げようと必死になる。
ここで逃げなければ、絶対触られたくない肉球をつかまれる。
そして、絶対されたくないことをされるんだ。
この際、ママの手を噛むことだって仕方ない。
ボクは「ウッー」と、ボクが出せる限界の低い声でママを威嚇する。
するとママは少しひるんで、ボクを抑えた手の力を緩ませる。
今だ、とばかりにボクはママの膝からジャンプして床に着地。
我ながら見事だ!
と、思うのもつかの間。
今度はしょうちゃんがボクを後ろから襲い、再びママの膝の上に乗せる。
これ、一瞬の出来事。
ボクはしょうちゃんにもさっきのような低い、そして本気の威嚇のうなりを見舞いした。
しょうちゃんはママみたいにひるまない。
ボクの大好きなジャーキーをボクの鼻先に差し出すんだ。
ボクは、ジャーキーをとるべきか、安心をとるべきか、一瞬迷う。
次の瞬間、ボクの口はジャーキーを捉えた。
すると警戒が甘くなる。
ボクは二人に左右から挟まれて身動きが取れない。
再び、威嚇のうなりを上げる。
と、せっかくのジャーキーが口から落ちる。
すかさず、しょうちゃんがそれを拾ってまたボクの鼻先に。
もう、こうなったら、ジャーキーが今どこにあるのかわからなくなってしまう。
くわえる
うなる
落とす
くわえる・・・
ずーっとこれの繰り返しだ。
アッ。と思った瞬間、ボクは鋭い痛みを感じてとっさに「キャンッ」という高い鳴き声を出した。
ママがボクのツメの血管まで切ったんだ!
これで、ママとしょうちゃんはボクの体を解放。
ママが、ボクの前足の爪を見る。
血が出てるよー。
「ごめーん」とママは、出血したところをティッシュで押さえた。
まあ、傷はそんなにひどくはなかったから良かったけど。
これだから爪切りはいやなんだよね。
ボクは真っ黒だから爪も黒いんだ。
だから、爪の中の血管が見えない。
血管を切らないように爪を切るのは、カンに頼るしかないんだよね。
ママはツメ切りの度に、こんな失敗をよくするんだ。
ただでさえ、肉球に触られるのが嫌なのに、これだもの。
ママは、ティッシュで押さえた指から手を離し、「イタイノイタイノ飛んでいけー」と言ってその手をしょうちゃんの体に投げつけた。
何のことかとボクが目を丸くして見ていると、しょうちゃんは、一瞬の迷いもなくそれに反応した。
「イタタタタ・・・」と言うのと同時に座った上半身を、まるで早いボールをを受け止めた時のように両手をお腹に充ててそのまま上半身を足の腿につけたんだ。
ボクはびっくりした。
「しょうちゃん!」
ママが、
ポッキ―の「イタイ」はしょうちゃんのとこに飛んで行ったよ、と教えてくれた。
ママの言う言葉を聞くとしょうちゃんは、折り曲げた上半身をゆっくり立て直してボクを見て笑った。
「ハハハ。痛かったね、ポッキー」
そういうと、ソファーから立ち上がって、何事もなかったかのように自分の部屋へと行ってしまった。
ママが、押さえてたティッシュをそっと外し、出血が止まったことを確認した。
そして薬箱から消毒液を出して、別のティッシュにシュッとかけて、同じところを押さえた。
ボクはその時初めて、指のイタイが感じなくなっていることに気が付いた。
しょうちゃんって強いんだな~。
ボクはしょうちゃんが消えた廊下に目をやりながら、そう思った。
「イタイ」はしょうちゃんのところに飛ばせるんだ。
しょうちゃんは、もしかしてママより強いのかも。
ボクは、ママから新たにもらったサツマイモのスティックを部屋の隅に運びながらそう思った。
また、今度イタイ目にあったら、しょうちゃんのところに飛ばせばいいんだな。
そうして、いつもの場所で初めて食べるサツマイモスティックをかじってみた。
ウオッツ!これ、おいしい!
ボクはそのスティックをソファーに隠すことなくきれいに平らげた。
そして食べ終わた後味を楽しむために口の周りをひと舐めしてから寝床に向かった。
今日も最後まで読んで頂きありがとうございます。
またこの次のお話でお会いできるのを楽しみにしています。
