
【小説】お信(最終・第三部)
『お信』
第三部
昭和六十二年、今年も彼岸を迎えたが暦に立つ秋は早く、夏の端はまだ残っていた。
熱海行き当日の朝。お信はフラフープで遊んでいた。腰をくねらせながら器用にフラフープを回すその姿を小猫が物珍しそうに眺めている。
「お信。そろそろ出掛けましょう。」
居間にいた継母がそう声を掛けると、お信は「うん。」と頷いてフラフープを納屋に戻し、庭からこちらへやって来た。
「で、お信。支度はできてるの?」
「まだなんにもしてない。」
「でしょうね。」そう言うと継母は、
「表で待ってるから五分以内に支度しなさい。」と先に家を出た。
そして一分後。
「おかあさま、おまたせ!」
「やけに早いわね。支度はもう済んだの。」
「済んだわ。」
と嬉しそうに言うお信の姿を見て継母は、
「あんたそれ普段着じゃないの。せっかく熱海に行くんだからよそゆきの恰好をすればいいのに。」
お信は浴衣姿であった。白地に藍一色で染めた木綿の浴衣は涼しげである。
「いいえ、あたしはこれでいいの。」
お信は一年を通して浴衣で過ごす。日常着も、寝巻も、営業中の作業着ですら全て浴衣で通す。割烹着は着ない。厨房の暑さには浴衣で風通しを良くしておき、汗に気を使わないようにしたいとのこだわりがあった。これは何も厨房に限った話ではない。お信は、底冷えのする冬の日も浴衣を着て仕入れに出発し、中学の卒業式も浴衣で出席し、町内の草野球大会にもやはり浴衣で出場した。
そんなお信を継母は「全天候型」と評したがお信はどこ吹く風であった。
「熱海に着いたら何しようかなあ。」
楽しげなお信の足元を見ると──いつもの駒下駄を履いており、そして頭陀袋を背負っていた。袋の中には替えの下着、替えの浴衣、店の余りで拵えた弁当が入っている。
木綿浴衣に駒下駄履きで肩には頭陀袋。そうしたお信の旅姿を継母は、
「まるで丁稚の藪入りね。」
と皮肉交じりにそう言ったが「えへへ。」とお信は継母の話をまるで聞いていない。
「ま、お信の好きにすればいいわ。」
そう語る継母の姿は──単衣の藤紫地に白を重ねて横縞の博多帯が締められており、いずれも裁ちおろしであった。桐正を履いてお信の前に立つ着物姿の継母は遠目にも近目にも優しく、そして美しく見せていた。
「あったっみ!あったっみ!」
いかに継母が粋な出で立ちをしていようとも、お信の関心は熱海旅行それのみであった。
「あったっみ!あソレ、あったっみ!」
「うるさい。で、店の戸締りはしたの?」
「もちろんしたわ。」
「家の戸締りは?」
「したした。」
──少し不安だな。そう思った継母は、家の雨戸、勝手口、小窓を全て点検した上で最後に「ラーメンお信」の入り口へ回り、シャッターが下ろされしっかりと施錠されていることを確認すると、シャッターの中央に張り紙がしてある事にふと気づいた。
モイスチャーをさがしにあたみへ行くことになったのでしばらくお休みします。
店主・をしん
継母は「まあいいか。」と貼り紙をそのままにしてお信の所へ戻ると、
「戸締りは問題なかったわ。出掛けるわよ、をしん。」
「はあい。」
ふたりは駅の方へ歩きはじめた。その道すがら、「バーバー小鉄」へ立ち寄り、親猫と小猫の世話を継母がそう言うと小鉄は快く引き受けた。
*
国鉄東京駅のホームまで来ると既に列車が到着していた。
「をしん。あの列車よ。」
「かっこいいなあ。」
「これは『踊り子』という名前だそうよ。」
「かわいいね。」
特急踊り子号の車内に入ると、秋の行楽日和に多くの乗客で賑っていた。
継母は窓側の席に座った。お信は通路側の席に座るやいなや下駄を脱ぎ、そして全体重を掛けて椅子の背もたれを百八十度後ろに倒した。
継母はお信の背もたれを元に戻した。
「次、また同じ事をしたら窓から突き落とす。」
「ごめんなさい。」
ふたりを乗せた列車は熱海を目指してようやく走り始めた。
列車が横浜に差し掛かった頃、車内販売の売り子がこちらの方にも回って来た。
「お信はどうするの。お腹が空いてるなら何か買えば?」
「買わない。なぜなら……」と言ってお信は頭陀袋を探り始めると、
「ほら見て。弁当を持って来たの。」
新聞紙に包まれた弁当箱を開くと、おにぎりが十二個入っていた。
「多過ぎやしないか……」と継母は言いかけたが、お信の折角の好意が台無しになると考え、心の内に留めることにした。
「あとねー、これも持って来たの。」
お信は嬉しそうに別の容器を差し出した。
中には大量のメンマが入っていた。
「店の残りで作ったの。さ、おかあさまも食べて。」
「多過ぎるわ。こんなに沢山食べきれるわけないでしょ。」
──言われてみればそうかも……目の前のテーブルには山盛りのおにぎりとメンマがどっしりとその座を占めている。
「おすそ分けしてあげたら。」
「なるほど。」
お信が辺りを見回すと、通路を挟んだ隣の席に親子連れが座っていた。
「ねえねえ、坊や。これ食べない?作り過ぎちゃったの。」「え、いいの?」「いいのいいの。」「あらァこんな沢山。どうもすみません。ほら、タカシ。ちゃんとお礼言いなさい。」「おねえちゃん、どうもありがとう。」
大量にあったおにぎりとメンマは半分以下にまで減った。
「これなら食べきれそうね。じゃあいただこうかしら。」
継母はまずメンマを口にした。さんざん食べてきた店の味である。
──ふるさとは遠きにありて思ふもの、そして悲しく思ふもの。つまり望郷と疎外の交錯。旅先でいつものを食べたところで疎外なんて微塵も無いけどこれはこれで一興なのかもしれない……継母はそんなことを思いつつ、おにぎりに手を伸ばした。そして一口食べた。具はメンマであった。
「ちょっとお信。あんたこれ、おにぎりの具までメンマじゃないのよ。」
「いっぱい余らせちゃったからこうするしかなかったの。」
「風情もへったくれもないわね。」
継母が呆れている向こうで「具もメンマだあ!」とおすそ分けした坊やの声が聞こえてきた。
列車は小田原を過ぎて根府川へ差し掛かろうとしていた。
相変わらずお信はメンマおかずにメンマおにぎりを一心不乱に食べている。その隣では「もうお腹いっぱい。」と継母が窓の外に目をやると辺り一面に太平洋が広がっていた。
「お信、外を見てみなさい。」
「海だ!」お信だけでなく、おすそ分けの坊やも同時に歓声を上げた。
「おっきいなあ。」と坊や。
「さすが日本海ねえ。」とお信。
「違うわ太平洋よ。手前は相模湾。」と継母。
「いいえ、ここは日本よ。日本の海だから日本海が正しいわ!」
と言い張るお信の理屈に誰一人言及することもなく、列車は真鶴から湯河原へと向かった。先程まで目と鼻の先にあったはずの海はその姿を潜め、屋根瓦の間から咲くホトトギスの紫が点々と視界に入るばかりであった。目的地の熱海までもうすぐである。
「お信、そろそろ到着よ。降りる準備をしましょう。」
「はあい。」
そう言うとお信は空になった弁当箱を窓から投げ捨てようとしたので、
「やめなさい。」
「でも周りのみんなも同じように窓から捨ててるわ。」
「あんたはみんなじゃない。」
お信はしぶしぶ弁当箱を頭陀袋にしまった。
「で、熱海へ行く目的は覚えてるわよね。」
「モイスチャーを探すことだわ。あるといいなあ、モイスチャー。」
「そうね。」と継母が生返事をしている内にようやく熱海に着いたので、坊やにさよならを告げてからふたりは列車を降りた。
*
熱海駅前は人でごった返していた──社員旅行、修学旅行、慰安旅行、家族旅行等々、そのほぼ全てが物見遊山を目的としているであろう雑多な人々を、これもまた雑多な宿の従業員が歓送迎にせわしく立ち働いており、それを目の当たりにした継母は、人の賑わいというよりうごめきだなとまずは思った。周囲を軽く見回すと少し先に、熱海の周辺地図と思しき立て看板が見えたので継母は、ちょっとすみませんと人を掻き分けながら目当ての看板まで進んだ。
──熱海海岸、來宮神社はさほど遠くはない。熱海城はさておき、梅園が気になるところだが季節外れの今、行ったところで何も無いだろう。となると、まずは近場の熱海海岸をそぞろ歩きしてみるか……あれ、そういやお信は?
「テメー、どこ見て歩いてんだよ。」
「は?そんなことアンタに関係無いでしょ。」
お信は地元熱海のちんぴらと睨み合っていた。
「しらばっくれてんじゃねーよ。人の足踏んづけといてその態度はなんなんだよ。」
「あたしじゃないってのよ。」
「どう見てもテメーが踏んだじゃねーかよ。」
「あたしが踏むわけないじゃない!」
「テメーだろ!」
事実、ちんぴらの足を踏んだのはお信であった。
その際、お信は「まあいいや。」と謝りもせず立ち去ろうとしたが、ちんぴらが見逃すはずも無く、よって、ちんぴらが怒るのは全くの道理であったがお信は知らん顔で無実を主張していた。
ちんぴらの靴にはお信の履いていた下駄の歯形がくっきりと残っており、これを見たちんぴらは「ぶち殺す。」と激昂、お信の胸ぐらを掴んだ。その眉間には青筋が立ち、拳はギリリと固められ、中指と人差し指には大きな指輪がはめられていた。つまり、ちんぴらはいつでもお信を殴る準備が整っていたが、それをとうに察していたお信も負けじと先手必勝、相手の顔面を殴ろうとした。が、ある問題に直面した──お信とちんぴらの身長差は二十センチ近くあり、そのため、お信の腕の短さでは殴りかかったところで、拳がちんぴらの顔面まで到達しないことが明白だったのである。
殴りたくてもお信の拳は届かない。
この状況にお信は焦る一方、ちんぴらは今まさに殴ろうと大きく振りかぶったところで「あッ!」と声を上げたお信、何かひらめいた様子で胸ぐらを掴まれつつも頭陀袋の中に手を突っ込み、ある感触を確かめるとそれを引っ掴んで袋から取り出し、ちんぴらの顔面めがけてこちらも大きく振りかぶった。
お信が手にしていたのはバリカンであった──これは今朝、お信と継母が行きがけにバーバー小鉄へ立ち寄った際、小鉄が「護身用に持っていきな。」とこっそりお信に持たせたものであった。バリカンの裏にはテープが貼られており、「バーバー小鉄・業務用」と書かれていた。つまり、お信は腕の短さを補うためにバリカンでちんぴらを殴ろうとしたのである。
お信は心の内で小鉄に感謝しつつ、
「熱海のちんぴらごときがこのアタシに立てつこうなんざ百年早いってのよ!」
「やってやろうじゃねえか!」
ふたりはお互いに殴りかかった。
腕の長さは互角、あとは腕力勝負となったがちんぴらの拳とお信のバリカンがそれぞれの顔面へあと数センチ……となったところでお信は背後から何者かに襟首を掴まれた──継母であった。
継母が襟首を掴んで引き離したことで、ちんぴらの拳とお信のバリカンはあえなく空を切り、継母はお信の襟首を掴んだままちんぴらに背を向けると、何も言わずお信を引きずってその場から足早に立ち去った。引きずられながらもお信はちんぴらを未だに睨み続けているその一方で、ちんぴらは唖然としてその場に立ち尽くしていたがこちらも負けじとお信を睨み返し、そしてとうとうふたりはお互いの姿が見えなくなるまで睨み合っていた。
駅から少し離れた仲見世通りに入った継母はようやくお信を引きずるのをやめた。そしてお信からバリカンを取り上げるとそれを頭陀袋ではなく、自らの旅行鞄の中にしまいこんだ。
「お信という名のサルは檻にでもぶちこんでおいた方がいいのかしら。」
「あたしはサルじゃなくて料理人よ。」
「珍獣・料理ザルに見合った頑丈な檻がこの辺に売ってたらいいんだけど。」
継母はお信を連れて仲見世を静かに歩き始めた。
その多くは温泉饅頭、かまぼこ、干物といった土地の名産を商う店舗で占められており、特に代わり映えはしなかったものの、「蒸し立てよ。」と言って継母がお信に温泉饅頭を買い与えてやれば「わあ、やったあ。」とお信はちんぴらとの喧嘩をすっかり忘れたのであろう、「この饅頭、顔の丸いあんたにそっくり。」と言う継母の言葉ですら聞く耳を持たず「甘くておいしー。」などと言ってはひとり上機嫌のお信であった。
仲見世の見物もそこそこに、通りを抜けると旅館が随所に建ち並び、その多くが数寄屋造りによるもので、材である土壁、杉、竹と一見して質素ながらも先に広がる海や山といった熱海の景観ともよく調和していた。
「渋かろか 知らねど柿の 初ちぎり」
継母は生垣を超えてそびえ立つ柿の木を見て、ふとそんな句を思い出した。加賀千代女である。
「ねえ、おかあさま。あのおいしそうな柿をぶちちぎろうと思うんだけど……どう?」
「だめに決まってる。」
──いよいよサルだな。千代女とは対極に位置する我が娘、お信。私がお信と同じ十八の頃は社会に生きる不安や分別が多少なりともあったように思うがどうやらこの子には微塵も無いらしい。ならば、あの柿をちぎってもよいと私が許可を与えるとお信は一目散にちぎるだろう、そしてかぶりつくだろう。
柿は果たして甘いか、渋いか。
「あれは渋柿だわ。」
継母は残念がるお信の袖を引いて再び道をくだり始めた。
*
熱海海岸にたどり着くと、ふたりの先には無辺にも海が横たわっており、それを縁取るかの様に観光客がここかしこに在った。
「おかあさま、あたしちょっと行ってくるから!」
お信は海の方へと駆けて行った。継母は傍らのベンチに腰を下ろすと扇子を取り出して扇ぎ始めた。青空の下、お信が砂浜をよちよち歩いているのがこちらからも見える。
「ちょっとお隣失礼。」
「ええどうぞ。」
老人は継母の隣に腰を下ろし、そして老人の方でも顔全体を団扇でせわしく扇げば、その所作に合わせてかぶっていたパナマ帽もゆらゆらと揺れ動き、その様子に継母は些かの滑稽を覚えた。
「地元の方ですか。」と継母が尋ねると、
「ああそうだね。どちらからお越しで?」
「東京から来ました。」
「東京のどちらかな。」
「深川です。辺鄙な下町でして。」
「深川も熱海も海の町、まあ似た者同士ですな。ところで向こうに居るのはあなたの娘さんかな?」
老人が指差す方を見ると、浜辺からお信がこちらに向けて両手を大きく振っていた。
「ええ、あれはうちの娘です。」
「無邪気なお子さんで。どうやら小学生のようですな。」
「驚かれるかもしれませんがあの子、あれで十八なんですのよ。」
「これは失敬。」と老人は帽子をかぶりなおしてから、
「ま、なんにせよ愛嬌のある娘さんなのでしょう。で、今日は何しに熱海まで?」
「今日はモイス……」
「もいす?」
「すみません、つい土地の言葉が出てしまいました。ただの観光です、娘が熱海に連れてけってうるさいものですから。」
「そうかい。では『お宮の松』はもうご覧になりましたかな。もしまだなら、ここから数分の所にあるからついでに行くといい。」
「ええ。」
とだけ言うと継母は照れ笑いを浮かべて、向こうのお信に手を振ってやった。会話はそれきりとなったので、継母と老人は浜辺で遊ぶお信を眺めることにした。
波打ち際までやって来たお信は見渡す限りの海を前に佇んではみたものの、大した感興も催すこともなく直ぐに飽きてしまった。傍らでは子供たちが砂で城を作ったり、貝殻を集めたりと楽しげである。
「ふふふ、無邪気ね。」
お信は微笑ましく思った。そしてすぐそばに落ちていた木の枝を拾うと砂地に、
「お信参上」
と大きく描いた。が、すぐに大波が押し寄せ、せっかく描いた「お信参上」は消し去られてしまった。続いてお信は、
「ラーメンお信は特売日」
と砂に描いたが、描き終わった瞬間、今度は小波が中途半端に文字を消したため「お信は特売日」という文言だけが残った。
──不謹慎な波だな。とお信は若干苛立ったが、ここへ来て波が静まり返ったため、この千載一遇のチャンスを逃すまいと今度は、
「しーちゃん毎日特売日」
とでかでかと砂に描き始め、描き終えると同時に「いい気味だわ。」と言ってげらげら笑ったが、それを待ち構えていたかの如く大波が到来、「しーちゃん毎日特売日」を一瞬にして飲み込んでしまったのである。
継母はお信が地団駄を踏んで何か喚き散らしている様子をぼんやり見ていた。
「私はこれで失礼。では良い旅を。」
老人はゆっくり立ち上がると元来た道へ引き返して行き、それから少し経ってお信が浜辺から戻って来た。
「熱海の海はどうだった?東京湾とは違うでしょう?」
「東京湾とは違って不謹慎だったわ。」
「そう。」と言った継母は、
「で、お信。あれは見つかったの?」
「あれって?」
「モイスチャーよ。熱海にあるんでしょ。」
と継母に尋ねられたお信はモイスチャーの事をすっかり忘れていたが、
「熱海の浜にモイスチャーは無い、という成果を得られたわ。」
「馬鹿ね。その論法を『悪魔の証明』というのよ。」
継母はそう言ったものの「仕方ないか。」と思い直した。
「そろそろ行きましょう。」
「はあい。」
*
継母とお信が海岸通りを歩いていると、立派な松の木がふたりの前に現れた。
松の周りには観光客と思しき人だかりができており、「これがお宮の松よ。」と継母が言ったそばからお信は我先にと件の松まで近づいて取り急ぎ「へえ。」とだけ言ってみた。松の緑は秋晴れの陽射しを受けて一層冴え渡っていたが、またしても「へえ。」とだけつぶやいて興味なさげなお信の様子に、
「ま、お信が見たところで所詮、松は松かもしれないけどどうやらいわれがあるそうよ。ほら、これを見てみなさい。」
継母が指を差した先に次の句碑があった。
紅葉山人記念 金色夜叉の碑
宮に似た うしろ姿や 春の月
一方のお信は句碑をそっちのけで「おかあさま!あれを見て!」と、今度はお信が指差す方を見てみると、お宮の松から少しだけ離れた場所に銅像があり──学生服姿の男が着物姿の女を足蹴にしているといった構図の銅像があった。
お信は観光客を押し退けながら銅像の前まで来ると、
「ひどい……こんな綺麗な女の人を蹴り倒すだなんて。最低の男だわ!」
「よく言うわね。ついさっきあんたも男の人をバリカンで殴ろうとしてたでしょう。」
「でもおかあさま、ちんぴらを殴るには殴るだけのれっきとした理由があったの。」
「そんならこの銅像の男にしてみても、足蹴にするだけのれっきとした理由があるし、この女性も足蹴にされて然るべき経緯がある。」
「え、もしかしておかあさまはこの二人を知ってるの?」
「当然よ。そこの句碑にも書いてある通り、この銅像は『金色夜叉』という物語の登場人物で、足蹴にしている男は主人公の貫一。倒れている女は貫一のかつての許婚、お宮。」
と言うと継母は続けて、
「貫一とお宮は相思相愛の仲にも関わらず、その実、お宮は自身の美貌に傲りがあったの。そして金持ちの男に見初められて、金に目がくらんだお宮はその男の求婚に応じる、貫一という許婚がありながら。つまり、お宮は愛ではなく金を取ったってことね。」
話をここまで聞いたお信は思わず、
「おかあさま、バリカンはある?」
「そんなもので何するつもり?」
「宮を殴る。」
「またこれだ。話は最後まで聞きなさい。」
継母は荒れるお信に呆れながら、
「そうしたお宮の裏切りを知った貫一は本人を問いただすと、お宮はどうしても金持ちの男の元へ行くと言う。で、激昂した貫一はお宮を蹴り飛ばすってわけ。」
「蹴られて当然ね。」お信は嘲笑った。
「でもねお信。お宮の銅像をよく観察してみなさい。貫一に蹴られながらもお宮は追いすがろうとしているでしょう。」
「そうさね。」
「お宮は愛と金に揺れながら金を選んだ。ただ、この時点でまだ何か隠している事がある。表情からもその様子が窺えるわね。」
「そうかも。それで?」
「二人が別れた後、失意の貫一は当て付けのせいか高利貸しとなり、一方の宮は金持男の元へ嫁ぎはしたものの貫一に対する後悔の念が募っていく。」
「それで?」
「お宮がどんなに謝ろうが貫一は宮を徹底的に遮断し続ける。手紙も一切読まない。」
「それでそれで?」
「ある日、貫一は夢の中で、貫一を想うがあまり自害したお宮、その覚悟に対し、夢の中とはいえ貫一はお宮を赦す。続いて貫一は心中間際のとある男女と出会い、この二人が金ではなく愛を選んだことを知る。そんな時、お宮からの手紙──惜くもなき命はあり候ものにて……から始まる未練と切実の混在した言葉の数々を貫一は目の当たりにする。」
「それでそれで?」
「そこから先は知らないわ。」
「えーそんなあ。そこまで話しといておかあさまってば殺生だわ。」
「金色夜叉は未完なのよ。作者の紅葉が連載中に死んだんだから仕方ないわ。ま、話の筋はざっとこんなところね。」
「にしても、続きが気になるなあ。」
「でもねお信。ここまでの話を知った上で改めてこの銅像を見ると印象が違ってくるでしょう。私なんかは、貫一もお宮もつくづく業の深い人物だと思ったわ。」
そう語る継母をよそにお信は、お宮の銅像をじっと眺め、美貌である彼女の境遇を半ば強引に自身に重ねると架空の恋物語を思い描いてうっとりしていた。この様子に継母は「あんたは業の源泉かもね。」と皮肉ったが、夢見心地のお信にその声は届かなかった。
「そろそろ行きましょうか。」
「ねえ、おかあさまが言ってた『お宮の隠し事』って結局何だったの?」
「さあね。私が読む限り、作中では明らかにされてないわ。どうしても気になるのならお信も金色夜叉を読んで調べればいい。ただ、それよりもあんたが熱海で調べるべきは……」
「モイスチャーね!」
そう言うとお信は心の中で、
「貫一とお宮。モイスチャーとお信。貫一とお宮。モイスチャーとお信。」
と繰り返した後に「あッ。」と何か思いついたらしく、行こうとする継母を呼び止めると、
「何?」
「ねえおかあさま、びっくりしないで聞いてほしいんだけど……」
「だから何?」
「なんとモイスチャーが見つかったの!」
お信の指の先には貫一の銅像があった。
「あの方がモイスチャーだわ!」
「ちがうわ貫一よ。」
そうしてふたりはお宮の松を後にした。
海岸通りを離れて市街地へ戻るように歩いていたが、彼岸というのに容赦なく照り付けてくる陽射しに継母は多少の疲れを覚えていた。時計を見ると午後三時を過ぎている。
「お信、今日はなんだか疲れたわ。少し早いけど宿に向かいましょう。來宮神社は明日にすればいい。」
「はあい……あああッ、いけない!」
とお信は何か思い出した様子で、
「おかあさま、本当にごめんなさい。実はすっかり忘れてたことがあるの。」
「何を?」
「宿の予約を。」
「宿なら既に取ってあるから心配無いわ。」
「よかった……あやうく野垂死するとこだったね。」
「大袈裟よ。」
ふたりは宿へ向かった。
*
その旅館は「民々楼」という慶応年間から続くいわゆる老舗であった。ただ、度重なる改装によって創業当時からの格調や格式といった面影は一見して感じられず、そのため老舗旅館というよりも昔ながらの宿屋といった方がこの場合自然であった。
民々楼にしても他の宿と同様、土地の銘木を材とした木造数寄屋造りで建てられたもので、客室数は他と比べて五室と少なく、正面からの外観はこじんまりとして見えはするが、宿の奥を通じて広がる中庭と外庭、そして大岩で囲われた外湯はその手入れもすっかり行き届いており、訪れた宿泊客はその微かに残る老舗たる所以を朧げながら感じ取ることができた。
「ほらお信、あそこに民々楼という看板が見えるでしょう。あの宿だわ。」
「民々……」お信は黙り込んだ。
「お信がぼったくられた民々書房と民々楼はなんの関係も無いから大丈夫よ。」
「いいや、あの憎っくき民々書房と家族経営かもしれないわ。」
「そんなわけがない。私はこの宿を知ってるの。至って普通の宿だから安心しなさい。」
「え。おかあさまはここに泊まったことがあるの?」
「……まあね。」
と継母は答えたが実際、民々楼に泊まったことはこれまで一度も無かった。
継母の夫、つまりお信の父は生前、この民々楼に行きたがっていたが病に斃れたため、とうとう行けずじまいに終わった。継母は夫が口にする民々楼という言葉だけはなんとなく覚えていたが、かといって夫がこの宿にどういった思い入れがあるのかまでは知らなかった。この際、宿はどこでもよかった。しかし──なにも熱海に定宿がある訳でもなし、母娘水入らずの民々楼逗留とは的外れの御追善、ただそこまであなたが訪ねたいというのなら……と継母は夫の意志を半ば介在させる形でこの宿を取ったのである。
「歓迎 ラーメンお信・御一行様」
そう掲げられた立て看板がまずはふたりを出迎えた。
「こうして改めてうちの屋号を見ると妙な名前だな。」
継母は少し気恥しかったが、一方のお信は「すごいすごーい!」と大喜びであった。
「ま、今更気にしても仕方ないか。」
ふたりは民々楼の館内へ入り、宿泊の手続きを済ませると早速部屋に通された。
「阿含の間」と称されたその部屋は、十畳敷の客室に床の間、障子を挟んで広縁が設けられており、ふたりが泊まるには十分であった。
継母は仲居が淹れた茶を一口飲むと、湯吞みを持って広縁の椅子に腰を下ろした。お信は畳の匂いを嗅いでいた。
「汗もかいたし着替えようっと。」
そう言うとお信は隅に置かれていた衣装箱を覗いた──お信の着物と同じ、白地に藍で染めたいつもの浴衣が入っていた。
「あたしのとまったくおなじやつだ……」
衣装箱の浴衣を広げて自分の浴衣と交互に見比べては困惑するお信、その後ろで継母はくすくす笑っていた。
「お信。よかったわね、老舗旅館と同じセンスで。」
とりあえずお信は宿の浴衣に着替えてみたが当然何の代わり映えも無い。頭陀袋には家から持って来た替えの浴衣がもう一枚入っており、やはりこれも宿と同じものであった。
お信に続いて継母も単衣から浴衣に着替えると「身軽でいいわね。」と言って時計を見ればまだ午後四時、再び椅子に腰を下ろして腕を組み、「少し寝るから。」とうたた寝を始めた。お信はこれといってやる事も無いので部屋を物色していたところ、床の間の掛け軸が目にとまった。
「室閑茶味清」
そう書かれてはいるものの何がなんだかよく分からない。
お信は、室蘭で茶づけを味わう清くんの姿を想像しながら、傍らの『館内施設のご案内』という冊子を開いた。すると、館内図に「大浴場(岩風呂)」と書いてあるのを見つけたお信は「これだ!」と声を上げ、
「ねえおかあさま、岩風呂があるらしいわ。入りましょうよ。」
「先に入りなさい。」
そう言うと継母はうたた寝へ戻った。
「じゃあ先に入ってるからあとで来てね。」
と小声で伝えるとお信はそのまま岩風呂へと向かった。
*
のれんを両手で勢いよく払いのけたお信は脱衣所に入るやいなや次から次へと服を脱ぎ捨ててそれをまとめて脱衣カゴに叩き込んでから手ぬぐい片手に大浴場へと続く引き戸を荒々しく開けっ放して中に入ると目当ての岩風呂まで一直線に進み、そのまま湯船に飛び込んだ。
お信が一番風呂であった。
湯けむりの立ち込める中、辺りを見回すと大中小さまざまな岩が湯船を囲うようにして組み上げられており、岩にそっと触れてみるとじんわりとして温かい。
「これならいけそうね。」
お信は岩に手足を掛けて岩山をよじ登った。そして、ひときわ大きな岩の上に立つと、そこから見える景色を眺めた──夕暮れの空にそびえ立つ山々は秋の兆しに緑と橙がところどころで混じり合い、山の麓から市街地にかけて家屋の明かりがまばらに浮かぶ一方で、今度は目線を西よりへ移すと、相模湾にとどまらず遥か向こうの海までも夕焼けが赤一色を全面に映し出していた。
この眺望に感じ入ったお信は思わず、
「家の風呂とは全然ちがうや。」
と至極当然の事を口走ると、岩の上から湯船めがけて勢いよく飛び込んだ。この行為を立て続けに五回繰り返したところで、そろそろ飽きてきたのか、
「さてと。体でも洗うか。」
洗い場の地べたにしゃがみ込んだお信は、備え付けの石鹼を使って体を洗い、そして風呂桶の湯を頭からかぶって流し終えたので、最後に髪を洗おうと目を擦りつつシャンプーと思われるボトルを手に取ったところ、そのボトルには次の様な文言が書かれていた。
「モイスチャー成分配合シャンプー」
これを目の当たりにしたお信は腰が抜けた。
そして「あわわわ……」とその場から後ずさりして腰抜けのまま脱衣所まで戻るとようやく立ち上がることができたので、衣服をサッと身に纏い「あったあった!モイスチャーがあったわ!」と急いで部屋に戻った。
継母が相変わらず縁側で寝ていたところへ障子がバンッと荒々しい音を立てて開いた。
「おかあさま!起きて!大変よ!」
お信は継母を揺さぶって起こすと、
「うるさい。何なのよもう。」
「大変なの!大変なことが起きたの!」
「はあ?というかお信、あんたその恰好どうしたの。びしょ濡れじゃないのよ。風呂からあがったんなら体ぐらいちゃんと拭きなさい、みっともないわね。」
お信の浴衣は襟から裾まではだけており、髪や腕からは雫が垂れていた。
「そんなことはどうでもいいの!おかあさま、大変なの!とうとう見つかったの!」
「何が。」
「モイスチャーよ!なんと大浴場にモイスチャーがあったの!」
「へえ。」とだけ継母は言ったが「いいから早く来て!」とお信は継母を引っ張って大浴場へ連れて行こうとするので、
「待って。落ち着きなさい。」「でもモイスチャーがあったの!」「わかったからとりあえず引っ張るのをやめなさい。」「ほら早く早く!」
継母はモイスチャーがあるという大浴場へしぶしぶ向かった。
「まあ。立派な岩風呂ね。」
と継母が言うそばから「いいから早く!こっちこっち!」とお信が急かすので「はいはい。」と継母は洗い場まで来ると「ほらおかあさま!これよ!」とお信が手にして見せたボトルには「モイスチャー成分配合シャンプー」とたしかに書かれてある。
「へえ。」とだけ言う継母をよそにお信は、
「まさかこんなに早くモイスチャーが見つかるなんてねえ。おかあさま、モイスチャーとはつまり、シャンプーのことだったのよ。」
「へえ。」
「でね、おかあさま。このモイスチャーを譲ってもらえないか、宿の人に相談しようかなって思うんだけどいいかしら?いいわよね?きっと良いお土産になるわ。」
嬉しそうに尋ねるお信は旅の目的を早々に達成したからか、その目は輝いていた。一方の継母は、お信の目をじっと見ながら何か考えている様子であった。そして、
「お信。これはモイスチャーではない。」
「え……」お信は絶句した。
継母は「残念だったわね。」と言ってから、その理由を次の様に語った。
「これがモイスチャーではない理由は大きく二点ある。まず、モイスチャー成分配合シャンプーには『成分』と記載がある。成分とは、物質を構成する一要素のこと。身近な例だと、鶏むね肉の主な成分はタンパク質だわ。でもお信は肉屋で鶏肉が売られているのを見て『タンパク質だな。』とは思わないでしょう?その物質の色や形状から類推して『鶏むね肉だな。』と見定めるはず。そしてこのモイスチャー成分配合シャンプーにも鶏むね肉と同じ理屈が成立する。要はこのシャンプーにはモイスチャーを構成するための、その一部分の、その一要素が混ざっているだけ。だからお信、残念だけどこれは純粋なモイスチャーではなく単なるシャンプーよ。」
「成分?オレンジジュースにオレンジが丸ごと入ってるわけじゃなくてオレンジの果汁が入ってるってこと?だからオレンジジュースとオレンジは別物ってこと?」
「厳密には違うけど今はその理解でいい。ま、このシャンプーの中からモイスチャー成分だけを抽出すれば純粋なモイスチャーを組成できるかもしれないけどあんたの頭脳ではほぼ百パーセント無理よ。あきらめなさい。」
そして継母は二点目の理由を語り始めた。
「お信、思い出してみなさい。あんたはこれを最初見たとき『シャンプーだ。』とまず思ったからボトルを手に取ったはず。それで当然なの。なぜならモイスチャーではないから。成分入りのシャンプーだから。にも関わらずあんたが『モイスチャー』だと判断するに至った過程はまず、この『モイスチャー成分配合シャンプー』という字面があんたを触発して、それを受けたあんたの単純かつ傲慢かつ愚鈍な感性が捉えたモイスチャー成分なる対象が乱雑な表象へと成り果てて心の中でわだかまっているだけ──つまり、あんたは勝手に混乱しているだけ。成分の意味すら知らないお信が理解に努めたところで客観的認識として共有することはできない、少なくとも私は認めない。そもそも、『モイスチャー』『モイスチャー成分』『シャンプー』これら三点は別の物としてそれぞれが独立して存在する。よって、この状態でお信がモイスチャー成分配合シャンプーをいかに明晰に認識しようとしたところで根本が違うんだからモイスチャーそれ自体に到達することはない、絶対に知り得ない。お信、冷静になりなさい。繰り返しになるけどこれはモイスチャーではなく成分入りのシャンプーよ。」
お信は混乱する頭の中でこうした継母の説明を反芻したが理解できなかった。
「完全に理解できたわ。」
「嘘おっしゃい。」
とは言ったものの継母は「分かるはずもないか。」と思ったので、
「以前、お信に『モイスチャーは熱海にある』と教えてくれた男の人が店に来たでしょう?カレーでビールを飲んでたあの客のこと。覚えてる?」
「もちろん。モイスチャーを知っている貴重なお方だわ。」
「で、カレーの男があんたに何て言ったのかちゃんと覚えてる?」
「熱海旅行は最高だぜ!って言ったわ。」
「そんなこと言ってない。あの人は『モイスチャーを言葉で説明するのは不可能』『しかし熱海に行けばきっと分かる』と言ったの。」
「そうさね。」
「ということは、モイスチャーという不明瞭なものを捉えるには己の感性に頼るしかない。その際の吟味から納得に至るまでの思考の過程、その不備は私がなんとかしてあげるから、あんたはモイスチャーがいつどこで現れても混乱することのないよう今後は冷静に構えておけばいいわ……無理だろうけど。とりあえず、今回のモイスチャー成分配合シャンプーの件は見当違いだからあきらめなさい。」
「はあい。」お信は生返事だった。
「じゃ、私は戻るから。」
「お風呂入っていかないの?」
「後で入るわ。」
継母は部屋に戻っていった。お信は気を取り直して髪を洗うことにした。再び手に取ったモイスチャー成分配合シャンプーで髪を洗ってみれば何の変哲もない、それはいつものシャンプーであった。
*
風呂からあがったお信が部屋に戻ると、座卓の前に継母が座っており「ほら、あんたもそこに。」と言うので向かいに座ってぼんやりしていたところへ仲居が料理を運んで来た。
座付、前菜、椀盛、焼物、煮物が並べられ、そして座卓中央に置かれた大皿には刺身が盛り合わせてあり、これらの御馳走を目の当たりにしたお信は緊張に手が震えた。
お飲み物はどうなさいますかと仲居が聞くので継母は酒をそう言って誂えた。
「お信も好きなものを頼みなさい。」
「オ、オ、オレンジジュース……」
と言ったそばからお信は食べ合わせの悪さに気付いて後悔した。
銚子とオレンジジュースがふたりの前に置かれると「ではごゆっくり。」と言って仲居は部屋を後にした。
「豪勢な料理だこと。さ、お信。早速いただきましょう。」
ずらりと並べられた料理の数々にお信は箸を持ったまま相変わらず硬直していたが、とりあえず箸を匙に持ち替えて目の前の茶碗蒸しを一口食べた──美味い。プリンと同じぐらい美味い。あっという間に食べ終えた。
「私のも食べていいわよ。」
継母の茶碗蒸しは一瞬にして空になった。
「遠くまで来たかいがあったわね。」
「うん。」
茶碗蒸しのおかげでお信の緊張もようやくほぐれてきたところでふと大皿の刺身に目が止まった──地物の魚は素人目にも鮮度良くとりどりに盛られ、笹を用いて紅葉や銀杏を模した飾り包丁のあしらいには料理人の丁寧な仕事が窺えた。この見事な盛りの細工に、お信は自らも料理人であることから「ラーメンお信」としての自負が沸々と込み上げてきた。
そうしたお信の内情を知らない継母は、
「綺麗な刺し盛りね。食べるのがもったいないぐらい。」
「ふん、どうだか。」
お信は妬ましげに鼻で笑いつつ、
「だっておかあさま、この刺し盛りはいくら見てくれが良くったって肝心の味が伴ってなければ台無し形無しよ。味ありきなのは料理の基本だもの。そして同業者のあたしには分かる、この刺し盛りは見かけだおしね。だからなるべく手を付けない方がいいわ。」
言い終えるとお信は刺身を睨みつけた。
「馬鹿ねあんたは。たかが横丁のラーメン屋が老舗の板前に対抗意識を燃やしてどうすんのよ。」
「でも……」
「でもじゃないわよ。この刺し盛りがそんなに怪しいんなら実際に食べて確かめればいい。その方がてっとり早いでしょ。」
「そうさね。ではラーメンお信様がこの舌で甲乙を見極めてあげる。」
高慢な態度のお信は刺し盛りへと箸を伸ばし、そしてカツオの刺身を一切れつまむと、まずはその身をじろじろと見た。
「ふん。こちとら江戸前の活きたカツオを食べてるっての。それと比べたら熱海のカツオなんかはちと鮮度が落ちるかもしれないけどさ。ま、そこは料理人のココで食わせてもらいたいものだわ、ココで。」
と言うとお信は腕をぱんぱんっと叩いた。
「ごたくはいいからさっさと食べなさい。」
「はあい。」
とりあえずお信は刺身を口に運び、そして舌に乗せた瞬間──うめえ!なんだこれ!舌にトロける!鮮度も良いけどそれ以上に料理人の「腕」で食わせてやがる!どうすればこんなものができるんだか……なんにしてもこんなうめえもん食ったことねえ!あっぱれ!
「おかあさま。このお刺身、見た目通りとってもおいしいわ。」
「でしょうね。」
継母も一口食べて満足そうに頷いた。一方のお信は次から次へと刺身を口に放り込んではその味に都度感動していた。
「お信。刺身だけじゃなくて他にもあるんだからもっとまんべんなく食べなさい。」
そう言われてお信はキンメダイの煮つけを食べた──甘辛くてうめえ!続いてタチウオの塩焼きを食べた──しょっぱくてうめえ!生麩の揚げ出しを食べた──ふわふわでうめえ!車海老の天麩羅を食べた──天つゆもうめえ!オレンジジュースを飲んだ──なんだかんだでこれが一番うめえ!
何を食べても「うめえ」と小声でぶつぶつ唸っているお信の様子に、継母は「味の分別も欠落しているのだろうか。」と思ったが、確かにここの料理は何を食べても美味しい。納得の様子で銚子を傾けようとしたところ、
「ねえおかあさま、あたしもお酒とやらを飲んでみようかしら。」
お信はこれまで一滴たりとも酒を飲んだことが無かった。
「そうね。あんたも十八だし少しぐらいは練習しておいたほうがいいかもね。ほら、お猪口。」
継母はお信の猪口に酒を注いでやると、
「まずはゆっくり少しづつ飲みなさい。」
お信は一気に飲み干した。
「ゆっくり飲みなさいって言ったのに……」
「平気平気。大丈夫みたいだわ。」
「ならいいけど。」
そうして継母もあらためて酒を一口飲んだ──酒は憂いの玉箒。物は言いようだな。いくら掃いたところで憂いも塵と一緒。巡り巡ってはまた積もり始めるだけだろう。憂いをきれいさっぱり取り除くなんて事が無理なのは今さら分かり過ぎている。ただ、今日は遠路はるばる娘と水入らず。少しぐらいは玉箒とやらに己を委ねるのも時の一興かもしれない……
「あー、誰でもいいから一発殴りてえ。」
お信はそう言うと継母を睨みつけた。
「あんたまさか、もう酔っぱらったの?」
お信の顔は首まで真っ赤に染まっており、その目は据わっていた。お信は猪口にたった一杯飲んだだけで泥酔していたのである。
「おい継母ァ!」
悪態がどういう訳か継母に向けられたが、これには継母も反射的に、
「小娘の分際で誰に向かってそんな口叩いてんのよ。いい加減にしないとそのツラひっぱたくわよ。」
と怒りを露わに言い返したところ、お信の表情はたちまち恐怖にこわばって「ひどい、あんまりだわ……」とわんわん声をあげて泣き始めたかと思いきや、今度は一転して「あはは!いひひ!うきき!えへへ、うひゃひゃひゃ!」と何がおかしいのかゲラゲラ笑い続け、そしてグーグーと鼾をかいて寝てしまった。
「怒り泣き笑い上戸なのかしら。」
継母は、大の字で眠りこけているお信をちらっと見て晩御飯の続きに戻った。
*
「ハッ、ここはどこ?」
お信が目を覚ますと、体には毛布が掛けられており、座卓の上にあったはずの料理は全て片付けられていた。
「あれ、おかあさまがいない。」
傍らの時計を見ると既に二十一時過ぎ、静まり返った座敷に続く庭先から鈴虫の鳴き声だけがうっすらと響いていた。
お信はなんだか損をした気分になったので、座卓の上に置いてあった茶菓子をとりあえず食べた。が、まだ納得がいかないので、継母が飲み残したと思われる酒を猪口に注いだ。今度は継母に言われた通り、ゆっくり少しづつ飲んでみた。そして、
「我が継母の探索に出かけよう。」
とほろ酔い加減でお信は部屋を出て、館内の見物がてら継母を探すことにした。
一階まで降りると受付に隣接した広間があり、そこでは風呂上がりの宿泊客がソファーに座って談笑していた。それを見たお信も近くに座ってソファーの感触を確かめていたところ、宿泊客の一人が、
「あそこに卓球場があるんだってさ。」
と言ったのをお信は聞き逃さなかった。
早速お信は卓球場へ入ると、そこには卓球台が二台設置してあり、その内の一台は既に他の者が使用していた。なら残る一台で卓球をすればいいや、そう思ったお信はいざラケットを握って台の前に立ってみたが、そもそも卓球は一人ではなく、最低二人から遊ぶものだという事実にようやく気が付いた。
「ってことは早くおかあさまを探し出してここに連れてこなければ……」
そう考えたお信は一旦卓球場を後にしようとしたところ、向こうの片隅にある粗末なのれんが目にとまった。
「ゲームコーナー」
お信はゲームコーナーののれんを潜って、辺りを見回すとそこには──ピンボール、花札、麻雀、インベーダーゲーム、そして最奥に「モグラたたき」と掲げられた遊技台があった。
お信はモグラたたきの前まで来ると、
「すんごい面白そう……」
と思わず声が出た。
しかし、肝心のモグラたたきは電源が入っておらず稼働していない様子が窺えた。
「モグラたたきをご要望のお客様はお近くの従業員までお声掛けください」
この張り紙を見たお信は受付へ直行、暇そうにしていた支配人と思しき男を連れて再度モグラたたきの前まで来ると、
「ほらほら早く。」
「はい、少々お待ちください。」
モグラたたきに電源が入ると楽しげな音楽が流れ、リズムに合わせて色とりどりの電灯が点滅を繰り返し、これを目の当たりにしたお信の心もすこぶる踊った。腹の底からモグラを叩きたいと思った。が、お信は何をどうすればモグラたたきが始まるのかよく分からなかったため困惑していたところ、それに気づいた支配人が、
「まずこのコイン投入口にお金を入れるんですよ。そしたらあとは勝手にゲームが始まるから、穴から出てきたモグラをハンマーで叩けばいいです。」
「なるほど。」
「では私はこれで。」
と言って支配人はその場を去ろうとしたが、
「おじさんちょっと待って!」
「なんでしょうか。」
「肝心のお金を持って来てないの……」
お信が悲哀の調子を込めてそう言うと、見かねた支配人は財布から五十円を取り出してお信に手渡してやり、
「ここは私が立て替えておくからチェックアウトの際に精算してくださいね。」
お信は礼を言うとすぐに五十円を投入、ハンマーを握り締めてモグラが穴から出てくるのを待った。その真剣な様子に支配人はかえって心が和んだのか、後ろからお信を見守ることにした。
穴からモグラが出てきた。と思いきや、すぐに頭を引っ込めた。驚いたお信は何も手が出せず茫然となったが瞬間、隣の穴からもモグラが、その奥からもモグラが出ては頭を引っ込めた。またもやお信はその俊敏なモグラの動作に驚いて唖然としていたらまた別の穴からもモグラが出現、また引っ込み、そしてあちこちの穴から雑多なモグラが出ては引っ込んでを繰り返したがお信は依然として硬直したままハンマー片手にその場に立ち尽くしていた。
この様子を後ろで見ていた支配人は、モグラに翻弄されて茫然自失状態のお信に対し、よりいっそうの微笑ましさを覚え、応援してあげたいと思った。
「お客さん、落ち着けば大丈夫ですよ。がんばってください。」
「うっさいわね!集中してるんだから黙っとけってのよ!」
とうとうお信は一度も叩けずじまいでモグラたたきを終えてしまった。
「ちょっとおじさん!どうしてモグラとの真剣勝負の真っ最中にあたしに話しかけるの?どうして邪魔をするの?なに?なんなの?おかげで集中が途切れたわ。すんごい良いところだったのにどうしてくれるのよ!」
「そんなムキにならなくても……」
「五十円。」
「え?」
「もう一回やるから五十円貸しなさいよ。」
支配人は納得のいかない様子でお信に五十円を渡すと再びお信とモグラの勝負が始まった。お信の目は血走っていたが、あいかわらず頭を出しては引っ込めるだけのモグラの挙動に手が出せないまま、穴からモグラが出てくるとそれに驚いてしまい叩く動作にまで至らず諦めてしまう、を繰り返していた。支配人は「なぜこの子はこんな簡単なことができないのだろう。」と不思議でならなかったが次の瞬間、お信の目の前の穴からモグラが出てきたので「今だ!叩いてください!」と声を掛けたが、その声に驚いたお信は目の前のモグラに反応することができなかった。そしてお信は、勝負の最中にも関わらず話しかけてきた支配人を無言のまま睨みつけた。
「後でこの子はまた私のせいにして激怒するに違いない。」
支配人は我が身を悟り、一方のお信はまたしてもモグラを一度も叩けないまま二回目の勝負を終えてしまった。
「五十円。」
「はいどうぞ。」
支配人がお信に追加の五十円を差し出すと、お信はそれを受け取る際に、
「次、話しかけたら殺す。」
と低い声で言った。
再びモグラたたきの前に立ったお信は、浴衣の両袖を肩まで捲り上げ、右手にハンマー、左手に五十円玉を握りしめると深呼吸を繰り返した──まさかこのあたしがモグラごときにこうまで愚弄されるとは夢にも思わなかった。がしかし、次こそは必ず仕留めてみせる。とはいえ、また同じ過ちを繰り返すかもしれない。さてどうするか……
しばらく思案していると大浴場で継母が発した次の言葉が不意に蘇ってきた。
「モイスチャーという不明瞭なものを捉えるには己の感性に頼るしかない。」
お信は五十円を静かに投入した。そして目を閉じた。
支配人はそのただならぬ気配を察して固唾を飲んだ。お信が息を殺して待ち構えていると最奥の穴からモグラがちらりと頭を覗かせた──直感したお信はハンマーで「確信」に渾身の一撃を浴びせた。
モグラは大きく宙を舞った。
依然としてお信は目を閉じたまま、次に穴から出てきた確信にハンマーを叩き込むと、二体目のモグラも打ち上がって地面に叩きつけられた。三体目のモグラも、そして四体目も、穴から出てきた直後にハンマーが顔面を直撃、モグラは穴に戻ることなくそのまま向こうに吹っ飛んでいった。
「ちょっとお客さん!そんな乱暴に叩いちゃいけない!やめなさい!」
アッパーカットでモグラを殴り飛ばすお信、それを支配人は止めさせようと試みたが、支配人の制止を振り切ってお信のハンマーは真芯を確実に捉え、次から次へとモグラを殴り飛ばしていったのである。
とうとう最後のモグラを殴り飛ばし終えるとお信の目は開き、そして我に返った。
「おかあさまのおかげでモグラを退治することができました。ありがとう。」
と心の内でお信は継母に感謝しつつ辺りを見ると、いたるところにモグラが転がっており、それを支配人が拾っていた。
「あたしも手伝うわ。」
「当然です。」
支配人は全てのモグラを穴に戻してやり、モグラたたきの正常動作を確認し終えると、
「二度とモグラたたきをしないでください。」
そう言い捨てて帰っていった。その悲しそうな後ろ姿を見てお信は少しバツの悪い思いに駆られたが、ともあれモグラとの大一番に勝利した事を胸に刻み込んだのである。
*
ゲームコーナーを後にしたお信は、継母を探す建前で再び館内を物色していたところ、一階通路奥に長のれんが掛かっているのが目に付いた。
のれん越しに中を覗いてみるとそこは調理場であった──今しがた厨房仕事を終えたと思しき法被姿の痩せた男が作業台に肩肘をついており、その厚ぼったい手、無数の傷跡が残る掌、そして親指の付け根には包丁ダコ、これを見たお信はこの男がただ者ではないことを覚った。
男はお信の視線に気が付いた。
「誰だいアンタは。」
「あたしはラーメンお信。」
「聞かねえ名だな。」
「東京あたりじゃ名の知れた料理人なの。覚えておいて損はないわ。」
今のお信はモグラに勝利したことで自信に満ち溢れていた。
「そのラーメンお信とやらが俺に何の用だ。」
「あなたはこの旅館の板前、しかも板長でしょう?あたしには分かるわ。」
「ああそうだ。」
「あたしはラーメンお信の総料理長よ。」
「だからどうした。」
「ところで、ここの料理はすべてあなたが作ってるの?」
「ああ。で、さっさと用件を言いな。」
お信は不敵な笑みを浮かべると、
「さっきあなたの料理を食べたんだけど、その味はどれも素晴らしかった。あっぱれよ。食通お信と呼ばれたこのあたしをここまで唸らせたのはあなたが初めてかもしれない。そこで提案があるの。あなた……うちの店で働いてみない?」
「働くわけねえだろ。」
「いや待って。ちゃんと仕事してくれたら報酬はうんとはずむわ。」
「金の問題じゃねえ。」
「そう……残念ね。じゃあどうやったらこんな美味しい料理を作れるのかレシピを教えてくださらない?」
「さっさと消えな。」
これにしびれを切らしたお信は、
「なにさ。レシピぐらい教えてくれたっていーじゃん。板長のケチ!」
「この野郎……」
カッとなった板長は傍らの出刃包丁を振りかざして脅すと、お信の目にはその出刃が長脇差に見えた──怖気づいたお信はじりじりと後ずさりし始め、そして「今日はこれぐらいにしといてあげるわ!」と捨て台詞を吐くとその場から一目散に逃げ出した。
板長は焼酎をコップに並々注ぐと唐辛子を振りかけ、それを一気に飲み干してから、
「ただの馬鹿だな。」
とつぶやいて帰り支度を始めた。
お信が部屋まで逃げ帰ってくると既に布団が敷かれており、奥の広縁に継母が居た。
「お信、どこ行ってたの。」
「その辺をうろついてただけよ。」
「あんたなんだか酒臭いわね。」
「晩ごはんの時に飲んだお酒がまだ残ってるのかも。そんなことより、おかあさまこそどこに行ってたの?」
「大浴場。」
そう言うと継母は小さく咳をした。
「湯冷めかしら。明日も早いことだしもう寝ましょう。」
「はあい。」
お信と継母は床に着いた。
*
翌朝。お信は二日酔いに苦しんでいた。部屋に朝食が運ばれて来ても相変わらず布団をかぶったまま、お信は昨晩の飲酒をつくづく後悔していた。
「あの程度の量でこうまで二日酔いになるなんてお信、あんたはお酒に向いてない体質かもしれないわね。」
「お酒なんて金輪際飲まない……」
朝食を済ませると継母はお信を残して朝風呂へ行き、少し経って戻って来たが依然としてお信は布団の中でうんうん唸っていた。
「午後には良くなるだろうからしばらく寝てるといいわ。」
「そうさね……」
「私は出掛けるから。」
「出掛けるってどこに。」
「その辺よ。昼前には帰るから観光の続きは午後にしましょう。」
そう言うと継母は身支度を始めた。
「ほら、あんたの朝ご飯は下げずに残してもらったから二日酔いが治まったら食べなさい。何かあれば宿の人を呼ぶといい。」
継母はひとりで表に出た。
この宿、民々楼は高台に位置しているため熱海の海を一望することができた。
継母が特に目的もなく海を左手に歩いていたところ、数名の着物姿の女性に追い抜かれた。どれも三味線を提げており、髪は島田に結われていた──温泉地とだけあってこの辺りにも置屋があるのだろう。にしてもこんな朝から置屋なんぞ行ったとて暇を食うだけのはず……
継母は不思議に思ったが角を曲がればそこにもまた芸者がそろそろと歩いていたので、少し離れてその後を辿っていると芸者連はある建物に入っていった。入口横には「芸妓見番」と札が下げてあった。どうやら置屋ではないらしい、して見番とは何だろう。すると「見学もできますよ。」と後ろから声を掛ける者がいるので連れられるがまま中に入れば、そこは芸者の稽古場、屏風を背にしてお座付き舞踊、鼓太鼓の拍子に三味線を鳴らしたりといった芸者の姿にようやく継母は事の次第を察した。
「朝から精が出ますね。」
「といってもこの娘たちはまだまだ見習い、半玉の内は大抵そんなものです。たまに踊りのお披露目なんかもしたりしてね。」
一見して職員なのか常連なのかは判然としない口ぶりの女はそう語ると「ほら、見てごらんなさい。」と言うので目線の先を追えば、白い顔をした小柄な芸者が踊り稽古の最中であった。
「あの娘なんてまだ十八だそうで。にして年増の風格がありますね。」
「はあそうですか。」
と返すにとどめて継母は芸者の着物を見たところ、肩と膝にそれぞれ白い芙蓉が染められており三日月模様の露芝は正に秋の装いであった──しかし芸者にしては地味過ぎやしないか……と思ったが彼女の白い顔に芙蓉の白といったあしらいを見るにつけ、少し儚いようにも感じられた。
芙蓉は朝に咲き夕にしぼむ花。
してみれば十八にして年増の風格という所感は言い得ているのかもしれない。ふと継母は白い顔の芸者が鼈甲の簪をしているのに気づいた──少し野暮だな。でも、そこが若さゆえの未熟さにして可愛らしさ。やはりこの芸者はまだまだ十八の半玉、という見立てに落ち着いた。そして思うのは芸者と同じ十八の我が娘、お信。その芸者姿をなんとなく想像してみたが、それはすぐさま「おちゃっぴい」という見立てとなり、浴衣に駒下駄で寸胴鍋を抱えているお信のほうが継母には快く映った。
芸妓見番を後にした継母は起雲閣を横目に過ぎて道をさらに下っていき海岸通りまで出て来た。左手には昨日訪れたお宮の松が見える一方、右手のずっと向こうには岬があり、継母はそこを目指す訳でもなかったが岬の方へと歩き始めた。海岸通りは今日も変わらず炎天下に晒されており、海に反射した陽射しが目に眩しく、初夏を思わせる程の陽の光は日傘を通り抜けて肌をいっそう白く映した。継母の肌は元々白かったが今や張りがない。
十数分歩いて少し眩暈がした。時計を見れば午前十一時、そろそろ宿に戻るか。継母は道を引き返した。通りには木陰も無ければ陽を遮るものは何ひとつ無い。車を拾おう。
そうしてとりあえずベンチに座った。陽射しが食い入り、皮膚までじりじり熱い。継母はまた歩き始めたが車の通る気配はいっこうになく、人の姿も見えなくなった。再び眩暈がした。構わず歩き続けると目の前にはお宮の松、その斜向こうから車らしき姿がぼんやりと見えた為、継母は咄嗟に手を挙げ、急ぎ足で通りから国道に続く階段に桐下駄の先が触れた瞬間、三度目の眩暈に襲われ足を踏み外した──継母よりも先に日傘だけが舞い上がり、その後を追うようにして継母は階段から崩れ落ちていった。車はすぐそこまで迫っており、見上げればお宮の銅像が映った──継母の空間が歪み、次いで継母の時間が徐々に狂い始めると、陽の光が消えて辺りは途端に黒へと変わり、銅像だけが暗闇の中を進んでいるのを見た。その朦朧とする意識の中で「漫然とした知覚の断片……」という声が頭に響き渡ると銅像の顔が浮かび上がり渦を巻いてふらふらと目の前まで迫り寄り「この愚か者めが……」と低い唸りを上げると渦の中で目が光った。そして継母の頭の中に渦が入っていったと同時に継母の目は色を失い、一瞬の静寂を経て、車の急ブレーキ音が辺り一帯に轟いた。
ここで継母の意識は完全に途絶えた。
*
「おねえちゃんはだあれ?」
「あたしはラーメンお信。」
二日酔いから醒めたお信は近所の子供達と居た。子供達はみんなして竹馬で遊んでおり、散策中のお信がそこをたまたま通り掛かったのである。
「どうしてラーメンお信なの?」
「元からラーメンお信よ。」
「だからどうしてなの?」
この質問にお信は軽い自己矛盾に陥った。
「でも、今は竹馬お信でもあるの。」
「どうして竹馬お信なの?」
「竹馬が得意だから竹馬お信なのよ。」
今度ははっきり答えることができた。
「ほら、ちょっと貸してごらんなさい。」
と言ってお信は子供から竹馬を取り上げると、まずは竹の触感を確かめた。
「これは孟宗竹ね。竹馬の材としては合格よ。」
「へえ。」
「確かあんたは宗助って名前だっけ。」
「そうだよ。」
「宗助、あんたの目利きは悪くない。で、この竹の産地は?どこに生えてたの?」
「すぐそこ。」
そう言うと宗助は民々楼の裏にある竹林を指差した。
「国産ってわけね。竹は何年モノなの?」
「わかんない。」
お信は改めて竹に触ると、
「ま、この竹は五年モノといったところね。まあ良しとしましょう。ただ、欲を言えば六年モノがいいわ。」
「ふうん。」
「あのね宗助。竹馬に使用する竹は国産の孟宗竹の六年モノが最高なの。」
「こくさんのもーそーちくのろくねんもの……?」
宗助は他の子供達と顔を見合わせると、言葉の語感におかしさを覚えたのか「もーそーちくもーそーちく!」と皆で笑い合った。
「では実技を見てあげる。まずは宗助、あんた竹馬に乗ってみなさい。」
「うん。」
宗助は竹馬に乗ってよろよろと歩いた。お信はため息混じりにぱんぱんッと手を叩くと「やめやめ!」と言って宗助を竹馬から引きずり降ろした。
「あーもう全然ダメ。宗助ってば話になんないわね。安定感がまるで無いし、見てるこっちがハラハラしちゃった。これだからズブの素人は……」
「なら、おねえちゃんがやってみてよ。」
お信は宗助から竹馬を取り上げると「いいわよ。」と言って実演を始めた。
「まずは右手で竹をギュっとこう!左手もこうしてこう!あとは足をいい感じに竹に乗っけてこれをこうしてこうやってうまいことこんな感じでこう!これをこう!こうしてこう!ほらね。安定して歩けるでしょう。」
お信の全く要領を得ない説明に宗助と他の子供達は一瞬唖然としたが、お信の自在な竹馬の乗りこなしに「すごいや。」と素直に感心した。一方のお信は「こうしてこう!」と得意げに言っては子供達の周囲をぐるぐると歩き回り、これに触発されて子供達も負けじと次々に竹馬に飛び乗った。
「あはは!あたしは竹馬お信よ!お馬鹿さんたちここまでおいで!」
そう言ってからかうお信を子供達は追いかけ始めた。
「竹馬お信め!逃げるなー!」
「ばーかばーか、捕まえてごらん!」
「まてー!」
「待つわけないでしょ、ホラこっちこっち!あはははは!孟宗竹!孟宗竹!」
そうしてお信と子供達が遊んでいるところへ、一台の車が止まった。
車には「民々楼・送迎用」と書かれてあり、中から宿の支配人が出てくると「居た居た!」と声を上げながらお信の方へ駆け寄って来た。
「お客さん大変です!」
「うるさい!モグラたたきだけじゃなくて今度は竹馬までジャマするつもり?いい加減にしないと孟宗竹で脳天ブチ砕くわよ。」
「違うんです、それどころじゃない!大変なんですって!」
「しつこいわね、なんなのよもう!」
「あなたのお母さんが事故に遭った!」
お信は竹馬から転げ落ちた。
*
支配人に抱きかかえられたお信が病室に入ると、継母は寝台で眠っており、その頭には包帯が巻かれていた。
すぐ隣に居た医師が言うには、
「取り急ぎ命に別状はありません。」
これを聞いてお信は涙が余計に溢れた。そしてようやく一人で立つ事ができたので継母の手に触れてみると、多少冷たい様な気もしたが確かに生きていると思った。ここで医師に事の次第を尋ねたところ、海岸通りを歩いていた継母は何のはずみか階段から落ちて頭を打ったらしく、偶然そこを通り掛かった車によって病院まで運ばれて来たのだという。
「頭をケガしたなんて……おかあさまは本当に大丈夫なんでしょうか。」
「頭部の外傷自体は小さいものです。とはいえ、経過を見る必要がありますので数日ここに入院して下さい。」
入院の手続きを終えたお信は支配人と共に再び病室へ戻ると、継母は相変わらず眠っていた。
「あたしはここに泊っていくからおじさんは帰るといいわ。」
おじさんは帰るといいわ。」
「ではそうさせてもらいます。」
と支配人は病室を出ようとしたところ、
「明日、おかあさまとあたしの荷物を持って来てね。着替えが入ってるの。」
「……はい。」
支配人は車で宿に帰って行った。
お信は寝ている継母の隣に座ると、その手を握りしめて「大丈夫、大丈夫。」と声を掛け続けた。途中、医師と看護婦が何度か回診に訪れたが、お信は「大丈夫。」とひとりそう言っては継母の手を離さなかった。
「ご家族の方に何かあったらそこのナースコールで呼び出して下さいね。」
お信は継母の身を案じつつも、耳を澄ますと寝息が聞こえてきたことで若干の安堵を覚えたのか、継母の息づかいの中で手を握りしめたままお信もいつの間にか眠っていた。
深夜。すっかり眠りこけているお信の手を継母がギュッと握り返した。
「おかあさま!気が付いたのね!」
とお信は声を上げたが、一方の継母は目を見開いて正面を向いている。
「心配したのよ、大丈夫?具合はどう?」
継母は何も答えなかった。
「ねえどうしたの?どこか痛むの?お医者さん呼ぼうか?おかあさまってば!」
すると継母は正面からお信へ顔を向け、継母とは思えぬ低い唸り声で次の様に言った。
「この愚か者めが……」
これに驚いたお信は椅子から転げ落ち、そして腰が抜けたままでナースコールの呼び出しボタンを震える指で連打した。
「はい。どうされましたか?」
「こ、こ、こ、この愚か者めが!」
「イタズラ電話はやめてください。」
「いやちがうの!なんていうかおかあさまの声がいきなりおかしくなっちゃって要するにこの愚か者めが!」
「とりあえずそちらに伺います。」
看護婦は継母の容体を確認したが特に変化は見られなかった。
「今日は色々あったことだし、あなたは疲れてるんですよ。」
お信を落ち着かせると看護婦は病室から出て行った。その直後、再び継母がお信の方へ顔を向けた──その視線は氷の様に冷たくお信の下に落ち、そして継母から「ううう……」と唸り声が上がると恐怖に慄いたお信は、朝のラジオ番組でいつの間にか覚えた陀羅尼の呪文、
「有に非ず、無に非ず、動に非ず、静に非ず、赤に非ず、白に非ず……」
これを継母に向かって一心に唱え続けたところ、継母の口から「空虚な文字列。」という言葉が返され、
「対象としての記号。」
「記号としての対象。」
継母はこれらの言葉を数回に分けて言い終えると最後に「この愚か者めが……」と吐き捨てる様に言って瞼が閉じられた。
この日を境に継母は一切の言葉を発しなくなった。
*
数日後。継母は脳の精密検査を受けた。
「異常は見られません。」
医師の言葉にお信は納得が行かず、
「おかしい。どうして異常が無いのにおかあさまは何もしゃべらなくなったの。」
「率直に申し上げて……」
そう言うと医師は続けて、
「よく分からないというのが現状です。そもそも事故による器質的変化であれば検査結果に現れるのですがご家族の場合ですと健康な人と何ら遜色はありませんでしたから原因の特定には至っていません。といって、またいつ容体が急変してもおかしくはない状況と思いますから引き続きの経過を見た上での判断になるでしょう。」
これを聞いたお信は無性にこの医師を殴りたくなったが、三日三晩に渡って継母を看病し続けたせいで精魂尽き果てており、そのため「はあ……」と溜息をつくだけであった。
病室に戻ると寝台の継母は相変わらず眠っており、隣には宿の支配人が居た。
「検査結果はどうだったですか?」
「異常は無いけど異常ありだそうよ。」
「どっちなんですか。」
「さあ。」
支配人は継母の着替えが入った紙袋をお信に差し出すと、
「ところであなたに身寄りの方はいないのですか?」
「いないわ。おかあさまだけ。」
と言ってお信は継母を一瞥した。
「一旦宿に戻ろうかな。」
病院を後にしたお信は、支配人の運転する車で民々楼へ向かった。その道中、支配人は「非常に申し上げにくいのですが。」と気まずそうな表情を浮かべて、
「今更で申し訳ない。宿に戻ってもあなたの部屋はありません。」
「どうして?」
「宿泊期間を過ぎたからです。当初あなた達親子は二泊三日の予定でしたからそれをとっくに過ぎた今、あの部屋には既に他のお客様がご宿泊されています。」
「ならソイツらをどかせばいい。」
「そんなことできるわけないでしょう。あなたは追加の宿泊代を払って頂いた上で、新たに別の部屋をお取り頂く必要があります。」
「はあ?宿代ですって?金はすべておかあさまの治療代にぶっこむから宿代なんざビタ一文払えないわ。」
「でしたらうちの宿はあきらめてもらうしかないです。」
「あのさあ。おじさんってばさあ……そら人情ってもんが無いわ!」
「どの口が言ってるんですか。」
「とりあえずおじさんの家にあたしを泊めなさいよ。」
「む、無理ですよ。うち狭いし……」
「じゃあさ!おじさんが宿代払って宿に泊まりなさいよ。で、あたしがおじさんの家に住むわ。」
「そりゃ無茶ですよ。」
「もう!じゃあどーすんのよ!」
こうしてお信と支配人が言い争っている内に民々楼へ着いたので、支配人は仕方なくお信を連れて館内に入った。
「おはようございます。」
と支配人に挨拶した仲居がお信を見るや、
「あら。どこかで見た顔だけど……もしかして支配人のお子さん?可愛いわねえ。」
「ちがいます。私の子じゃありません。」
「いいえ、あたしは支配人の隠し子よ。さっさと認知してちょうだい。」
「あなたは黙ってそこで待ってて下さい。」
と言うと支配人はお信を玄関口の椅子に座らせ、宿の従業員を集めて何か話し始めた──十数分後。お信の元に支配人が戻って来ると、
「結論から言うと、あなたはしばらくこの宿に居ていいです。」
「やった!おじさんありがとう!」
「ただし、あなたが寝泊まりするのは客室ではなく、今は使用してない小部屋なので少し汚いかもしれません。」
「なあに平気よ。」
「風呂も使って頂いて構いません。食事はまかない飯ですが朝昼晩の三食。」
「え、ご飯の世話までしてもらえるなんて。本当にいいの?」
「よくありません。」
そう言うと支配人は真剣な表情になった。
「まず部屋代は払わなくてもいいです、汚いので。ただ入浴代と食事代、当館としてもこれだけは払って頂きたい。」
「でもお金はおかあさまに全額ぶっこむから出せないわ。」
「そこでご相談です。あなたの職業は料理人でしょう?」
「まあね。」お信は嬉しかった。
「ですから、あなたはこの旅館の厨房で働いて、そこで稼いだお金で料金を支払えばいいわけです。」
これを聞いてお信は以前、厨房に潜入した際に板長と喧嘩したことを思い出した──あのクソ野郎の下で働くなんて……
「あなたにとって悪くない条件だと思います。厨房で働いてみてはどうですか?」
「ムリな話だわ。」
「なぜです?」
お信は途端に悲しい顔を拵えると、
「だって、厨房で働くとなると仕入れ、仕込み、調理、片付けといった感じで一日中つきっきりの仕事ですもの。お医者さんはあたしに言ったわ、おかあさまの容体はいつ急変してもおかしくないって。ということは、あたしはいつでも病院に駆けつけられるようにスタンバイしておく必要があるでしょう?だから拘束時間の長い厨房仕事は無理なの……」
「そういった事情なら仕方ないですね。では客室清掃はいかがでしょうか。」
「常にスタンバイしておかなきゃいけないから客室清掃も無理なの……」
「じゃあ風呂掃除は?」
「しつこいわね!何回言わせんのよ!スタンバイがあるってんだから何もかも無理なの!スタンバイ甘くみてんじゃないってのよ!ねえアンタさあ……なんなの?金と命どっちが大事なの?ねえどっち?命に決まってんでしょ!金の問題なんてどうとでもなるわよ!」
「え、どうとでもなるというのは?」
「……貸しなさいよ、金。」
「なぜ私が金を出さないといけないのですか……」
「あたしは金を出せって言ってるわけじゃなくて貸せって言ってるの!なによ!モグラたたきの時は気前よくポーンと五十円貸してくれたじゃないの!どうしてそれと同じことが今できないの?モグラ代は貸せるのになぜフロ代とメシ代は貸せないのかって聞いてんの!なにもアンタの金をふんだくろうとしてるわけじゃないんだから一瞬貸しとけってのよ!おかあさまが良くなったら全額返すんだから今は黙って貸しといてくれればいいじゃないのよ!」
言い終えるとお信はあまりの興奮に血が上りよろめいてしまったが、この様子を見ていた宿の女将が駆け寄って支えてやると、
「ねえ支配人。お金ぐらい貸してあげればいいじゃないですか。この子は母親思いのとっても優しい娘さんだと思いますよ。」
──どこがだよ。支配人はまずそう思ったが女将を含め、多くの従業員がこちらを見ている事に気付いた。
「……わかりました。滞在中のお金は少しだけ貸してあげます。」
こうしてお信は支配人の支援の下、民々楼に住みつく事ができたのである。
*
さらに数日後。お信はあてがわれた四畳半で、支配人が運んできた朝のまかない飯を食べ終えると宿の送迎車で病院へ向かった。
お信が病室に入ると継母はカレーライスを食べている最中であった。
「おかあさまってば、またカレーなの……」
「これしか食べません。」
付き添いの看護婦は首を傾げながらそう言った。
継母は事故に遭ってから三日後に眠りから覚め、ようやく固形食へ切り替わったが口にするのは最早カレーのみであった。
継母の反応は今日も無かった。
「ねえおかあさま。たまにはカレー以外にも何か食べてみたら?」
「…………」
「ねえ聞いてる?」
「…………」
「おい継母ァ!」
「…………」
お信の罵声も虚しく、継母はカレーを体に取り入れるとそのまま寝てしまった。
「再検査の結果も異常は見られません。ですが神経系に何か問題があるようにも見受けられます。」
怪訝な顔つきで医師はそう言った。
「おかあさまは良くなるんでしょうか。」
「何かのきっかけで突然回復することもあれば回復しないこともあります。」
「まさか死んだりはしないのよね?」
「引き続き経過を診ることにしましょう。」
この曖昧な回答に、再びお信は医師を殴りたい衝動に駆られたが「死ぬわけがない。」と気を取り直し、病室へと続く廊下をぼんやり歩いていたところ眩暈に襲われた。次いで、お信の脳裡に継母の声がよぎり──それは普段通りの調子であった。
「何をいまさら。ええ。やがて死ぬわ。あんたも私も一度は死ぬ。よかったわねお信。死を生きる現実は平等に与えられているといえるわね。」
お信は立ち上がると直ぐに病室へ戻ったが相変わらず継母は眠っており、傍らの看護婦に尋ねてもやはり眠っていたという──死なれてたまるか。して、あの医者は何かのきっかけで良くなるかもと言ってたっけ……
その夜、民々楼に帰ったお信は晩のまかない飯を食べ終えると、
「飯、足りねえよ」
と書いた紙きれを空き皿に乗せてから、厨房にこっそり返却した。
そして翌朝。支配人がまかない飯を持ってお信の部屋を訪れると、当のお信はモグラを両脇に抱えて寝ていた。
支配人は二体のモグラの内、一体だけを取り上げたところお信が目を覚ましたので、ふたりは向かい合って朝ご飯を食べ始めた。
支配人はお櫃のフタを取った。
「なんだか今日はご飯の量が多いですね。」
「成功だわ……」
早速お信は飯の余りでおにぎりを拵えると、今日も病院へ向かった。
「ほら見ておかあさま。今日はおにぎりを作ったから食べてみて。」
継母はおにぎりに見向きもせずカレーを体内に取り込んだ。
別の日、お信は病院の調理場を借りた。
「おかあさま、今日はラーメンを作ったの。カレーばっかり食べてると余計頭がヘンになるわ。ね、ラーメン食べてみない?」
継母は正面を向いたまま全くの無表情であった。
お信が継母の肌に触れると現実的な存在としての継母を確かに認めはするものの──それはお信の思い込みであろうか、それ自体から自分が斥けられている様にも感じられ、目の前に在りながらどこか真実性を欠いた何かを認めたところでその果てに陥るのは──お信は宿の自室でひとり頭を抱えていた。何をどうすれば継母が元通り良くなるのか見当が付かなかった。医者の言う「何かのきっかけ」を真に受けて拵えたおにぎりとラーメン、それらは全て徒労に終わったが、それよりもお信は自分の存在にすら気付かない継母というものが何より辛く、継母が告げた「やがて死ぬわ。」という言葉が再び脳裡をよぎると居ても立っても居られなくなった。
*
その晩、民々楼の厨房でひと仕事終えた板長が焼酎を飲んでいたところ、のれんから顔だけを覗かせる者がいる。
「またお前か。」
「こんばんは。ラーメンお信です。」
「部外者は出てけ。」
「出てけと言われりゃあたしゃ出ていきますけど、その前に一言申し上げておきたいことがありまして。」
そう言うとお信は厨房へ入った。
「何だ。」
「あたしのおかあさまのために料理をしてほしいんです。何か作ってやってください。」
「嫌だ。」
「板長の料理の腕を見込んでのお願いなの。あなたにしかできない相談なの。一品だけでいいからどうかお願いします。」
「嫌だ。自分でやりな。」
「あたしの料理だとおかあさまは見向きもしないんです。このままだとカレーの食べ過ぎで気が狂って死ぬかもしれません。だからおかあさまを救ってやってくれませんか。」
「断る。帰れ。馬鹿。」
「この人でなしのクサレ板長がァ!」
早々に堪忍袋の緒が切れたお信は板長に飛び掛かったがあっけなくかわされてしまい、反対に首根っこを掴まれると、そのまま厨房の勝手口まで引きずられて行った。
「二度と来るなよ。」
板長がお信を放り捨てようと勝手口の扉を開けたところで、
「父ちゃん!やめてあげて!」
と板長に待ったを掛けたのは、かつてお信と竹馬で遊んだ子供──宗助であった。先程から一部始終を盗み聞きしていた宗助は勝手口の前に立ちはだかった。
「宗助。邪魔だ、どけ。」
「やだ!だってこのおねえちゃんは僕に竹馬を教えてくれたんだもの。おかげで僕も上手に乗れるようになったんだ……なのに父ちゃんったらひどいよ!料理ぐらいしてあげればいいじゃん!竹馬お信がかわいそうだよ!」
「竹馬お信?」板長はお信を見た。
「そう。あたしはラーメンお信、またの名を竹馬お信。」
とりあえず板長は、息子の宗助に「お前も出てけ馬鹿野郎。」と頭に拳骨を食らわせると宗助は声を上げてわんわん泣き始めた──これに触発されたお信は自分をかばってくれた宗助の仇を討つことを誓うと、相変わらず板長に首根っこを掴まれたまま身動きが取れない状態ではあったものの、すぐ傍らの大きなぬか樽が目に付いた。
「ぬかみそ掻きまわして古漬けを取り出すぐらい自分でやんなさいよ。」
これはお信が継母にさんざん言われてきた小言である。
「このクサレ板長の顔面にぬかみそをぶち撒けてやる……」
泣きわめく息子に板長は呆れたのかお信を掴んでいた手が一瞬緩んだ。すかさずお信は精一杯腕を伸ばしてぬか樽に己の手を突っ込むと──お信の亡き実母マサヱが、そして亡き父親がぬかを通じてお信の中に浮かび上がってきた。
「お信ちゃん。大きくなったわね。」
実母マサヱの声に続いて、
「お信。善く生きろよ。」
父の声がお信の中に響き渡ると、
「おとうちゃん、おかあちゃん……」
お信は大泣きに泣いた。これを受けてどうした事か宗助も一層泣きわめき、ふたりの泣き声は厨房中にこだました。
板長はこの様子に訳も分からずお信を掴んでいた手を離してやると、自身も疲れたのかその場に座り込んで訳を尋ねることにした。
*
「ああ、そうだ。このぬかは確かにお前の親父さんから頂いたものだ。」
「やっぱり……」
「政五郎さんにはその昔、えらい世話になったがああも簡単に逝っちまうとはな。」
お信の父・政五郎と板長は料理人修業時代の師弟関係にあり、そして板長が独立の際、政五郎は餞別として先祖代々受け継がれたぬかと共にこのぬか樽を板長に贈ったのだという。ふたりはそれぞれの独立後、顔を合わせることは遂に無かったが、政五郎の死だけは人づてに聞かされていた。
「にしても……お前が政五郎さんの娘だったとは驚いたな。」
「うん。おとうちゃんはとっくに死んじゃったけどね。でね、おかあちゃんももう死んじゃったの。でも、おかあさまはまだ生きてるってわけ。」
「何言ってんだお前は。」
ここでようやくお信は、継母が事故に遭ってから今日に至るまでの一部始終を板長に語って聞かせた。そして改めて継母の為に何か作ってもらえないか恐る恐るお願いすると、
「また明日の夜ここに来い。」板長は続けて、
「あとな、俺は板長じゃなくて宗十郎だ。次からそう呼べ。」
お信は宗十郎に礼を言うと素直に部屋へと戻っていったので、宗十郎も宗助を連れて厨房を後にした。
そして明くる日の晩、お信と宗十郎は厨房で向かい合っていた。
「では宗十郎さん。料理の方をひとつお願いね。」
「嫌だ。」
「え、昨日約束したじゃん。」
「してない。俺は、また明日来いと言っただけだ。」
「じゃあ料理は一体誰が……」
「料理はお信、お前がやれ。」
「無理だわ。だっておかあさまはあたしの料理なんて見向きもしないんだもの。」
「そんなら俺の料理ではいよいよ無理だな。」
「どうしてなの?」
「細かいことはいいからつべこべ言わずにお前が手を動かせ。どうにかしてやるから。」
「……はあい。」
とは言ったもののお信は何をどうすればいいか分からずまな板の前で硬直してしまった。
宗十郎は胡瓜のぬか漬けで焼酎を呑み始めた。これを見たお信は昨日と同様、ぬか樽に手を突っ込んでみた。
しかし、父と実母の声は聞こえなかった。
「母親に何を食べさせるか決まったか?」
「……モグラの姿焼き。」
「何も決まってないみたいだな。来い。」
宗十郎はお信を連れて厨房から受付前の広間に来ると、そこに宿泊客の老夫婦が居た。
「お信、むこうに年寄りが座ってるだろ。」
「そうさね。」
「もしお前がこの旅館の料理人なら、あの年寄り夫婦にどんな料理を出す?」
「満漢全席。」
「馬鹿かお前は。」
次に宗十郎は、受付でうたた寝をしている支配人を指差した。
「お前ならあの狸おやじの為に何を作る?」
「ラーメンライス。」
「悪くはねえな。」と宗十郎は続けて、
「いいかお信。前にお前が母親に作ったおにぎりとラーメンは自発の産物。お前が何を食わしたいかではなく、今現在相手が何を望むのか直感しろ。これが料理の基本にして最後の肝心だ。」
「おかあさまが望むもの……」
お信と宗十郎は厨房へ戻ることにした。
*
お信はまな板の前に立つと目を閉じた。
数分が経過した。宗十郎が訝しげにその様子を眺めていると不意にお信は、
「おとうちゃん。」
とつぶやいたがその声は宗十郎には聞こえなかった。依然お信は目を閉じたままである。
お信から再び「おとうちゃん。」という言葉が出ると今度は平静の様子で宗十郎の顔をじっと見た。
「どうした。」
お信は沈黙したまま改めて宗十郎を見たが宗十郎自身はその視線を感じなかった。
「どうした。」
また数分が経過した。ここで宗十郎はお信を察し、その視線が此方の顔から首の方にかけて徐々に下がっていくのを認めた。
「おとうちゃん。」
これに対して宗十郎の口から自然と「生憎だが……」という断りが出ると、
「昨日の晩、俺は家でこんなものを見つけた。が、しかし。」
そう言うと宗十郎は懐から一枚の紙切れを取り出した──紙にはかつて何か書かれてあったようだが経年劣化に伴い、紙は焦げ茶に変色、染料が滲んでいることに加えて虫食いで穴だらけであり、かろうじて「政五郎」と父の名前が書いてあることしか判別できない状態であった。
「どうやらお前の親父さんが残したものと思うがとても読めたもんじゃねえ。」
「見せて。」
ここでようやくお信の声を認めた宗十郎がボロボロの紙切れを手渡した瞬間、お信は全てを直感した。
お信によるとその紙切れには──
是は秘中の秘なり みだりにすべからず
まず豆腐よきほどにきり
葛湯を土鍋にて常のごとく煮て
あみ杓子にてすくひ
器へよそひ 山葵みそ少し固くして
器の端に塗りつけ 豆腐をみそに
引きずりて食するべし
みそのこきうすき加減だいじなり
膳に供すれば 元気をまし
身体すこやかならしむ
考を尽くさんとならば財を愛すべからず
政五郎
読み終えたお信はその内容を宗十郎にも話して聞かせた。
「これこそおかあさまが望む一品だわ。宗十郎さん、おとうちゃん、ありがとう。」
「俺にはただの湯豆腐としか思えねえんだがな……」
「いいえ、全く違うわ。」お信は断言した。
「ねえ、宗十郎さん。豆腐はある?」
「ああ。」
「葛粉と味噌はある?あと土鍋は?」
「好きに使いな。」
その晩、お信は父・政五郎が残した秘中の秘、その調理法に従ってこの一品を完成させるべく試行錯誤を繰り返した。
まず、お信は豆腐を「よきほどに」切った。葛湯を「常のごとく」煮た。味噌の「こきうすき」を加減した。その最中、宗十郎はお信の素人包丁に何度も口を挟もうとしたが、お信と政五郎の絆に確信めいたものを覚えたため何も言わず作業を見守ることにした。
そして夜明け前。とうとうお信の口から「できた!」という声と共に完成した料理を宗十郎が見ると──灼熱の葛湯で煮えたぎる土鍋の中に豆腐が湯気を立てて浮かんでいたのである。
*
その日の朝。
支配人の運転する車には、土鍋と食材の入った紙袋を大事そうに抱えたお信、そして宗十郎が乗っていた。支配人は宗十郎が居ることに疑問を感じたが、彼らのただならぬ雰囲気に気圧されて何も言わずに病院まで車を走らせ続けた。
三人は継母が居る病室の入口まで来ると、
「おじさんはここで待ってて。」
とお信が言うので支配人は病室には入らず、扉の前で待たされることになり、一方のお信と宗十郎は病室をそのまま過ぎて病院内の調理場に侵入した。
十数分後、烈火の如く煮えたぎる土鍋を盆に乗せたお信とそれに続いて宗十郎が調理場から出てくると、再び病室へと向かった。
支配人の「土鍋?そんなもの持ってどうするつもりですか。」と言う声を無視して宗十郎は病室の扉を勢いよく開けたところ、そこには虚ろな目をした継母が今まさにカレーを食べようとするところであった。
「宗十郎さん!おかあさまを止めて!」
「おう。」
宗十郎は継母に駆け寄るとまずはカレー皿を取り上げようと継母の手を掴んだが、継母は激しく抵抗して皿を離そうとしない。宗十郎にとってこの女性の腕力、一方で虚無に満ちた表情は驚異であった。
「なんて力だ……びくともしねえ!おい支配人!黙って見てねえでお前も手伝え!」
「は、はい。」
支配人がカレー皿を掴むと宗十郎は後ろへ回り、継母を羽交い絞めにした。すると一瞬、皿を掴んでいた継母の指が浮いたのでその隙を突いて支配人は継母からカレー皿を奪い取ることに成功した。
「おじさん!それ持って遠くに逃げて!」
「え、逃げるってどこへ?」
「インドでもエジプトでも西荻窪でもどこでもいいから今すぐこの場から逃げてって言ってんの!さっさと行け!」
お信に言われるがまま支配人はカレー皿を持って病室から飛び出してどこかへ行った。
宗十郎は相変わらず継母を羽交い絞めにしていたが、カレーを奪われた継母がさらに抵抗し始めたのでこれに負けじと宗十郎も力を加えたがしかし、それはかろうじて継母の動きを封じ込めたに過ぎず、宗十郎の手は徐々に震えはじめた。
「とても女の力とは思えねえ……おいお信!早くしてくれ!」
「わかってる!」
お信は煮えたぎる土鍋の中に匙を突っ込んで、灼熱の葛餡を纏った豆腐をすくい上げると豆腐に味噌を塗りつけた。そして羽交い絞めにされている継母の口元まで匙を近づけたところ、継母の抵抗がさらに激しくなったため、宗十郎は最後の力を振り絞って継母を押さえつけた。
「お信!それを早く母親に食わせろ!」
がしかし、ここへきて継母は口を固く閉じて歯を食いしばった。
この最後の抵抗を目の当たりにした宗十郎は「俺はもう限界だ……」と諦めて力尽きようとしていた矢先、お信が継母の鼻をギュッとつまんだ──反射的に継母の口が開いた。
「おかあさま……つめが甘かったわね!」
「今だ!いけお信!」
お信は継母の口の中めがけて灼熱の餡かけ豆腐をぶちこんだ──口中に広がっていった豆腐は全身を駆け巡って最奥の領域に達するとそこから黒い塊がとぐろを巻きながら継母の脳まで昇ってたちまち渦と化し、そこに豆腐の白が重なった。継母は意識が徐々に鮮明になる中で渦の中心にある「目」を見た気がしたが塊の黒は白へと染まり、続いて継母の視界だけが歪むと再び意識が遠のいていくその中で渦は一瞬の内に継母から発散していった。と、ここで継母は舌の上でほとばしる豆腐を実感した。
「熱ッ!」
と叫んだ継母は熱さのあまり豆腐を吐き出した。目の前にはお信が次の豆腐を匙に乗せ、継母に食べさせようとしている。
「ちょっとお信やめなさい!あんた親に向かってなんて事すんのよ!」
宗十郎は継母を掴んでいた手を離すと、
「お信やめとけ。もう大丈夫だ。」
と言ったが無我夢中のお信にはまるで聞こえておらず、灼熱の餡かけ豆腐を継母の口に放り込もうとしていた。
「どなたか知りませんがお信を止めてやってください!」
継母からお願いされた宗十郎は、今度はお信を羽交い絞めにすると、ここでお信もようやく我に返った。
今、お信の前には継母の「熱い熱い。」と言って頻りに水を飲む姿があった──熱い熱いの調子は昨日までの虚無に満ちた目や低い唸り声ではなく、普段の継母通りであった。
この光景を俄かに信じられなかったお信は試しに「おい継母ァ!」とおそるおそる言ってみた。すると、
「黙りなさい!さっきからどうしたというの。で、そもそもここは一体どこなの……お信、順を追って説明しなさい。」
と継母が鋭い目つきと聴き慣れた声でお信を叱りつけたため、お信は泣きながら「いつものおかあさま!」と言って継母の胸に飛び込んだ。
「元に戻ったのね!会いたかったわ!」
「ああ熱い熱い。」
こうして舌に負ったやけどにより継母の退院はさらに二日延びたのである。
*
継母の退院後。
ようやく熱海から東京へ帰る事になったふたりは、民々楼で最後の挨拶をしているところであった。
「この度は多大なご迷惑をお掛けして申し訳ありません。宿からお借りしたお金は東京に着き次第すぐに送金させて頂きますので。」
継母が深々と頭を下げると支配人はようやく胸を撫でおろした。
「おじさん、本当にありがとう。」
お信の言葉を聞いて支配人は、この子と過ごした拷問の様な日々から解放されるのかと思うと泣けてきた。もう二度とこの宿に来てくれるなとすら思った。
「またいつでも来い。」
宗十郎はお信にそう言うと「親父さんの供養には必ず行くから。」と袂から一片の紙切れ──政五郎秘中の秘を手渡した。
「おとうちゃんの形見だと思って大事にするね。」
「宗十郎さん、東京に是非いらして下さい。うちの人もきっと喜びますわ。」
継母はそう言うとまた丁寧にお辞儀をした──それにしても。あの目、そしてあの渦の様なものは何だったのか。幻覚、幻聴とは果たしてああいったものなのだろうか。今はある程度の理解にまで及ばないが東京に帰ったらゆっくり考えてみよう……と思い返している傍で、お信と宗十郎は小声で何やら話している。
「おかあさま。ここを出るまでにまだ時間はあるわよね?」
「まあ多少ならいいけど、どうして。」
「いいからちょっと来て。」
お信は継母の手を引いて厨房へ入ると「急がなきゃ。」と言って豆腐を切り土鍋に火をかけた。そして案の定、継母の前に煮えたぎる土鍋が置かれると、
「さ、おかあさま。食べてみて。」
「またこれか。あまり気が進まないわね。」
「前におかあさまが病院で食べたときは気が動転して味が分からなかったと思うけど、今はもう落ち着いたことだしさ、今度はよく味わって食べてほしいの。」
「食べたらすぐ出発よ。」
「うん!熱いから気をつけて食べてね。」
「知ってる。」
継母は、灼熱の餡かけ豆腐を匙で掬うと粗熱が取れるのを待ってから口に運んだ──まだ少し熱いが素直に美味しいと感じた。亡き夫の料理と同じ味がした。途端に熱を感じなくなった。味が消えた。すると目の前のお信も消えた。宗十郎も消え、土鍋も厨房の調理器具も次から次へと消えると厨房も含めた全体が空白になり、そこにお信の姿だけがぼうっと現れ、何の変哲もない普段通りのお信が片腕を伸ばして指を差したその先には虚空に浮かんだ豆腐一丁、そのままお信は継母と共に豆腐の白へ消え入った。
「ねえおかあさま。モイスチャーってこういう事だと思うの。」
「……熱ッ。」
継母は宗十郎の差し出したコップの水を少しだけ飲み、そして豆腐をもう一口食べてから「どう?おいしい?」と嬉しそうに尋ねるお信にこう言った。
「ごちそうさま。」
そうしてお信と継母は民々楼を後にして東京へと帰ったのである。
*
彼岸もとうに過ぎて冬の寒さもひとしお、年の瀬はすぐそこに迫っていた。
暮れという季節は多くの人を敏感にさせるのであろうか、来たる正月の高揚に往来は普段以上に溌剌としており、そうした多くが行き交う中を鴇色に無地の袷、黒い羽織を重ねた装いで歩いていたのは継母であった。
その姿は取り込みごとの多い季節にただひとり落ち付き払っているように見えたが、本人にしてみればそれは見当違いというものであり、継母は蛇目傘を差していた──細かい雨の降る晩であった。
継母はラーメンお信ののれんを潜った。
「お信ちゃん、ただいま。」
「あ、おかあさま。おかえりなさい。」
店内は多くの客で賑わっていた。ここも師走だなと思いつつ継母は顔見知りの常連に暮れの挨拶を済ませると奥のカウンター席に座ろうとしたが、卓上に「予約席」と書かれた札が置いてあったため継母は首を傾げた。と、それに気づいてお信がこちらにやって来た。
「おかあさま専用にあたしが予約しておいたの。席が埋まりがちだから。」
「私の事なんて気にしなくていいのよ。」
「ほんとは嬉しいくせに。」
継母をからかうとお信は続けて、
「晩ごはんまだでしょう。どうする?」
継母は壁に掛けられたメニューを見た。
・ラーメン ── 三百円
・お信ラーメン ── 四百円
・カレー ── 三百円
・お信カレー ── 四百円
・おしんこ ── 五十円
・ガーリックシュリンプ ── 三百円
そうしたいつものメニューの隣には、
・モイスチャー ── 時価
継母はクスッと笑った。
「ねえおかあさま、何が食べたい?」
「モイスチャーにしようかな。」
「はあい。」
早速お信は土鍋に葛湯を入れて火をかけ、そして豆腐を取りに冷蔵庫へと向かったのである。
【完】
付録①「お信・人物相関図」

付録②「お信百景」

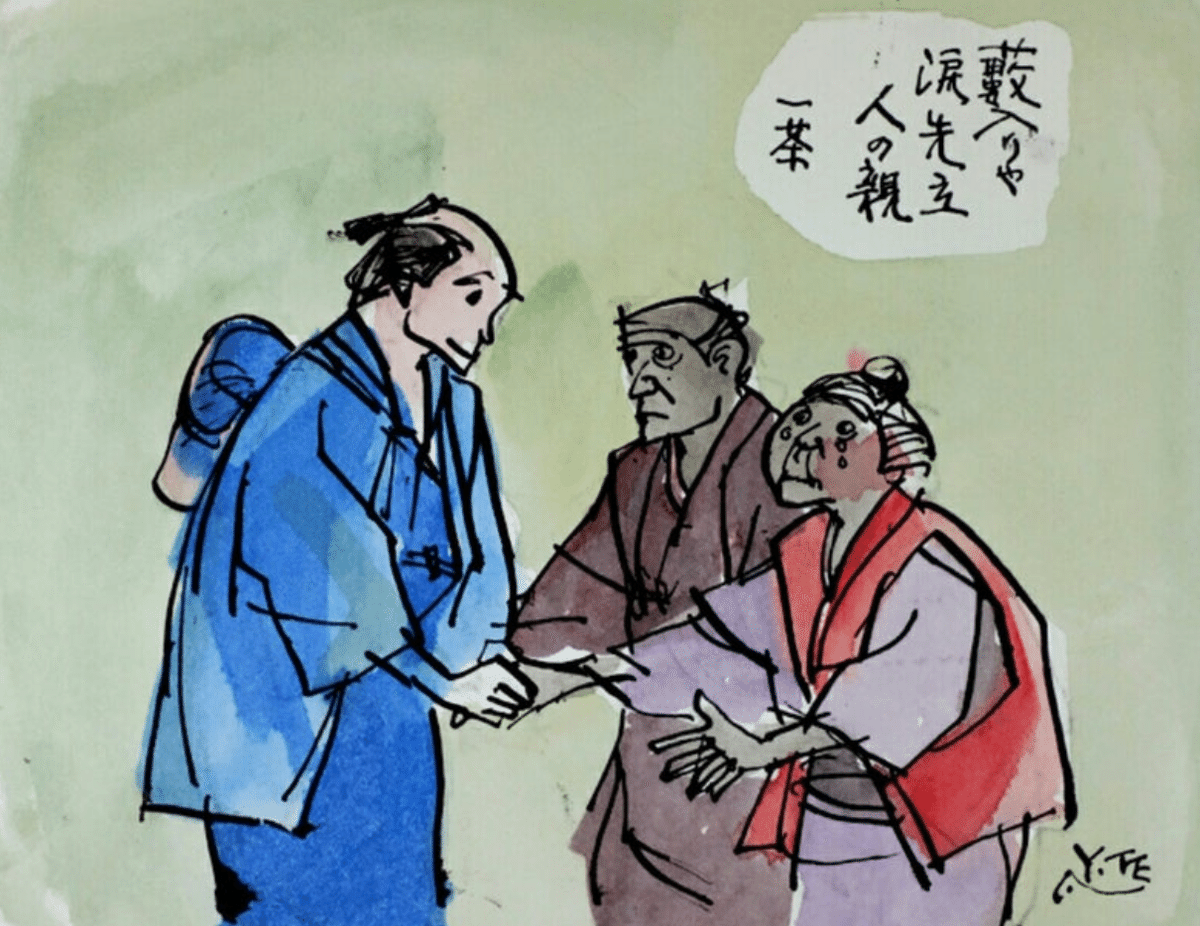
と皮肉交じりにそう言ったが「えへへ。」とお信は継母の話をまるで聞いていない。

継母は窓側の席に座った。お信は通路側の席に座るやいなや下駄を脱ぎ、そして全体重を掛けて椅子の背もたれを百八十度後ろに倒した。

「違うわ太平洋よ。手前は相模湾。」と継母。
「いいえ、ここは日本よ。日本の海だから日本海が正しいわ!」
と言い張るお信の理屈に誰一人言及することもなく、列車は真鶴から湯河原へと向かった。


「よく言うわね。ついさっきあんたも男の人をバリカンで殴ろうとしてたでしょう。」

「そんなもので何するつもり?」
「宮を殴る。」

そう書かれてはいるものの何がなんだかよく分からない。 お信は、室蘭で茶づけを味わう清くんの姿を想像しながら、傍らの『館内施設のご案内』という冊子を開いた。


これを目の当たりにしたお信は腰が抜けた。

言い終えるとお信は刺身を睨みつけた。




「はい。どうされましたか?」
「こ、こ、こ、この愚か者めが!」
「イタズラ電話はやめてください。」

スタンバイ甘くみてんじゃないってのよ!



「おかあさま……つめが甘かったわね!」
以上
