
Weekly自分_220912-220918_知らない間に...
はじめに
このnoteの無料部分では、僕が日々なんとなくやっている『糸井重里さんの「今日のダーリン」を読んだ感想文』が見れます。
また、有料部分は今週気になった情報のリンク集になっています。
特に気になったものは所見みたいなものも書いてあるので気になる人はぜひ購読してください。
今週の雑感
昨日、高松に行っていました。
用事は日中に終わったので、終電の時間までいろいろと街でも見てみるかと思いブラブラしていました。
高松、角を曲がればうどん屋さんが見つかる、なんてことも意外とないのですが、美味しそうなお店があるなぁと思いながら歩いていました。
高松、中心街が平らで自転車があれば本当にどこまでも行けてしまうので本当に好きな街です。
うどんもビールも美味しかったです。
今週の「今日のダーリン」を読んで
9月12日
『主人公があかるく元気なので、つい見入ってしまった』
『その人がいると元気になるような人は、声がよく出ている』
『じぶんがあかるい声を出していると、その声を、じぶんも聞くからあかるくなる、そういう好循環があるんじゃないか』
『「日々の祈り」とか「念仏」とかも、そういうもの』
という言葉を拾いました。
僕も昔はなんとなく「自分が思うかっこいい像」みたいなものがあって、そのイメージになんとなく自分を近づけてみようとしていました。
ただ、それをしていても全然楽しくない!
だって必要なことしか喋らないようなキャラクターだったんだもの!
そういう無理をしているとギャップみたいなものがやっぱりあって、初対面の人にはそのギャップを持ったキャラクターで認識されちゃうものだから、飲みにいったときとかに素が出てしまうともう大変で、「ぜんぜん違いますね〜」みたいな話になったりしたりしていました。
それが徐々にめんどくさくなってしまい、少しづつありのままでいるようにしたのですが、そうするともう楽で楽で…みたいな経験があったなぁと思いました。
いつもニコニコ現金払い
そんな言葉がモットーです
9月13日
『直感をもっと信じろと言われる。そうだ、直感的にそう思う』
『反射的な感情にとらわれてはいけないとも言われる。そうだ、それは危なっかしすぎる。』
『直感とか感情のなかには、「人間」がいる。理屈や論理のなかには、「ほんと」がある。』
『人間はほんとだけで生きていないものだから、ややこしい』
という言葉を拾いました。
最近、バランス感覚というものを考えています。
おそらく「ルーズな文化とタイトな文化」という本を読んでいるからなのですが、僕たちはあんがい白黒はっきりした分かれ方ができないものだなと思っていたことがあながち間違っていないらしいぞということが書かれている本で、最近はそれを夢中で読んでいます。
野生の反対が理性だとするならば、今の世の中はとても理性的にできているように思ったりするのですが、その理性というものは長い時間を掛けて今の人にとっての野生みたいなものにとって変わるような気もしています。
人類が科学みたいな物語を見つけてから2000年くらい経ったと思うのですが、その間に無造作に積み上げられてきて、真ん中らへんでぺちゃんこになってしまっている野生だか理性だかわからんものの棚卸しをするタイミングがもしかすると来ているのかもしれないなぁと思います。
知らんけどね。
9月14日
『糸井重里さんは、「読書百選」みたいなことばかり、ずっとやってきているような気がするそうだ』
という言葉を拾いました。
いろんな人が気軽にオススメしたりされたりする場所はきっとなんだかいい場所なんだろうなと思ったりしています。
ただ、そういった場所がどういった条件で成り立つかは今一つわかっていません。
というのも、今の時代はおそらく「情報の時代」というもので、情報が大きな価値を持っている時代とも言えてしまうので、そんな価値のあるものをポンポン共有しあえるような場所というものはなかなか成立しなさそうな予感がしています。
かと言って、情報は情報の形では何も価値を持たないのも事実です。
きちんと誰かによって使われないとその効用がわからない、みたいな感じです。
ここまで書いてみて、「あぁそうか、これもバランスの話をしていたのか」と気づいたりしています。
下半期の個人的なテーマは『バランス』に決定かもしれません。
9月15日
『「死が来る」は「帰り支度」』
『死というのは、「死がある」のではなく、個人の総体が「消える」側面も持っています』
『昔よりケチになって、同時に気前よくなってもいるようだ』
という言葉を拾いました。
生まれようとして生まれたわけではないのだから、死のうとして死んでいくものでもないように最近感じています。
形あるものはいつか滅すると言ったりしますが、形というものが何にあって何にないかが生きれば生きるほどわからなくなるように思っています。
「へうげもの」という漫画に丿貫という登場人物がいて、そのキャラクターの最後も本当に自分の身の回りの一切合切を処分しきってスッといなくなってしまう様が本当に美しいなと思ったりしました。
西洋や中東だと自分の名前の付いた建物を寄進したりして後世に自分の名前を残したりしていますが、それも自分や一族のためのものではなくて公共性を持ったものなので、半分くらい他人のものなのかもしれませんね。
思い出だけを残すのも難しいですね。
9月16日
『「口説き落とせなそうで、落とせそう」というあたりが、いちばんモテる』
『「解けないわけでもない難問」というものを、一部の人間はあんがい好きなのかもしれない』
『大人たち、ほんとうの難問にはちょっと疲れているからね』
という言葉を拾いました。
辛そうで辛くない少し辛いラー油みたいなものなのだろうなぁと思いました。
電車に貼ってある受験問題の広告、僕もついつい深く考えてしまったり一緒に乗ってる人に問いかけてみたりして楽しむような人なのですが、本当にすごく適切に問題を選んでいるように思っていて、発想力や一度解いたことがあるかを見るような問題を多く出題されているように思います。
受験勉強は詰め込みだ!と言っている人もいるように思うのですが、僕は別にそんなこともないように思っていて、受験勉強も中盤くらいから楽しくなってきてしまったタイプに人間でした。
わからないことがわかるようになるのは楽しいのですが、そこまで行くのに少し時間が掛かってしまうのは悩ましいところではありますね。
あのブドウはきっと酸っぱい!なんて言ったりもしますけども。
9月17日
『同じ「知ってる」でも、実はそれぞれの「知ってる」はちがう』
『おれの思うそれは、おまえの思うそれとちがう』
『ちがうものが、重なったりつながったりもするから愉快』
という言葉を拾いました。
こういうときに、ついつい「どこまで知っているのか?」でマウントを取ってしまいたくなってしまいがちなのですが、最近はそれをぐっとこらえるようにしています。
それは自分がある程度おじさんになってきたことも関係あると思っています。
だって年長者の方が詳しいに決まってんじゃん!しかも年長者側から聞いてきてるってことは絶対にある程度調べてるじゃん!
って思ってしまうからです。
カモノハシみたいに口頭で説明されたらいったいどんな動物なのかわからなくなってしまいそうな生き物の話も、標本だったり写真や動画などがあると一気に伝えやすくなったりするので、もしかすると大切なのはメディアなのかもしれませんね。
知らんけど!
9月18日
『送り手の経験をしっかり感じている人は、受け手になったとき、送り手のことも想像する。受け手としていろいろ感じている人は、送り手になったとき、受け手を想像して工夫する。』
『あっちと、こっちは、どっちも』
『受け手で送り手。消費者で生産者。口説かれる人で口説く人。教わる人で教える人。「&」で行ったり来たりさせてみたい。』
という言葉を拾いました。
どちらにもなれるほうがきっと豊かなのだろうなぁと思います。
ただ、両方になるのは本当に難しいので、どこかでどちらかで進むと決めないといけないような気もしていて、なかなか決めることも難しいなぁと思います。
そう考えると「何かを決める」という事は思った以上に自分の中のリソースを喰ってしまう行為なのかもしれません。
とは言っても、決めない状態をずっと続けていると先に進んでいたものも先に進まなくなったりするので、決めない状態を維持し続けるのも良くないのかなぁと思います。
決めることと決めないことの一番いいバランスはどういう具合で決めたらいいのかなぁとたまに悩んだりもしますが、時間が解決してくれたりもすると思うのでほどほどにしとこうと思います。
以下有料部分
さて、ここから下は購入者限定になります。
内容は今週の気になるトピックに関してだったり、ネットサーフィンしてて有用だなと思ったリンク集になります。
気になる人は100円で僕が飽きて更新を止めるまでは新しいものも見放題なので買ってみてね!
ここから先は
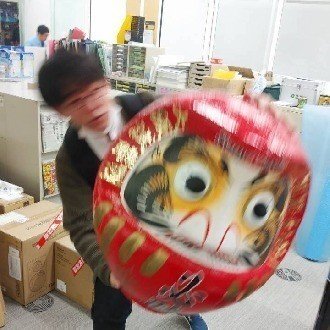
更新終了-有益なことは書かない日記
備忘録代わりに日記を書いています。
大阪で音楽関係の仕事をしています。 アニメや漫画、TVゲームからボードゲームまで広く遊びが好きです。
