
戦争の原因を探ることの難しさを論じた『戦争の原因』(2010)の紹介
ジャック・レヴィ(Jack S. Levy)とウィリアム・トンプソン(William R. Thompson)は戦争の研究で数多くの業績があるアメリカの政治学者であり、2010年に『戦争の原因(Causes of War)』という著作を出版しています。これは戦争の原因を説明するために構築されてきた理論を系統的に整理し、紹介したもので、これまでの研究成果を概観するときに役に立ちます。
Levy, J. S. & W. R. Thompson. (2010). Causes of War. Wiley-Blackwell.
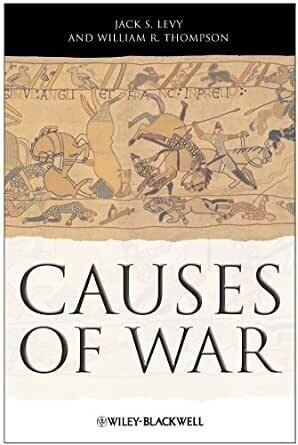
1 戦争学の序論
2 システム・レベルの理論
3 二国間の相互作用
4 国家と社会のレベル
5 意思決定:個人レベル
6 意思決定:組織レベル
7 内戦
8 結論:分析レベル、原因、戦争
戦争は「広義には政治的組織の間の持続的か組織的な暴力」として定義されますが(p. 5)、その形態は実に多種多様です。第一次世界大戦のような大国間の戦争だけが戦争ではなく、イラクやアフガニスタンで起きた非国家主体による反乱、さらに前近代社会における部族間で起きた戦争も戦争の一種として捉えることができるでしょう。そのため、やや曖昧さが残る定義であるともいえます。
しかし、著者らはあらゆる暴力を戦争と捉える見方には反対しています。彼らはカール・フォン・クラウゼヴィッツの議論を踏まえ、戦争において見られる暴力が、他の社会的状況で見られる暴力に比べて、限界近くまで拡大する性質があるという立場をとっており、また戦争が政治的目的を達成するための手段であることを強調しています。つまり、戦争は政治と切り離して理解することが不可能な事象であり、この視点を研究の基礎と見なしています。
「戦争が始まると外交は止まり、外交と武力は国益を維持、促進するための2つの代替的な戦略であると主張されることがある。このような見方は誤解を招きやすい。武力の行使やその威嚇は、しばしば交渉戦略にとって不可欠な要素となる。武力行使は、敵対国の費用と便益の計算に影響を与え、敵対国の行動を変えるように説得することを目的としているという点において、高度に強制的な活動である。その目的は、戦争を続ける費用が十分に大きいために、交渉による解決を通じて直ちに譲歩することが有利であると敵対国に悟らせることにある」(Ibid.: 9)
著者らの考えでは、単なる紛争と戦争は区別すべきものとされています。例えば、敵対的な二国間の国境地帯で小規模な衝突が起き、一方、あるいは双方に死傷者が出たとしても、それを直ちに戦争と見なすべきではありません。
なぜなら、それは一過性の衝突である限り、本格的な政治的な交渉には至らないためです。そのような衝突が持続性を持った戦闘になるようなエスカレーションを引き起こしたならば、それは戦争と呼ぶに値するようになります。このような局面では、国家は数週間、あるいは数か月にわたって部隊を移動、展開させ、それぞれの立場を主張し、その決意の強さを誇示しようと駆け引きを始めるためです。
このように戦争を捉えた上で、著者らは戦争の原因を説明する理論を3つのグループに区分することができると述べています。これは政治学者のケネス・ウォルツの著作『人間・国家・戦争』(1959)の枠組みに沿った整理の仕方であり、ウォルツは戦争原因論の類型として、信念、性格、心理的プロセス、政治的社会化など個人レベルの要因に着目したもの、政治制度、利益団体、社会構造といった国家レベルの要因に着目したもの、そして国力の分布、同盟のパターン、国際社会の構造といった国際システム・レベルの要因に着目したものに大別できると論じていました。著者らはこの枠組みを受け入れることによって、最近の研究成果を体系的に整理するための枠組みを導入しています。それが本書の章立てにも反映されています。
本書の内容をすべてをもれなく紹介することは難しいのですが、結論を先取りすると、著者らは戦争の原因を考える場合、多様な経路が戦争の発生に関係していることを示そうとしています。戦争は必ずしも一定の因果関係で発生するような事象として考えることはできず、異なる要因が異なる経路で作用しているにもかかわらず、同じような結果が生じる可能性があるのです。
まず、システム・レベルで戦争の原因を説明した理論として、著者らは「勢力均衡論」(古典的リアリズム、構造的リアリズム、新古典的リアリズム)と「覇権安定論」(勢力移行論、長期循環論)を比較しています。どちらも国家間の対外的な勢力関係のパターンが戦争のリスクをどのように変化させるのかを考える理論ですが、これらは国際的安定性が達成され、戦争が防止される条件について異なる見方を示しています。例えば、リアリズムは能力の均衡を戦争防止の要因として重視しますが、覇権安定論は能力の不均衡を重視しています。
その他にも多くの点が違いがあり、リアリズムの内部でも論争はあるのですが、戦争のリスクを特に高める行動を計量的アプローチで特定する「戦争へのステップ(steps to war)」の成果を踏まえれば、リアリズムの論理に依拠した対外政策、例えば脅威に対する軍備拡張や同盟形成が戦争のリスクを高めることが示唆されており、覇権安定論により強い妥当性があるように思われます。圧倒的な能力で他国の動きを封じる覇権国が弱体化すると、各国の能力が拮抗しやすくなり、結果として戦争のリスクが高まると考えられます。
ゲーム理論の枠組みから戦争の原因を交渉の失敗として説明する「戦争の交渉モデル」では私的情報や約束遵守の問題が効率的な外交的解決を妨げることが明らかにされており、これは戦争がどのような交渉過程から発生する事象であるかを理解する上で興味深い洞察を与えてくれます。交渉モデルは、交渉が可能な場面と、不可能な場面があることを示しており、特に双方が現状の勢力関係について共通の認識を持てない場合、あるいは合意が将来的に履行されると確信できない場合に、戦争に訴えることが合理的な選択肢として浮上しうることを示しています。
国内の要因に注目した理論として、著者らは過去の学説として影響力があったマルクス・レーニン主義の思想家が提案した帝国主義論を取り上げ、それがヨーゼフ・シュンペーターのエリート主義の議論に取り入れられ、戦争原因論として発展したことが示されています。シュンペーターの説明によれば、国家の対外政策は必ずしも国民の集団的な利益を追求するものではなく、国内政治で支配的地位を占める軍事的、経済的エリートの間で生じる対立や駆け引きから形成されます。
この考え方は対外政策分析におけるジャック・スナイダーの理論をはじめとするマルチ・エリート・モデルに発展しており、そこではエリートが一枚岩の集団ではないこと、意思決定の場で妥協を積み重ねた結果、いびつな対外政策が形成されてしまい、国力の限界を超えた過剰拡張政策に乗り出す場合があることなどが説明されています。
政治制度が戦争に与える影響を考慮したものとして注目すべきが民主的平和論の研究です。民主的平和論(democratic peace theory)では、政治体制が民主的になるほど、戦争に訴えることに慎重になり、民主主義国同士は戦わなくなるパターンを説明した理論です。これは統計的分析によって強い裏付けが得られており、戦争原因論にとって大きな価値がある理論です。政治体制が戦争の原因と密接な関係にあること、民主主義の発達が戦争遂行を抑制する効果があるという知見は、本書で取り上げられた数多くの戦争原因論の中で最も信頼できる成果だといえるでしょう。
著者らはサミュエル・ハンチントンが唱えた文明の衝突論も、この国内の要因から戦争を説明する理論の一つとして紹介していますが、それは宗教的、民族的なアイデンティティの違いが各国の相互敵意を強化すると想定する点において、後述する個人レベルの要因を強調した理論ともいえます。ただし、この理論の実証的妥当性に関しては大きな疑問があり、他の理論ともあまり整合的ではありません。文化が社会的アイデンティティを通じて人々の政治的認知に影響を及ぼす可能性があることを指摘したと解釈するならば、ハンチントンのモデルは心理的モデルの一種として位置づけた方がよかったかもしれません。
著者らは人々が認知的なバイアスや感情的な誘導に影響を受けており、結果として非合理的に見える戦争を始めるという可能性にも目を向けています。戦争が多大な費用をもたらす非効率な政策であるにもかかわらず、しばしば政策決定者に選択されることを説明する場合、個人レベルの心理を理解することが重要です。この個人レベルに注目する理論の特徴は、政策決定者の性格や認知、あるいは社会的コミュニケーションの性質を問題とすることであり、例えば官僚政治に特有の集団心理や硬直化した意思決定過程が国家の政策決定に及ぼす影響を説明する理論も、個人レベルの理論と位置付けられています。
戦争の状況を理解することは極めて認知的な負荷が大きな作業であるため、当事者であっても、あらゆる選択肢を検討し尽くことはできません。危険が迫るストレス環境に置かれた人々は、状況の曖昧さに対する認知的な許容度が低下するので、問題を過度に単純化し、誤認や誤解も生じやすくなります。このため、政策決定者は自分が検討すべき選択肢をあらかじめ直感的に絞り込み、その後で綿密な費用と効果の分析を行う傾向が生じます。このような二段階の意思決定過程は心理的モデルの一種である政治ヒューリスティック論として定式化されており、戦争の決定は必ずしも全面的に非合理的ではないものの、それは限定的な範囲で合理性が発揮されるにすぎないことが示されています。
以上の記述は本書の成果の一部を捉えたものにすぎませんが、著者らは戦争原因論の成果を多面的、総合的に総括しようとしていることはお分かり頂けるのではないかと思います。圧倒的な能力を持った覇権国の不在、互いの能力に関する認識の不一致や、約束を遵守されないという恐れがあること、政権を構成するエリートの利害対立や政治体制の独裁的な性格が強いこと、意思決定者のバイアスや誤認の状態などが、戦争を引き起こす要因として複数のレベルにわたり存在しています。しかし、戦争原因論は依然として、これらの知見を十分に統合できているわけではなく、大きな課題が残されていることを著者らは認めています。
厄介なのは、複数の要因が組み合わさっているだけでなく、異なった要因が作用しているのに、同じ結果を生じさせる等結果性(equifinality)が戦争に見られることです。仮に個別の戦争の過程を注意深く調査し、戦争の発生の要因らしきものを特定できたとしても、問題は片付くとは限りません。なぜなら、それらの要因を取り除いた場合でも、まったく別の要因が作用し、結果として同じ戦争が起こらないとも限らないためです。
個別の戦争の原因を説明することは一般的に想像される以上に難しい作業であり、むしろ全般の戦争の原因を説明する方が容易なことであるかもしれません。この難しさについて著者らはウォルツも認識していたことを紹介しており、「ウォルツ(1988)は、ネオリアリズム理論では『何千年にもわたって繰り返される悲惨な戦争』を説明することはできるが、『なぜ特定の戦争が行われるのか』を説明することはできないと述べてることで、この区別を認識していた」と記しています(Ibid.: 217)。著者らは、これからも研究は進展すると期待しつつも、戦争の原因を特定できるかどうかは、依然として不透明な状況であることを率直に求めています。
「クラウゼヴィッツは、「戦争の霧(fog of war)」が存在することを正しく認識していたが、それと同じように平和の霧(fog of peace)も存在している。この霧は戦争の遂行を複雑にするものであって、また我々の戦争、特に戦争の原因に対する理解を妨げている。この数十年にわたる研究者集団の努力によって、戦争の霧は多少は解消されてきた。さらなる進展があることが期待されており、約束されており、また必要とされてもいるが、戦争の霧が完全に晴れるかどうかは不明確である」(Ibid.: 219)
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

